第2章 > 第2節 > 1 米 国
【総論】
2001年9月11日の同時多発テロ以降、テロとの闘いへの対応について強い支持を受けてきたブッシュ大統領は、米国民の間で広がっていた安全に対する不安感も背景に、2002年を通じて引き続き高い支持率を維持してきた。こうした高い支持率を背景に、10月にはイラクに対する武力行使を容認する決議が上下両院で可決され、11月5日の中間選挙では、共和党は上下両院で多数を獲得するという歴史的な勝利を収めた。さらには、11月25日、テロ対策を始め国土安全保障を一元的に担当する国土安全保障省の設置法が成立した。
対外的にも、米国は、引き続き国際的なテロとの闘いを主導するとともに、大量破壊兵器等の拡散問題を安全保障上の重大な挑戦と位置づけて取り組んできた。2002年1月の一般教書演説においてブッシュ大統領は、北朝鮮、イラン、イラクを「悪の枢軸」と名指しした。9月に発表された米国国家安全保障戦略においては、米国の大義は自由な社会と平和の防衛であるとして、テロや大量破壊兵器等の拡散といった冷戦後の新たな脅威に対して断固たる姿勢で臨むとの考えを示した。
こうした取組にあたって、ブッシュ政権は、日本を始めとする同盟国との関係や国際協調を重視する姿勢を維持してきた。国家安全保障戦略においても、同盟諸国を始めとする国際社会との協調を重視していく姿勢が強調されたほか、イラク問題への対応においても、ブッシュ大統領は9月の国連総会における演説において、安全保障理事会(安保理)を通じて取り組んでいく姿勢を表明し、パウエル国務長官が中心となり、同盟国や安保理理事国との協議を重ねた。その結果、イラクの大量破壊兵器等の廃棄を確保するため、イラクが現に関連安保理決議に対する「重大な違反」を行っていることを認定し、国連と国際原子力機関(IAEA)による強化された査察の受け入れを要求する安保理決議1441が全会一致で採択された。
日本外交の基軸は対米外交であるが、それは、日本及びアジア太平洋地域の平和・安定と繁栄の実現にとって、日米安全保障体制や日米経済関係の緊密化が不可欠であるのみならず、国際社会の諸課題に日米両国が協力してリーダーシップを発揮していくことが日本の国益にとって極めて重要であるとの認識に基づいている。2002年には、2月のブッシュ大統領の訪日や、9月の小泉総理大臣の訪米等を通じ、首脳間の個人的な信頼関係が一層強化された。
テロとの闘い及び大量破壊兵器等の拡散問題、特にイラク及び北朝鮮をめぐる問題は、2002年の日米協力の主要な焦点となり、首脳・外相レベルを始めとして両国間で頻繁に協議が行われてきた。日本は、引き続きテロとの闘いにおける米国のリーダーシップに対して強い支持を表明し、テロ対策特別措置法の下での米軍等に対する協力支援活動を続けている(11月19日、自衛隊派遣期間の半年間延長等を決定)。また、アフガニスタンの復興支援においても、幹線道路の建設等の分野を始め、日米両国は「平和の定着」に向けた緊密な連携を継続している。
2003年はペリー提督が浦賀に来航してから、2004年は日米和親条約の締結からそれぞれ150年目にあたる。150年の歴史を経て、日米両国は、アジア太平洋地域における最も強固な同盟関係を維持するに至っている。ブッシュ大統領が2002年2月の訪日の際に国会で行った演説で述べたとおり、今後、日米両国は「自由な太平洋国家の共同体」としてのアジア太平洋地域の将来像を共有し、その実現を図っていくため、同盟国として緊密に協力していかなくてはならない。また、日米関係の基盤の更なる強化を図っていくためにも、両国国民の間の相互理解と交流の一層の深化・拡大に努めていくことが求められている。
ブッシュ大統領との会談に臨む小泉総理大臣(2月 提供:内閣広報室)

【米国内政】
米国同時多発テロ以降の米国国民の安全に対する不安を背景に、2002年1月の一般教書演説においては、経済安定と並び、テロとの闘い、国土防衛が主要なテーマとなった。ブッシュ大統領は、主要国内課題への取組を推進するため、また、中間選挙に向けた共和党候補の応援と資金集めのため、米国同時多発テロ以降控えていた地方遊説を年初より活発に行った。
3月には、米国同時多発テロ以降沈静化していた党派的対立が再燃し、地方裁判所判事の任命が上院司法委員会で承認されないなどの事態が起きた。これまで無制限に集金可能であったソフトマネー献金を禁止する選挙資金改革法が、中間選挙後施行として成立したが、ブッシュ大統領が重要視していた減税法案の恒久化やエネルギー法案等は成立しなかった。
5月に入ると、政府が2001年9月11日以前にテロの可能性に関する事前情報を入手していたことが明らかになり、民主党は激しい批判を開始した。その後、批判の対象は大統領から連邦捜査局(FBI)、中央情報局(CIA)などの情報担当連邦機関へと移り、特別調査委員会の設置が提唱された。こうした情勢を背景に、6月、ブッシュ大統領は、1947年以来最大の連邦政府改革となる国土安全保障省の設置を提案した。国土安全保障省及び米国同時多発テロに関する特別調査委員会の設置法案は11月末に成立・署名された。
内政面では、企業の不正経理問題も深刻な問題となった。1月のエンロン社の破綻に続き、6月、大手長距離通信会社ワールド・コムの不正経理が発覚した。ブッシュ大統領は相次ぐ企業スキャンダルと景気後退の懸念に対応する必要性を訴え、議会も異例の速さで企業会計制度改革法を成立させた。これは、不正経理問題が米国経済そのものへの信頼を揺るがし、また政治資金の観点からも米国内政上深刻な問題となり、民主・共和両党とも、11月の中間選挙をにらみ、速やかな対処を迫られたためである。
夏休み明けのワシントンの政治は、一変してイラク問題を中心に推移した。ブッシュ大統領は、9月4日、議会に対して対イラク武力行使容認決議の採択を求めた。同決議は10月10日に下院、翌11日に上院で可決された。世論調査によれば、米国民の6割がイラクに対する武力行使を支持しているほか、95%近くが、フセイン政権が大量破壊兵器を保有している、あるいは開発を行っていると考えており、約7割は、フセイン大統領が米国に対して大量破壊兵器を使用しようとしていると考えているとの結果が出た。
このような中で11月5日に行われた中間選挙においては、経済・社会等の内政問題のみならず、テロ、イラク等の安全保障問題も大きな焦点となった。ブッシュ大統領は、60%台の高い支持率を背景に、選挙終盤にも精力的に接戦区の候補を応援し、米国民の安全に対する不安感に強く訴えかけた。結果として、上院で共和党が51議席を確保して多数党を奪回し、また、下院でも共和党は229議席を確保して多数党を維持した。新任大統領の最初の中間選挙で、政権党が議席を増やすのは戦後初めてのことであり、大統領、議会両院を共和党が占めるのは、ブッシュ政権最初の半年を除けば、アイゼンハワー政権第1期前半以来のことである。これは、共和党の歴史的勝利であり、また、ブッシュ大統領に対する国民の信任が示されたとも評価できる。一方で、議席差は小差であり、今後の議会運営は決して容易ではないと見られている。
ブッシュ政権は、今後の重要課題として、テロとの闘い、イラク問題への対応等と並び、景気対策に早急に取り組んでいくことになる。12月、ブッシュ大統領は、オニール財務長官とリンゼー大統領補佐官の辞任を発表し、後任にスノーCSX社会長、フリードマン元ゴールドマン・サックス会長をそれぞれ指名した。一方、ロット共和党上院院内総務は、サーモンド上院議員100歳の誕生日の祝辞に際し、人種隔離政策を擁護する発言を行い、強い批判を受け、共和党保守派の支持も失い、院内総務を辞任した。次期院内総務には、共和党選挙委員長を務めたフリスト上院議員が、電話投票により選出された。
米連邦議会の勢力比較

【米国経済】
米国経済は、10年間に及ぶ史上最長の景気拡大の後、2001年3月から景気が後退し、米国同時多発テロの影響もあり2001年の実質国内総生産(GDP)成長率は0.3%となったが、2001年第4四半期から再び景気は拡大局面に入ったと見られている。2002年第1四半期には、減税や金融緩和の効果により個人消費・住宅投資が堅調な伸びを示したことに加え、在庫調整が著しく進展し、GDP成長率(前期比・年率)は、5.0%と高成長を示した。こうした需要の回復に牽引され、生産は2002年初から増加に転じ、雇用も持ち直した。しかし、第2四半期には、個人消費の鈍化等により、実質GDP成長率は、1.3%と大きく後退した。第3四半期は、住宅投資や、低金利に支えられた自動車販売に牽引される格好となった個人消費等が寄与し、成長率は4.0%と大幅に回復したものの、第4四半期は、個人消費の大幅な鈍化が影響し、成長率は0.7%(第1次速報値)と失速した。
景気回復が緩やかになった原因としては、株価の下落や企業部門の回復の遅れが挙げられる。株価は企業会計への不信の高まりなどから5月以降急速に下落し、10月には、ダウ平均株価は約5年振り、ハイテク株中心のナスダック総合指数も約6年振りの安値水準を更新した。こうした株価下落が消費を抑制しているものと見られ、消費者や企業心理にも悪影響を及ぼした。企業部門も、設備投資の回復が遅れるなど回復の抑制要因となっている。
財政面においては、米国同時多発テロを受けて成立した総額400億米ドルの緊急歳出法案及び航空業界を支援するための150億米ドルの緊急支援法案に加え、2002年3月には、失業者保険給付期間の延長及び法人向け税制優遇措置を盛り込んだ景気刺激策法案が成立した。ブッシュ大統領は、2001年6月に決定した10年間に1兆3,500億米ドルに及ぶ減税の恒久化を目指しているが、中間選挙で共和党が上下両院において勝利を収めたことに伴い、その実現性が高まっている。なお、積極的な財政政策に加えて、景気の悪化等による税収減もあり、2002年度の財政収支は1,580億米ドルの赤字となり、5年振りの赤字に転じた。
金融面においては、2001年に過去最多となる年間11回の利下げを実施した結果、金利は十分に低い水準にあり、また、景気が回復局面に入ったことから、2002年では10月まで金利は据え置かれていた。しかし、景気の先行き不透明感が消費・生産・雇用を抑制しているとして、連邦準備制度理事会(FRB)は、11月に0.50%の利下げを実施し、政策金利であるフェデラル・ファンド(FF)レートの誘導目標は1.25%と歴史的な低水準となった。
現在、米国経済は、高い生産性を引き続き維持しているとはいえ、 今後の景気を左右する上で最も注目されている設備投資の回復の勢いがかなり弱いものとなる見込みであること、
今後の景気を左右する上で最も注目されている設備投資の回復の勢いがかなり弱いものとなる見込みであること、 財政赤字が拡大する中での経常赤字のファイナンス問題(注)、
財政赤字が拡大する中での経常赤字のファイナンス問題(注)、 対イラク軍事行動への懸念等が足を引っ張る可能性もある。
対イラク軍事行動への懸念等が足を引っ張る可能性もある。
2002年の米国の通商政策に関する重要な動きは、クリントン前政権下の1994年に失効してから8年振りの復活となる大統領貿易促進権限法の成立である。この成立を受け、ブッシュ政権は自由貿易協定(FTA)締結に向けた交渉を積極的に推進する意図を表明している。また、2005年までの妥結が目指される世界貿易機関(WTO)ドーハ開発アジェンダについても交渉を加速していく意向である。このような米国の通商政策の新たな展開が日本の経済外交に及ぼす影響にも注視していく必要がある。
【米国の対外関係】
ブッシュ大統領は、2002年1月の一般教書演説において、外交の基本方針として、テロ・専制からの平和・自由、民主主義の防衛、テロとの闘いのための国際連帯の構築、国益に基づいた外交上の優先順位の設定、同盟国との関係強化、ミサイル防衛を含む新たな戦略的枠組みの形成、大量破壊兵器の不拡散等を打ち出し、孤立主義に陥らず世界に関与し続ける姿勢を明確にしている。
とりわけ、テロや大量破壊兵器等の拡散といった冷戦後の新たな脅威への対応の必要性はブッシュ政権の対外関係を大きく規定するものとなった。ブッシュ大統領は、一般教書演説において、大量破壊兵器を入手しようとし、テロを支援する国家として北朝鮮、イラン、イラクに言及し、これらの国家及びその同盟者たるテロリストは、世界平和に脅威を与えることを意図する「悪の枢軸」を構成すると名指しで非難した。また、9月にブッシュ政権の下で初めて議会に提出された米国国家安全保障戦略では、冷戦後はならず者国家やテロリストが新たな脅威となり、これらが大量破壊兵器を使う可能性がある中で、テロリストらが死をも恐れず、また、国家として活動しないことを最大の防御としているために、従来の抑止が通用しないなど、安全保障環境が根本的に変化したと表明した。さらに、12月に発表された「大量破壊兵器と闘う国家戦略」では、敵対する国家やテロリストによる大量破壊兵器の保有は米国の直面する「最大の安全保障上の挑戦の一つ」であると位置づけ、これに対する国家戦略として、拡散対抗、不拡散、大量破壊兵器使用の結果への対処のための米国の政策を示した。
ブッシュ政権はイラクをめぐる問題を最優先課題として取り組んできた。7月、国連とイラクの協議が物別れに終わり、国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)及び国際原子力機関(IAEA)による査察が再開されず、緊張が高まる中で、9月12日、ブッシュ大統領は、国連総会一般討論演説を行った。同演説では、これまでのイラクの安保理決議の不履行を指摘し、安保理を通じた対処の必要性を強調し、必要な決議の採択を目指す考えを示した上で、イラクが対応しない場合には行動は不可避となると発言した。また、ブッシュ大統領の要請にこたえる形で、10月に米国の上下両院で採択された対イラク武力行使容認決議は、イラクによる脅威に対して、米国の安全を保障し、イラクによるすべての関連安保理決議の履行を確保するため、大統領が必要かつ適切と認める米国軍隊の投入を容認した。その後、体制を強化した査察の受け入れを始めとする義務の履行をイラクに対し強く求める安保理決議1441が11月8日にシリアを含む全会一致で可決し、11月27日には約4年振りにイラクへの査察が再開された。しかしながら、イラクの協力が不十分なことから、2003年1月28日には、ブッシュ大統領が一般教書演説の中でイラクの大量破壊兵器等の廃棄の必要性を改めて指摘し、2月24日には、米国は、英国及びスペインと共に新たな安保理決議案を提出した。3月7日には修正決議案が提出され、安保理では、同修正決議案をめぐり議論が行われてきたが、16日の米国、英国、スペイン、ポルトガルによる首脳会談を経て、17日には、パウエル米国務長官は、同修正決議案について安保理での投票を求めないことを決めたと述べた。また、同日、ブッシュ米大統領は演説を行い、フセイン・イラク大統領は48時間以内に同国を立ち去るよう、さもなければ武力紛争の結果を招く旨述べた(3月18日現在)。
イラクと同じく「悪の枢軸」と名指しされた北朝鮮については、ブッシュ政権は2001年6月に対北朝鮮政策の見直し作業を終了して以降、前提条件なしに北朝鮮との協議を開始する用意があるとの考えを表明しており、2002年4月には北朝鮮も米国との対話を再開する意向を表明した。7月末のブルネイにおけるASEAN地域フォーラム(ARF)閣僚会合の際に、パウエル国務長官と北朝鮮の白南淳〔ペクナムスン〕外相が非公式に接触し、また、10月にはケリー国務次官補がブッシュ大統領の特使として訪朝した。しかし、ケリー国務次官補の訪朝の際に、北朝鮮がウラン濃縮計画の存在を認めるに至り、米国内で、議会を中心に1994年の米朝の「合意された枠組み」や朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)の存続に懐疑的な声が強まった。特に、「合意された枠組み」に従ってKEDOを通じて行われてきた年間50万トンの北朝鮮に対する重油供給の継続に対する反対が強まり、11月14日にニューヨークで開かれたKEDO理事会は12月以降の重油供給の停止を決定し、将来の再開は核兵器開発計画の撤廃に向けた今後の北朝鮮の行動にかかっていることを明らかにした。ブッシュ政権は、北朝鮮の核兵器開発問題について、日本や韓国を始め、中国やロシアも含む関係国との緊密な連携の下で外交的圧力を通じた平和的解決を目指すとしているが、同時に、米国が対話に応じるためには、まず北朝鮮が核兵器開発計画の撤廃を表明することが必要であるとの立場をとっている。
2002年を通じて、ロシアとの関係は一層進展した。米国は、対弾道ミサイル・システム制限(ABM)条約の規定に従い、6か月前に通告を行った上で、6月に同条約から正式に脱退したが、その前月の5月に行われたブッシュ大統領の訪露に際して、ブッシュ大統領とプーチン大統領は、戦略核兵器削減に関する条約(モスクワ条約)に署名し、「新たな戦略関係に関する共同宣言」を発表した。これらの合意は、米露両国の首脳が信頼と協調に基づき、より安定した二国間関係を構築し、そのような関係を踏まえた新たな戦略的枠組みを作り上げていこうという強い意志を示したものであると考えられる。また、米国同時多発テロ以降の協調関係により関係が改善した中国についても、2月にブッシュ大統領が訪中し、10月には江沢民〔こうたくみん〕国家主席が訪米し、北朝鮮やイラクをめぐる問題等につき前向きな意見交換を行った。米中間では、引き続き台湾問題、中国の軍拡についての懸念、人権問題等懸案事項はあるものの、基本的に良好な関係が続いている。
ブッシュ政権は、貧困国がテロの温床になり得るとして、2006年までに開発援助の額を50億米ドル増額(約5割の増額に相当)するという「ミレニアム・チャレンジ会計」を発表するなど、開発分野にも積極的に取り組んでいく姿勢を示している。また、米国は、9月の国連総会での演説で国連教育科学文化機関(UNESCO)への復帰を表明したが、その一方で、引き続き京都議定書や包括的核実験禁止条約(CTBT)等、一部の多国間の枠組みに対しては慎重又は否定的な姿勢を維持している。
流鏑馬を鑑賞する小泉総理大臣とブッシュ大統領(2月 提供:内閣広報室)
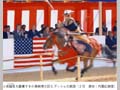
【日米関係】
2002年においても、日米両国は、幅広い分野に関する緊密な協議や政策協調を進めるとともに、日米安保体制の信頼性の更なる強化に努めてきた。そのような中で、日米間においても、テロとの闘い及びイラク、北朝鮮をめぐる問題が大きな焦点となった。
日本と米国は、2002年1月に、サウジアラビア、欧州連合(EU)と共に、東京で開催されたアフガニスタン復興支援国際会議の共同議長国を務め、大きな成果を上げた。その機会に行われた日米外相会談では、テロとの闘いや、アフガニスタンの和平・復興支援に関する両国の連携が再確認されるとともに、在沖縄米軍の問題につき、緊密に協議を継続していくことで一致した。また、9月の小泉総理大臣の訪米では、日米両国は、サウジアラビアと共に、アフガニスタンの幹線道路の建設に協力していくことを発表した。
2月には、ブッシュ大統領が就任後初めて訪日した。日米首脳会談では、テロとの闘いにおける日本の協力に対して、ブッシュ大統領が謝意を表明した。直前の一般教書演説における「悪の枢軸」への言及もあり、北朝鮮、イラン、イラクをめぐる問題への対応が注目される中で、ブッシュ大統領は、米国としてすべての選択肢を排除していないが、平和的に解決したいと考えていると述べた。また、首脳会談においては、ブッシュ大統領より小泉総理大臣の構造改革への全面的支持が表明されるとともに、沖縄問題、地球温暖化問題等について率直な意見交換が行われた。さらに、訪日中、ブッシュ大統領は国会で演説し、日米両国は「自由な太平洋国家の共同体」としてのアジア太平洋地域の将来像を共有し、更なる緊密な協力が必要であることを強調した。
北朝鮮の白南淳外相も出席し、朝鮮半島情勢が大きな焦点となった第9回ARF閣僚会合の機会に行われた日米外相会談では、直前の日朝外相会談や米朝外相間の接触も踏まえ、北朝鮮情勢に関する意見交換が行われ、今後とも北朝鮮への働きかけにおいて日米で緊密に連携していくことで一致した。また、イラク問題への対応について、パウエル国務長官より、米国として日本を始めとする同盟国と緊密に協議していくとの考えが改めて確認された。その後、8月27日から28日に東京において竹内外務事務次官とアーミテージ国務副長官との間で行われた日米次官級戦略対話においても、イラク情勢や北朝鮮情勢を含む国際的な諸課題に関し、様々な角度から率直な意見交換が行われた。
8月末から9月にかけて南アフリカで開かれた持続可能な開発に関する世界首脳会議(ヨハネスブルグ・サミット)の機会に、川口外務大臣とパウエル国務長官は、安全な飲料水を入手する、あるいは基本的衛生施設を利用することができない人の割合を2015年までに半減するという国際的目標の達成に向けた日米水協力イニシアティブ「きれいな水を人々へ」を発表した。2002年においては、保健等の分野を始め、日米間の開発分野での協力も進展し、2001年6月の日米首脳会談の際に発表された「安全と繁栄のためのパートナーシップ」でうたわれている地球規模の問題への取組に関する日米協力も進展した。
9月には、米国同時多発テロ1周年と国連総会の機会に、小泉総理大臣及び川口外務大臣が訪米した。小泉総理大臣は、ボストンに引き続き、ニューヨークを訪問し、外交評議会と時事通信の共催による講演会において「21世紀の日米同盟:三つの挑戦」と題する演説を行った。日米首脳会談では、小泉総理大臣が、ブッシュ大統領の国連総会での一般討論演説に強い感銘を受けたことを述べ、イラク問題への対処にあたっては国際協調が重要であることを強調し、ブッシュ大統領もこれに同意した。また、ブッシュ大統領より、直後に予定されていた小泉総理大臣の訪朝に対して改めて力強い支持が表明された。川口外務大臣は、13日にニューヨークでパウエル国務長官と会談を行い、イラクや北朝鮮をめぐる問題について意見交換を行った後、さらに16日及び17日には、ワシントンでライス大統領補佐官、パウエル国務長官、ラムズフェルド国防長官、ゼーリック通商代表等と相次いで会談を行った。また、ワシントンの戦略国際問題研究所(CSIS)において、「共通の挑戦:米国と日本、現在の日本の見方」と題する政策演説を行った。一連の会談の中で、川口外務大臣より9月17日の小泉総理大臣の訪朝の結果について説明し、核やミサイルを含む安全保障上の問題を含め、北朝鮮をめぐる問題への対応につき、今後とも緊密に連携していくことを確認した。米国からは、今回の訪朝への支持が表明された。
その後も、イラク及び北朝鮮をめぐる問題については、日米間で首脳・外相レベルを始めとした様々なレベルで協議が頻繁に行われたほか、国際的な枠組みでの活動を通じ、緊密な協議・連携を継続してきた。テロ対策特別措置法の下での米軍等に対する協力支援活動の継続は米国から高く評価されており、12月にインド洋へ海上自衛隊がイージス艦を派遣したことは、テロとの闘いにおける日本の任務遂行能力を高めるものとして歓迎された。
12月には川口外務大臣が石破防衛庁長官と共に日米安全保障協議委員会(「2+2」〔ツー・プラス・ツー〕会合)に出席するため訪米した。協議の中で、テロとの闘い、イラク、北朝鮮、ミサイル防衛、在日米軍にかかわる諸問題につき率直な意見交換が行われ、これら諸課題への取組において、同盟国として、日米両国が緊密に連携を行っていくことが確認された。会合後の共同発表においては、日米両国として、イラク問題については安保理決議1441の履行をイラクに対して引き続き強く要請していくこと、また、北朝鮮に関係する安全保障上の問題については、北朝鮮に対し、あらゆる核兵器開発計画の迅速かつ検証可能な方法での廃棄、弾道ミサイルに関連するすべての活動の停止、生物兵器禁止条約(BWC)の完全な遵守及び化学兵器禁止条約(CWC)への加入を要請しつつ、平和的解決を追求する姿勢が表明された。
G8外相会合に際し、パウエル国務長官と会談する川口外務大臣(9月)

【日米経済関係】
最近の日米経済関係は、かつてのような摩擦に象徴される関係から脱却し、建設的な対話を通じた協調の関係へと変貌を遂げた。このような協調の精神に基づき、米国と日本が取り組んでいくべき分野は、WTO新ラウンドといったグローバルな規模のものから、各々が取り組む地域的経済連携の構築やアジア経済情勢等の地域的レベルのもの、さらには、構造改革、規制改革、金融機関及び企業の改革といった個別・二国間のものまで多岐に及んでいる。
ブッシュ政権は、経済政策を、同盟国との連携強化という外交政策全体の不可分の要素として位置づけている。米国は、日本経済の回復が、日米両国経済や世界経済全体の繁栄のみならず、アジア太平洋地域の安定と繁栄に不可欠であると認識しており、小泉総理大臣の構造改革を強く支持している。
2001年6月の日米首脳会談の際にブッシュ大統領との間で合意された日米間の経済対話の枠組みである「成長のための日米経済パートナーシップ」は、こうした日米経済関係の変質を反映したものであり、2002年には、以下のように建設的な対話が行われてきた。
 二国間、地域的、グローバルな問題について戦略的な対話を行う次官級経済対話については、5月に第2回会合が開催され、日米両国経済の現状・経済運営、WTO新ラウンド、アジア太平洋及び米州地域における地域協力、開発援助政策、テロ対策措置及び「パートナーシップ」の今後の運営等につき率直な意見交換が行われた。
二国間、地域的、グローバルな問題について戦略的な対話を行う次官級経済対話については、5月に第2回会合が開催され、日米両国経済の現状・経済運営、WTO新ラウンド、アジア太平洋及び米州地域における地域協力、開発援助政策、テロ対策措置及び「パートナーシップ」の今後の運営等につき率直な意見交換が行われた。
 民間部門からの建設的な意見等(インプット)を得る官民会議については、日米双方の民間・政府関係者の参加の下、5月に第1回会合が開催され、「持続可能な成長のための環境整備:生産性の向上と企業再生」というテーマで企業統治等の企業活動に関する諸課題や市場における政府の役割等が議論された。また、11月にはワシントンで民間からの参加者のイニシアティブの下、同会議のフォローアップ会合が開催された。
民間部門からの建設的な意見等(インプット)を得る官民会議については、日米双方の民間・政府関係者の参加の下、5月に第1回会合が開催され、「持続可能な成長のための環境整備:生産性の向上と企業再生」というテーマで企業統治等の企業活動に関する諸課題や市場における政府の役割等が議論された。また、11月にはワシントンで民間からの参加者のイニシアティブの下、同会議のフォローアップ会合が開催された。
 日米規制緩和対話を発展・改組した「規制改革及び競争政策イニシアティブ」については、電気通信、情報通信技術(IT)、エネルギー、医療機器・医薬品の各分野と分野横断的な規制に関する日米双方の要望について、各作業部会及び次官級の上級会合を行った。その成果は、両首脳への第1回報告書としてとりまとめられ、6月のG8カナナスキス・サミットの際に行われた日米首脳会談の機会に公表された。10月には、2年目の対話に関する要望書の交換が行われ、以後、各作業部会が順次行われてきた。
日米規制緩和対話を発展・改組した「規制改革及び競争政策イニシアティブ」については、電気通信、情報通信技術(IT)、エネルギー、医療機器・医薬品の各分野と分野横断的な規制に関する日米双方の要望について、各作業部会及び次官級の上級会合を行った。その成果は、両首脳への第1回報告書としてとりまとめられ、6月のG8カナナスキス・サミットの際に行われた日米首脳会談の機会に公表された。10月には、2年目の対話に関する要望書の交換が行われ、以後、各作業部会が順次行われてきた。
 日米貿易問題についての早期警戒的な仕組みである貿易フォーラムについては、7月に東京において第1回会合が開催され、農業関連や公共工事の問題等について議論された。
日米貿易問題についての早期警戒的な仕組みである貿易フォーラムについては、7月に東京において第1回会合が開催され、農業関連や公共工事の問題等について議論された。
 両国における外国直接投資のための環境改善について議論する投資イニシアティブ、金融・財政政策やマクロ経済政策について議論する財務金融対話についても各種会合が行われてきた。
両国における外国直接投資のための環境改善について議論する投資イニシアティブ、金融・財政政策やマクロ経済政策について議論する財務金融対話についても各種会合が行われてきた。
米国の貿易赤字に占める対日貿易赤字の割合はピーク時の65%から15%以下に低下しており、現在は、日米両国間で政治問題化するような大きな個別の貿易摩擦案件はないが、日本として懸念する事項は存在している。
例えば、3月20日、米国政府は、1974年通商法201条(セーフガード)に基づき鉄鋼関連製品について関税引上げを柱とする救済措置を発動した。日本は、同措置について、WTO協定に反する保護主義的措置であるとして、WTOに提訴した。これを受け、WTOでは日本と欧州共同体(EC)を含む8提訴国による小委員会(パネル)が6月14日に設置され、第1回会合が10月29日及び30日、第2回会合が12月10日から12日にかけて開催された。
また、前述の企業会計制度改革法は、独立監査機関の創設、会計監査法人の独立性確保、企業経営者責任の厳格化等を定めている。しかし、同法の適用対象となる日本企業からは、米国に上場している外国企業の監査を担当する外国会計監査法人にも独立監査機関の効力が及ぶとする点や、独立した社外取締役のみから構成される監査委員会の設置義務を課している点に関して懸念の声が挙がっており、日本政府としても日本企業への適用を除外するよう米国政府に対し要望している。

 次頁
次頁

 今後の景気を左右する上で最も注目されている設備投資の回復の勢いがかなり弱いものとなる見込みであること、
今後の景気を左右する上で最も注目されている設備投資の回復の勢いがかなり弱いものとなる見込みであること、 財政赤字が拡大する中での経常赤字のファイナンス問題(注)、
財政赤字が拡大する中での経常赤字のファイナンス問題(注)、 対イラク軍事行動への懸念等が足を引っ張る可能性もある。
対イラク軍事行動への懸念等が足を引っ張る可能性もある。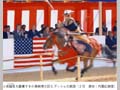

 二国間、地域的、グローバルな問題について戦略的な対話を行う次官級経済対話については、5月に第2回会合が開催され、日米両国経済の現状・経済運営、WTO新ラウンド、アジア太平洋及び米州地域における地域協力、開発援助政策、テロ対策措置及び「パートナーシップ」の今後の運営等につき率直な意見交換が行われた。
二国間、地域的、グローバルな問題について戦略的な対話を行う次官級経済対話については、5月に第2回会合が開催され、日米両国経済の現状・経済運営、WTO新ラウンド、アジア太平洋及び米州地域における地域協力、開発援助政策、テロ対策措置及び「パートナーシップ」の今後の運営等につき率直な意見交換が行われた。 民間部門からの建設的な意見等(インプット)を得る官民会議については、日米双方の民間・政府関係者の参加の下、5月に第1回会合が開催され、「持続可能な成長のための環境整備:生産性の向上と企業再生」というテーマで企業統治等の企業活動に関する諸課題や市場における政府の役割等が議論された。また、11月にはワシントンで民間からの参加者のイニシアティブの下、同会議のフォローアップ会合が開催された。
民間部門からの建設的な意見等(インプット)を得る官民会議については、日米双方の民間・政府関係者の参加の下、5月に第1回会合が開催され、「持続可能な成長のための環境整備:生産性の向上と企業再生」というテーマで企業統治等の企業活動に関する諸課題や市場における政府の役割等が議論された。また、11月にはワシントンで民間からの参加者のイニシアティブの下、同会議のフォローアップ会合が開催された。 日米規制緩和対話を発展・改組した「規制改革及び競争政策イニシアティブ」については、電気通信、情報通信技術(IT)、エネルギー、医療機器・医薬品の各分野と分野横断的な規制に関する日米双方の要望について、各作業部会及び次官級の上級会合を行った。その成果は、両首脳への第1回報告書としてとりまとめられ、6月のG8カナナスキス・サミットの際に行われた日米首脳会談の機会に公表された。10月には、2年目の対話に関する要望書の交換が行われ、以後、各作業部会が順次行われてきた。
日米規制緩和対話を発展・改組した「規制改革及び競争政策イニシアティブ」については、電気通信、情報通信技術(IT)、エネルギー、医療機器・医薬品の各分野と分野横断的な規制に関する日米双方の要望について、各作業部会及び次官級の上級会合を行った。その成果は、両首脳への第1回報告書としてとりまとめられ、6月のG8カナナスキス・サミットの際に行われた日米首脳会談の機会に公表された。10月には、2年目の対話に関する要望書の交換が行われ、以後、各作業部会が順次行われてきた。 日米貿易問題についての早期警戒的な仕組みである貿易フォーラムについては、7月に東京において第1回会合が開催され、農業関連や公共工事の問題等について議論された。
日米貿易問題についての早期警戒的な仕組みである貿易フォーラムについては、7月に東京において第1回会合が開催され、農業関連や公共工事の問題等について議論された。  両国における外国直接投資のための環境改善について議論する投資イニシアティブ、金融・財政政策やマクロ経済政策について議論する財務金融対話についても各種会合が行われてきた。
両国における外国直接投資のための環境改善について議論する投資イニシアティブ、金融・財政政策やマクロ経済政策について議論する財務金融対話についても各種会合が行われてきた。