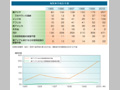第2章 > 第4節 > 3 国際組織犯罪、薬物、海賊
【国際組織犯罪】
経済のグローバル化やハイテク機器の進歩、人の移動の拡大などが進む現代社会において、国際組織犯罪が大きな問題となっている。これに対処するため、国際的な協力が強く求められるようになり、2001年も引き続き国連、G8等において精力的な取組が行われてきた。
国連で作成交渉が行われてきた国際組織犯罪条約及びその関連議定書(人の密輸、不法移民及び銃器の3議定書)は、銃器議定書を除き、2000年11月に国連総会で採択され、12月にイタリアのパレルモで署名会議が開催され、日本は国際組織犯罪条約に署名した。なお、銃器議定書は、2001年5月に国連総会で採択された。これらの条約・議定書の交渉にあたって、日本はG8間の調整グループの議長を務め、また、条約交渉の事務局であった国連の国際犯罪防止センター(CICP)に資金拠出を行うなど、交渉の促進に大きな役割を果たしてきた。また、腐敗や汚職が、開発や民主主義に対する重大な阻害要因となっているとの認識から、腐敗対策条約の交渉が、国連において2002年から開始されることが決定され、その枠組みについての議論が行われた。
国連での国際組織犯罪条約の採択を踏まえ、アジア地域において国際組織犯罪対策に関する国際協力を推進するため、2001年1月に、警察庁と外務省の共催で、アジア太平洋国際組織犯罪対策会議を東京で開催した。この会議にはアジア地域を中心に30を超える国、地域、国際機関から法執行機関幹部等約230名が参加し、全体会合のほか、銃器対策、薬物対策、組織犯罪対策及びハイテク犯罪技術対策の各分野の個別会合において、有意義な意見交換を行った。
通称リヨン・グループと呼ばれるG8国際組織犯罪上級専門家会合では、1995年以来、様々な国際組織犯罪対策が議論され、サミットでの議論に貢献してきたほか、国際組織犯罪条約の交渉に大きな貢献をしてきた。最近では、司法協力、法執行、ハイテク犯罪が、新しい課題として議論されている。米国同時多発テロ後は、リヨン・グループに蓄積されてきた国際組織犯罪対策の知識や経験を、テロ対策に効果的に役立てるとの新たな役割が期待されている。
2001年5月には、東京において、第2回ハイテク犯罪対策官民合同ハイレベル会合が開催された。この会合は、九州・沖縄サミットのコミュニケにも言及されているとおり、ハイテク犯罪対策には官民双方の協力が不可欠であるとの認識の下、開催されたものである。G8各国から官民のハイレベルの専門家が参加し、日本からは、植竹外務副大臣を団長に、外務省、警察庁、法務省、経済産業省、総務省などの政府専門家に加え、プロバイダーを含む電気通信事業者、情報機器メーカー、大学などの民間の専門家も多数参加した。同会合では、通信データの保存や保全、ハイテク犯罪の脅威分析や予防といった様々な課題について、活発な議論が行われた。
国際組織犯罪に対する国際的取組

【薬物】
2001年2月、ボリビアにおいて、第4回国際麻薬統制サミットが開催され、欧米、中南米諸国を中心に27か国から173名が参加し、代替作物の開発等につき議論が行われた。日本から佐々木知子参議院議員、江田康幸衆議院議員が参加し、第5回国際麻薬統制サミットを日本に招致したいとの意図表明を行った。
また、9月の米国同時多発テロを契機に、薬物問題とテロの関係について国連等において各国より関心が表明され、アフガニスタンにおけるケシ栽培の再開及び周辺国の取引の増大に対する各国の懸念が表明された。日本は、国連薬物統制計画(UNDCP)に対し、2001年度に338万ドルを拠出しており、このうち、アフガニスタンからのケシ及びアヘンの主たる流出経路となっているイラン及びタジキスタンにおけるUNDCPの取締り強化プロジェクトに対して60万ドルを拠出した。また、ミャンマーの主たるケシ生産地におけるUNDCPのプロジェクトに対して、UNDCP拠出金及び人間の安全保障基金から70万ドルを拠出した。
【海賊】
近年、世界における海賊事件の報告件数は増加の一途を辿っており、1995年には132件であった報告件数(注1)は、2000年には471件と約3倍以上(注2)に増加している。海賊事件は、特に東南アジア海域において多発しており、2000年に全体の50%以上に当たる257件が同海域において報告されている(注3)。東南アジア海域において海賊事件が頻発し、その被害が深刻化することは、石油等のエネルギー源の輸入を同海域における海上輸送に依存している日本にとって、大きな脅威となっているだけでなく、アジア地域全体の秩序の安定と経済の発展にも影響を与えている。
深刻化する海賊問題を解決していくため、日本は、国際海事機関(IMO)、ASEAN+3(日中韓)及びASEAN地域フォーラム(ARF)等の枠組みにおける国際協力に積極的に参加するとともに、2000年4月の海賊対策国際会議において具体的な対策として採択されたアジア海賊対策チャレンジ2000及び海賊対策モデルアクションプランを踏まえ、東南アジア地域における海賊対策に関する協力を積極的に実施している。
日本は、東南アジア諸国との協力強化を目的として、海上保安庁の巡視船を2001年8月にシンガポール、10月にフィリピン、12月にタイに派遣し、東南アジア周辺の公海上を哨戒するとともに、各国海上警備機関との連携訓練や意見交換を実施した。また、日本は、関係国の海上警備機関職員の取締り実務能力の向上を図るため、2001年4月より海上保安大学校への留学生受け入れを開始し、10月には、海上犯罪取締りセミナーを開催した。さらに、2001年3月に、日本の船会社の自主警備対策の強化・推進を目的として、インドネシア、国際海事局(IMB)等の関係者との協力の下、検討会を実施するとともに、沿岸国の緊急通報リストの作成・周知等による国際的な緊急情報連絡体制の整備を推進している。
こうした具体的協力に加えて、日本は、海賊対策に関するアジア諸国の地域協力を推進する方途を探るため、2001年10月、ASEAN、中国、韓国を含む17の国と地域から海賊対策にかかわる政府関係者、船主協会関係者、民間の研究者、IMO及びIMBの代表者の参加を得て、東京において海賊対策アジア協力会議を開催した。同会議の結果、海賊対策に関する地域協力の推進のためには地域協力協定の作成を検討することが必要であり、その具体的な内容について検討するため専門家作業部会を発足させるべきであるとの認識が共有された。同会議の結果を踏まえて、11月にブルネイで開催されたASEAN+3首脳会議において、小泉総理大臣が、海賊対策に関する地域協力協定の作成を政府レベルで検討するための政府専門家作業部会の開催を提案し、各国の賛同を得た。
アジア諸国は日本のこうした数々のイニシアチブを高く評価しており、日本は、今後とも海賊事件の撲滅に向けて、関係国との連携や協力の強化を図るとともに、海賊対策のために必要な技術支援や人材育成を積極的に行っていく方針である。
海賊対策アジア協力会議に出席する杉浦外務副大臣(10月)

海賊事件報告件数
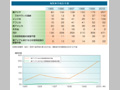

 次頁
次頁