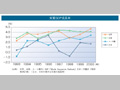第2章 > 第2節 国際経済
【総論】
2001年においても国際経済においてグローバル化の進展が見られた。そのような中で、9月11日に発生した米国における同時多発テロは、航空業界、保険業界を始め様々な分野に深刻な打撃を与え、グローバル化の度合いを深める世界経済に大きな影響を与えた。
グローバル化の進展は、情報通信技術(IT)などの飛躍的発展と相俟って、多くの企業や個人が国境を越えて活躍する機会を増大させている。グローバル化は、本来、すべての国や人々に大きな恩恵をもたらしうる動きである。しかし、実際には、グローバル化によってもたらされる恩恵が必ずしもすべての国や人々によって等しく享受されているわけではなく、貧富の差の拡大などグローバル化の「陰」の部分にも注目が集まるようになっている。1月のダボス会議や7月のG8ジェノバ・サミットの際にはグローバル化に対する激しい抗議運動が見られた。
このような中、技術進歩が十分な効果を発揮し、すべての国や人々がこのグローバル化の恩恵にあずかれるようにするための体制作りが、国際経済にとっての大きな課題となっている。5月の第3回国連後発開発途上国(LDC)会議、7月のG8ジェノバ・サミット、11月のドーハにおける世界貿易機関(WTO)第4回閣僚会議などは国際社会のそうした取組の一環である。例えば、ジェノバ・サミットにおいては、アフリカにおける平和、安定及び貧困撲滅といった課題に取り組むために、G8としての行動計画を次回サミット(2002年6月のカナナスキス・サミット(カナダ))までに策定することが決められた。日本はこのような国際社会の取組の中で積極的な役割を果たすとともに、開発途上国への二国間の支援等を通じ、グローバル化の「陰」の問題にも積極的に取り組んできている。
なお、グローバル化の進展とともに、地域的及び二国間の経済連携の動きも進展しつつある。2002年の年頭に欧州12か国でユーロ通貨の流通が開始されたことに示されるように、世界各地において、新たな経済秩序を模索する動きが続いている。日本は、WTOを中心とするグローバルな枠組みの強化を図ると同時に、2002年1月に日・シンガポール新時代経済連携協定が両国首脳間で署名されたことに象徴されるように、二国間の枠組みも推進していく。
実質GDP成長率
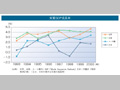

 次頁
次頁