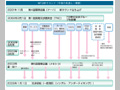第1章 > 6 > (3) 多角的貿易体制の強化
【総論】
公正な自由貿易の基盤である多角的貿易体制を維持し、強化していくことは、日本にとって重要な課題である。日本は、従来から、関税引き下げ等の更なる貿易自由化及び時代に応じたルールの策定・改善を行うために、世界貿易機関(WTO)の新しい多角的貿易交渉(以下「新ラウンド」)を早期に立ち上げることが重要であると考えており、1999年、シアトルで開催されたWTO第3回閣僚会議で他の加盟国と共に新ラウンド立ち上げを試みた。しかし、各国の利害の対立等の理由から新ラウンドの立ち上げは失敗した。その後、様々な協議、調整が行われ、2001年11月に、カタールのドーハで開催された第4回閣僚会議において、新ラウンドの立ち上げが成功したことは、今後の多角的貿易体制の維持・強化にとって大きな意義を持つと考えている。
【新ラウンドに至るまでの経緯及び概要】
日本は、従来から、すべての加盟国・地域の関心を反映した幅広い交渉議題の下で新ラウンドを立ち上げるべきであると主張し、その実現に向けて積極的に国際会議を主催し、議論を主導してきた。また、ドーハでの閣僚会議の直前である9月にメキシコの主催により開催されたWTO非公式閣僚会合や、10月にシンガポールの主催により開催されたWTO非公式閣僚会合でも、こうした日本の考えを主張し、各国と協力して議論を導くことで、新ラウンド立ち上げに向けた機運を作り出すことに成功した。最終的に、11月のドーハでの閣僚会議において、加盟国は新ラウンドの立ち上げに合意し、新ラウンドでは、今後3年間(2005年1月1日まで)交渉を行い、その結果を原則として一括受諾(シングル・アンダーテイキング)として取り扱うことを決定した。新ラウンドでは、一部の国が主張してきたような貿易の自由化のみを議題とした交渉ではなく、日本が主張してきたとおり、アンチ・ダンピング(AD)、補助金等貿易ルールの策定と改善を含む幅広い分野が交渉の対象となっている。今後は、新ラウンド交渉をいかに日本の国益に沿った形で進めていくかが重要となる。新ラウンドにおける主な交渉分野の内容及び日本の考え方は、以下のとおりである。
WTO新ラウンドの全体の枠組み(閣僚宣言の構造)

WTO新ラウンド(今後の見通し:概要)
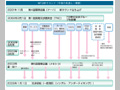
来日したムーアWTO事務局長と会談する河野外務大臣(1月)

〈農業〉
WTO農業協定(注1)に基づき「合意済みの課題(BIA)」(注2)として2000年から交渉が開始されている農業分野については、さらに野心的な目標(農工一体論(注3))に基づいて農業交渉を進めるべきだと主張するカナダ、オーストラリア、ブラジル等のケアンズ・グループ(農産物輸出国グループ)と、交渉結果を先取りするべきでないと主張する日本、EU等が対立していた。閣僚宣言では、日本等の主張が反映され、農工一体論は盛り込まれず、現状の農業交渉を継続することになった。今後とも日本は、多様な農業の共存が図られるような農産物の貿易ルールの実現を目指していく考えである。
〈サービス〉
同じくBIAとして2000年からすでに交渉が開始されているサービス分野については、閣僚宣言で、交渉を遅滞なく進展させることを確保するための交渉の枠組みが決まったことが重要である。具体的には、加盟国は、最初の要望事項(リクエスト)を2002年6月末までに提出し、これに対する最初の回答(オファー)を2003年3月末までに提出することになっている。日本は、今後ともサービス貿易の一層の自由化に向けて積極的に交渉に参加していく考えである。
〈アンチ・ダンピング(AD)〉
アンチ・ダンピング(AD)協定の見直しには、米国等が反対する一方で、AD措置の濫用は多角的貿易体制の脅威であるとして日本を始めとする多くの国がAD協定の見直しのための交渉の開始を求めていた。新ラウンドにおいて、そのような主張が受け入れられ、AD協定の規律の明確化及び改善について交渉することになった。日本は、AD措置が濫用され貿易活動が阻害されることのないように、今後の交渉を通じて、AD協定の規律の強化を求めていく考えである。
〈投資〉
投資分野については、日本や欧州連合(EU)等が交渉の開始を主張する一方で、自国の開発政策を拘束されることを嫌う開発途上国の一部が交渉に反対していた。結局、投資については、他のシンガポール・アジェンダ(注4)と共に、これまでの検討作業を続け、第5回閣僚会議(注5)以後にコンセンサスで交渉を開始する決定がなされることになった。今後は、貿易関連分野における能力向上(キャパシティ・ビルディング)等により、交渉開始に消極的な開発途上国に働きかけを行うとともに、第5回閣僚会議以後、円滑に交渉が開始できるよう検討作業を加速化させることが重要である。
〈貿易と環境〉
貿易と環境の問題については、狂牛病や遺伝子組換え食品等食品の安全に関する世論の高まりを背景に、EUが新ルールの策定を含む交渉の開始を主張していたが、環境保護を理由とする貿易制限が保護主義の隠れ蓑となることを懸念する開発途上国や米国が反対していた。閣僚宣言では一部の事項(多国間環境協定(MEAs)とWTOルールとの関係(注6)など)について交渉を開始することになった。今後、日本は、地球規模の環境問題や資源の持続的利用の観点に配慮しつつ、この問題により積極的に取り組んでいく考えである。
〈実施問題等〉
実施問題(注7)は、一部の開発途上国が、実施問題の解決が新ラウンド立ち上げの前提条件であると主張するなど大きな論点となっていたが、閣僚宣言とは別に、ドーハ閣僚会議において、「実施問題に関する決定」を行ってその一部を解決するとともに、未解決の項目は新ラウンドの交渉対象となる事項と、WTOの関連委員会で扱われる事項とに分けて、取組を継続することになった。新ラウンド交渉を円滑に進めるためには開発途上国との連携が必要不可欠であり、日本としても開発途上国の関心に適切に配慮していく考えである。
【加盟国・地域の拡大】
多角的貿易体制を普遍化し、強化していくためには、より多くの国・地域がWTOに参加することが重要である。2001年には、リトアニア、モルドバ、中国、台湾のWTO加盟が承認され、WTOに加盟している国・地域は計144か国・地域となった(2002年1月現在)。特に、中国のWTO加盟は、中国の対外的な貿易経済面での法的な予見性と安定性を高めるとともに、市場アクセスの改善に貢献するものであり、中国の改革開放を促進し、ひいては世界の繁栄と安定に資すると考えられる。また、ロシア、ベトナム、サウジアラビアを始めとする32の国・地域が加盟申請を行っており、加盟交渉を通じて、市場アクセスの改善と国内制度改革を促していくことが重要である。
【WTOの下での紛争解決制度】
WTOの紛争解決制度は、関税及び貿易に関する一般協定(GATT)時代に比べ、手続が整備・強化され、期限も明確にされたため、加盟国によって積極的に利用されている。パネルに付託される事案件数も、GATT時代から飛躍的に増加し、1995年1月のWTO設立以来、2001年10月中旬までに239件の協議要請が行われ、53件につきパネル・上級委員会の報告書が発出された。
日本も積極的にこの制度を利用している。例えば、米国のAD・相殺関税税収の提訴者への分配を義務づけるバード修正条項をめぐる問題に関しては、2002年度中にパネル報告を発出することが予定されている。また、熱延鋼板に対する米国のAD措置をめぐる問題については、米国の敗訴が確定し、WTO勧告の実施期間に関する仲裁の結果、米国は2001年11月23日までに国内法改正を含む実施手続を完了することになった。
WTOの中立かつ公正な紛争解決制度は、多角的貿易体制の安定性の確保に役立っている。また、この制度は、個別の紛争を解決するだけではなく、判例形成を通じたルール作りにも貢献している。現在、WTO紛争解決制度の改善に向けた検討作業において、日本も積極的に参加し議論に大きく貢献しており、新ラウンドでも紛争解決手続了解(注8)の改善及び明確化について2003年5月までに合意できるよう交渉を行うことになった。今後とも、紛争解決制度の実効性と信頼性を高めていくことが重要である。

 次頁
次頁