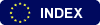| 英 国 |
EMUは英国にとっても有益であるが、欧州大陸諸国との景気サイクルのずれ等の理由から、まだ参加する体制は整っていない。2002年までに行われる次期総選挙後に参加の是非を問う国民投票を実施することを念頭に準備を進める。
ブレア首相は、99年2月に参加移行計画を発表し、政府としてユーロ導入に前向きな姿勢をアピールしたが、6月の欧州議会選挙で反ユーロを掲げた保守党に敗北してからは、政府の積極姿勢はトーンダウンしている(ただし、ブレア首相自身は慎重姿勢に転じたことを否定する発言を行っている)。 |
| デンマーク |
国内世論の動向を見極めつつ、通貨統合参加に関する国民投票の実施時期を探る。ただし、99年8月、ラムスセン首相は国民投票の実施時期は2000年秋までは発表しないと表明している。
99年1月からERM2(為替相場メカニズム:自国通貨とユーロとの間で為替相場を一定の範囲で連動させるシステム)に参加。 |
| スウェーデン |
総選挙及び国民投票によって決定すべき問題であるが、政府としてユーロ導入に向けた準備作業は継続していく。
8月、パーション首相はユーロ参加の是非は国民投票で決定されるとの見通しを表明。2000年春に開催される与党・社会民主労働党の党大会においてユーロ参加が支持されれば、国民投票の実施日程等が決定される見込み。 |
| ギリシア |
4ヶ国中で最も参加に前向き。2001年当初からの参加を念頭に収斂基準達成を目指して経済改革努力中(既に十分達成可能な水準)。ERM2にも99年1月から参加。加盟申請を2000年3月に実施、同年6月のEUサミットにて承認される見込。 |