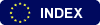最近のEU情勢
平成13年7月
<ポイント>
- EUは、ユーロ導入、アムステルダム条約の発効等により統合を一段と深化させてきた。また、拡大についても、新規加盟交渉を12か国と行っており、2002年末までに新規加盟国を受け入れる体制を整備する予定。
- この拡大に対応するために、EUは機構上改正すべき事項について、2000年2月より政府間会合(IGC)を開催し協議を行ってきたが、最終的に2000年12月のニース欧州理事会において、首脳レベルでの決着が図られ、EUの新たな基本条約となるニース条約に関する合意が成立した。2001年2月にニース条約のEU加盟国による署名式が行われた。
- 安保・防衛政策分野においては、EU独自の危機管理部隊への各国の貢献や関連機関の創設が正式に承認されており、今後は、早期に実働可能なものとなるよう必要な作業が継続される他、NATOとの関係が焦点。
- 欧州統合のあり方を巡って、2000年来フィッシャー独外相の「欧州連邦国家」構想や、これを受けたシラク仏大統領の「パイオニア・グループの形成」による統合の進展に関する構想などをはじめとして、EUの拡大による力の分散を防ぎつつ統合を進展させるための論議が活発化しており、ベルギー議長国下で欧州統合の将来に関する方向付けがなされるべく議論が進められ、12月の「ラーケン欧州理事会」で欧州の将来に関する「ラーケン宣言」が発表される予定。
|
1.EU拡大:加盟交渉国が6か国から12か国へ増大
| (1) |
1998年3月31日、EUはポーランド、チェッコ、ハンガリー、エストニア、スロヴェニア及びサイプラスの6加盟申請国との間で加盟交渉を開始した。また、ルーマニア、スロヴァキア、ラトヴィア、リトアニア、ブルガリア及びマルタの6ヵ国については、2000年2月15日より加盟交渉を開始した。
現在準備が進んでいる国から、個別分野における交渉が進められている。
|
| (2) |
トルコは、99年12月のヘルシンキ欧州理事会で加盟候補国と認められたが、今後加盟交渉を開始するには、人権、領土、サイプラス問題の解決といった政治基準を満たすことを要請されている。
|
| (3) |
EU加盟候補国の加盟時期について、最も早い加盟候補国は、2002年末までに加盟交渉を終え、2004年の欧州議会選挙に参加するとのタイムテーブルに、条件付きで合意した。 |
2.EU機構改革:新EU基本条約となるニース条約について合意
| (1) |
1999年5月1日に発効したEUの新たな基本条約であるアムステルダム条約)で、解決が先送りされた将来のEU拡大に対応するため改正すべき3事項(欧州委員会委員数の見直し(注1)、特定多数決票数配分の見直し(注2)及び右多数決適用範囲の拡大)について協議するため、2000年2月より機構改革に関する政府間会合(IGC)が開催された。
|
| (2) |
このIGCでは、上記3事項の他にEU拡大に対応する体制作りを目的としたEUの制度的問題(例:欧州議会の議席数、欧州司法裁判所の裁判官数と機能、会計検査院の権限等)や、「より密接な協力」(注3)についても議論された。
|
| (3) |
2000年12月のニース欧州理事会で、首脳レベルでの日程を延長して行われた調整の結果、これら機構改革問題は、新しいEU基本条約となる「ニース条約」に関する合意によって一応の決着をみた。この結果、欧州委員会の構成(注4)、特定多数決の適用分野の拡大や新しい票配分(注5)、「より密接な協力」発動要件の緩和、欧州議会の議席再配分等が合意された。
|
| (4) |
ニース条約は2月26日に全加盟国の署名が行われ、今後各国における批准を経て発効。また更なる条約の再編、EUと各国の権限分配の明確化等を議論し、ニース条約を更に改訂する条約交渉のための政府間会合(IGC)を2004年に開始することで合意された。
|
| (5) |
ニース条約の批准手続きは18ヶ月以内に終了することが政治的期待として表明されており、2002年末までの発効が目指されている。しかし、6月に実施されたアイルランドの国民投票において同条約が否決されたため、アイルランドの今後の手続の行方次第では、今後のスケジュールに若干の遅延が起こる可能性もある。
| (注1) |
独、仏、英、伊、西より各2名、残り10か国より各1名の委員を選出 |
| (注2) |
各国別に異なる票が配分された加重投票
独、仏、英、伊に10票、西に8票、蘭、ポルトガル、ベルギー、ギリシャに5票、オーストリア、スウェーデンに4票、フィンランド、デンマーク、アイルランドに3票、ルクセンブルグに2票 |
| (注3) |
より密接な協力(closer cooperation):全構成国が同じペースで統合を推進することができない場合に、一部の加盟国が他より先行して特定の分野について政策統合を行う方式(「先行統合」とも称されている)。ニース条約においては、発動要件の緩和等により「強化された協力」(enhancedcooperation)と称されることとなった。 |
| (注4) |
2005年から1国1委員制とする。委員数の上限については、加盟国数が27か国になった時に、委員数の上限を27名未満に固定するための決定を行い平等の輪番制をとる。 |
| (注5) |
英、独、仏、伊に29票、西に27票、蘭に13票、ギリシャ、ベルギー、ポルトガルに12票、スウェーデン、オーストリアに10票、デンマーク、フィンランド、アイルランドに7票、ルクセンブルグに4票。なお、加盟交渉国についても、ポーランドに27票、ルーマニアに14票、チェッコ、ハンガリーに12票、ブルガリアに10票、スロヴァキア、リトアニアに7票、ラトヴィア、スロヴァニア、エストニア、サイプラスに4票、マルタに3票の票数配分が決定された。なお、今回の合意のポイントとしては、特定多数決の成立に人口の要素が加味され、加盟国数に拘わらず、賛成した国の人口がEU全人口の少なくとも62%を代表していることが必要となった。 |
|
3.欧州基本権憲章
| (1) |
人権及び基本的自由の尊重が謳われているEU条約の中に、人権カタログ規定が置かれていないことから、これを規定するため99年10月に設置された評議会において欧州基本権憲章草案作成作業が進められてきた。
|
| (2) |
2000年10月のビアリッツ特別欧州理事会に評議会作成草案が提出された結果、年末のニース欧州理事会で首脳レベルで正式に承認され署名が行われた。
|
| (3) |
憲章の内容は前文と尊厳、自由、平等、団結、市民権、司法の分野等に保護されるべき権利が明確化されており、全体で54条からなる。 |
4.共通外交安全保障政策(CFSP)における進展
| (1) |
99年5月1日に発効したEUの新しい基本条約であるアムステルダム条約により、共通外交安全保障政策の強化(上級代表の創設、CFSP分野への特定多数決・建設的棄権制度の導入等)が図られることとなった。
|
| (2) |
具体的にはソラナ前NATO事務総長は、99年10月18日にEUの共通外交安保政策上級代表に就任し、11月25日には西欧同盟(WEU)事務総長を兼任することとなった。
|
| (3) |
99年11月、EU外相理事会に初めて各国国防相も出席し軍事面を含めた議論が行われた。こうした議論を踏まえ、EUが紛争防止・危機管理等の任務を行うため、5~6万人規模の危機管理部隊(常設ではなく必要に応じ加盟国が要員を派遣し、60日間の準備期間で部隊を編成、最低1年間駐留できる能力を付与)の創設や、関係機関の創設について99年12月のヘルシンキ欧州理事会で合意が得られた。
|
| (4) |
また2000年6月のフェイラ欧州理事会の結果、NATOとの合同作業部会設置や、非軍事的危機管理措置として5000人規模の文民警察部隊の設置等が合意された。
|
| (5) |
2000年11月のWEU閣僚理事会において、WEUの一部機能のEUへの移行計画(危機管理任務、衛星センター、安全保障研究所のEUへの移行等)が合意され、事実上WEUは形骸化されることとなった。
|
| (6) |
同月に、ヘルシンキ欧州理事会で設定された危機管理部隊に関する目標を達成するためにEU各国の貢献をコミットする能力誓約会議が開催され、各国からの貢献の合計は10万人以上の兵員のプール、約400機の戦闘機及び100隻の艦船となった。12月のニース欧州理事会では、この危機管理部隊の骨格案や、3つの関連機関(政治安全保障委員会、軍事委員会、幕僚部)の正式な発足が承認された。
|
| (7) |
今後は、この危機管理部隊が早期に実働可能なものとなるよう作業が継続される他、NATOとの関係の整理がなされる必要がある。 |
5.2002年1月1日:単一通貨ユーロ紙幣・硬貨の流通
| (1) |
EUの経済通貨統合(EMU)は1990年7月から3段階で進められてきたが、1999年1月1日、最終段階である第3段階に移行し、単一通貨ユーロが導入され、欧州中央銀行(ECB)による統一金融政策が開始された。これに伴い、ユーロ参加各国(下記(2)参照)の通貨とユーロとの交換レートが1998年12月31日をもって不可逆的に固定された。
なお、ユーロ紙幣・硬貨の流通開始は2002年1月1日であり、それまでの間、ユーロは金融機関間の取引や、クレジットカードによる決済等、現金を伴わない場合のみ使用可能である。
|
| (2) |
1999年1月1日からEMU第3段階に参加したのは、EU加盟15ヵ国中、英、デンマーク、スウェーデン、ギリシャを除く11ヵ国(※)であった。これら不参加国のうちギリシャは、2001年1月1日より参加しており、合計12か国が現在ユーロを導入している。また、デンマークは2000年9月28日にユーロ参加の是非を問う国民投票を実施したが、反対多数で否決され、同国のユーロ参加は当面目途が立たない状況となっている。
| (※) |
独、仏、伊、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、アイルランド、スペイン、ポルトガル、オーストリア、フィンランドの11ヵ国 |
|
| (3) |
ユーロの対ドル相場は、導入以来ほぼ一貫した下落傾向が続いている。2000年7月下旬以降再び下落傾向となった相場に対し、9月25日にはECBの主導により日米欧(英・加含む)の協調によるユーロ買い介入が実施された。介入後一時相場は安定したが、再び相場は軟化し、10月26日には史上最安値の1ユーロ=0.823ドルを付けた。その後11月上旬にECBが単独介入を繰り返し、また11月後半以降には米国景気の減速感が強まったことから一時相場は反転したが、2001年に入り再びユーロの下落傾向が続いている。
2000年までのユーロ安の主たる要因としては、(イ)米欧間の景気格差(米国の好景気が持続したこと)、(ロ)欧州における構造改革の遅れ(労働市場の硬直性や企業活動への政府の介入)、(ハ)ECBの金融政策に対する市場の信認の未確立、(ニ)直接投資・証券投資による欧州から米国・日本等への資金流出等が挙げられていた。このうち(イ)以外の要因は基本的に現在も持続していると考えられる。
ユーロ圏は米国にほぼ匹敵する経済規模を有しており、ファンダメンタルズも減速感があるとはいえ、基本的にはまずまず堅調であることから、中期的にはユーロ相場は安定するものと予想される。但し、過度のユーロ安はインフレ圧力をもたらしており、主たるユーロ安要因のうち、労働市場改革といった構造改革の進捗状況やECBの金融政策の動向には今後とも注意を要する。 |
6.欧州社会モデルの推進
| (1) |
2000年3月23日~24日にリスボンで特別欧州理事会が開催された。右会議では、狭義の雇用問題にとどまらず、IT革命への対応を一つの軸として、知識社会への移行を強力に推進しつつ社会的疎外や貧困の解消のため能動的な社会福祉政策をも追求するという「欧州社会モデル」のあり方等、経済・社会問題について包括的に議論された。
|
| (2) |
特別欧州理事会は、「より多くより良い雇用とより強い社会的連帯を確保しつつ、持続的な経済発展を達成し得る、世界で最も競争力があり、かつ力強い知識経済となること」というEUの今後10年間の戦略的目標を明確にした。
また、具体的措置として、(i)競争力がありかつ力強い知識経済への移行準備(IT革命対応、研究開発支援、起業支援等)、(ii)欧州社会モデルの改革(知識社会にむけた教育・訓練、エンプロイヤビリティの改善等積極的な雇用政策、社会的疎外の解消)、(iii)より一貫した体系的な政策実施(毎年春の欧州理事会でのモニタリング実施)を決定し、右措置による年約3%の持続的な経済成長、2010年までの70%の就業率の達成(現在61%)及び女性就業率60%の達成(現在51%)等の目標を掲げた。
|
| (3) |
2000年12月のニース欧州理事会においては、「新社会政策アジェンダ」が採択され、「欧州社会モデル」の刷新を図り、質量両面において雇用を改善し、リスボン特別欧州理事会における合意内容を実行に移すための具体的な提言が示された。 |
7.税制改革:「税制パッケージ」の政治的合意
ユーロ圏をより強固な経済単位として確立させるために、ユーロ導入により顕在化した税制の不均等、税収ロスを解消し、雇用促進的な税制を構築するための「税制パッケージ」(注6)が2000年6月のフェイラ欧州理事会において、大枠として(すなわち、適用すべき制度や最終合意までに確保すべき点等が枠組み的に)政治的合意に達した。
この内、加盟国間の意見対立が大きい利子課税については、第三国への働きかけを含め、スケジュールに沿った作業が行われている。
| (注6) |
税制パッケージは、以下の3点を内容とする。
(a)域内非居住者利子課税に関する指令
(b)法人課税に関する行動規範(コード・オブ・コンダクト)の受容
(c)グループ企業間の利子及びロイヤリティ支払いに係る課税に関する指令
|
8.電子欧州行動計画(e Europe 2002)
| (1) |
情報化が雇用、成長、生産性に大きな影響を及ぼすとの認識の下、情報社会の便益を全ての欧州市民が享受することを確保するためのイニシアティブ。
|
| (2) |
ニュー・エコノミーへの移行を行うための条件を整備する戦略を提示した電子欧州行動計画(e Europe 2002)が、2000年6月のフェイラ欧州理事会において承認された。
|
| (3) |
電子欧州行動計画(e Europe 2002)は、3つの大きな目標(注7)を掲げており、2002年末を計画全体達成のための最終期限としている点が特徴。
|
| (4) |
2000年12月のニース欧州理事会においては、同行動計画の進捗状況とこれまでの成果が報告された。今後は2001年3月のストックホルム欧州理事会においても、進展が評価される予定である。
| (注7) |
「3つの目標」
(a)より安価で、より高速で、より安全なインターネット
(b)欧州市民の技能及びアクセス向上に対する投資
(c)インターネットの活用の奨励 |
|
9.狂牛病・口蹄疫問題
| (1) |
仏では2000年に入って狂牛病発生件数が増加傾向にあったこと、大手スーパーで感染が疑われる牛肉が販売されたことを受け、社会問題化した。一方、2000年11月に西及び独において初の狂牛病感染例が確認され、EU全域に波紋が広がった。
|
| (2) |
2000年12月、緊急農相理事会は感染経路と推定される動物性飼料(骨肉粉飼料)の6ヶ月間にわたる全面的な使用禁止を決定した。
|
| (3) |
牛肉価格の支持のため追加的な予算措置がとられており、共通農業政策の見通し議論にも影響を与える見込み。
|
| (4) |
今春欧州で発生した口蹄疫は終息に向かいつつある。 |
10.今後の欧州統合のあり方を巡る議論
| (1) |
フィッシャー独外相は、2000年5月12日に「国家連合から連邦へ、欧州統合の最終目的に関する思考」と題した講演を行い、欧州統合の今後10年以上先を見通した長期的展望についての見解を発表した。その中でEUの東方拡大は必然であること、拡大後にEUが役割を果たしていくためには、最終的には欧州憲法条約の締結による連邦の設立が必要であろうということ等を提案した。
|
| (2) |
これに対し、シラク大統領は、独を訪問し6月27日に連邦議会にて行った演説の中で、欧州統合の中期的な課題としては、主権国家に代替する超国家の創設を否定し、加盟国の同意に基づく「共同主権」の行使、仏独を中心とした「パイオニア・グループ」の組織による統合の進展を提唱した。
|
| (3) |
更に、10月4日には、欧州議会においてプローディ欧州委員長が欧州委員会や欧州議会の役割の強化による共同体としてのアプローチを主張する一方、ブレア英首相は10月6日にポーランドにて欧州政策演説を行い、欧州市民が欧州大統領を選んで欧州議会を欧州の立法府とするような欧州連邦という方式には反対の意を表明した。2001年に入り、更にシュレーダー独首相やジョスパン仏首相も相次いで、各々の欧州の将来像に関する構想を発表し、議論が活発化している。
|
| (4) |
ヴェルホフスタット・ベルギー首相に選ばれたデハーネ前ベルギー首相、アマート前イタリア首相、ドロール元欧州委員長、ゲメレク元ポーランド外相から成る「ラーケン・グループ」を中心に、12月のラーケン欧州理事会で発表する欧州の将来についての「ラーケン宣言」の準備が行われる。 |
|