|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > G7 / G8 |
|
| ||||||||||||||||
| トップページ > 外交政策 > G7 / G8 |
| ようこそ リヨンへ! |
|---|
 |  |
|---|---|
| 見晴らし台から見たリヨン | 現代美術館 (Musee de l'art contemporain) |
| ●2つの川が合流する町 ●ヨーロッパの十字路、リヨン ●リヨンの歴史 18世紀、改革者の時代 |
II. リヨン・今日の顔
|
●1. 国際都市リヨン ●2. リヨン市の行政 ●3. リヨンの産業と日本企業 リヨンと日本との関係 リヨンの日本語教育 リヨンを中心としたローヌ・ アルプ地方について |
I. リヨン概観
2つの川が合流する町
2つの川が洗う町リヨンは、豊かな水の恵みを受け、ローマ時代から栄えた2000年以上の歴史を誇るフランス第2の都市である。人口は近郊を含め126万人。
ソーヌ西側には古代ガリア・ローマ時代の遺跡のあるフルビエールの丘や、中世からルネッサンス時代の面影が残る旧市街(ヴューリヨン Vieux Lyon)がある。ローヌ川とソーヌ川にはさまれた半島地区(プレスキル Presqu'ile)はローマ帝国以来、物資集散所となり、やがて町の中心となった。ローヌ川の東側には、ビジネス街が広がっている。
リヨンの歴史
| 18世紀、改革者の時代 | |
|---|---|
| ジャカード(Marie-Joseph JACQUARD): | ジャカード機織り機の完成 |
| チモニエ (Barthelemy THIMONNIER): | ミシンを創案 |
| ギメ (Emile GUIMET): | 東洋博物館開設 |
| クロード ベルナール (Claude BERNARD): | 東洋博物館開設肝臓のグリコーゲン機能を明らかにした生理学者 |
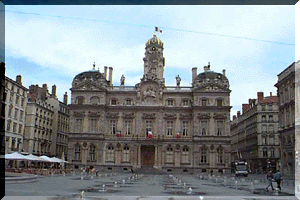 |
| 市庁舎(HOTEL DE VILLE) |
2. リヨン市の行政
| リヨン市の 人口: |
上述のリヨン都市共同体=クルリーで126万人 |
|---|---|
| リヨン市長: | レーモン・バール氏(ジスカール・デスタン大統領時の首相、UDF支持) |
| 市会議員の 構成: |
前市長ミシェル・ノワール氏(元RPR)の流れを継ぐアンリ・シャベール氏と、レーモン・バール氏の政策協定により、9区のうち5区(2・4・5・6・7区)が市長与党(市議会多数派=UDFとReussir Lyon)によって占められ、他の1区は緑の党が、3・8・9区は社会党系が多数派を占める。これに対し、リヨン市を囲む周辺新市街地ヴィユルバンヌ、ヴェニシューなどは、伝統的に社会党・共産党が強い。なお、市長は市議会、区長は区議会で選出される。リヨン市議会議員の党派別構成は定数73名中、社会党系19、UDF系17、ReussirLyon15、RPR系12、エコロジスト系5、共産党3、フロン・ナショナル2である。 |
| ローヌ県: | 県庁所在地はリヨン市、県知事はメルシエ氏。 ローヌ・アルプ地方については下段参照。 |
3. リヨンの産業と日本企業
リヨン市周辺は多数の産業が発達している。特に前述した繊維産業の他、化学・準化学工業、医薬品、食品加工が盛んである。
リヨン市以南ジェルラン地区は、新しく開発された産業拠点であり、パスツール研究所、ワクチンのメリュー研究所、コンタクト・レンズの眼球内移植に成功しているドミランス社など、近代的な設備を誇る研究所が立ち並んでいる。
一方、リヨン近郊は他の地方に比べ、外国企業の進出は比較的遅かった。日本企業についても同様である。最も古くからリヨンに進出したのは、丸紅系のテクマテクスで、津田駒の織機の販売を目的とする。ここ数年、リヨン商工会議所の外国企業誘致(ADERLY=リヨン地方経済開発協会)が功を奏し、91年より、光洋精工がルノーの下請けSMI社を買収、93年より、住友化学がローヌ・プラン化学と合併会社設立など、日本企業の着実なリヨン進出が続いている。他に、古河機械、ユニチカなどが挙げられる。
| フランス在留邦人数比較 | |
|---|---|
| リヨン市 | 200名 |
| ローヌ県 | 415名 |
| ローヌ・アルプ地域圏全体 | 1,005名 |
| パリ市 | 7,971名 |
| フランス全体 | 18,543名 |
| ※1995年10月1日現在の在留届実績ベースによる (在仏日本国大使館) | |
「河霧立ちこめし河岸通の景色よし」
「毎日の濃霧天地は永遠の黄昏なり。然れどもロオン河上の暗澹たる景色却て歩を停めて打眺むるに好し」
「薄き霧に掩われし河の景色は病める美女の微笑めるに似たり」
「余はロオンの流れを見るも今宵限りぞと思へばおのづから歩みも遅く欄干に凭れて涙を流しぬ」
1908 永井荷風
後年、国費留学生としてリヨンに滞在した遠藤周作は、中世に逆戻りしたような錯覚に陥る15~17世紀の古色蒼然たる家並みの続く旧市街をテーマにしている。3年前(1993年)には彼の最新作「深い河」で再び川の流れる町リヨンを舞台に物語を展開している。熊井啓監督により映画化され、リヨンで大規模な撮影が行われた。
日本からフランスへの文化移入の面でも、1876年、リヨンの経済人・文化擁護者であるエミール・ギメが文化使節として訪日し、1879年には、ギメの収集した日本美術品を紹介する美術館をリヨンに開設した。
一方、多くのリヨンの人々が明治維新以後、すぐれた産業技術を日本にもたらした。例えば、海軍技師レオンス・ヴェルニーは横須賀軍港を建設。あい前後して、サンテチェンヌの技師が日本の天皇家に宮仕え、生野銀山の開発に寄与したことも見逃せない。
またリヨンは、19世紀初頭から約1世紀半、絹製品を世界中に輸出していた『絹の町』であり、日本は明治初頭にイナバタ・カツタロウによる絹染め技術の導入、佐倉常士、井上伊兵衛による近代機械絹織物技術の習得、ジャカード機の購入等その分野で多くの技術を学んだ。現在でも国際絹業協会(ISA)の本部がリヨンに置かれている。
1994年は、リヨンと横浜が友好都市となって30周年にあたり、数多くの公式記念行事、市民レヴェルの文化交流が行われた。
それに先立ち、1993年10月にはジャパン・フェスティヴァルがリヨンで開催され、3日間にわたり日本の伝統的芸術が披露され、会場は3日間満員のリヨン市民で賑わった。また、昨年1995年10月には、リヨン日本人センター(ドバール神父主催)において日本週間が開催された。
リヨンの日本語教育
リヨンは日本語教育に熱心である。公立校は、二つの高校で第二外国語として日本語の選択が可能。大学は、日本語科のあるリヨン第三大学以外にも、理工系のグランゼコール(Ecole Centrale, INSA, Ponts et Chaussees)、商学系(ESC)で日本語を第二外国語として選択する学生が毎年1クラスずつ生まれている。
私立校は2校(オンブロザ、リヨン国際学校)で日本語教育を行っている。前者は、フランス人一般に小学校からの日本語学習の道を開いている。後者には、1994年9月より、リヨン市・市商工会議所などの支援の下で日本語科が設置され、日本人家庭、日仏家庭の子弟が、日本の文部省の指導要領に添った日本語教育を受けている。この他、文部省の認定を受けた日本語補習校がある。
なお、日本からの留学生は、アリアンヌ・フランセーズやカトリック大学への語学留学、大学各学部、グランゼコール、様々な研究所への留学・研究生等と多様である。
リヨンを中心としたローヌ・アルプ地方について
| BACK |
|
| ||||||||||