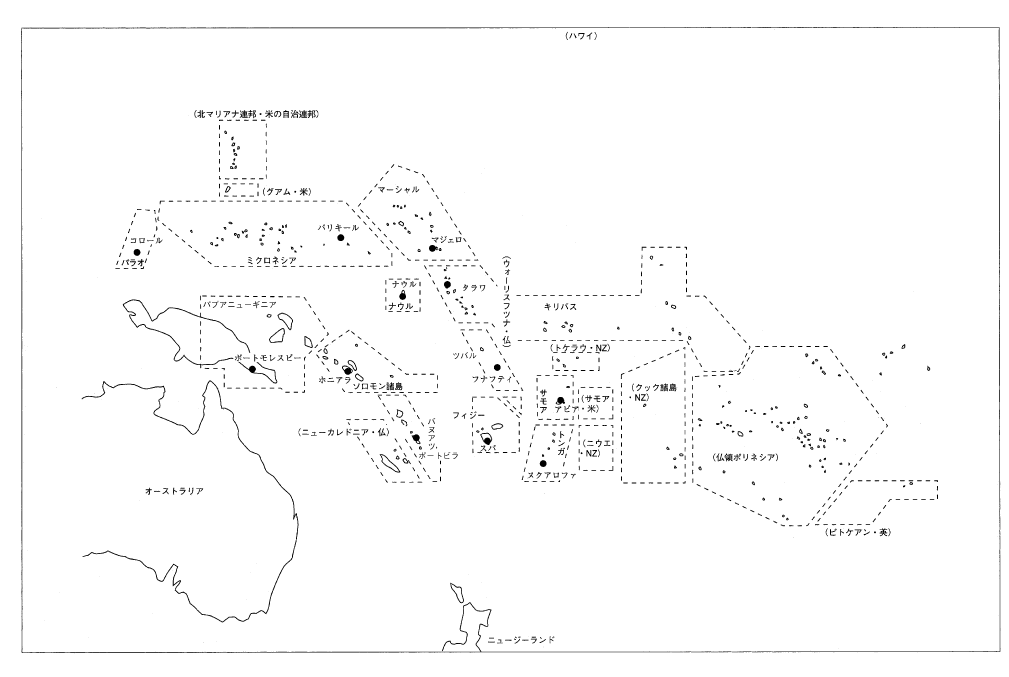西カロリン諸島からメラネシアにかけての西太平洋の諸国は、面積も比較的大きく、PNGの金、銅、ニューカレドニアのニッケルに見られるように地下資源に富む国もあり、比較的土地生産性も高い。これに対して、中部太平洋のミクロネシアからポリネシアにかけては火山島や珊瑚礁島が多く、火山島が比較的肥沃な土壌を形成し熱帯性農作物の栽培に適しているのに対し、珊瑚礁島は農作物等の生産性が著しく低いとの違いがある。
これら島嶼国の地場産業はその殆どが一次産品依存型であるため、国際市況価格の影響を受け易く、品質の面からも十分な競争力を備えておらず、経済的に脆弱である。そのため、総じて旧宗主国等による無償援助を中心とする各種援助、あるいは出稼ぎ労働者の本国送金に大きく依存している。雇用確保の見地から、行政部門の肥大化と硬直化が見られ、その財源を外国からの財政支援に依存する側面もある。また、独立後の歴史が浅いことから人材、経験の不足により政治・社会体制が十分に整備されていないことに加え、国土の拡散性、国内市場の狭隘性、国際市場からの地理的隔絶とこれを補完するための運輸・通信手段の不備、一部を除き天然資源に恵まれていないこと等から、多くの困難に直面している。
また、旧宗主国の「援助疲れ」により財政支援は大幅に削減され、従来の依存関係が薄れてきていることもあり、これら島嶼国は、外貨獲得手段の多元化を図るとともに、公共部門の縮小、貿易・投資・観光促進を通じた民間セクターの育成努力等新たな経済運営を強いられている。
我が国政府の大洋州地域との関係は、第一次大戦時より第二次大戦終了までのおよそ30年にわたるミクロネシアの委任統治に始まる。その後も島嶼国の独立に伴い、友好協力関係を推進してきている。また、広大な漁業水域を有するこの地域は我が国遠洋漁業にとり伝統的な漁場である。更に、近年に至り、これら地域諸国の対日期待感の高まりに伴い要人等の交流も活発化しており、関係は一層緊密化しつつある。
また我が国は、大洋州諸国で構成される「太平洋諸島フォーラム(PIF)や環境分野における地域協力の枠組みである「南太平洋環境計画(SPREP)」等の地域機関との協力も進めている。2003年5月には第3回日・PIF首脳会議(太平洋・島サミット)を沖縄において開催した。右サミットにおいては、小泉総理及びガラセPIF議長(フィジー首相)が共同議長となり、PIF各国・地域首脳の出席を得て
同首脳宣言は、以下のとおり五つの重点政策目標と重点分野を骨子として、我が国とPIFとの共同行動志向型の内容となった。
重点政策目標
・国連ミレニアム開発目標
・「人間の安全保障」や「平和の定着」
・PIF諸国が合意した地域政策の枠組み
・他のドナー国・機関や市民社会との協力
重点分野
・地域の安全保障の強化
・より安全で持続可能な環境