これら地域の諸民族は古代に独自の王朝を築いたり(ルーマニアのダキア王国)、中世に大国を築いた(リトアニア公国、ポーランド王国、ハンガリー王国、ブルガリア王国)ものもあるが、近世に至ってはロシア帝国、ハプスブルグ帝国、オスマントルコ帝国の影響下の被支配民族の立場におかれた。第1次世界大戦後のベルサイユ体制で、中・東欧諸国は民族自決の原則の下、一時的に独立を勝ち取ったものの、第2次世界大戦後にはソ連の影響下におかれた。アルバニア、ユーゴ等のようにソ連と一線を画した独自路線を取る社会主義諸国も存在したが、総じてソ連と共に共産圏の一翼を担った。
これら諸国は、長い列強の支配にもかかわらず、ほとんど全ての国が民族独自の言語を有し、それに応じた独自の文化を保有している。宗教的に見ても同地域にはカトリック、プロテスタント、東方正教会系、イスラム教の他、東方帰一教会(グレコ=カトリック)等多種多様である。
(2) これら諸国は政治面では、89年の民主化以降、一般に、欧州への回帰を目指し、政治・経済面で欧州への統合を目指す政策をとり、また、安全保障面では、欧州にとどまらず米国との関係を重視する政策をとる国が多く、進捗状況に差違はあるものの、各分野の改革を早急に進めている。これらの政策は、具体的にはNATO及びEUへの加盟を目標とする政策となって現れる例が多い。また、経済面では、市場経済化を目指す過程で移行経済特有の経済の落ち込みや混乱を記録したが、ポーランド、ハンガリー、チェコを中心に海外直接投資の累積が進み、またEU加盟に向けた制度改革の進展により着実に経済水準が向上している。
表―1 欧州諸国の人口、一人当たりGNP及び我が国との関係
図―1 欧州地域
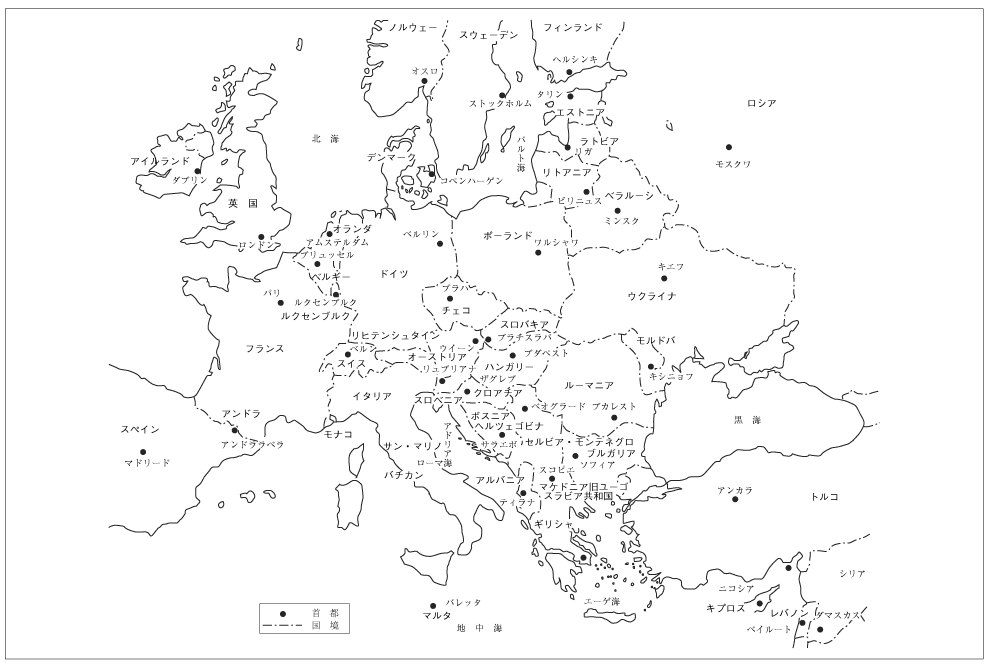
コソボ地域においては、90年にアルバニア系住民が住民投票を経て「コソボ共和国」として独立を宣言したことを契機に、ユーゴスラビア・セルビア側は、コソボ州議会の解散、自治権剥奪等弾圧を強めた。その後、ユーゴ・セルビア当局とアルバニア系住民の対立が続く中、98年2月、セルビア治安部隊とアルバニア系のコソボ解放軍(KLA)の間で武力衝突発生を境に紛争が激化し、ユーゴ連邦軍も介入した。これに対して国際社会は外交努力を行うも、ユーゴ政府が和平案を受け入れず、コソボにおける人道的惨事が発生する可能性が高まったとして、99年3月、北大西洋条約機構(NATO)がユーゴを空爆した。その結果、99年6月にユーゴ政府は和平案を受諾し、国連安保理決議1244が採択され、武力紛争が終結した。武力紛争終結後、コソボでは上記決議に基づき、民主的な多民族社会に基づく実質的自治を構築するために、民生部門を担当する国連コソボ暫定行政ミッション(UNMIK)と軍事部門を担当する国際安全保障部隊(KFOR)の下で和平履行がすすめられる一方、現在、UNMIKが有する権限の一部を2001年11月の議会選挙を経て成立したコソボ暫定自治政府諸機構(PISG)に委譲する作業も行われている。
ボスニア・ヘルツェゴビナでは、92年4月、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国(旧ユーゴ)からの独立を巡ってムスリム系、クロアチア系、セルビア系住民の間で大規模な紛争が勃発し、各民族がボスニア全土で覇権を争って戦闘を繰り広げ、その結果死者20万、難民・避難民220万と言われる戦後欧州で最悪の紛争となった。その後、95年12月、デイトン和平合意の成立により戦闘は終息し、ボスニアはムスリム系、クロアチア系住民を主体とする「ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦」、セルビア系住民を主体とする「スルプスカ共和国」という2つのエンティティから構成される一つの国家となった。現在、上級代表事務所(OHR)、NATO中心の多国籍部隊SFORがそれぞれ民生面及び軍事面での和平履行を担っている。
クロアチアにおいては、80年代末の東欧諸国の民主改革が進む中、90年4月、戦後初めての複数政党制による選挙が実施され、それまで政権にあった共産主義者同盟が敗退、民族主義的傾向の強いクロアチア民主同盟(HDZ)が圧勝し政権の座についた。新政権設立後、90年12月に民族主義的性格の濃い新憲法が採択され、ユーゴスラビア連邦離反の動きは加速した。91年5月、独立を問う住民投票で94%が旧ユーゴからの独立を支持し(セルビア人はボイコット)、議会は独立宣言を採択。これをきっかけにセルビア人勢力との間で戦闘となった。92年1月に一旦停戦合意が成立し、国連保護軍が展開するなか、欧州諸国を皮切りに各国がクロアチアの国家承認を行った(但し同停戦合意は守られず、その後も多数の停戦合意がなされたが戦闘は96年初頭まで継続した)。95年、クロアチアはセルビア勢力より国土の一部を回復、残された東スラボニア(クロアチア北東部)では96年から国連暫定統治機構による統治が行われたが、右が98年1月に撤退したことにより、クロアチアは全領土に主権を回復した。
マケドニアでは、2001年2月頃、アルバニア系住民の地位改善を求めるアルバニア系過激派武装勢力との間で武力衝突が起こったが、同7月に停戦合意が成立し、8月にマケドニア・アルバニア両系政党間で政治合意が成立した。
また、ハンガリーでは、第1次大戦後にハンガリーの領土が解体されたことから、特に、スロバキアとルーマニアはハンガリー系少数民族の問題を抱えることになった。これら諸国の間では同問題がしばしば政治問題化することもある。
更に、バルト三国はソ連邦内の共和国であったことから、国内に少なからずロシア系少数民族を抱えており、特に、ラトビアでは、ロシア少数民族の割合が3カ国中最も大きいことから、ラトビア国籍の付与する基準がロシア側との間の懸案となっている。
(3) 我が国との関係
中・東欧、バルト及びNIS諸国地域に対し、我が国は欧州統合の深化と拡大を見越しつつ良好な関係の構築に努めている。冷戦終結後より、中・東欧地域の民主化・市場経済化のための支援を実施してきた他、近年では、チェコ、ハンガリー、ポーランドを中心に我が国からの直接投資も増加傾向にあるなど、これら諸国と我が国との関係は更に重要性を増している。
また、バルカン地域に対しても、我が国は、紛争後の国内復興のための援助を続けている。特に、