この地域には、近年飛躍的な経済発展を遂げてきた東南アジア諸国、市場経済の導入に取り組んでいる「移行国」であるインドシナ諸国やモンゴル、更に中国など、経済の発展段階が大きく異なる様々な国が混在しているが、特に近年、地域内における貿易、投資を通じた経済的な相互依存が進展している。世界銀行の「世界開発報告1998/99」によれば、1人当たりGNP年平均成長率(96~97年)でみると、低中所得国全体の平均が3.3%であるのに対し、東アジア及び大洋州地域の低中所得国の平均は、5.6%となっているなど(世界全体では1.8%)、先発ASEAN諸国やアジアNIEsを中心に、経済的に世界で最も活力ある成長を遂げていた。
しかし、97年7月のタイ・バーツ下落に端を発した東アジア地域の通貨・金融危機が発生し、これにエル・ニーニョ現象による干魃や森林火災等が拍車をかけ、この地域全域にわたる経済・社会混乱を生み出した。
これらの諸国においては、経済構造改革等の各国の自助努力や我が国を中心とした国際社会の支援により、通貨は安定を取り戻し、民間資金も再び流入してきた。落ち込んでいた実体経済も99年には輸出の増加や内需の回復により回復基調に転じた。
しかし、原油価格高騰、米国の景気減速、世界的なIT不況、一部の東南アジア諸国の政情不安定、通貨・金融危機の影響を受けた国々の国内金融制度改革の遅れに対する懸念といった種々の要因により、2000年下期以降、東アジア諸国の景気拡大テンポは急速に鈍化し、国際通貨基金(IMF)やアジア開発銀行(ADB)といった国際機関は、これらの国々の2001年の成長率見通しを累次下方修正している(例えば、IMFは、2000年10月時点では5.0%としていたASEAN4カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン及びタイ)の成長率見通しを、2001年5月には3.4%に、同年10月には2.4%に、同年12月には2.3%に下方修正した)。
表―1 東アジア諸国の人口、一人当たりGNP及び我が国との関係
図―1 東アジア地域
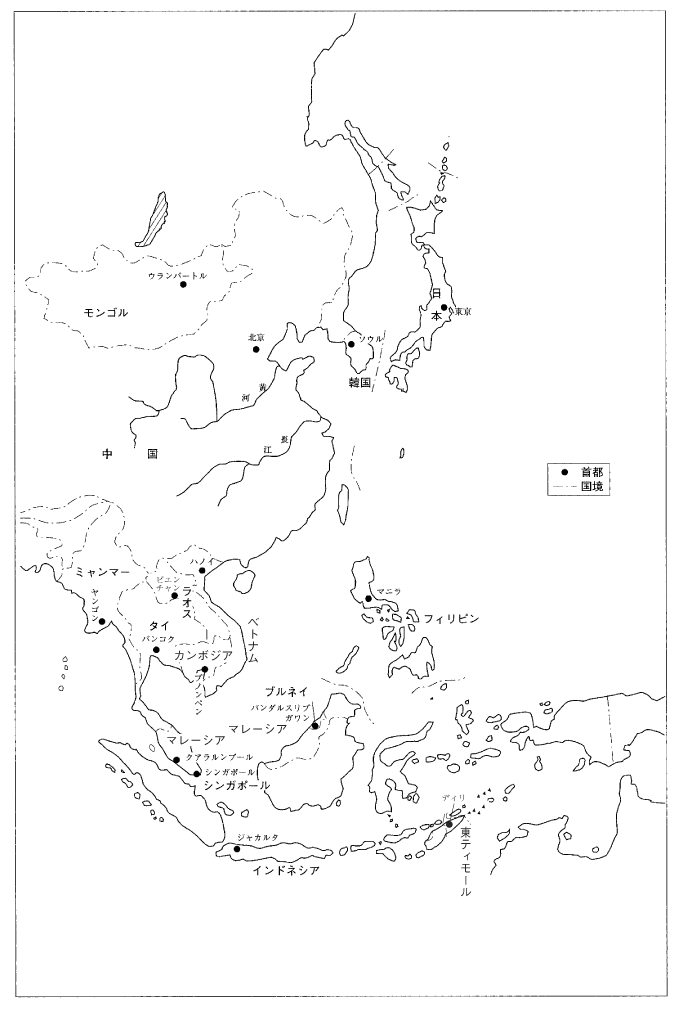
東アジア地域における地域協力に向けた最近の動きとして、97年に「ASEAN+3(日中韓)首脳会議」が初めて開催され、98年以降定例化されており、東アジア諸国間の対話が深化しつつある。2002年11月のASEAN+3(日中韓)首脳会議においては、「東アジアのあり方」について議論され、小泉総理から地域の格差是正のためにメコン地域開発ASEAN総合イニシアティブ(IAI)や、BIMP―EAGA(東ASEAN成長地域)への支援の重要性が表明されたほか、「人の交流・人材育成促進に関する有識者会合」の報告書が提出された。
更にASEAN+3(日中韓)の枠組みでは、財務大臣会議(99年4月)、経済閣僚会議・労働大臣会議(2000年5月)、外務大臣会議(同年7月)、労働大臣会議(2001年5月)、農林大臣会議(同10月)、観光大臣会議(2002年1月)、エネルギー大臣会議(同9月)及び環境大臣会議(同11月)がそれぞれ初めて開催され、東アジアにおける地域協力が拡大・重層化している。
ASEANについては、99年4月30日にカンボジアが第10番目の国として加盟し、創設32年目にして「ASEAN10」が実現した。ASEANは、90年代に入り、首脳及び閣僚レベルでの対話のスキームを維持・強化するとともに、域内協力も強化しつつある。97年には、アジア経済危機の深刻な影響下にありながら、総合的中期目標である「ASEANビジョン2020」が、また98年には同ビジョンの実現のための6カ年計画として「ハノイ行動計画」が策定され、現在、同計画に従い各種プロジェクトが推進されつつある。一方、これに先立ち、92年の第4回ASEAN公式首脳会議においては、域内の経済関係の強化を図るべく、「ASEAN自由貿易地域(AFTA)」の創設が合意され、これを受けてASEAN各国において域内貿易自由化、投資促進に向けた努力がなされている。なお、99年末の第3回ASEAN非公式首脳会議においては、同年9月のASEAN経済閣僚会議で合意した輸入関税撤廃の実現目標年を更に前倒しし、ASEAN原加盟国5カ国及びブルネイについては10年、新加盟4カ国については15年とすることが決定されている。また、ASEAN地域統合促進の観点から、2000年11月に開催された第4回ASEAN非公式首脳会議において議長国を務めたシンガポールのゴーチョクトン首相より、ASEAN域内の原加盟国と新規加盟国間の経済格差を是正し、ASEAN全体の競争力を高めることを目的としたASEAN統合イニシアティブ(IAI)が提唱され、その場でASEAN首脳の合意が得られた。ASEANとしては、長期プログラムであるIAIを進める上で、人材育成、情報通信技術(ICT)、インフラ及び地域経済統合の4分野を重点分野とし、現在73件が策定され、援助国・国際機関に対して支援を求めており、我が国としてASEAN側の主体的取組を評価しており、2003年12月に東京で開催された日・ASEAN特別首脳会議において発出された「東京宣言」及び「行動計画」において我が国はIAIの下での事業の実施を通じASEAN統合という目標の実現を支援する旨表明している。
また、ASEANは「ASEAN地域フォーラム(ARF)」の設立など積極的な外交イニシアティブを発揮している。96年には、シンガポールのゴーチョクトン首相(当時)の提唱に基づきアジアと欧州との関係強化を目的に「アジア欧州会合(ASEM)」が開催され、3月にバンコクで開催された第1回首脳会合を以て急成長するアジアと欧州が対等な立場で対話・協力を行う場ができた。98年4月に、ロンドンにおいて開催された第2回アジア欧州会合(ASEM2)ではアジアにおける金融・経済危機などについて意見交換が行われた。2000年10月にソウルで開催された第3回首脳会合(ASEM3)では、21世紀におけるアジアと欧州の協力のあり方、朝鮮半島情勢などについて議論された。2002年9月、コペンハーゲンで開催された第4回首脳会合(ASEM4)では、朝鮮半島情勢等の地域情勢、テロ対策、WTOなどの経済連携等について議論された。
我が国もこの地域の一員としてこれらの諸国との政治・経済・文化等あらゆる面で長年にわたる緊密な相互依存関係を保ってきている。
また、2002年1月のシンガポールにおける小泉総理の政策演説を踏まえ、2003年においては、日本ASEAN交流年2003を実施するとともに、12月には、東京において、史上初めてASEANの首脳が域外国に一同に会する日ASEAN特別首脳会議を開催し、これまでの協力関係を踏まえ、将来に向けての友好協力関係を規定する「東京宣言」を発出したほか、同宣言の別添として「行動計画」を策定した。また、同特別首脳会議の機をとらえて、ASEAN10カ国と二国間会談を実施し、タイ、フィリピン、マレーシアとの間で、包括的経済連携交渉の開始を合意した。
90年代に入ってのインドシナ情勢の安定化に伴い、メコン地域開発に対する国際的な関心が高まった。これを受け、95年の第5回ASEAN公式首脳会議(バンコク)においてメコン地域開発に積極的に参加していくことが合意され、96年6月に当時のASEAN7カ国とメコン河流域国(カンボジア、ラオス、ミャンマー、中国)による閣僚会議が開かれた。
我が国はメコン地域開発に従来より積極的に取り組んできており、地域全体の調和のとれた開発につき幅広い討議・意見交換を行う場として、95年2月にインドシナ総合開発フォーラム閣僚会合を東京で開催した。その後、流域各国は97年半ばに始まったアジア経済危機により大きく影響を受けたが、我が国は経済危機の時にこそ開発のモメンタムを維持し、将来展望を示すことが必要との観点から98年11月にメコン地域開発に関するワークショップを東京で開催し、開発戦略とプライオリティの明確化、広域開発のフラッグシップ・プロジェクトの推進等について流域6カ国、ドナー国・国際機関からの合意が得られた。更に99年4月には、流域の総合開発にかかる諸問題につき民間部門の認識を高めることを目的として、学界、関係国政府、国際機関、NGO、産業界よりオピニオンリーダーを招いて、メコン地域の総合開発に関するシンポジウムが我が国後援の下、バンコクにて開催された。
メコン地域の開発における「フラッグシップ・プロジェクト」として、インドシナ半島をベトナム東岸から東西に横断する「東西回廊」の整備が進められている。我が国は右回廊の運輸インフラ整備の主要部分を担っているほか、99年5月、ADBと協力して沿道地域の実体経済開発のための援助促進・調整の第一段階として東西回廊に関する会合を開催した。
最近では、2001年7月、流域4カ国(ベトナム、ラオス、タイ及びカンボジア)に派遣した政府ミッションの結果を踏まえ、同年11月の日・ASEAN首脳会議において、「東西回廊」の経済回廊化、「第2東西回廊」(バンコク―プノンペン―ホーチミン道路)の整備を今後の協力の柱とすることを表明した。その後、同月、タイのムクダハンにて開催された東西回廊に関する4カ国閣僚会合(タイ、ベトナム、ラオス及び日本)に、我が国より山口外務大臣政務官(当時)が出席し、東西回廊を含むメコン地域開発についての我が国の基本的考え方等について表明した。また、「東西回廊」を今後どのように「経済回廊化」していくかにつき情報・意見交換を行うことを目的として、我が国外務省、JICA、JBIC、アジア開発銀行(ADB)、越外務省が共催者となり、2002年12月16~17日にベトナムのダナンで「東西回廊」に関するワークショップを開催した。同ワークショップには、ベトナム、ラオス、タイ、ミャンマーという関係国の政府関係者に加え、隣国カンボジア及び他のASEAN加盟国、関心ドナー国・国際機関、更に地域の商工会議所を含む民間企業関係者が参加した。更に、ムクダハンにおける上記4カ国閣僚会合のフォローアップとして、本件ワークショップ直後の12月18日、同じくダナンにおいて、関係政府間での高級実務者会合(SOM)が行われた。