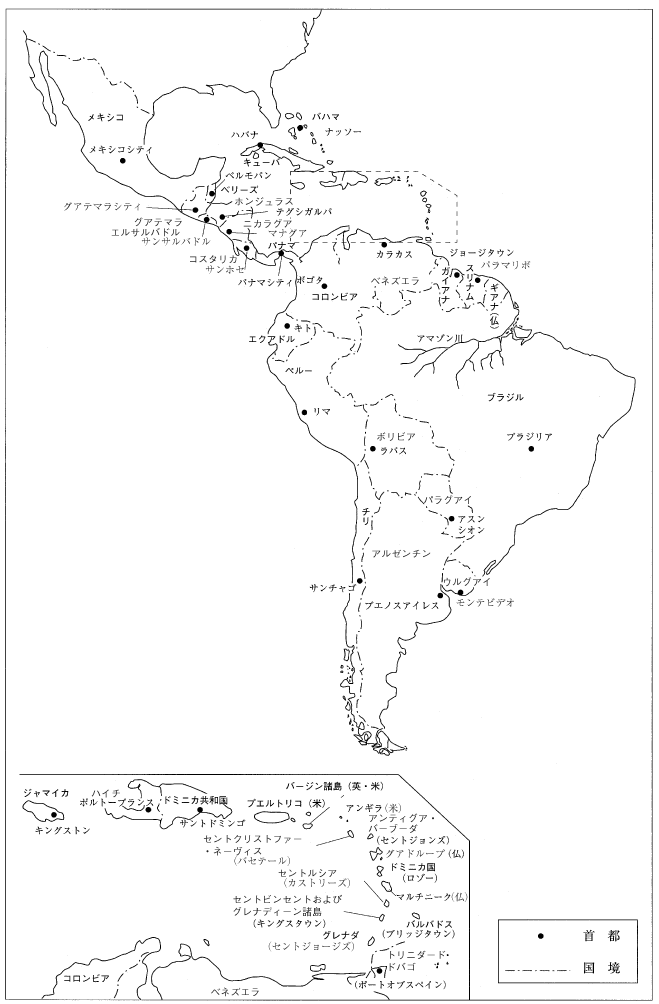中南米地域は、メキシコ、中米、カリブ諸島、南米大陸からなる地域で、世界地表面積の約15%を占めている。人口は約5億2,670万人(2002年、世銀)であり、その多くは、スペイン語、ポルトガル語圏である。33の独立国といくつかの外国領に分かれている。
中南米は赤道をはさんで南北に広がり気候風土は様々であるが、アンデス山脈の西側とアルゼンチン西部が乾燥地域である他は湿潤な耕作可能地域である。そのため農業生産力は豊かで、特にブラジルの中南部のサバナ・温帯地域、アルゼンチンのラプラタ川流域の温帯地域は一大農業地帯となっている。また地下資源も豊かで、鉄鉱石、銅、銀、ボーキサイト、スズ等を多く埋蔵するほか、原油・天然ガスも産出する。
このような豊かな天然資源を背景に、第一次産業及び鉱業は盛んであるが、鉱業を除く第二次産業及び第三次産業は、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン等の一部の国を除き依然として遅れている。多くの国は経済を一次産品及び地下資源の輸出に依存し、その基盤は脆弱である。世銀の分類では、中所得国に分類される国が比較的多く、一般に途上地域の中でも中進地域と位置付けられているが、多くの国で国内の所得格差が大きく、社会資本への投資不足もあり、深刻な貧困問題が存在している。加えて麻薬、環境等の問題もあり、中南米地域各国は依然として経済社会開発を必要としている。
中南米では、60年代以降軍事政権が相次いで登場したが、80年代初めより各国で民政移管が実現し、民主化が定着しつつある。94年にハイチの民政復帰が実現したことにより、現在では、ほぼ全ての中南米諸国が民主的政権を擁するようになった。
中南米の経済は、80年代に深刻な累積債務問題を抱え、「失われた10年」と形容された経済危機を経験したが、90年代に入り、中南米諸国は新自由主義的開放政策野本、貿易・金融の自由化、民営化等の経済改革を進め、その結果経済成長は91年から2000年までの年間平均成長率で3%強に改善し、慢性的な高インフレ率も概ね収束した。
こうした経済状況は、中南米に対する国際的信頼の回復と相まっており、その証差として、外国投資の流入があげられる。90年代を通じて、中南米は世界の開発途上地域中で東アジアと並ぶ外国投資先となっている。
2002年は世界的な経済成長の鈍化や、アルゼンチン金融危機等の影響を受け減速したものの、2003年は主要輸出産品価格の改善や世界経済回復を通じた需要増により、全体として緩やかながら回復基調にあり、1.5%の経済成長率が見込まれている。
現在、中南米地域においては、政治・経済両面における域内協力・域内統合の動きが活発である。政治面では、中南米主要18カ国により構成される「リオ・グループ」や、中南米33カ国、米及びカナダが参加し、我が国もオブザーバー参加している「米州機構(OAS)」等では、中南米諸国の民主化定着への貢献のほか、経済統合プロセス、軍縮・軍備管理等に関する意見交換等を行い、中南米地域の諸課題の解決に向け積極的に活動しており、域外国との対話の強化も近年益々盛んである。また、経済面では、現在中南米には、交渉予定のものを含め20以上の地域経済統合に向けたイニシアチブが存在する。代表的なものとしては、南米南部共同市場(メルコスール:ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ)、グループ3(G3:メキシコ、ベネズエラ、コロンビア)、アンデス共同体(ボリビア、コロンビア、エクアドル、ペルー、ベネズエラ)、中米共同市場(CACM:グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア、ホンジュラス、コスタリカ)及びカリブ共同体(カリコム:トリニダード・トバゴ、ジャマイカ、バルバドス等14カ国及び1地域)等がある。中でもメルコスールは、95年1月に関税同盟として発足し、その後チリ、ボリビア、ペルーの二カ国と経済補完協定を締結して準加盟国とし、アンデス共同体との間でも経済補完協定を締結したほか、現在EUと連合協定交渉を行い関係強化を目指している。近年は各地域統合の組織化(常設機関の設置)に加え、統合の拡大や他の統合体との自由貿易樹立へ向けた関係強化を図っている。さらに、94年12月にキューバを除く南北米州34カ国の首脳を一同に集め、マイアミで開催された第1回米州サミットにおいては、民主主義の強化や経済・社会開発の促進等の分野で広範かつ具体的な行動計画が採択され、南北米州全域を統一市場とする「米州自由貿易圏(FTAA)構想」が打ち出された。2001年4月にカナダのケベックにて行われた第3回米州サミットでは、2005年1月までにFTAA交渉を終了させ、同年12月までに協定を発効するとの合意がなされ、FTAA実現に向け大きく前進した。さらに2003年11月にマイアミで行われた閣僚級会合において、2005年1月までにFTAAを実現することが再確認された。また、99年6月及び2002年5月には中南米諸国及びEU諸国によるEU・ラ米サミットが開催され、両地域間の政治・経済両側面で協力の拡大を謳った。