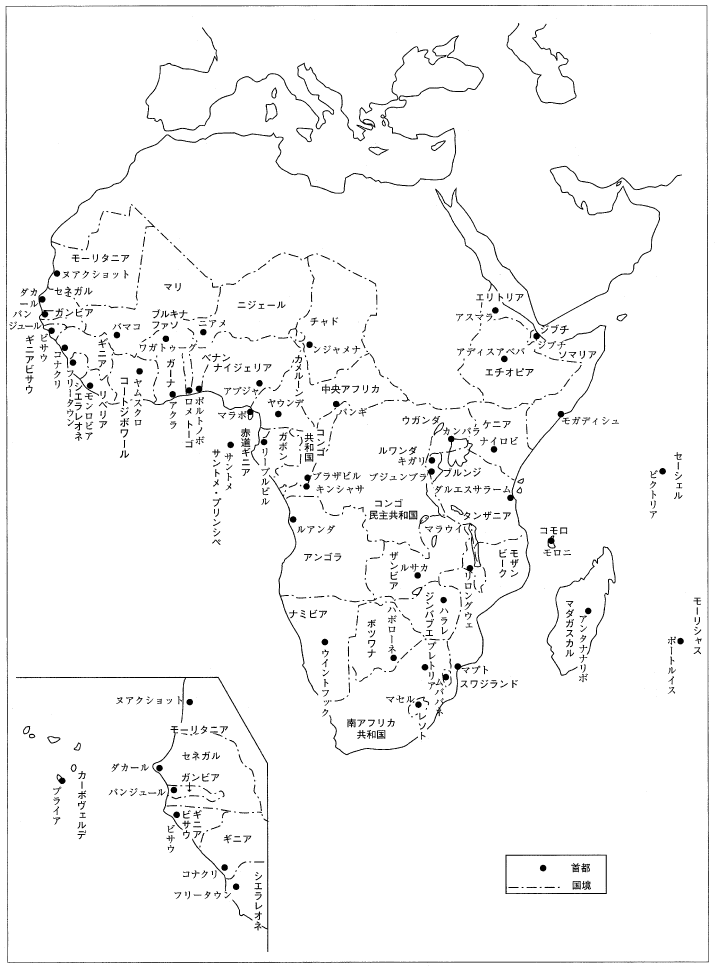(1) アフリカの地理的特色
アフリカ(注1)は、47カ国により構成される。同地域は、多様な気候分布を呈しているが、サハラ砂漠、カラハリ砂漠のような乾燥地帯やコンゴ河流域など高温多湿な熱帯雨林地帯などの自然環境が比較的多くの部分を占めているのが特徴である。
(2) アフリカの政治、経済及び社会状況
政治面では、80年代までは国家としての統一性を維持する観点から指導者の出身部族グループを中心とした一党独裁体制が少なからず見られていたが、90年代に入り、冷戦構造が崩壊する中、多くの国において、複数政党制への移行及び複数政党制の下での自由選挙の実施等、民主化の動きが主流となってきた。
同地域は、被植民地時代からの人為的な国境、国家基盤の脆弱性等を背景に、貧困、民族・宗教上の対立、経済利権、独立問題等の複雑な要素が絡み合い、世界でも最も多くの武力紛争が発生している。武力紛争の発生・継続に伴い、大規模な難民及び国内避難民の発生、エイズ等感染症の蔓延、武器・薬物の流入等が深刻な問題となっている。
経済面では、80年代以降、それまでの生産部門の低迷、公共セクターの肥大化、一次産品の国際市況の低迷等による経済の停滞を克服するとの観点から、市場経済原理導入を主眼とする世銀・IMF主導型の構造調整政策が多くの国で開始された。しかし、構造調整政策の実施は、緊縮財政政策、公務員の削減による失業者の増加、社会サービスの低下等から、特に社会的弱者に対するしわ寄せ(いわゆる構造調整の社会的側面)をもたらした。さらに、厳しい自然環境に加え、急激な人口増加と貧困等を背景に森林伐採と砂漠化が進行し、土壤の生産力低下が一層貧困に拍車をかけるといった悪循環が生じているほか、多くの国における主要産業である一次産品の国際市場価格が80年代後半以降低迷していることにより、アフリカの経済社会状況は依然厳しい。
同地域では、国連の認定するLDC(後発開発途上国)49カ国(2001年)のうち33カ国が存在する。2000年時点で一人当たりGNPが1,000ドルを超える国は8カ国(セーシェル、モーリシャス、ボツワナ、ガボン、南アフリカ、ナミビア、スワジランド、カーボベルデ)にとどまっている。
(3) 我が国との関係
我が国とアフリカとの間の貿易投資関係は全体として依然低調な状態にある。2001年の我が国の対アフリカ諸国輸出総額は44.3億ドル(前年比12.3%減)、輸入総額は45.4億ドル(前年比8.4%減)であり、我が国の総輸出額及び総輸入額のそれぞれ1.1%及び1.3%にすぎない。2001年度の我が国の対アフリカ直接投資は241億円であり、対外直接投資全体のわずか0.6%である。
他方、我が国は、アフリカが直面する諸問題の解決に貢献することは世界の平和と安定のためにグローバルな責任を有する我が国の責務であるとの観点から、アフリカ諸国の経済的困難の克服に向けた自助努力を支援するため、93年に開始した「アフリカ開発会議(TICAD)」プロセスを中心に、経済協力の推進、人的交流と相互理解の増進に加え、アフリカ開発に対する内外世論の喚起等に努力している。また、開発に深刻な影響を及ぼす紛争の問題に関しても、アフリカ諸国自身の紛争予防・管理・解決能力の強化のための協力に努めている。
2001年は、1月に森総理(当時)が現職の総理大臣として初めてサハラ以南のアフリカ(南アフリカ、ケニア、ナイジェリア)を訪問し、南アフリカにおいて、「アフリカ問題の解決なくして21世紀の世界の平和と繁栄はなし」との基本認識の下、我が国の対アフリカ協力の基本的考え方に関する包括的政策を打ち出した(注2)。
(注1) ここではサハラ砂漠以南のアフリカ地域を指す。ただし、スーダンを除く。以下同様。
(注2) 小泉総理は持続可能な開発に関する国際会議(ヨハネスブルグ・サミット)に出席するために、2002年9月に南アフリカを訪問し、前年の森総理(当時)のアフリカ訪問に続く、2年連続の総理大臣のアフリカ訪問となった。川口大臣もヨハネスブルグ・サミット出席の機会を捉え、我が国の外務大臣としては18年ぶりとなるアフリカ公式訪問を行い、8月26日から29日にかけてエチオピア及びアンゴラを訪問している。