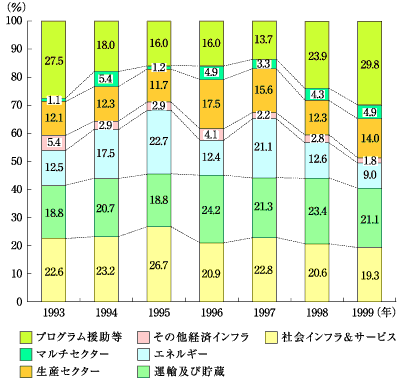(1) 協力の意義
現在、世界では約8億3,000万の人々(うち約7億9,100万人が途上国に居住)が飢餓や栄養不足に苦しんでいると言われている。多くの途上国では、急増する人口に食料生産が追いつかず、外貨不足から食料輸入にも困難を抱えている。また、経済発展の著しい途上国においても、肉類消費の拡大等、食生活の高度化により飼料用の穀物需要が増大し、食料需給への圧力が生じている。このほか、干ばつや洪水などの自然災害、紛争や内戦に起因する食料不足の問題等もある。このように、途上国の緊急を要する食料事情の悪化への対応や、途上国の中長期に亘っての安定的食料供給の確保は、国際社会が取り組むべき重要な課題の一つとなっている。
また、途上国の開発にとって重要な課題の一つに貧困削減があるが、途上国においては貧困人口の大半が農村地域に集中している。したがって、貧困問題の解決のためには、農業・農村開発が不可欠かつ最も有効な対策の一つであり、また同時に開発にとり中長期的課題である経済成長を達成するための最善の方途でもある。実際、97年から始まったアジア経済危機を通して、職を失った都市住民を農村が再び吸収するという緩衝機能も見直され、農業の重要性が再認識されている。このように、都市と農村との地域格差是正を図るとともに、地域住民の主体的な取り組みと農業資源の総合的な開発利用を促す上で、総合的な農業・農村開発への支援は極めて重要である。
更に、多くの途上国では、不適切な焼畑農業や灌漑管理・過放牧等の結果、森林資源の減少や土壌の劣化による作物収量の減少、砂漠化等の問題が発生している。農業開発に当たっては、
持続可能な開発会議(CSD)やODA大綱で掲げられた環境と開発と両立の視点を重視しつつ、持続可能な農業開発に向けた支援を実施していく必要がある。
96年には世界食料サミットが開催され、世界の食料安全保障の達成と栄養不足人口の2015年までの半減等が途上国の農業開発の目標の一つとされた(ローマ宣言)。また、98年10月に開催された第2回
アフリカ開発会議(TICAD―

)で採択された「東京行動計画」においても、優先的行動計画の一つとして農業開発が合意されている。
(2) 協力の現状と今後の課題
近年、食料・農業分野において日本は、食料不足や栄養状態の改善のみならず、農村地域の総合的な開発や環境保全型農業の推進に向け、多岐に亘る協力を実施している。
例えば、有償資金協力については、98年度よりタイで実施されている「地方開発・雇用創出農業信用事業」において、農業・農業生産活動の効率化、農産物の品質向上、植林の促進、環境保全型農業の推進を行うとともに、農業協同組合銀行(BAAC)を通じて地方の小規模農民にサブ・ローンを供与している。これによって、地方の小規模農民の所得向上、植林事業による森林面積の拡大、環境保全型農業の推進のほか、女性の就業機会を含む新たな雇用創出が期待されている。
また、無償資金協力については、99年度に実施したインドネシアの「東部地域灌漑施設整備計画」等で主に施設・機材の供与を行ってきている。
そのほか、プロジェクト技術協力では、98年度までインドネシアで実施された「南東スラウェシ州農村総合開発計画」において、農業・農村総合開発計画の策定や基盤整備、営農技術等の指導・訓練等を行い、農家所得の向上や村の活性化を図るとともに、持続可能な農業・農村開発に必要な地方行政職員及び中核農民の能力強化を行った。また、農民組織(農協等)を強化するための技術支援等も実施されている。
今後政府としては、昨年8月に公表された「ODA中期政策」を踏まえ、

生産資機材の供与や灌漑施設の建設のほか、市場へのアクセスに資するインフラ整備や流通管理のための協力の推進、

品種改良等農業技術や漁業技術の向上とその効果的な普及のための支援、

農業技術等の普及や農業用水・水産資源の管理に関する住民の組織化や行政能力向上への配慮、

緊急非常事態の対処手段として重要な食料支援の適切な活用、に努めることとしているが、近年、特にアフリカを中心とした援助の流れとして、貧困削減戦略ペーパー(PRSP)やセクタープログラムアプローチ等援助国間のセクター開発における援助協調、パートナーシップ等を求める流れがある中で、我が国もそれらの流れを踏まえつつ今後の援助の方向を検討していく必要がある。
(1) 協力の意義
教育を受けることは、それ自体が基本的人権の一部であると同時に、人口増加の抑制、女性の地位
向上、民主主義の基礎ともなるものである。人造りは国造りの基本であり、基礎教育水準の向上は、途上国の開発に必要な人材育成にとっての鍵である。
一方、途上国では、未だに1億1300万人以上の子供たちが基礎教育を受けられず、約8億8,000万人の人々が読み書きできない状況にある。例えば、96年における初等教育の就学率は、ブルキナ・ファソで32%、エリトリアで29%であるなど、特に低所得国、サハラ以南アフリカ諸国における教育の普及の遅れは著しい。また、中途退学者が多いという問題も指摘されている。
教育分野での協力は、途上国の人造りを通じて、他の分野での協力の効率を高めるとともに、日本語教育、留学生交流を通じて日本の文化に対する関心を深め、相手国との友好関係の促進につながる重要な意義を有する。
国際社会においても、近年、開発の文脈において、途上国における教育、人材育成に大きな関心が寄せられている。これはDAC「新開発戦略」で、全ての国における2015年までの初等教育の普及や2005年までの初・中等教育における男女格差の解消を開発目標として掲げていることにも表れている。
また、本年4月にダカールで開催された「
世界教育フォーラム」では、90年にタイで開催された「
万人のための教育会議(Education for All)」において決議された初等教育の普遍化、男女就学率格差是正等の開発目標の進捗状況の評価が行われ、同目標を達成するための今後の方針が「
ダカール行動枠組み(Dakar Framework for Action)」として採択された。
(2) 協力の現状と今後の課題
日本としても「ODA中期政策」において掲げられた重点課題「貧困対策や社会開発分野への支援」の中で、基礎教育の重要性、途上国における女性支援の視点の重視を掲げており、教育(特に基礎教育)分野重視の姿勢を打ち出している。例えば、無償資金協力においては、基礎教育分野での関連施設建設等(学校建設の他、「日本・ラオス人材協力センター」の建設等)への支援を中心に、放送教育の拡充や教員の養成・再教育等にも協力分野を広げている。また、99年度に創設された留学生無償資金協力を通じ、初年度は2ヶ国からの日本への留学生を支援した。草の根無償資金協力を通じては、現地事情に精通したNGOとも連携しつつきめ細かな援助が行われている。さらに、98年10月に開催された第2回
アフリカ開発会議において、日本は教育・保健医療・水供給の分野に対し、向こう5年間で、約900億円の無償資金協力を目指すことを表明し、開発調査等を実施し、2000年10月までに127.87億円の無償資金協力が実施されている。
技術協力においては、プロジェクト方式技術協力、青年海外協力隊による教育分野の実績が多く、特に、青年海外協力隊の活動は、児童のほか教員も対象にしており、これまで相手国から高い評価を得ている。
有償資金協力においては、近年、教育関連施設拡充や人材開発を目的として円借款を供与してきている。98年度には、マレイシアにおける東方政策を、99年度には、フィリピンでの貧困地域中等教育計画をそれぞれ支援した。また、留学生支援についても、引き続き円借款等を通じた協力が行われてきている。
その他、国連教育科学文化機関(UNESCO)等の国際機関とも連携を取りつつ、就学率や識字率の向上のための支援を実施している。
これら教育分野における協力は、他の分野における協力以上に相手国の自助努力が基本となることから、相手国の自主性及び相手国特有の社会的・文化的背景への配慮が不可欠である。また、教育開発の段階は国毎、さらには地域毎に異なるため、日本としては、相手国側と密接な政策対話を行い、現地のニーズを的確に把握した上で、地域の事情に合った現実的な援助を行っていくことが必要である。
今後政府としては、ODA中期政策を踏まえ、

校舎・資機材に関するハード面での協力のみならず、学校運営等の組織・能力強化への支援、カリキュラム・教材開発、教員教育など教科教育・教育行政両面にわたるソフト面での協力強化を図り、

女子の基礎教育支援を重視するとともに、

開発の主体である住民への啓蒙活動や、協力案件の実施において住民参加を進めるため、青年海外協力隊の活用や民間援助団体(NGO)との積極的な連携を図っていくこととしているが、近年、特にアフリカを中心としたセクター別の援助協調の流れ(セクター・ワイド・アプローチ(SWAPs)、コモンファンド、ハーモナイゼーション等)も踏まえつつ、教育分野への我が国援助の方向性を検討していく必要がある。
(1) 協力の意義
途上国において貧困削減や社会開発を推進するためには、持続的経済成長の達成が不可欠の前提条件であり、これを下支えするのが運輸基盤を含む経済・社会インフラである。
運輸基盤の未整備は、人口集中が進む大都市圏での交通渋滞を深刻化させるのみならず、地方での生活必需品の輸送並びに住民の教育や医療等サービスの享受に悪影響を与えているほか、環境の劣化や都市・地方間での格差拡大の原因ともなっている。
途上国における効率的な運輸基盤整備への支援は、物流輸送の合理化や、産業開発・雇用創出、人口の分散、地域間格差の是正や地方における貧困削減、さらには環境の保全に資するものである。
(2) 協力の現状と今後の課題
運輸分野においては、道路、鉄道、空港、港湾等のインフラ整備に見られるように大規模で、かつ経済的効果の高いものが多く、有償資金協力(円借款)の比重が高い(99年については運輸分野全体の約8割以上を占める)。また、この分野では、運輸関連の工場整備や、教育・訓練施設の建設といった資金協力に加え、総合交通計画策定等に対する技術協力など幅広い協力を実施している。
ODA中期政策においては、経済インフラ整備の実施に際し、貧困地域や貧困層に利益が及ぶよう配慮するとの協力の在り方を明示している。運輸分野の円借款案件についても、従来は幹線道路整備への支援が中心であったが、近年では地方貧困地域へのアクセス道路の整備等の協力が拡大している。また、特にある程度経済的発展を遂げた途上国については、インフラ整備それ自体ではなく、運輸分野の政策策定・実施や運営の支援といったよりソフト面の支援に移行しつつあるが、今後より一層メリハリの効いたODAを実施していく必要がある。
この分野での課題としては以下の点がある。
(イ) マスタープラン策定等への協力
運輸基盤の整備は途上国の経済構造や国土利用形態を決定する鍵となる。特に、都市部における交通渋滞や交通安全状況は先進国以上に深刻であるほか、地方における交通網整備の遅れは、効率的な経済発展達成の障害となっている。途上国における交通網整備への支援に際しては、正確な現状把握に基づくマスタープランの策定と、これに沿った適切な案件の形成・実施が肝要である。
この関連では、98年度にフィリピンに対し供与された「幹線道路網整備事業(

)」が具体例として挙げられる。同事業は、国土のバランスのとれた発展と物流効率化による地方経済の発展のため、南北を結ぶ日比友好道路に加え、東西を連結するボンガボン・バレル道路、更に島嶼部の周回道路の整備を行うものである。また、99年度には「日比友好道路修復計画(

)」の供与が決定されており、ミンダナオ島をはじめとする地方経済の活性化に寄与することが期待される。
(ロ) 広域インフラに対する協力
途上国への協力の一形態として複数国に裨益する広域協力があり、特に運輸インフラには広域的性格を有するものが少なくない。例えば、近隣諸国に跨る交通網整備への協力は、地域全体での貿易投資の促進等経済・社会開発上の裨益効果が期待し得る。
日本は、現在、アジア開発銀行(ADB)と共同でインドシナ地域での道路網整備を支援しているほか、南部アフリカ開発共同体(SADC)等との連携を通じ、この地域での広域インフラ整備を支援している。特に無償資金協力により実施される「チルンド橋建設計画」は、SADC加盟国たるザンビアとジンバブエの国境を繋ぐものでありSADC域内全体の経済発展に寄与することが期待される。
(ハ) 民活インフラ支援
急速な経済成長を実現する途上国ではインフラ需要も急増しており、これをまかなうためには途上国自身の資金や先進諸国からの公的援助のみでは対応が困難である。近年では、民間資金の導入によるインフラ整備への取り組みが活発化しており、政府としても、これらの民間インフラ整備が円滑かつ適切に進展するよう積極的に支援することとしている。例えば、タイの「バンコク地下鉄建設事業」(第

期)では、政府が路線等のハード面を整備し、運用等のソフト面を民間等が行うという、新たなスキームを導入している。
(二) 環境への配慮
道路や橋、鉄道、空港などの経済インフラ整備は、持続可能な経済発展のための経済体質の強化や貧困格差と地域格差の是正のために重要であるが、この分野での支援を行うに当たっては、同時に環境への配慮を行うことが不可欠である。そのため、日本は環境への影響が大きい案件に円借款及び無償資金協力を行う際に開発調査の段階で環境影響評価(EIA)を実施している。具体的には、国際協力銀行(JBIC)及び
国際協力事業団(JICA)がそれぞれ策定した「環境配慮のためのガイドライン」に基づき、個別案件における事前評価を実施するとともに、専門家を活用した途上国自身のEIAの実施や行政能力の向上を支援している。