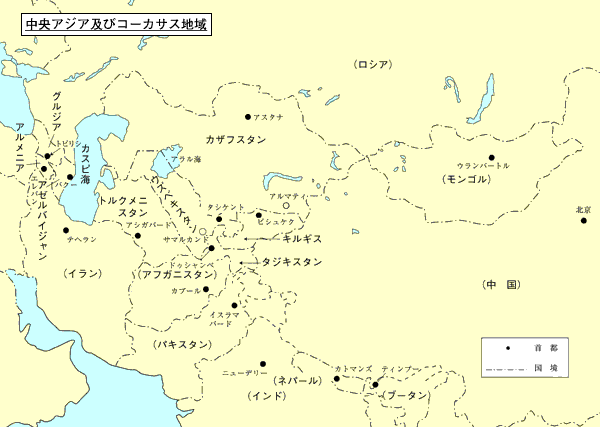(1) 中央アジア(ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン)及びコーカサス(アゼルバイジャン、アルメニア、グルジア)地域は、ユーラシア大陸のほぼ中央部に位置し、古くからステップ遊牧民とオアシス定住民とが独自の文化をつくってきた。1917年のロシア革命後、同地域はソ連の共和国となり、現在の国境は1924年にほぼ決定した。80年代半ば以降、ソ連のペレストロイカとともに民族主義の気運が高まり、各共和国は91年12月のソ連解体に伴い、独立を果たした。
両地域は、面積約420万平方キロメートル、人口7,000万人を擁する。ロシア人の比率はカザフスタン及びキルギスにおいて高く(各々30%及び13%)、他国は10%以下である。中央アジア5カ国においては、言語はロシア語も使用されているが、タジキスタンはペルシャ語系言語、他の4カ国はチュルク(トルコ)語系言語を公用語としている。また、宗教はすべてイスラム教スンニー派であるものの、政治と宗教は分離している。コーカサス3国においては、民族、言語、宗教とも各国で異なる。アゼルバイジャンはアゼルバイジャン人が83%、公用語はチュルク語系のアゼルバイジャン語、宗教はイスラム教(シーア派)、アルメニアはアルメニア人93%、公用語は印欧語系のアルメニア語、宗教はキリスト教(アルメニア教会)、グルジアはグルジア人70%、公用語は独立の地域言語であるグルジア語、宗教はキリスト教(グルジア正教)及びイスラム教(スンニー派)が主流となっている。
(2) 中央アジア及びコーカサス地域諸国は、いずれもCIS(独立国家共同体)の一員として、ロシアをはじめとする旧ソ連諸国との結びつきが極めて強いほか、近隣諸国であるトルコ、イラン、中国等との関係も強化しつつある。また、中央アジア諸国は一般的にイスラム過激派の浸透と民族紛争の拡大を懸念しており、この地域の安全と安定についてロシアと共通の利害を有している。こうした観点から、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタンは、共同軍事演習などでロシアと共に安全保障面での協力を続けている。
コーカサス3国においては、アゼルバイジャンとアルメニアのナゴルノ・カラバフ紛争、グルジアにおけるアブハジア紛争及び南オセチア紛争等の民族紛争が存在し、現在、沈静化しているものの、未解決である。
(3) 経済的には、国家計画経済から市場経済への移行に伴う混乱が各国の経済に大きな影響を与えており、生産の落ち込み、インフラ老朽化等、課題は多い。一部の国では市場経済化の改革努力がマクロ面を中心に95年頃から一定の成果を上げ、経済成長率がプラスに転じるなどの変化が見られていたが、現在もロシア経済に大きく依存している国が多いため、98年夏に発生したロシアの金融危機に際しては、対外収支悪化等により国内経済への波及がみられた。99年には、カザフスタンでは石油価格が持ち直したこともあり、経済の回復が見られたが、キルギスでは依然として厳しい経済情勢が続くなど、各国の経済状況は益々多様化している。
中央アジア5カ国はソ連崩壊後、世銀・IMFへの加盟を果たし、また欧州復興開発銀行(EBRD)の加盟国としての地位を旧ソ連から承継している。更に、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタンはアジア開発銀行(ADB)にも加盟を果たしており、これらの機関による融資が可能となっている。
(4) カザフスタン、キルギスは96年にベラルーシとともに統合強化条約を締結したが、具体的進展は見られていない。また、自由貿易圏構想、関税同盟、中央アジア経済共同体など、様々な域内協力の枠組みが設立ないし検討されているが、実質的な協力は進展していない。また、99年4月、アゼルバイジャン、ウズベキスタン、グルジアは、CIS集団安全保障条約から離脱したが、中央アジアでは、イスラム過激派の浸透に対する警戒もあり、新たな安全保障体制の構築も模索されている。
(5) 我が国との関係は総じて良好であり、92年4~5月に渡辺副総理兼外務大臣(当時)がカザフスタン、キルギスを訪問し、99年5月に高村外務大臣がウズベキスタン及びアゼルバイジャンを訪問している。中央アジア諸国からは大統領、首相クラスの訪日が相次いでおり、99年12月カザフスタンから大統領が訪日した。またコーカサス地域からは、98年2月アゼルバイジャンから、99年2月グルジアから、それぞれ大統領が訪日している。