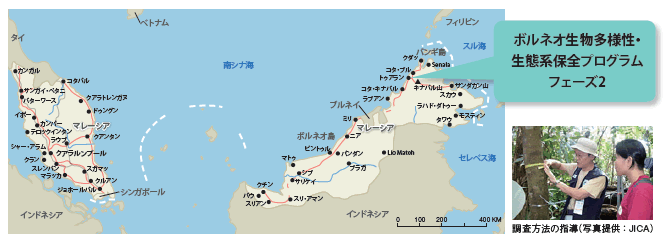囲み 1 自然環境保全分野の日本の取組~2010年国際生物多様性年に向けて~
地球上には、3,000万種ともいわれる多様な生き物が暮らしています。私たち人間もこの多様な生物から構成される大きな生態系の一員であり、そこから多くの恩恵を受けながら生きています。しかし、人間の活動により、生態系の破壊、生物種の減少が進行し、2005年に発表された「国連ミレニアム・エコシステム評価」においては、生態系がもたらす恩恵の劣化は、今世紀前半の間に顕著に増大することが予測されています。
生物の多様性の保全とその持続可能な利用などを目的とした国際的枠組みとしては、1992年5月に採択された生物多様性条約があります。この条約は、同年6月にリオ・デ・ジャネイロ(ブラジル)で開催された国連環境開発会議(UNCED、地球サミット)で署名開放され、1993年12月に発効しました(2009年9月現在190か国および欧州共同体が締結)。2010年は「国際生物多様性年」に指定されており、世界各地で生物多様性保全に関する多くの行事が開催される見込みですが、日本では、同年10月に生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が愛知県名古屋市で開催されます。
また、日本が2002年に発表した「持続可能な開発のための環境保全イニシアティブ」では、自然環境保全を政府開発援助(ODA)を中心とした環境協力の重点分野の一つとして位置付けています。さらに、2005年に策定した「政府開発援助に関する中期政策」においても、自然保護区の保全管理、森林保全・管理などの自然環境保全を重点課題の一つとしており、これらに基づいて、ODAを通じて、開発途上国における生物多様性の保全および持続可能な利用を支援しています。支援の具体例としては、パラオにおける「国際サンゴ礁センター強化プロジェクト」や、マレーシアにおける「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム」などがありますが、ここでは、マレーシアのプログラムの概要を紹介します。
マレーシアのサバ州には世界的に多様な生態系が見られますが、伐採やプランテーション開発により熱帯雨林が急速に減少しており、加えて保護区の面積率も低いことから、近年絶滅危惧種が多くなっています。このため、日本は2002年2月から2007年1月まで「ボルネオ生物多様性・生態系保全プログラム」(フェーズ1)を実施しました。具体的には、サバ州政府やサバ大学を主なカウンターパートとして、研究教育、州立公園管理、野生動物生息地管理、環境啓発の4つを有機的に組み合わせ、貴重なボルネオの生物多様性・生態系を持続的に保全するための活動を実施しました。また、現在実施中のフェーズ2においては、フェーズ1で行った保全活動の成果をもとにし、サバ州における行政制度としての生物多様性・生態系保全体制を確立し、強化することを目指しています。
COP10では、2010年以降の目標(ポスト2010年目標)が決定されることとなっています。2010年以降の取組に関する議論のなかでは、希少種の保護や、保護地域の管理などの直接的な自然保護の分野だけでなく、農林水産業などの活動において持続可能な生産を行う、社会資本の整備に当たって生物の生息域を創出するなど、幅広く生物多様性の保全に向けて取り組むことが重要な課題となっています。また、開発援助においても、この生物多様性の主流化の流れを踏まえて、幅広い分野で生物多様性に配慮した支援が必要であるとされています。
来るCOP10のホスト国となる日本は、今後、自然環境保全分野で一層のリーダーシップをとるとともに、様々な開発援助において、生物多様性に配慮した展開をすることが期待されています。