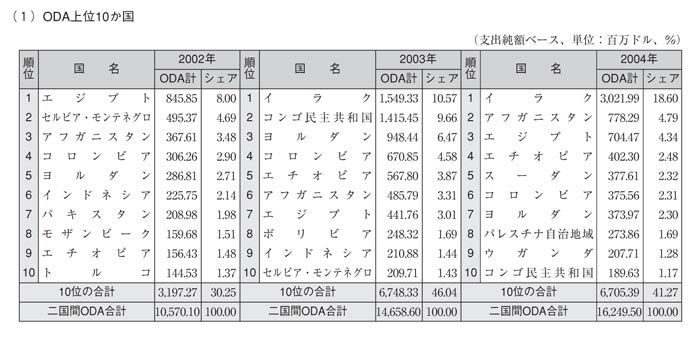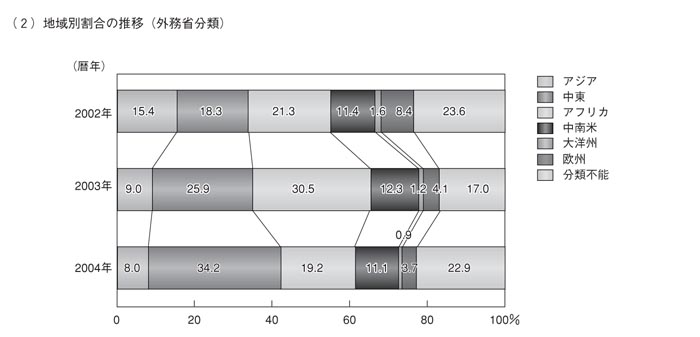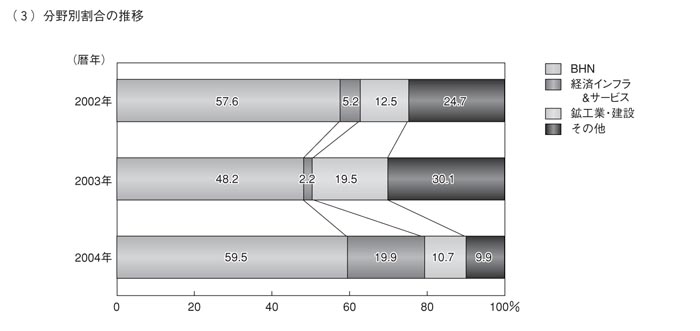資料編3,4,5章 > 第4章 > 第2節 > 1 米国
第2節 主要援助国・機関のODAの概要
1 米国
(1)援助政策等
(イ)米国では、8年間にわたる民主党政権に代わり、2001年に共和党のブッシュ大統領が就任し、同年春頃から共和党色の強い新政策が次々と打ち出された。さらに、同年9月11日に発生した同時多発テロもあり、2002年3月には開発援助50%増を打ち出すなど、米国の援助政策は大きく変貌することとなった。
(ロ)新政権がまず着手したのは、国際開発庁(USAID:United States Agency for International Development)の再編である。ナツィオスUSAID長官(当時)は2001年4月に米上院で承認を求める際の証言で、USAIDが国務長官に報告し指示を仰ぐと述べ、援助を外交目的のため実施するとの方針を明確に示した。
(ハ)同長官は、同年5月の上院証言では、USAIDの「4つの柱」(援助の実施方法の柱としての「グローバル開発アライアンス(GDA)」、そしてプログラムの柱としての「経済成長と農業」、「グローバル保健」、「紛争予防と開発救援」から構成)を発表した。これは、外交政策のツールとしての自らの効果を高めるため、主要な活動目的と方法とを明示し、既存の予算項目を横断する形で柱を提示することとしたものである。さらに、組織面でも、これらの柱に応じた形で部局が再編され、政策立案を担う局に予算調整権限を与えてその機能を強化すると共に、GDA事務局及びプログラムの柱に相当する3つの局が新設された。
(ニ)同年7月、ブッシュ大統領は、世界銀行本部での演説において、国際開発金融機関による最貧国支援のグラント部分を50%まで引き上げること、及びそれを教育、保健等の分野に振り向けることを提案した。そして、国際開発協会(IDA)13次増資交渉で米国は強硬姿勢をとり、欧州と対立した(結局、本問題は2002年7月にグラント化率を全体の18~21%とする方向で決着した)。
(ホ)また、同時多発テロの結果、米国はテロとの闘いを多方面で強力に展開することとなったが、これは貧困と開発の問題に対する米国の認識と政策に深い影響を与えることとなった。2002年3月、ブッシュ大統領は、モンテレイでの開発資金国際会議開催前の米州開発銀行本部での演説で、「開発のための新たな約束」と名づけられる新たなイニシアティブを発表した。この主要点は以下のとおり。
[1]今後3年度内(2004年度から2006年度まで)に、米国の開発援助を50%増額し、最終的に年額50億ドル増の水準に到達させる。
[2]この増額分は、「ミレニアム挑戦会計(MCA:Millennium Challenge Account)」という新たな特別会計とされ、良い統治、人材育成(保健・教育)、健全な経済政策という3分野での強いコミットメントを示した国に配分される。国務長官と財務長官は、国際社会と対話しつつ、これら3分野での進展を測り、明確で具体的かつ客観的な基準を作成する(2002年11月、ミレニアム挑戦会計は既存の省庁とは別に新たに設立される「ミレニアム挑戦公社(MCC:Millennium Challenge Corporation)」が管理し、閣僚級の理事会(議長は国務長官)がその監督をすることが発表された。同時に、対象国の選定基準が明らかにされた)。
(へ)2002年9月に発表した国家安全保障戦略では、開発の推進に1項目が割かれ、貧困の削減を米国の対外政策の最優先事項と位置付けて、ミレニアム挑戦会計のほか、世界銀行等の援助効果増大、貿易自由化、保健、教育、農業等への取組を強化するとしている。以降、国家安全保障戦略における開発の地位が向上し、開発(Development)は、外交(Diplomacy)および防衛(Defense)と並ぶ3本柱(3つのD)と位置づけられるようになった。さらに2006年3月に発表した国家安全保障戦略においても、9つの重点分野のうち、2つにおいて開発の重要性に言及されている。
(ト)2004年9月に国務省に復興・安定化調整官室が新設された。ポスト・コンフリクト及び複雑な緊急事態を含む危機に対応する能力を増強し、移行期における復興・安定化を支援し、平和・民主主義・市場経済への道筋に確実に向かわせることを目的とした国務長官の直轄の組織であり、計画と実施において国防省と緊密に連携しつつ、6か月おきに公開・インテリジェンス情報を基に脆弱国の特定を行い、該当国に関する危機回避プランと、実際に危機的状況が発生したときに備えた災害時対応計画(contingency plan)を策定することとなった。
(チ)2006年1月にライス国務長官はジョージタウン大学での演説において「変革的外交」を打ち出し、その中で、米政府の対外援助の新しい方向性を発表した。そして、[1]対外援助が米国の広範な対外政策目標に合致するために、出来る限り効果的に活用されることを確実にし、[2]国務省とUSAIDにより実施される対外援助を、より一層連携されたもの(align)とし、[3]米国政府が、納税者にとって信頼できる給仕(steward)であること、を示した。また、その一環として、国務省に対外援助部長という副長官級のポストを設置し、USAID長官が兼任することを発表し、初代対外援助部長にトバイアス氏(前グローバルエイズ調整官)が就任した。
(リ)トバイアス長官は、「途上国が国民のニーズに対応し、国際システムで責任ある行動をとる民主的で良く統治された国家を建設し、維持することを助ける」ことを対外援助の究極の目標に掲げ、成果重視と援助効率性向上を重要課題とした。また、評価の基準として、対象国の発展段階を5つのレベルに分け(復興国、開発国、変革国、協力国、脆弱国)、5つの目標([1]平和と安全、[2]正当で民主的な統治、[3]国民への投資、[4]経済成長、[5]人道支援)における達成度合いを示すマトリクス「国別対外援助枠組」を策定中である。更に、対外援助の焦点として5つのゴール([1]中東における持続的で重要な治安パートナーシップ、[2]伝統的な東欧パートナーシップの支持、[3]アンデス地方における麻薬対策、[4]HIV/エイズとの闘い、[5]人道危機への対応)を挙げ、対外援助戦略のプライオリティを明確に示している。
(ヌ)ブッシュ政権における各種開発援助イニシアティブ等
[1]イラク復興支援
ブッシュ大統領は2005年11月30日に「イラクにおける勝利のための国家戦略」を発表し、イラクの自立への移行を支援するためには政治、安全保障及び経済の3分野における中長期的取組が必要であり、2006年は決定的に重要な年であると訴えた。この立場に立脚し、米行政府は、2004年までに議会から認められた約209億ドルのイラク復興支援予算に追加する形で、2006年補正予算で約16.1億ドル(6月に歳出法が議会通過)、2007年通常予算で約7.7億ドルの関連予算を議会に要求した。また、米政府は、イラク周辺国や欧州諸国等に対し、プレッジ済の支援の早期実施及び新規・追加支援を働きかけている。
2005年10月19日、ライス国務長官は上院外交委員会の公聴会において、イラクにおける文民と軍の活動の統合を強化するためにPRT(Provincial Reconstruction Team)を設置するとの決定を発表した。2006年7月までに4か所のPRTが設置され、米及びコアリションの軍人及び文民が参加し、イラクの地方行政能力向上のための支援等を実施している。
2006年5月にイラク新政府が発足したことを受け、国際社会による対イラク支援を一層本格化する機運が盛り上がる中、6月にイラクを訪問したブッシュ大統領は、帰国後、イラクが定める開発戦略に沿って国際社会が支援を約束することを内容とする「イラク・コンパクト」をイラク及び国連主導で策定することを支持する立場を明らかにした。
[2]アフガニスタン復興支援
アフガニスタンについては、治安分野改革における国軍再建プログラムを主導し、2006年1月から2月にかけてロンドンにおいて開催された国際会合において、その準備過程も含めホスト国であった英国と共に主導的役割を果たした。同会合においては、2006会計年度の新規プレッジと前年度以前からの繰越を合計した40億ドルの支援を行うことを表明し、これは同会合における各国・機関からのプレッジ総額の4割近くを占める額であった。なお、現在までの米のアフガニスタン復興支援向けプレッジ額は、100億ドルを超える水準に達している。
[3]ポスト・コンフリクト国支援
紛争後や混乱脱出後の状態にある、ボリビア、リベリア、スーダン、グルジア、ハイチ等のポスト・コンフリクト国への支援を積極的に行っている。国務省に復興・安定化調整官室を設置し国防省との緊密な連携体制を確立すると共に、PRT活用等、軍民の連携を模索中である。
[4]ミレニアム挑戦会計(MCA)
このイニシアティブについては、議会における審議が長引いたものの、2004年1月にミレニアム挑戦法が成立するとともにミレニアム挑戦会計初年度の予算として10億ドルが承認された。その後、2月には最初のMCC理事会が開催され、5月には2004会計年度の16のMCA適格国注)が発表された。2005年会計年度のMCA適格国として新たにモロッコが加わった。
2005年に入ってから、4月のマダガスカルとの最初の合意を皮切りに7か国(ホンジュラス、カーボヴェルデ、ニカラグア、グルジア、アルメニア、ベナン、バヌアツ)とのコンパクトを締結し、MCAにようやく本格的な動きが見られるようになった。さらに2006年7月には9か国目となるガーナとのコンパクトを承認している。
しかし、予算については当初の予定ほど議会の承認が得られていない。2004会計年度の予算は10億ドルであり、2005会計年度は25億ドルを要求したものの、15億ドルしか認められず、2006会計年度では2002年3月にブッシュ大統領が50億ドル規模を目標とすると表明したにもかかわらず、政府要求の段階で30億ドルの要求にとどまり、承認されたのは17.7億ドルのみである。2007会計年度では30億ドルを要求しているが、依然、当初予定の50億ドルには大きく隔たりがある。
3年間で合計約43億ドルの予算を承認されているが、2006年7月時点でコンパクトを締結しているのは、8か国15億ドルのみであり、議会からは、ディスバースの遅さとこれ以上の予算が必要なのかを疑問視する声が大きい。他方、ダニロビッチCEOは今後1年間以内に6~7か国の新規コンパクトが予定されており、今までの承認予算分の全てが費やされる予定である旨を議会で証言し、2007会計年度は要求満額が承認されることを強く望んでいる。
このイニシアティブは、援助量、援助手法の観点から、被援助国のみならず、他の援助国にも大きな影響を与える可能性があり、今後の運用が注目されている。また、MCCとUSAIDが、互いにどのような協力関係の下で米国の開発援助を実施していくのかについても関心が高まっていたが、両機関は相互に密接に協力しつつ、USAIDは特に敷居国プログラム(もう少しでMCA適格国になりうる国がMCA適格国となれるよう支援するプログラム)において中心的役割を担うこととされている。
[5]大統領エイズ救済緊急計画(PEPFAR)
2003年1月、ブッシュ大統領は、5年で150億ドルのPEPFARを発表するとともに、初年度の2004年度は20億ドルを議会に対して要求した。5月には、「エイズ・結核・マラリアに対する米国リーダーシップ法」が成立し、5年間で150億ドルのエイズ対策の支出が可能となるとともに、資金配分や関係省庁間の調整等を行うグローバル・エイズ調整官が国務省内におかれることとなった。また、2004年度については、議会における審議の結果、政府要求よりも5億ドル増額され、24億ドルが承認された。2005年度については27億ドルが承認、2006年度については要求満額の32億ドルが承認された。これは、ミレニアム挑戦会計が、政府要求よりも削減された形で承認されたのと対照的であり、議会のエイズ対策への強い支持を示すものであった。なお、2007年度については、40億ドルが要求されている。
本件イニシアティブでは、重点15か国注)を中心に、5年間で200万人のHIV/エイズ患者への治療支援、700万人を対象とした感染予防、孤児を含む1,000万人の感染者への治療支援を達成することを目標としている。
[6]災害復興支援 (津波被災支援、震災支援)
2004年末から2005年初頭にかけて、米国の対外援助政策で注目された動きは、津波被災支援であった。米国は、津波被害発生後直ちに、日本、オーストラリア、インドとともにコアグループを結成し、緊急人道援助の調整において主導的な役割を果たした。
米国は緊急人道援助として、3億5,000万ドルの支援を表明したほか、復興支援も含めた支援として約9億ドルをコミットした。津波被災支援に関しては、ブッシュ大統領はブッシュ元大統領及びクリントン前大統領を動員して、広く民間よりの募金を呼びかけた。民間募金は、最終的には10億ドルを越える額が集まったと言われている。
また、2005年10月に発生したパキスタン等大震災向け支援については、5.1億ドルをコミットし、国際社会の調整において主導力を発揮した。
[7]対アフリカ支援
2005年はG8プロセスにおいても、国連のプロセスにおいても、アフリカ開発に焦点が当たったが、米国もここ数年アフリカに対する支援を強化している。2000年と比較して、2004年には米国はアフリカに対する援助を3倍に増やしている。また、米国の新しい開発援助イニシアティブであるMCA、PEPFARとも、アフリカ諸国が対象の中心となっている。6月には、ブッシュ大統領がアフリカの人道危機に対応するために、6億7,400万ドルの追加支援を発表したほか、5か国注)の大統領を招いて、アフリカ成長機会法(AGOA)が米・アフリカ間の貿易を増大させ、アフリカの貧困削減に大きく貢献している旨発表した。
[8]援助量及び革新的資金メカニズムについての考え方
2005年1月に発表されたミレニアム・プロジェクト・レポート等を契機として援助の量についての議論が盛んに行われた。こうした中で、米国は、いくつかの国については援助量を拡大するのに適した国があることを認める一方で、援助量に過度に焦点を当てる姿勢に懐疑的立場を示し、開発途上国のオーナーシップ、ガバナンス、援助の効率性等、モンテレイコンセンサスを重視すべきであるとの主張を行っている。
欧州諸国が革新的資金メカニズムとして主張している国際金融ファシリティ(IFF)や国際税といった構想については、米国は自国の予算制度と合わないこと等を理由に一貫して反対している。
[9]ブッシュ政権2期目の対外援助政策
ブッシュ政権1期目に、MCA、PEPFAR等のイニシアティブを打ち上げ開発援助予算の増額をコミットした後、2005年からの第2期目におけるイニシアティブのフォローアップが注目されていたが、各々のイニシアティブの本格ディスバースが開始され、開発援助予算も順調に大幅増額を続けている。2006年に入り、国務省対外援助部長を新設し、開発援助政策と外交政策のより一層の一貫性を保つ体制が整いつつある。
(ル)日米援助協調
日米間では、従来より日米保健パートナーシップ、日米水協力、アフガニスタンにおける幹線道路の建設等各分野、プロジェクトごとに協力してきているのに加え、2005年3月、ライス国務長官が訪日した際、日米両国は「戦略的開発協調」を進めていくことについて合意した。同年9月にワシントンDCにおいて第1回会合(次官級)を開催し、両国が戦略的に重要と捉える地域・分野において協調を進めていくことで見解の一致を見た。
人道問題への対応についても、2004年12月に、局長級の人道問題に関する日米パートナーシップ定期会合の第1回会合、2005年6月に第2回会合、2006年6月に第3回会合を開催し、人道問題分野における両国の関心国や対応策に関し意見交換を行い、協力関係を強化してきている。
(2)実施体制
二国間援助は、資金協力、技術協力ともに基本的にUSAIDが国務省と密接に協議の上実施してきているが、こうした既存の組織に更にMCCが加わっている。USAIDは援助プログラムの実施を専門省庁に委託することもある。国際機関を通じた援助のうち、世界銀行や地域開発銀行等の国際開発金融機関については財務省が管轄し、国連専門機関については国務省が管轄している。なお、国際開発金融機関を通じる援助の場合も、外交政策の観点から国務省が関与する。
USAIDの特徴は、海外事務所に多くのスタッフを置き、具体的な援助実施の権限が現地事務所に委ねられている点である。なお、2006年3月末現在のUSAIDの職員総数は8,214人であり、内訳は、ワシントンDCの本部に1,850人、海外事務所に6,364人となっている。
MCCに関しては、2006年7月現在の職員数は本部と海外事務所を合わせて238名であり、2006年中に300名まで増員する計画である。なお、海外事務所に関しては、開発プログラムは被援助国のオーナーシップに委ね、海外事務所による被援助国管理を最小限に留めるという考えのもと、現時点では5名(近日中に追加で7名を派遣する予定)を配置しているのみである。
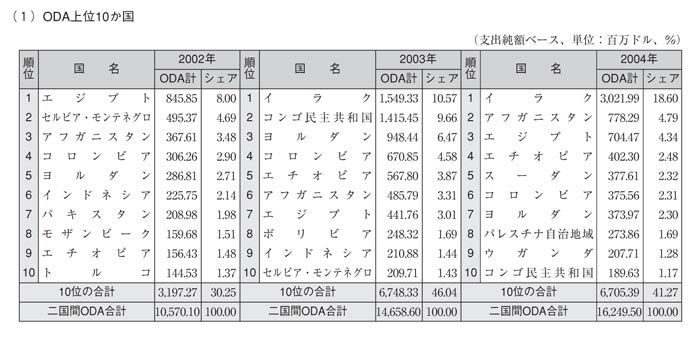
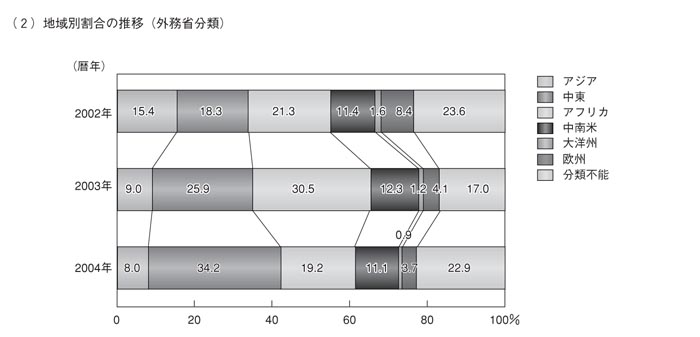
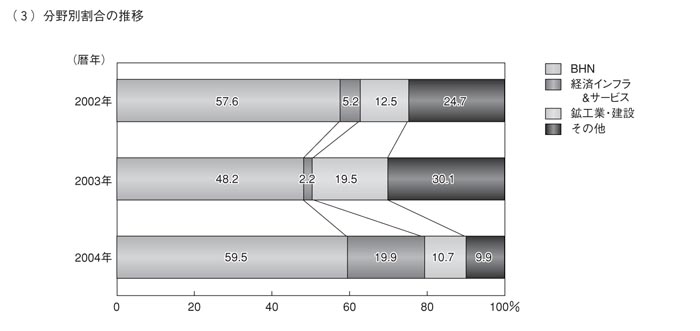

 次頁
次頁