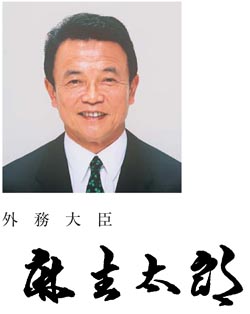本文 > 巻 頭 言
巻 頭 言
日本の政府開発援助(ODA)は、1954年の開始以来、時代とともに変化する日本及び国際社会の課題の解決に寄与してきました。日本は開発援助という外交政策手段を積極的に展開することによって、開発途上国の経済発展と人道支援を通じて世界の平和と安定に寄与し、また、地球的規模の課題の解決に取り組んできました。
本年初頭に私の演説で申し上げましたとおり、「情けは他人のためならず」であります。日本の開発援助による支援は、対象地域の自助努力を支援し、その地域を発展・安定させることによって、回り回って日本の安定や繁栄につながってくるものであり、またそうでなくてはなりません。援助を通じて現地の人々とともに汗を流すことによって、日本の戦後の発展の経験や知見、勤勉な労働姿勢といった文化を伝えていくことも重要です。さらに、新興国が台頭するなど新しい国際環境の下で、日本の経済的繁栄を確保するために、貿易・投資環境の整備、経済連携の推進や資源・エネルギーの確保等のためにODAを有効に活用していくことも大切です。そうした中で、ODA事業量を積み増し、ミレニアム開発目標という国際的な目標の達成に向けた取組を強化することや、イラク、アフガニスタンといった国々の平和と復興を支援していくことは、国際社会における日本の責務です。開発援助に求められる役割はますます多様で重要なものになっています。
このような取組には、腰の据わった戦略が必要となります。また、開発援助をより効果的かつ効率的なものとすることも重要です。このため、2006年には多くの改革がなされました。まず、4月には海外経済協力の基本戦略を審議する海外経済協力会議が内閣総理大臣の下に設置されました。次いで8月には、経済協力の企画立案・調整能力を強化するため、外務省に国際協力局を新設しました。さらに、11月には国際協力機構(JICA)法を改正し、有償資金協力、技術協力及び無償資金協力の実施をJICAの下に一元化することが決定されました。こうした一連の改革により、経済協力の戦略性を高めるとともに、援助の各種の手法を有機的に連携させ、効果的かつ効率的に実施していく体制を整えました。
今年の白書では、日本の援助が国際社会の平和と発展、また、日本の安全と繁栄の確保に果たしてきた役割を辿っています。その上で、今日の国際環境の中で求められているODAの新たな使命が何であるか、そしてその広範なる使命を果たすべく行っている改革について特集しています。また、実績については、最近の事例に言及しつつ報告しています。本書により国民の皆様の開発援助への理解がさらに深まり、一層のご支援を賜ることができれば幸いです。
2006年12月
 次頁
次頁