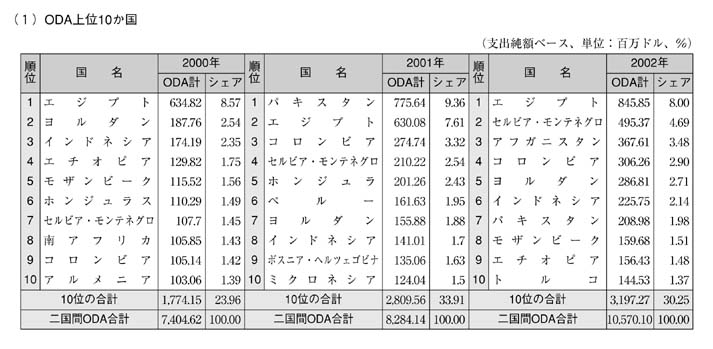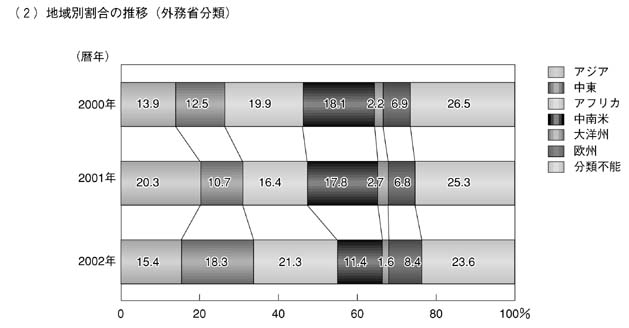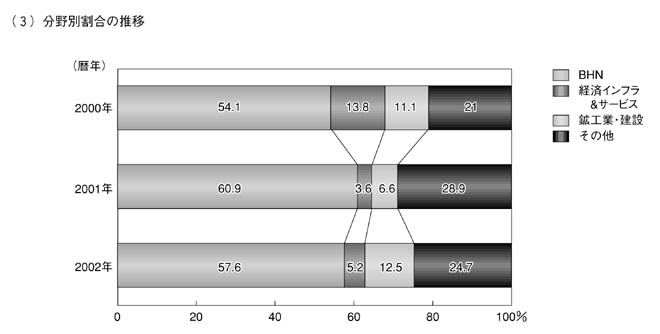資料編 > 第4章 > 第2節 > 1 米国
第2節 主要援助国・機関のODAの概要
1 米国
(1)援助政策等
(イ)米国では、8年間にわたる民主党政権に代わり、2001年に共和党のブッシュ大統領が就任し、同年春ころから共和党色の強い新政策が次々と打ち出された。さらに、同年9月11日に発生した同時多発テロもあり、2002年3月には開発援助50%増を打ち出すなど、米国の援助政策は大きく変貌することとなった。
(ロ)新政権が先ず着手したのは、国際開発庁(USAID:United States Agency for International Development)の再編である。ナツィオスUSAID長官は2001年4月に米上院で承認を求める際の証言で、USAIDが国務長官に報告し指示を仰ぐと述べ、援助を外交目的のため実施するとの方針を明確に示した。
(ハ)同長官は、同年5月の上院証言では、USAIDの「4つの柱(Four Pillars)」(援助の実施方法の柱としての「グローバル開発アライアンス(GDA)」、そしてプログラムの柱としての「経済成長と農業」、「グローバル保健」、「紛争予防と開発救援」から構成)を発表した。これは、外交政策のツールとしての自らの効果を高めるため、主要な活動目的と方法とを明示し、既存の予算項目を横断する形で柱を提示することとしたものである。さらに、組織面でも、これらの柱に応じた形で部局が再編され、政策立案を担う局に予算調整権限を与えてその機能を強化すると共に、GDA事務局及びプログラムの柱に相当する3つの局が新設された。
(ニ)同年7月、ブッシュ大統領は、世界銀行本部での演説において、国際開発金融機関による最貧国支援のグラント部分を50%まで引き上げること、及びそれを教育、保健等の分野に振り向けることを提案した。これを受けて、国際開発協会(IDA)13次増資交渉で米国は強硬姿勢をとることとなり、欧州と対立することとなった。(結局、本問題は2002年7月にグラント化率を全体の18-21%とする方向で決着した。)
(ホ)また、9月11日の同時多発テロの結果、米国はテロとの闘いを多方面で強力に展開することとなったが、これは貧困と開発の問題に対する米国の認識と政策に深い影響を与えることとなった。2002年3月14日、ブッシュ大統領は、モンテレイでの開発資金国際会議の開催4日前の米州開発銀行本部での演説で、「開発のための新たな約束(a new compact for development)」と名づけられる新たなイニシアティブを発表した。この主要点は次のとおりである。
[1]今後3年度内(2004年度から2006年度まで)に、米国の開発援助を50%増額し、最終的に年額50億ドル増の水準に到達させる。
[2]この増額分は、「ミレニアム挑戦会計(Millennium Challenge Account)」という新たな特別会計とされ、良い統治、人材育成(保健・教育)、健全な経済政策という三分野での強いコミットメントを示した国に配分される。国務長官と財務長官は、国際社会と対話しつつ、これら3分野での進展を図り、明確で具体的かつ客観的な基準を作成する(2002年11月、ミレニアム挑戦会計は既存の省庁とは別に新に設立される「ミレニアム挑戦公社(Millennium Challenge Corporation)」が管理し、閣僚級の理事会(議長は国務長官)がその監督をすることが発表された。同時に、対象国の選定基準が明らかにされた)。
(へ)さらに、2002年9月に発表した国家安全保障戦略では、開発の推進に1項目が割かれ、貧困の削減を米国の対外政策の最優先事項と位置付けて、ミレニアム挑戦会計のほか、世界銀行等援助効果増大、貿易自由化、保健、教育、農業等への取組を強化するとしている。
(ト)2003年には、ポストコンフリクト対応としてのイラク・アフガニスタン復興支援等や、ブッシュ政権の二大開発援助イニシアティブとも言われるミレニアム挑戦会計及びエイズ緊急対策を巡って、政権と議会との間で攻防がなされた。
[1]ブッシュ大統領は、9月7日、203億ドルの対イラク復興支援及び8億ドルのアフガニスタン復興支援を含む対テロ戦争2004年度戦時補正歳出法案を議会に提出することを発表した。議会においては、イラク復興支援に関し、全額贈与とするか一部借款とするかにつき意見が分かれたが、最終的には、総額としては政府要求より削減されたものの、186億ドルが全額贈与として承認された。また、アフガニスタン復興支援については、12億ドルに増額された形で承認された。
[2]ミレニアム挑戦会計については、議会における審議が長引いたものの、2004年1月23日にミレニアム挑戦法が成立するとともにミレニアム挑戦会計初年度の予算として10億ドルが承認された。その後、2月2日には最初のMCC理事会が開催され、5月6日には2004会計年度の16のMCA適格国(アルメニア、ベナン、ボリビア、カーボ・ヴェルデ、グルジア、ガーナ、ホンジュラス、レソト、マダガスカル、マリ、モンゴル、モザンビーク、ニカラグア、セネガル、スリランカ、バヌアツ)が発表される等の進展が図られている。このイニシアティブは、被援助国のみならず、他の援助国にも大きな影響を与える可能性があり、今後の運用が注目されている。また、ミレニアム挑戦公社とUSAIDが、互いにどのような協力関係の下で米国の開発援助を実施していくのかについても関心が高まっている。米政府は2004年2月、2005会計年度対外援助予算を議会に提出し、MCAについては25億ドルを要求しているが、厳しい財政状況の中、MCAが未だ目に見える効果を上げていないこともあり、下院通過時点では12億5,000万ドルにとどまっている。
[3]2003年1月、ブッシュ大統領は、5年で150億ドルのエイズ対策緊急計画を発表するとともに、初年度の2004年度は20億ドルを議会に対して要求した。5月には、「エイズ・結核・マラリアに対する米国リーダーシップ法」が成立し、5年間で150億ドルのエイズ対策の支出が可能となるとともに、資金配分や関係省庁間の調整等を行うグローバル・エイズ調整官が国務省内におかれることとなった。また、2004年度については、議会における審議の結果、政府要求よりも4億ドル増額され、24億ドルが承認された。これは、ミレニアム挑戦会計が、政府要求よりも削減された形で承認されたのと対照的であり、議会のエイズ対策への強い支持を示すものであった。なお、2004年6月、米政府はエイズ対策緊急計画の15番目の重点国としてベトナムを加えることを発表した。
(チ)2004年の米国の対外援助政策においては、2003年に引き続きイラク・アフガニスタンをはじめとするポストコンフリクト等への対応について以下のとおり積極的な取組がなされている。
[1]2003年秋以降、情勢が不安定となっているボリビアについては、米国は1月にボリビア・サポートグループを立ち上げ、ボリビアにとって深刻な課題であった財政赤字の補填の問題解決に向けてリーダーシップを発揮した。
[2]リベリアについては、2月にニューヨークにおいて、国連、世銀とともにリベリア国際復興会議を主催し、2億ドルのプレッジを行った。
[3]アフガニスタンについては、3月及び4月にベルリンにおいて開催された国際会議において、その準備過程も含め主導的役割を果たしました。また、同会議において2004会計年度については10億ドルの新規プレッジを含め22億ドルの支援を行うことを表明した。なお、米政府は議会に対し、2005会計年度予算として12億ドルを要求している。
[4]スーダンに対しても、6月にジュネーブにおいて開催されたダルフール・ドナー会議において、1億8,850万ドルの追加支援を行うことを表明した。これにより、2003年2月以降の米国のダフールに対する支援は約3億ドルとなる。
[5]5月にブラッセルにおいて行われたグルジア支援会合においても、米国は2004年中の1億6,000万ドルの支援及び議会の承認が得られることを前提とした毎年1億ドルの支援(2005及び2006会計年度)を表明した。なお、グルジアはMCAの適格国に選ばれており、米国の対グルジア支援は今後大幅に増加する可能性がある。
[6]7月、ワシントンにおいて行われたハイチ支援国会合においても、その準備過程でリーダーシップを発揮するとともに、2004及び2005会計年度に2億3,000万ドルの支援を実施することを表明した。
(2)実施体制
二国間援助は、資金協力、技術協力と共に基本的にUSAIDが国務省と密接に協議の上実施されてきているが、こうした既存の組織に、今後さらにミレニアム挑戦公社が加わることになっている。USAIDは援助プログラムの実施を専門省庁に委託することもある。国際機関を通じた援助のうち、世銀や地域開発銀行等の国際開発金融機関については財務省が管轄し、国連専門機関については国務省が管轄している。なお、国際開発金融機関を通じる援助の場合も、外交政策の観点から国務省が関与する。
USAIDの特徴は、渉外事務所に多くのスタッフを置き、具体的な援助実施の権限が現地事務所に委ねられている点である。なお、2003年9月末現在のUSAIDの職員総数は7,943人であり、うち本官が2,334名(3分の1は在外勤務)、現地採用は5,609名等となっている。
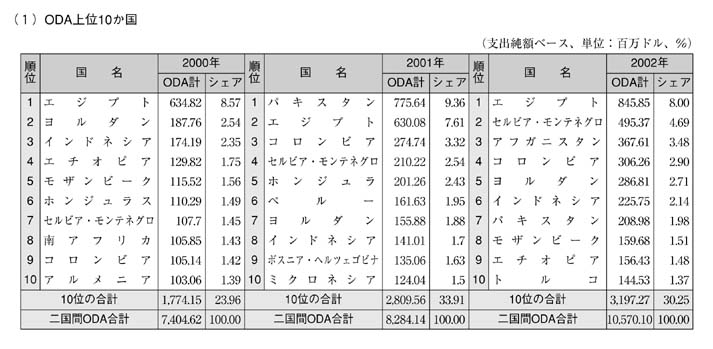
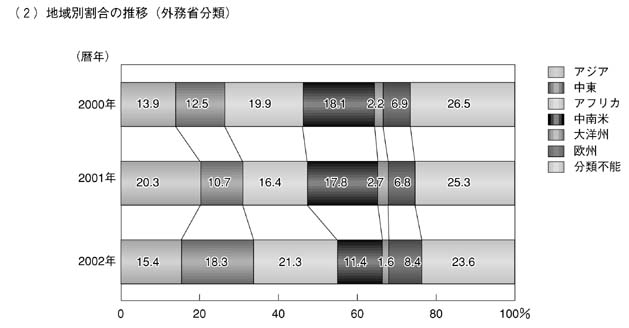
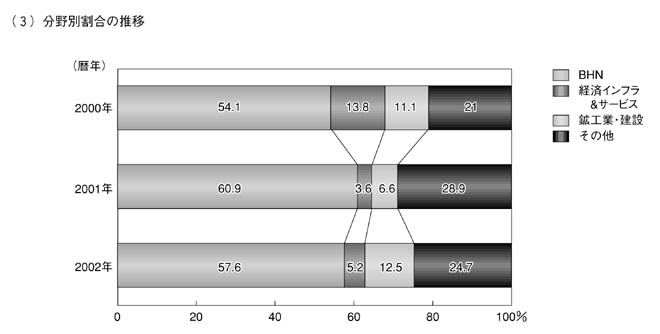

 次頁
次頁