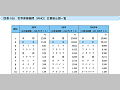資料編 > 第3章 > 第3節●国際機関 > 12 世界保健機関(WHO:World Health Organization)の概要と実績
48年4月7日設立。我が国は51年5月16日の第4回総会において、加盟が認められた。
WHOは、国際連合の専門機関であり、46年、ニューヨークで開かれた国際保健会議が採択した世界保健憲章(48年4月7日発効)によって設立された。
「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達すること」(憲章第1条)を目的としている。
WHOの予算は2年制であるが、活動の財源は、加盟国の義務的分担金(各国の分担率は国民所得等に基づいて算定される国連分担率に準拠)により賄われる通常予算(Regular Budget)と、加盟国及びUNDP、世界銀行等の他の国際機関からの任意拠出に基づく予算外拠出(External-Budgetary Contribution)からなっている。
通常予算は、主として職員の給与、会議の開催、保健・医療に関する調査・研究、情報の収集・分析・普及、器材購入、各国政府に対する助言等に振り向けられ、予算外拠出は、通常予算ではカバーできないフィールド・レベルの技術協力等を中心とした事業活動に使われている。
WHOは各加盟国により構成され、1年に1度開催される世界保健総会を最高意思決定機関としており、総会で選出された32か国が推薦する執行理事により構成される執行理事会が、総会の決定・政策の実施、総会に対しての助言または提案を行っており、総会の執行機関として行動するという仕組みになっている。
総会では、事業計画の決定、予算(2年制)の決定、執行理事国の選出、新規加盟国の承認、憲章の改正、事務局長の任命等を行うほか、保健・医療に係る重要な政策決定を行う。
一方、予算外拠出については、WHO事務局が作成した事業計画案についてドナーとWHO事務局間で協議を行い、決定される。
通常予算については、定められた項目別に事務局が事業を実施する。事業の実施状況については、執行理事会・総会に報告がなされる。
予算外拠出については、WHO事務局とドナーとの間の合意事項に基づき、事業が実施され、事業終了後にはWHOからドナーに対し、報告が行われる。
WHOは、保健衛生の分野における問題に対し、広範な政策的支援や技術協力の実施、必要な援助等を行っている。また、伝染病や風土病の撲滅、国際保健に関する条約、協定、規則の提案、勧告、研究促進等も行っており、ほかに食品、生物製剤、医薬品等に関する国際基準も策定している。
地域事務局が主体となって行っている仕事の大半は、WHOの事業のうち最も重要なものとして位置づけられている各国に対する技術支援である。これに対して、WHOの全予算の約7割が振り向けられている。技術支援は、通常(1)専門家の派遣、(2)資材供与、(3)フェローシップの提供という形式で与えられる。
図表-159 WHOの地域別予算割合

新たに発生した感染症(エボラ出血熱、新型インフルエンザなど)や、すでに克服されたと思われていた感染症の再興(コレラ、結核など)が、世界的規模で大きな問題となっていることから、これらを「新興・再興感染症」の問題として総合的・重点的に対策を講じている。96年には新たな部局を設け、世界的常時監視網の構築、集団発生時に迅速かつ的確に対応するための体制確保、科学的で正しい知識や対策の普及に努めている。
また、特定の疾患の根絶や制圧にも力を注いでいる。重点的な予防接種事業の推進により中南米に次いで西太平洋地域においても2000年10月に京都でポリオ制圧宣言が出されたほか、メジナ虫症も数年後には根絶が可能な状況となっている。さらには、ハンセン病、リンパ・フィラリア症、アフリカの風土病であるオンコセルカ症、ラテン・アメリカの風土病であるシャーガス病などについても、制圧対策が強力に推進されている。
さらに、麻疹、破傷風、ジフテリアなどの疾患の発生を防ぐ拡大予防接種計画、結核に対し直接管理の下に服薬を行う短期療法(DOTS)、病気の子どもに幅広くケアを提供するための小児期疾患総合管理対策、日常の疾病対策に不可欠の医薬品を適切に供給・管理するための必須医薬品対策などを、重点活動として推進している。
医薬品、血液製剤、食品、化学物質等に関する安全対策にも重要課題として取り組んでおり、各般の基準策定、副作用など危機管理上重要な情報の迅速な提供などにも努めている。
安全な出産を確保するための妊産婦対策や家族計画などのリプロダクティブ・へルス対策、自然災害や紛争等の緊急事態における緊急人道援助などについても力を注いでいる。
また、マラリアなどの熱帯病に対する治療法やワクチンなどの予防法開発を初めとして、研究開発の振興にも努めている。さらには、クローニングの人への適用に対する警告発信など、最近の科学技術に関し、生物科学的観点のみならず社会的・倫理的観点も含めた総合的対策にも取り組んでいる。
98年7月、事務局長がノルウェーのブルントラント氏に交代したが、新体制下においては、上記の事業を引き続き実施するほかに、マラリア対策、タバコ対策、保健部門開発の3事業を重点事業として推進することとしている。特にタバコ対策については、99年5月のWHO総会において、「WHOたばこ対策枠組条約」策定のための政府間交渉組織とその準備会合の設置が決議され、2003年5月を目途に枠組条約を採択することを目標に作業している。
51年の加盟以来、我が国は、WHOの活動に積極的に参画している。この間、我が国は9回にわたって、執行理事会の理事指名国に選ばれている。
WHOは、2000年12月現在で3,486名(専門職1,293名、一般職2,065名)の職員がいるが、そのうち邦人職員は38名。本部事務局長は邦人である中嶋宏博士が2期10年間務めていたが、98年7月に引退した。他方、西太平洋地域事務局長については、98年9月に選挙が行われ、尾身茂博士が当選し、99年2月に就任した。
2000-2001年の一般会計予算は8億4,265万ドル(2年間の総額)。一般予算の財源は、加盟国の義務的負担である分担金により賄われる。2000年の日本の分担率は20.244%で、分担金は約8,400万ドル。米国(分担率25%)に次いで第2位の拠出国となっている。また、このほかにも特定の重要課題(新興・再興感染症対策、医薬品安全対策、食品安全対策など)における技術協力等の推進に資するため、任意拠出を行っている。
75年に世界規模で開始されたWHOの拡大予防接種事業は着実に実績を上げ、予防接種率の向上と共に、対象疾患の報告数は減少傾向を示し、特に現在この事業の中で大きなウエイトを占めているポリオ根絶計画は、WHO西太平洋地域事務局管内で着実に成果を挙げ、2000年10月に根絶が宣言された。
根絶が宣言された西太平洋地域でのポリオ根絶計画は、継続的な我が国の支援と協力を通じてはじめて可能となったことが、被援助国のみならず、支援国、国際機関の間で広く認識され評価されているところである。我が国の政府開発援助による全国一斉投与用経口ポリオワクチン必要量全量の供与(ラオス、ベトナム、カンボジア、モンゴル、パプアニューギニア)は、WHOの助言、要請を基に当該国政府との二国間政府協力の形で実施されている。
ポリオ根絶にかかるコールドチェーン用機材及び車両等も、同様に、WHOをはじめ関係国際機関の助言、要請を基に、二国間政府協力の形で援助が行われている。
技術協力の面では、国際協力事業団によるプロジェクト方式でのポリオ根絶への技術協力(ラオス)及びポリオ根絶計画のための研修員の本邦諸協力機関への受け入れ、さらには国立感染症研究所において、現在西太平洋地域の基幹試験機関として地域内各国より送付される便検体よりのポリオウイルス最終同定と各国のウイルス同定施設に対する技術協力が行われている。
今後は、残る南アジア、アフリカ諸国に対し、撲滅に向けた援助を続けていくこととしている。また、南太平洋諸島のフィラリア病対策として、2000年度より協力を実施している(特定感染症対策特別機材)。
こうした子どもの健康分野だけではなく、エイズ・結核・マラリア対策についても我が国はWHO特にWPRO(西太平洋地域事務局)と緊密な連携をとりつつ行っており、特に結核等については、WPRO が調整している。中国貧困地域への我が国の抗結核薬の供与が他ドナーの援助の呼び水となった経緯がある。
World Health Report, 2001(WHO発行)
世界保健機関 http://www.who.int
図表-160 世界保健機関(WHO)主要拠出国一覧
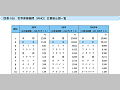

 次頁
次頁