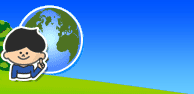| 開発途上国(外務省パンフレット「ODA-世界と地球の未来のために」より) |
わたしたちの身の回りにはいつも食べ物や水や衣服があり、当たり前のように舗装(ほそう)された道を歩いたり乗り物を使ったりして学校や病院に通っています。
しかし、地球規模で見渡してみると、これは決して「当たり前」のくらしではありません。世界約190カ国のうち実に約150もの国々が、産業や技術の発達が遅れている国であり、そこでは1日にわずか100円や200円程度のお金で生活しなければならない人たちもたくさんいます。そのため、学校にも行けないこどもたちや、お金をかせぐために働く子どもたちもたくさんいます。
人々が飢えや貧困に苦しんで、十分な食料や飲み水が得られなかったり、教育や医療を満足に受けられなかったりする国々のことを、開発途上国とよびます。そこでくらす人びとは、世界の人口(約61億人)の8割以上を占めています。 |
 |
| *「開発途上国」に対し、産業や経済が発達している国々のことを「先進国」とよびます。 |
 |
 |
|
|
|
 |
| さまざまな問題 |
| [戦争、紛争] |
| 第二次世界大戦後もなお今日にいたるまで、世界ではどこかで戦争やさまざまな争いがおこっています。そしてその多くは、開発途上国でおこっています。
|
 |
| [地雷] |
地雷とは、地面に埋められていて、近づいたり触ったりすると爆発する武器です。
戦争中に設置された後、戦争が終わっても多くの地雷がそのままになっているため、その土地で生活する人びとが被害を受けています。
|
 |
| [難民] |
難民とは、戦争・紛争や地震などの災害によって本来の居住地を離れざるを得なくなった人々のことです。
現在、世界各地に約2300万人の難民が存在するといわれています。
|
 |
| [環境問題] |
| 近年、産業や経済の急速な成長の一方で、大気汚染や自然環境破壊などの環境問題が注目されています。とりわけ、二酸化炭素など温室効果ガスと呼ばれるガスが大気中に増加することにより地球全体として大気や地面の温度が上昇し、自然の生態系や人類に悪影響を及ぼす地球温暖化問題は、地球規模の深刻な問題となっています。
多くの開発途上国においても、急速な都市化や工業化によって温室効果ガスの排出量が増加しています。また途上国では貧困などを背景に、森林からの過剰な燃料採取や伐採、過剰な放牧、非持続的な焼き畑農業などによる環境破壊の問題もあわせ持っています。
|
 |
| [HIV/エイズ等の感染症] |
2001年には世界で4000万人以上のHIV/エイズ感染者が存在しており、死亡者数は年間300万人以上、毎日8,000人以上の人が亡くなっています。結核は毎年900万人がかかっており、うち200万人以上の人が亡くなっています。マラリアについても年間110万人以上の人が亡くなっています。
特に開発途上国では、栄養や保健・衛生上の問題から、感染症にかかると別の感染症に感染しやすくなり、そしてますます多くの人に感染が広がってゆくといった悪循環が発生しています。
単なる個人の健康上の問題に留まらず、国際化の進展により人の移動がますます容易になる中で、国際社会全体にとって大きな脅威(きょうい)となっています。
|