ヨハネスブルグの風
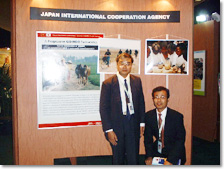
左:高橋部長
右:広岡外務省民間援助支援室首席事務官
|
ヨハネスブルグに向かう飛行機の中で読んだ南アフリカの新聞記事に目が留まった。美しい紫色の花を咲かせるジャカランダの木は外来種であり自国の植物生態系を守るために伐採しようかという記事であった。ジャカランダは多くの東部・南部アフリカ諸国の風景と人々の心に溶け込んだ樹木である。植物の世界でも国際化とナショナリズムに揺れているのかと思った。
ヨハネスブルグ・サミットは1992年にブラジルのリオデジャネイロで開催された環境サミットの10年後に開かれたためリオ・プラス10とも呼ばれている。この10年間にどのような変化があったのか。10年前のリオ・サミットと今回のサミットの両方にドイツ政府代表として参加した環境派で与党社会民主党のモニカ・ガンセンフォース国会議員と話をする機会を得た。「リオの会議では各国参加者は思ったことをただ発言しただけの印象であった。しかし今回のサミットは利害関係のある政府代表、国際機関、NGOなどが組織化されて議論が非常に具体的になった。」私には参考になる情報であった。このサミットでは議論が具体的になったために意見の違いが明確になり対立も鋭くなったようだ。160余ケ国から参加しているこのサミットを失敗させたらもう二度とこのような世界の首脳が一同に会する国際会議は開くことが出来なくなり世界の人々は手の届かない貧富の差と壁に絶望をするだろうという危機感が一方では共有されているため、その駆け引きと折衝は連日連夜続けられている。
ヨハネスブルグ・サミットのテーマは「持続可能な開発」。環境と開発をどのように両立させることができるのか。世界が立ち向かう大きなチャレンジである。8月26日初日の全体会議は南アフリカのムベキ大統領の開会のスピーチで始まった。そして保健、農業、水と衛生、生物多様性、エネルギー、横断的分野、総括討論の議論と各国の発表が毎日行われた。顧問団はそれぞれの分野を分担した。私は保健分野に政府代表団の一員として参加した。水と衛生、エネルギー、総括討論にはオブザーバーとして傍聴した。会議の流れの中で「議論から実行に移ろう」「資金が不足している」という声が国際機関と各国政府代表団から多く聞かれた。保健分野だけで今後不足する資金は年間300億ドルという国際機関の発言があった。聞いて一瞬溜息をついた。各国政府や公的機関代表が多い会議において主催者側の意向で議論を盛り上げるために民間の産業界の代表が公式発言者の一人に入っていた。コーポレート・ガバナンス(企業統治)とコーポレート・アカウンタビリティ(企業の説明責任)を問う議論がある一方、企業側から興味深い切り口の発言が総括討論であった。「私も皆さんと同じく途上国の貧困を何とか救いたいと思っています。ここでは民間の産業界を開発分野で利益を挙げていることを悪く言う人が多いですが利益とは汚い言葉ではありません。皆さん方の議論にはマーケット(市場)という発想と議論が全くありませんね。ここでの議論を私は危機感を持って聞いています。利益なくして持続可能な開発をどのように進めることが出来るのですか。資金が不足していると発言をしている皆さんの政府や団体こそ外部からの資金援助に依存している限り持続可能な組織ではなく、それでどのような持続可能な開発することが出来るのですか。」途上国と開発援助機関の自助努力の必要性の指摘でもあった。
日本からヨハネスブルグには約50のNGOから380人ほどが来ていると聞いた。環境分野の提言(アドボカシー)型NGOが多い。日本のNGOの多くは厳しい財政状況に置かれていることを考えるとこのサミットに対する関心度は潜在的に非常に高いと思う。皆、エネルギッシュに活動をしている。一方、途上国に実践型プロジェクトを有する日本の開発型NGOの数が少なく寂しい気持ちになった。持続可能な開発を実践するために世界の関心は議論から途上国での実践プロジェクトへ益々シフトするだろう。そして日本の援助の心と成果を日本の人々ばかりでなく多様なチャネルで世界へ発信しその反響を受信する必要性とシステム作りは非常に高まっている。改めて日本のODAとNGOのパートナーシップのあり方が重要な課題になると思う。
ヨハネスブルグ・サミットに臨む日本政府の現地事務局体制は内閣府、財務省、外務省、文部科学省、経済産業省、環境省、農林水産省、国土交通省、厚生労働省(順不同)の担当者が所管の議題を担当している。NGOに対応するため石川NGO大使が着任している。 NGO連絡室も設けられた。南アフリカの在プレトリア日本領事館に勤務経験があり南アの事情に詳しい伊藤外務省経済局漁業室長がNGO連絡室長となり、広岡外務省民間援助支援室首席事務官、本道在スペイン日本大使館一等書記官、土屋外務省地球環境課事務官、小野在南ア日本大使館専門調査員、丹呉在英国日本大使館理事官の6名の体制で顧問団と日本のNGOの要望などに柔軟に対応をしている。刻々と変化するサミットの進捗状況の情報提供や各国との交渉の最前線に臨んでいる各省庁担当者からのNGO側へのブリーフィングと意見交換、日本の国会議員との懇談会などの便宜を図っている。NGOの参加者からも好評であった。
世界では毎年、約1000万人の子どもが死んでいる。妊娠と出産に係る疾病と事故で年間58万人の女性が命を落としている。その結果、年間200万人の孤児が発生している。HIVの感染者は現在約4000万人。それでも世界の人口は7700万人ずつ増えている。現在の地球上の人口は63億人から2050年には93億人になると予想されている。増える30億人の99%は途上国で起きる。食糧、保健医療、飲み水などが現在でも絶対的に不足している途上国でどのような持続可能な開発が出来るのかという非常に重い課題への取り組みが残された。政府とNGOとの相乗効果を生むパートナーシップのあり方を改めて考えてみたい。
WSSD政府代表団顧問 高橋秀行(ジョイセフ(家族計画国際協力財団))
|