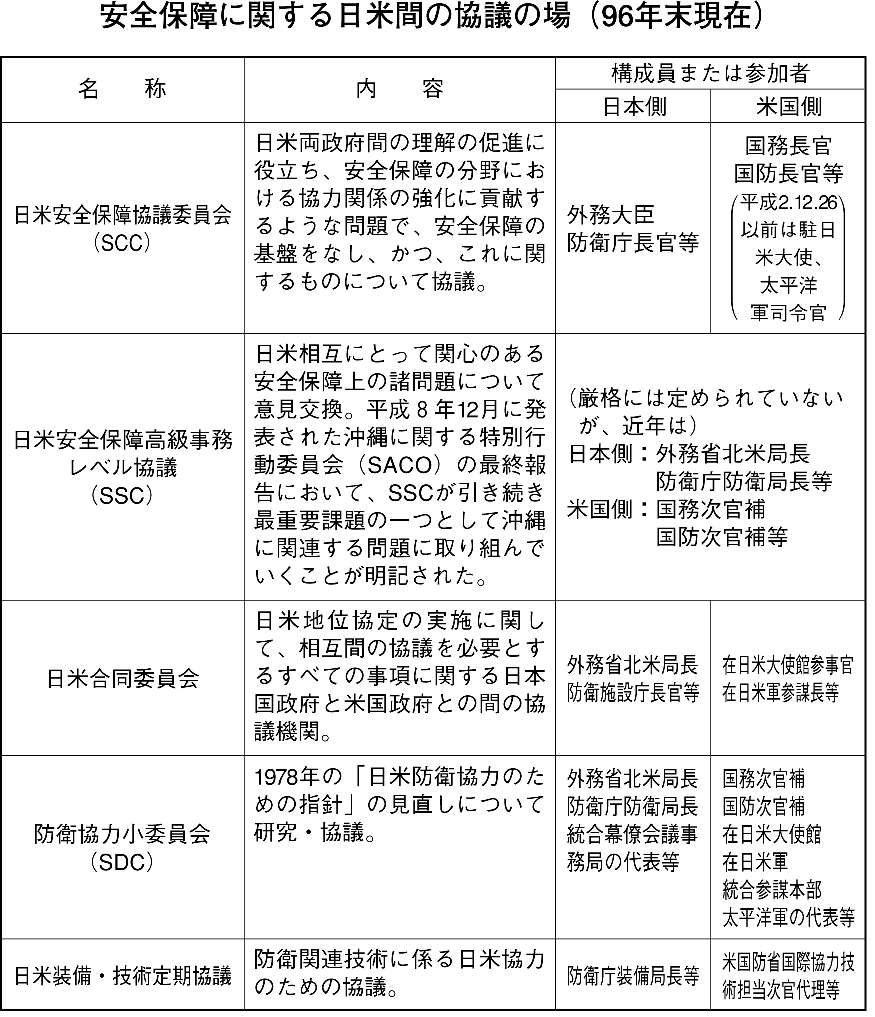(2) 日米安全保障体制
イ.日米安全保障体制の意義
日本が、必要最小限の防衛力を保持するとの政策の下、平和と繁栄を享受していくためには、今後とも日米安保条約に基づく米国の抑止力が必要である。また、日米安保体制は、国際社会における広範な日米協力関係の政治的基盤となっており、さらに、アジア太平洋地域全体の安定要因である米国の存在を確保し、この地域の平和と繁栄を促進するためにますますその重要性を高めてきている。

ロ.日米安全保障共同宣言
こうした認識の下、日米安保体制を効果的に運用し、安全保障面での協力を進めていくため、日米間では、さまざまなレベルで密接な対話と意見交換が重ねられてきた。過去1年以上にわたるこのような緊密な対話の成果として、4月のクリントン大統領訪日時に、橋本総理大臣とクリントン大統領により日米安全保障共同宣言が発出された。この宣言は、日米安保体制の重要な役割を改めて確認するとともに、21世紀に向けた日米同盟関係のあり方につき内外に明らかにしていくという意味で極めて重要な意義を有するものである。具体的には、日米がアジア太平洋地域においてより安定した安全保障環境のために協力していくこと、日米安保体制を基盤とした日米間の各般の協力を推進することを含め、21世紀を見据えた日米安保体制のあり方を幅広い観点から明らかにしている。また、国際情勢、とりわけアジア太平洋地域情勢についての情報・意見交換を一層強化すること、両国の防衛政策及び在日米軍の兵力構成を含む軍事態勢について引き続き緊密な協議を推進すること、施設・区域に関連する問題に積極的に対応することなどがこの中で確認されている。なお、4月の日米首脳会談に先立って、日米安保条約の円滑かつ効果的な運用に寄与すること及び国際連合を中心とした国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的として、自衛隊と米軍との間で物品又は役務を相互に提供するための枠組みを設けるための日米物品役務相互提供協定が署名された。
ハ.「日米防衛協力のための指針」の見直し
1978年に策定された現行の「日米防衛協力のための指針」の見直しの開始も、日米安保共同宣言において表明された。この「指針」見直し作業は、95年11月に決定された新防衛大綱の内容と調和を保ちつつ、冷戦後の新たな安全保障情勢の中で、日米間の防衛協力を一層増進するために行われるものである。6月には日米安全保障協議委員会の下部機構である防衛協力小委員会を改組し、この見直し作業を効果的に行うための体制を整備し、作業に着手した。そして、9月の日米安全保障協議委員会において「指針」見直し作業の進捗状況報告が出され、この作業が97年秋に終了することを目途に行われることが明らかにされた。
この見直し作業においては、日米安保共同宣言において示されたとおり、日本周辺地域において発生し得る事態で日本の平和と安全に重要な影響を与える場合における日米間の協力に関する研究を始めとする検討が行われているが、この作業はあくまでも日本国憲法の枠内で、日米同盟関係の基本的な枠組みを変更することなく行われるものである。また、両国の国内及び近隣諸国における理解を増進するため、見直し作業の透明性を保つよう配慮する方針である。
ニ.在日米軍駐留の支援
日本政府は、在日米軍の駐留を支援するため、96年に発効した新たな「駐留経費に関する特別協定」に基づき米軍従業員の労務費並びに米軍の光熱水料及び訓練移転費を負担するなど自主的にできる限りの努力を行ってきている(96年度には、在日米軍駐留経費としてこの特別協定関係部分を含め約6,389億円を負担)。米国政府は、このような日本側の努力を高く評価しており、駐留経費負担を始めとする日本の努力は、この地域における安定要因としての米軍のプレゼンスを確保する上で重要である。
ホ.防衛技術面の米国との協力
防衛分野において、日本との技術の相互交流に対する米国側の関心は高く、日米の防衛技術交流を更に進めることは日米安保体制の効果的な運用を確保する上で重要な課題となっている。現在既に進められているダクテッドロケット・エンジン、先進鋼技術及び戦闘車両用セラミック・エンジンの共同研究に加え、9月にはアイセーフ・レーザー・レーダーの共同研究が開始されることとなった。また、航空自衛隊の次期支援戦闘機(F-2)については、今後F-2を130機調達することを承認した95年末の閣議了解を受けて、F-2生産についての日米政府間取極が締結された。
また、弾道ミサイル防衛(BMD)については、BMDは今後の日本の防衛政策を検討していく上で重要な検討課題であるとの考えに立って、その導入の可否等についての政策判断を行うために必要な情報を収集するため、日米間で事務レベルの検討が行われている。