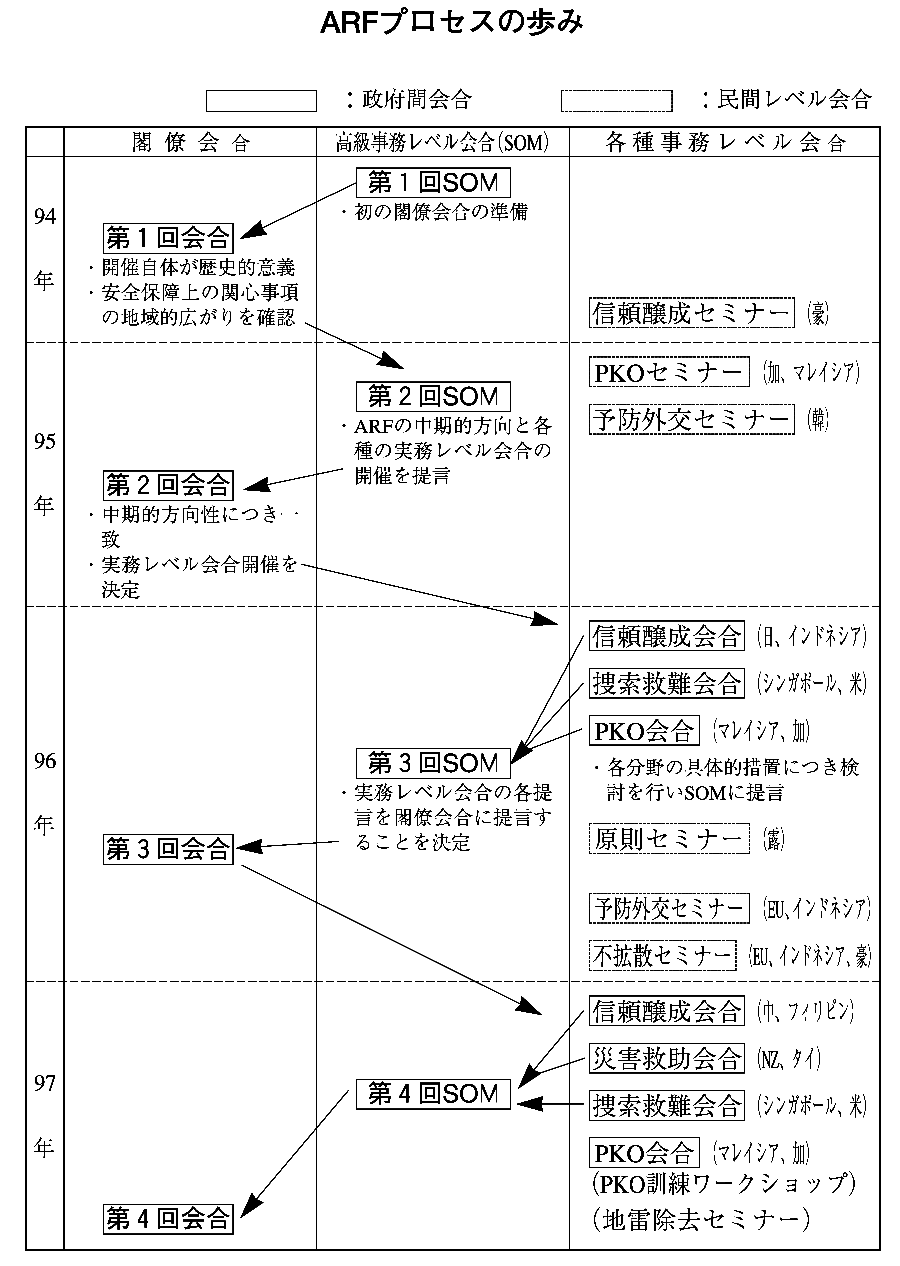| 3.アジア太平洋を巡る地域協力 |
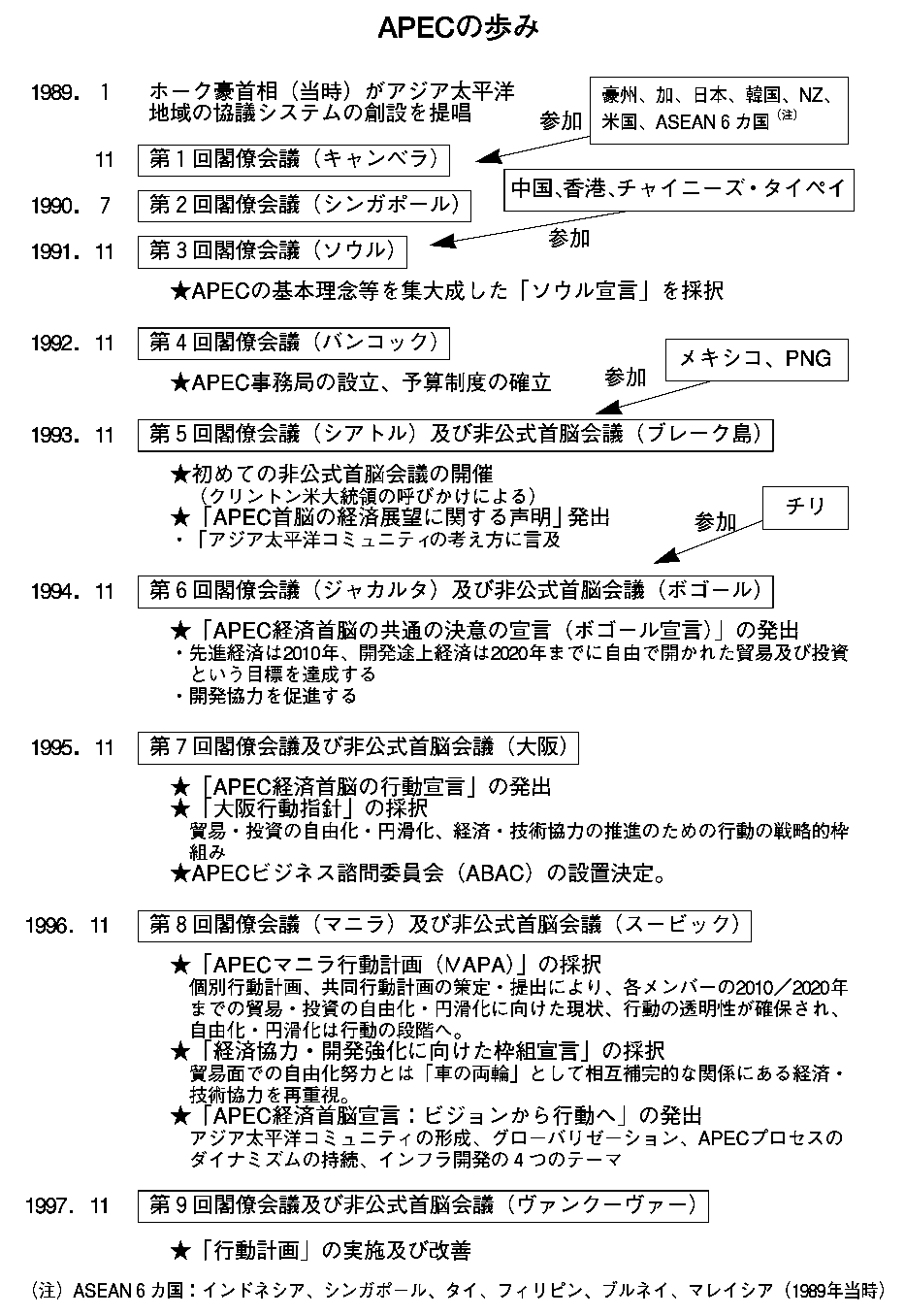
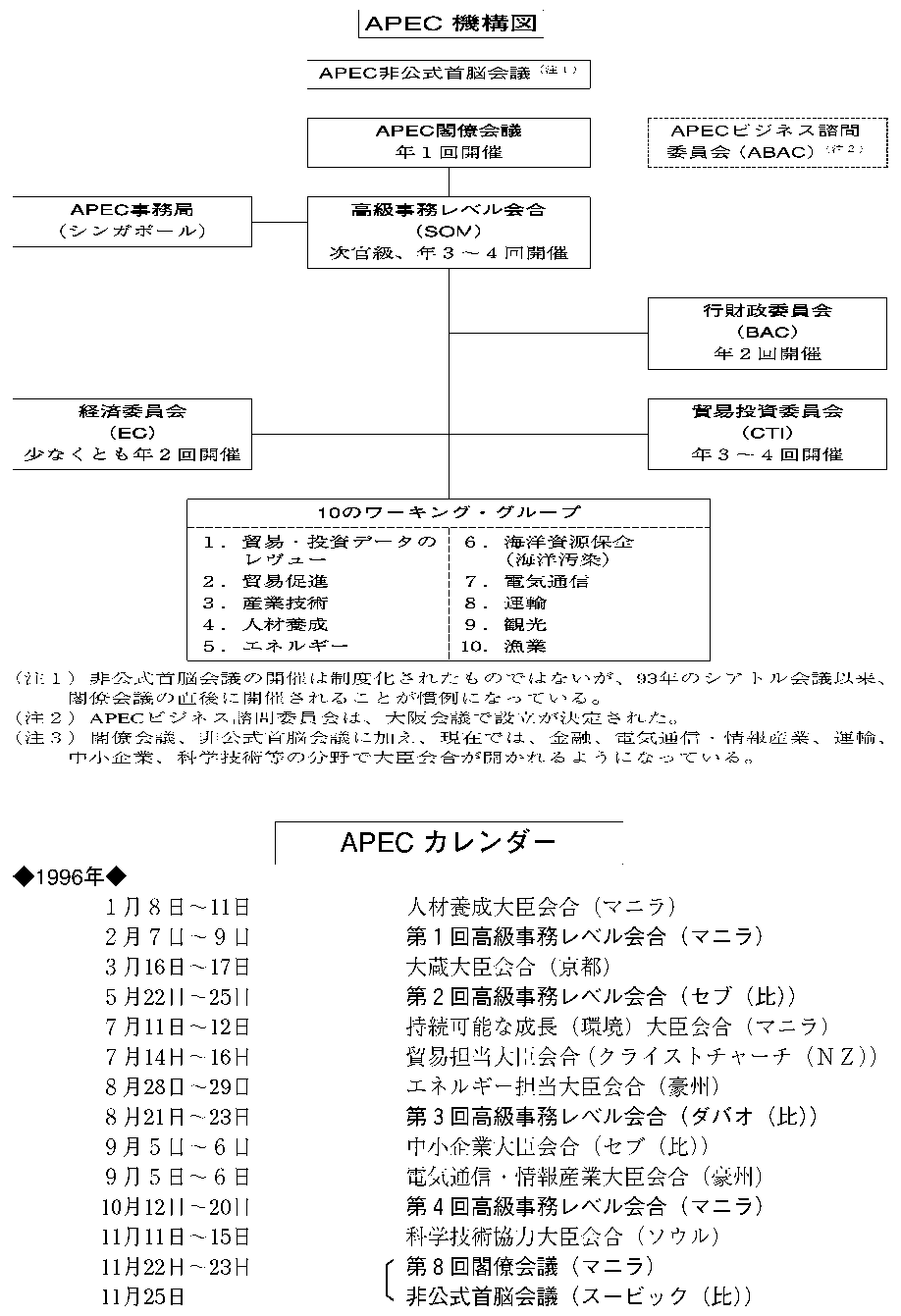
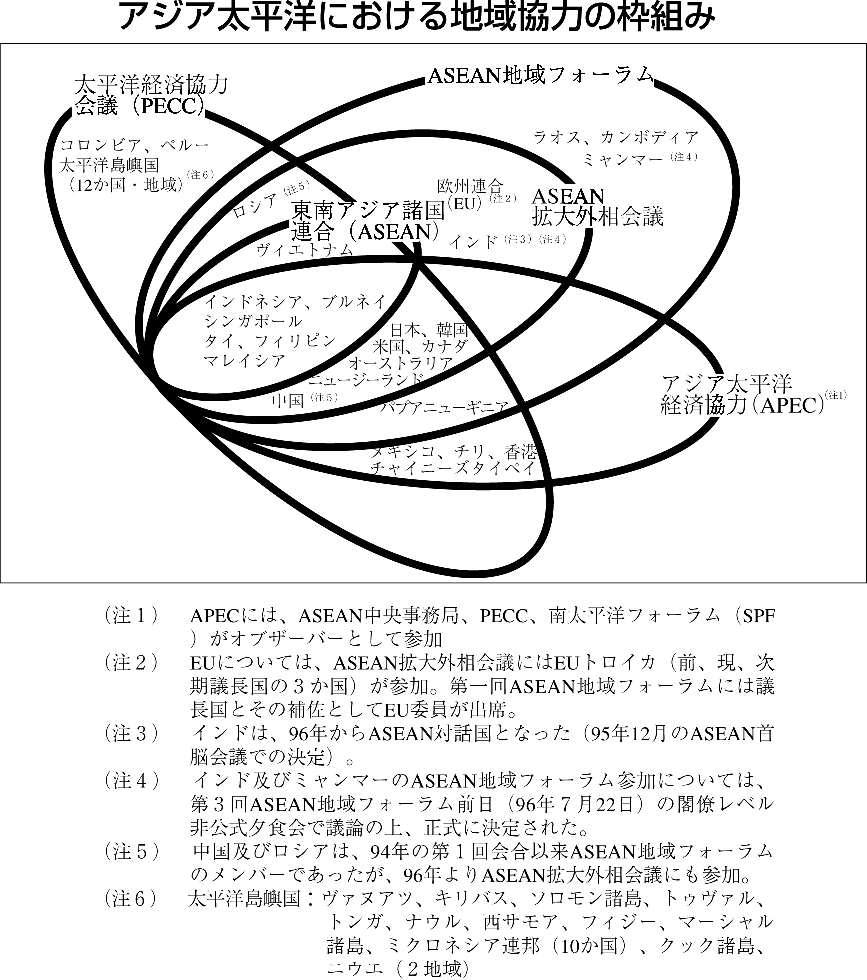
[APECフィリピン会合の意義]
アジア太平洋経済協力(APEC)は、歴史、言語、文化、社会・経済体制やその発展段階において多様な、18の国・地域を包含する地域協力であり、貿易や投資の自主的な自由化や広範な分野における経済・技術協力を進めつつ、アジア太平洋地域における経済発展のダイナミズムを維持しようとする協力の枠組みである。この多様性・自主性の特徴を活かしつつ、貿易・投資の自由化及び経済・技術協力を促進すべく、フィリピンで、11月22日及び23日、第8回閣僚会議(マニラ)が、25日、第4回非公式首脳会議(スービック)が開催された。
93年に開催された第1回非公式首脳会議は、アジア太平洋コミュニティーの形成という理念を提示したという点において、APEC が大きな変革をとげる契機となった。この理念は、94年のボゴール宣言において「2010年/2020年までの貿易と投資の自由化・円滑化の達成と経済・技術協力の促進」という明確な目標として明記され、翌95年、日本が議長として開催した大阪会合において、目標に向けての今後の具体的取組の指針が提示された。
96年のフィリピン会合は、この指針に従い、各メンバーが今後自由化に向けて取ろうとする具体的な行動を示した「個別行動計画」を提出し、また全メンバーが共同して APEC の各フォーラムを中心に進めることとなる「共同行動計画」を策定したという点において、APEC 自由化プロセスにおける「行動元年」とも呼び得る会合であった。
この他、APEC が当初活動の中心にすえていたがその後自由化重視の陰に隠れがちであった経済・技術協力の進め方を見直し、再度焦点をあてたこと、APEC の新規参加問題について一定の結論を出したことが、成果としてあげられる。
[フィリピン会合の具体的成果]

(イ) 自由で開かれた貿易と投資の実現に向けて
|
APEC での自由化プロセスの行動開始を最も端的に現すのが、マニラでの閣僚会議において採択された「マニラ行動計画(MAPA:Manila Action Plan for APEC)」である。この行動計画の中核をなすのが個別行動計画(IAP)、共同行動計画(CAP)であり、大阪行動指針の第一部(貿易・投資の自由化・円滑化)で記載される15の対象分野における具体的な行動を包括的に示している。例えば、日本の個別行動計画には、規制緩和、基準・適合性、投資、ビジネス関係者の移動などの分野を中心に、現時点で成し得る限りの措置が包括的に盛り込まれている。 それぞれの行動計画は、分野ごとに、短期、中期、長期の区分に従って、今後取られる自由化措置が明記されている他、冒頭部分では各国の自由化について簡潔にまとめられている。アジア・太平洋を取り巻く18もの国と地域がそろって自由化計画を提出したことは画期的な意義を有すると言える。また、この行動計画を公表することは、APEC域外や民間ビジネス界に対しても、APEC 地域の自由化行動の透明性・予測可能性を高めることになり、さらには、2010年/2020年の自由化達成に向けての各メンバーの進捗状況につき比較可能性を向上させ、ピア・プレッシャー(「仲間内の圧力」)をかけることのできるものとなっている。 これら行動計画は、97年1月から実施に移され、その実施状況、更には協議、レヴューのプロセスを経て、毎年改定されていく継続的作業である。96年は行動の初年度でもあり、全18メンバーが揃って計画を提出したこと自体が大きな成果として評価され得るが、今後は自由化達成に向けての着実な措置の実施及び行動計画の一層の充実をはかることが求められている。APEC の自由化は、各メンバーの「協調的自主的行動」により進めることとなっているが、真の自由化の実現のためには、今後各メンバーの一層の自覚と努力が求められている。 さらに、APEC の自由化の成果は、民間にとって有益な「目に見える成果」であるべきとの考え方から、APEC ビジネス諮問委員会(ABAC)が設置され、10の主要提言を含む報告書も提出された。 |
(ロ) 経済・技術協力の再重視
| APEC 創設時の活動の中心であった経済・技術協力は、従来の援助国・被援助国の関係ではなく、相互支援と自主性の原則に基づきつつ、この地域に存在する経済格差を解消するとの発想によるものであった。ここ数年の APEC の活動が自由化に傾きがちであった中で、議長国フィリピンのイニシアティヴにより、経済・技術協力に再度焦点が当てられたことも、96年の会合の特徴であった。具体的には、経済協力・開発強化に向けた枠組みに関する閣僚レベルでの宣言が発出され、APEC における協力に際しては、目標、指導原則、経済・技術協力の性格、テーマと優先付け等を行うべきであるということにつき共通の認識が得られた。 |
(ハ) 首脳宣言の採択と日本のイニシアティヴ
| スービックで開催された非公式首脳会議では、APEC 地域18メンバーの首脳が一堂に会し、(i)アジア太平洋コミュニティーの形成、(ii)グローバリゼーション、(iii)APEC プロセスのダイナミズムの持続、(iv)インフラ開発の4つのテーマに基づき意見交換が行われ、「APEC 経済首脳宣言:ビジョンから行動へ」を採択した。橋本総理大臣からは、日本のイニシアティヴとして、①アジア太平洋コミュニティ形成の観点から、情報通信インフラ整備の必要性を訴え、「アジア太平洋情報通信基盤テクノロジーセンター(神戸)」の積極的活用を呼びかけ、②太平洋の環境保全のため、日本の地球観測衛星の APEC ワイドでの活用と珊瑚礁保全等への共同での取組を提案、③地域の膨大なインフラ需要に対応するため、貿易保険機関の協力及びインフラ情報ネットワークの設立、④麻薬や銃器の不正取引防止対策等の国境を越えた社会経済問題を取り上げることを検討することを提案した。 |
(ニ) 新規参加問題への取組
| フィリピン会合においては、今後の APEC のあり方を規定する新規参加問題に関して一定の結論が出された。即ち、閣僚会議において、(i)96年に凍結を延長しないことを決定、(ii)97年に参加申請審査のための基準を精緻化し改訂、(iii)98年にこの基準に基づき新規メンバー名を発表、(iv)99年に新規メンバーの参加を認めることにつき意見の一致をみた。現在、11か国・地域が、新規参加を希望しており、今後、具体的な検討が行われる予定である。 |