【国連平和維持活動(PKO)】
国連自らが平和と安全に直接携わる中心的な活動としては、国連平和維持活動(PKO)(注29)がある。
PKOは、本来、安保理の決議に基づき、国連が停戦合意の成立後に、紛争当事者の間に立って、停戦や軍の撤退の監視等を行うことにより事態の沈静化や紛争の再発防止を図り、紛争当事者による対話を通じた紛争解決を支援することを目的とした活動である。しかし、現在ではその任務は多様化してきている。すなわち伝統的な任務に加え、選挙、文民警察、人権、難民帰還の支援から行政事務や復興開発まで含む複合的なPKOが増加している。
2004年には、アフリカのコートジボワールとブルンジ、中南米のハイチにおいて新しいミッションが始まり、展開中のPKOの総数は16となり、全世界で6万人を超える要員が活躍している。
日本は、PKOへの協力を含む国際平和協力を実施してきている。近年では東ティモールにおいて、2002年より国連東ティモール暫定行政機構(UNTAET)に、同年5月の東ティモール独立後は引き続いて国連東ティモール支援団(UNMISET)に、2004年6月まで、女性隊員を含むのべ約2,300名の自衛隊施設部隊や司令部要員を派遣し、同国の国づくりに協力(注30)してきた。また、1996年以来、ゴラン高原における停戦の監視などにより中東和平プロセスを下支えするUNDOFに継続的に要員を派遣しており、これまでの派遣人数は800人を超えている(注31)。

▲東ティモール国際平和協力隊より、帰国報告を受ける小泉総理大臣(6月 提供:内閣広報室)
さらに2004年10月には、PKOへの参加とは別に、国際平和協力法(注32)に基づく人道的な国際救援活動として、スーダン西部ダルフール地域における紛争の激化により隣国チャドへ流入したスーダン難民のため、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の要請を受け、難民用テント700張を輸送・譲渡した(ダルフール地域における紛争の詳細について138ページ参照)。
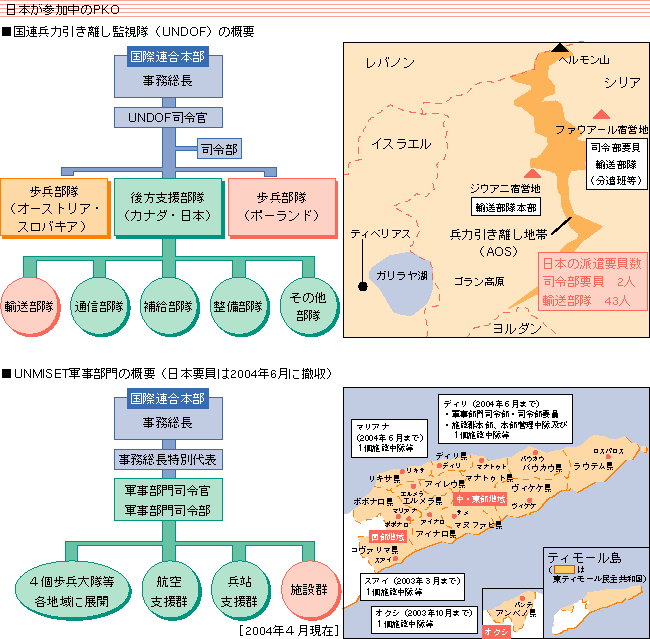
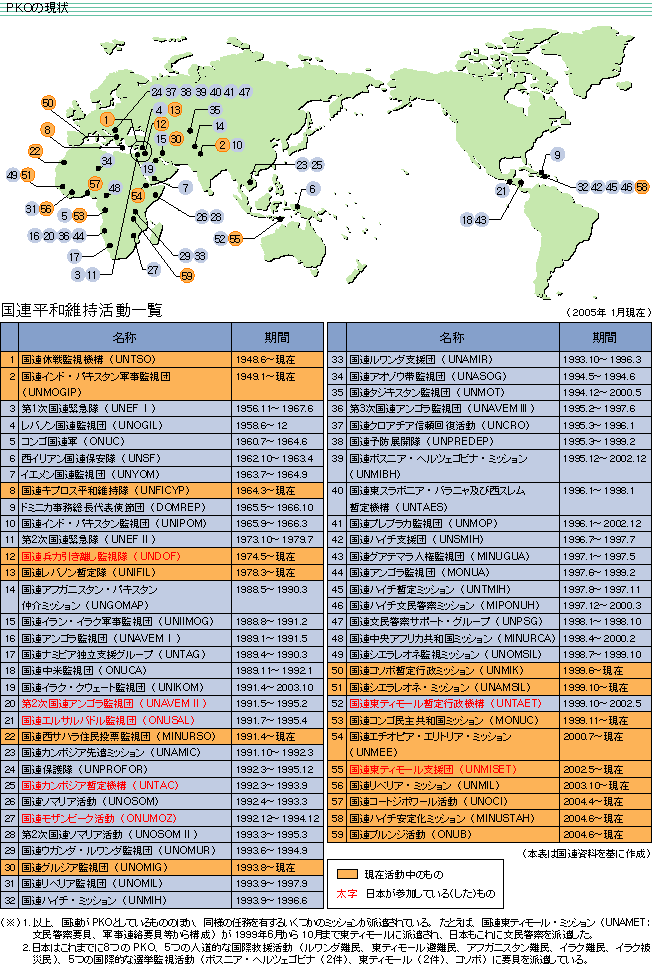
Excelファイルはこちら
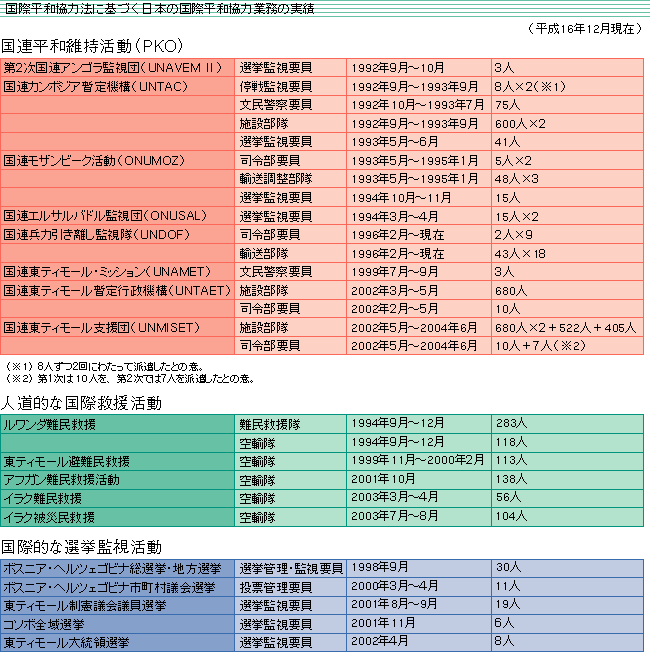
Excelファイルはこちら