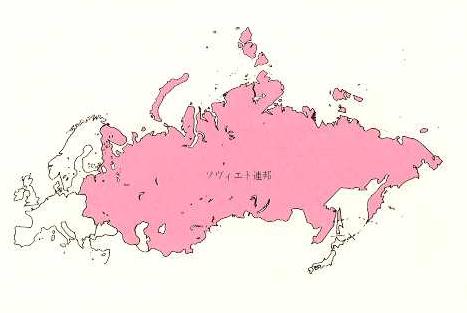
第4節 ソ 連
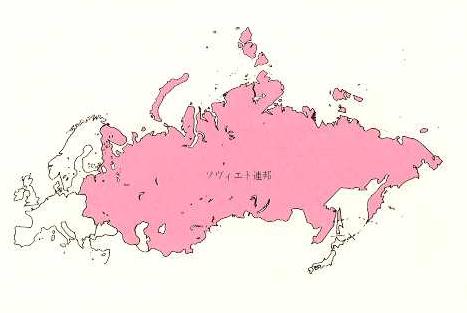
1. 内 政
(1) 政治改革の進展
ゴルバチョフ政権が成立後5年目を迎えたこの1年は、大幅な政治改革が断行されたという意味でソ連史上画期的な1年間であった。国内では、(あ)バルト3国、コーカサス地方等での民族問題の尖鋭化、(い)物不足、インフレ、失業等の経済的混乱の深刻化、(う)共産党の権威・指導力の低下等を背景に、ペレストロイカの現状に対する国民の不満が高揚し、党指導部に対する保守派の批判が強まった。ゴルバチョフ政権は、(あ)もはや共産党の力だけでは現在の社会的危機状況を克服することは困難であり、他の社会勢力の協力が必要である、(い)そのためには、権力を党から国家機関に委譲することが不可避であるとの認識の下、このような困難な局面を打開し、改革路線に一層弾みをつけるために、90年2月に共産党拡大中央委員会総会を招集し、憲法からの共産党の指導的役割条項の削除、複数政党制の容認及び大統領制の導入等を提案した。この提案は、党内の急進改革派及び保守派との激論を経て採択された。
90年3月の連邦人民代議員大会で初代大統領にゴルバチョフ書記長が選出された。大統領は従来の最高会議議長に比較し、(あ)軍の最高司令官となる、(い議会からの法案差し戻し権を有する、(う)議会の解散権を有する等の点で大幅に権限が強化された。また、大統領の付属機関として大統領会議と連邦評議会が設置された。
90年7月には第28回党大会が開催された。同大会では、保守派から指導部に対する激しい批判が見られ、エリツィン・ロシア共和国最高会議議長等、急進改革派の一部が離党したものの、結果的にゴルバチョフ大統領は、(あ)保守派を押さえ込み、(い)ペレストロイカ路線と現在の外交路線に対する党全体の承認を獲得し、(う)党が社会の前衛党から複数政党下での議会政党に変貌するとの方向性に対する基本的承認を取り付け、党大会を成功裡に乗り切った。
さらに、ゴルバチョフ大統領は党機構面でも書記長の補佐と書記局の主宰を任務とする副書記長を新設した。ゴルバチョフ大統領自身は書記長に選出され、副書記長にはゴルバチョフ大統領の推薦したイワシコ前ウクライナ最高会議議長が選出された。また、政治局、書記局等の指導部にもゴルバチョフ大統領の影響下の人物を多く配置する等、党内での政権基盤の強化を図った。
(2)「派閥」の形成
大幅な政治改革が進む中で、党指導のあり方に関する党内の議論が活発化し、その結果、急進改革派の地域間代議員グループを中心とする民主綱領派、保守派を中心とするマルクス・レーニン主義綱領派等の「派閥」が形成された。特に、地方選挙における民主綱領派の活躍は目覚ましく、90年4月にポポフ・モスクワ大学教授がモスクワ市議会議長に選出され、5月にエリツィン連邦最高会議代議員がロシア共和国最高会議議長に当選した。民主綱領派の中には、第28回党大会で同派の主張が受け入れられなかったことを不満として、連邦党から脱退を表明し、新党を設立する動きもみられる。
また、「民主化」の下で「複数政党制」に向けて市民が自主的に結成する非公認団体も結成され、ロシア民主党、自由民主党、社会党、キリスト教民主同盟等、多種多様な団体が登場した。
(3) 民族問題
民族問題に関しては、バルト3国、コーカサス地方、中央アジア諸国で問題が尖鋭化し、これらの問題の解決はゴルバチョフ政権にとってペレストロイカの中心を占める重要課題となった。同政権は、89年9月に民族問題全般について審議するための党中央委員会総会を招集し、民族政策に対する党綱領を採択したが、その後も民族紛争は一向に鎮静化せず、むしろ複雑化の方向に向かった。
バルト3国では、独ソ不可侵条約締結50周年にあたる89年8月に同3国をつなぐ「人間の鎖」が組織され、バルト3国のソ連邦からの独立志向とバルト国民の団結の強さが表明された。12月にはリトアニア共産党が連邦共産党からの脱退を決定した。90年3月のリトアニア最高会議選挙では民族戦線サユジスが過半数を制し、同戦線を中心勢力とするリトアニア最高会議は3月11日にリトアニアのソ連邦からの独立宣言を採択した。ゴルバチョフ政権は同宣言を連邦憲法違反とし、これを撤回させるべく石油、天然ガス等の供給削減を実施した。これに対し西側諸国は対話を通じた平和的な解決を求める声明や談話を発表し、これらの措置の撤回を求めた。6月、リトアニア最高会議は連邦との交渉期間中における独立宣言の一時停止を宣言し、その結果、制裁措置は解除された。
また、エストニアが3月30日、ラトヴィアが5月4日に独立宣言に踏み切り、3国が足並みを揃えた。ただし、エストニア及びラトヴィアは、移行期間を設け、連邦側との交渉による独立達成を志向している。
88年2月に始まったナゴルノ・カラバフ自治州の帰属をめぐるアゼルバイジャン人とアルメニア人との民族紛争では、多くの犠牲者が出ている。連邦政府が同自治州を直接管轄する特別措置も効を奏さず、状況は一層深刻化した。89年末、両民族の対立が激化し、90年1月には大規模な流血事件に発展するに及び、ゴルバチョフ政権も遂に紛争地域に非常事態宣言を布告し、正規軍等を投入して武力制圧を断行した。
中央アジア地域では、89年6月のウズベク暴動(注)に引き続き、90年6月にキルギス共和国オシ州で住宅建設用地の確保等をめぐりキルギス人とウズベク人が衝突し、これがキルギス共和国全体に拡大して、死者150名以上が発生した。
このような民族問題は、さらにロシア共和国、ウクライナ共和国等の連邦構成共和国の独自性を求める動きへと波及した。
90年6月12日、ロシア人民代議員大会は「ロシア共和国の主権に関する宣言」を圧倒的多数で採択し、同主権宣言は直ちに発効した。同主権宣言は、(あ)ロシア共和国の憲法・法律が連邦の憲法・法律に対し優先すること、(い)ロシア共和国が天然資源の所有、利用等に対する排他的権利を有すること、(う)ロシア共和国は連邦からの脱退権を留保すること、(え)ロシア共和国の領域は国民投票による意思表明なしに変更されないこと等を規定している。
このようなロシア民族主義の高揚等を背景に、ロシア共和国独自の党組織の創設を求める声が高まり、90年6月、ロシア共和国共産党の創設が採択された。ロシア共和国共産党の第一書記にはポロスコフ・クラスノダール地方党第一書記が選出された。
ウクライナ共和国も90年7月16日に主権宣言を行い、共和国軍の創設、自国通貨の発行等につき決議を行った。その他、モルダビア、ウズベク、カザフ、白ロシアの各共和国も主権宣言等を行った。
このような状況の中でゴルバチョフ政権は新しい形として「緩やかな連邦制」を目指し、現在連邦評議会を中心に検討を行っている。
(4) 経 済
ペレストロイカの開始以来5年間、政治改革やグラスノスチ(情報公開)などの分野に比べ、経済面では国民が生活の中で実感しうる成果は見られず、物不足やインフレなど、事態はむしろ深刻化しつつある。89年夏に各地の炭坑で起きた大規模なストライキ、民族間の対立と紛争、規律の弛緩などの影響もあって、89年の主要経済指数は88年を大幅に下回り、さらに90年上半期の経済実績は前年同期比でGNP1%減と異例のマイナス成長となり、経済の混迷の度合いは一層深まっている。ペレストロイカの流れを進展させる上で最も重要な意味を持つ国民生活向上の課題も、解決が見られないばかりが、依然消費物資、食料不足の状況が続いている。一部品目については配給券制が導入されたり、物不足を補うため、食品・消費財を大量輸入しているが、それでも問題は一向に解消されていない。お金があって買いたいのにものがないので買えない、いわゆる未充足需要は89年末の段階で1,650億ルーブル(約2,600億ドル)に上る。
このような状況の中で、試行錯誤の過程を経ながらも市場指向型経済を目指して、所有法の制定を始めとする各種経済関係法令の整備や経済改革に関する政府プログラムの作成が進められている。
所有法(90年3月採択)は、所有形態の多様化を図り、特にイデオロギーとも絡んで従来国有形態を偏重しがちであった傾向を是正して非国営セクターに法的正当性を付与する目的で制定された。ただし、この法律によって資本主義経済におけるような生産手段の私有が認められたということではなく、いわゆる「私有」の対象となる範囲は個人農業経営などの一部のものに限られたものとなっている。
このほかにも、既に賃貸基本法(89年11月)、土地基本法(90年2月)、企業法(90年6月)などが採択されており、今後、税制、銀行、雇用、反独占などの法律が制定される予定となっている。
89年秋頃から、経済改革のタイム・スケジュールを打ち出したプログラムが検討され、12月、同プログラムは人民代議員大会で採択されたが、90年に入り、ゴルバチョフ大統領はこのプログラムの保守性を指摘しつつ、改革の「加速化」、「急進化」を強調し始め、見直しの気運が高まった。
このような動きを受ける形で、その後、新しい政府プログラム案が作成され、大統領会議での検討をも経て、5月24日最高会議にルイシコフ首相の報告の形で上程され、審議された。その内容は調整市場経済への移行を95年までに3段階を経て行うことを予定するもので、市場指向性を強めたものとなっている。特に、経済改革最大の課題である価格改革は91年から本格的に着手し、食品価格を約2倍値上げし、特にパン類については90年7月1日から約3倍値上げすることを予定していた。これらの値上げに際しては併せて補償措置を予定してはいるが、国民生活を直撃する内容であるだけに、国民の間に不安や動揺も予想され、モスクワでは市民による買占めの動きも見られた。
他方、このプログラム案も、物価値上げ反対の声が強く反映して、結局政府が9月1日までに新たな代替案を作成することとなり、これが秋以降の最高会議第3会期で審議されることとなった。なお、7月1日からのパン類値上げについても秋以降再検討されることとなった。
2.外 交
ソ連は、東欧情勢が急変し、ドイツ統一問題が急浮上する中で、東欧への不介入の姿勢を貫き、さらに、これに対する支持を与えることにより、欧州における戦後秩序の崩壊と新秩序の模索を促した。対米外交においても、首脳会談、外相会談を通じ協調関係に向けた多くの具体的成果を挙げた。さらに、韓ソ首脳会談の実現等、アジア地域においても新しい動きを示した。
(1) 対米・対西欧関係
対米関係では、89年12月、米ソ両首脳は、マルタにおいてプッシュ米大統領就任後初の会談を行った。両首脳は、同会談を交渉を目的としない非公式会談としつつも、広範な問題にわたって意見を交換し、戦略核兵器削減交渉(START)及び欧州通常戦力(CFE)交渉について90年内の合意を約した。また、会談後の合同記者会見において、米ソ関係が対立から協力に向かいつつあることを確認し、両国関係の「新時代入り」を宣言した。
その後、90年5月末~6月初めにワシントンで開催された米ソ首脳会談では、戦略兵器削減交渉に関する基本合意を共同声明として発出し、化学兵器廃棄協定、通商協定等、多くの協定に署名した。他方、同首脳会談では、今後の国際秩序構築の上での重要問題であるドイツ統一問題及びバルト3国問題については、両者の立場の理解は深まったものの、対立は解消せず、今後の継続協議とされた。
ソ連の対西欧外交を見ると、ゴルバチョフ書記長は、フィンランド(89年10月)、イタリア(11月)を訪問したほか、マルルーニー・カナダ首相(11月)、ミッテラン仏大統領(12月及び90年5月)、サッチャー英首相(6月)が訪ソした。
これらの首脳会談を通じて、ソ連は経済活性化のため各国に対し資本及び技術の導入を促進するため二国間関係の強化や対ソ経済協力の必要性を訴え、貿易、経済関係の多くの協定や取極を締結した。西欧の統合に向けた動きに対して、ゴルバチョフ書記長は特に西独、フランスを訪間した際に「欧州共通の家」の建設を強く呼び掛けた。シェヴアルナッゼ外相は12月、ブラッセルを訪問し、ソ連・ EC間の貿易・経済協力協定に署名した。イタリア訪問に際しては、ヴァチカンに法王を訪問し、ヴァチカンとの外交関係樹立に合意し和解を達成した。
他方、11月9日のベルリンの壁の崩壊により現実的問題となったドイツ統一について、ソ連は当初、日程に上っていないとして、コール西独首相のドイツ統一に関する10項目提案(11月)に対しても強く反発した。
その後、モドロー東独首相の統一ドイツの中立化を条件とした両独統一構想(2月)を支持する立場を表明した。ゴルバチョフ書記長は、訪ソしたコール首相との会談(2月)において、ドイツ統一問題が基本的にドイツ人の民族自決権の問題であることを認めた。
(2) 対東欧関係
ソ連は、従来、資本主義諸国との関係に適用してきた主権尊重、内政不干渉、選択の自由等の諸原則を社会主義諸国との関係にも適用し、東欧各国にペレストロイカを勧奨し、各国の自主性尊重を強調した。
ソ連は、ポーランドでの「連帯」主導の連立内閣成立(9月)、ベルリンの壁の崩壊(11月)、さらにはルーマニアにおけるチャウシェスク政権の崩壊(12月)等、各国における改革への動きに支持を与えた。また、ゴルバチョフ書記長は、ワルシャワ条約機構加盟国首脳会議(12月)を開催し、「プラハの春」に軍事介入した5か国の連名で、またソ連単独で、同軍事介入を批判する声明を発表した。90年に入り、ソ連とチェッコ・スロヴァキア(2月)、ハンガリー(3月)との間で91年夏までのソ連軍撤退に関する協定が署名された。
(3) 対アジア関係
中ソ間では、89年5月の中ソ関係正常化以降、田紀雲副総理の訪ソ(7月)、ルキヤノフ最高会議第一副議長(9月)及びファーリン党中央委員会国際部長(12月)の訪中が行われた。90年4月、李鵬総理がソ連を訪問し、中ソ両国は、両国関係を平和共存5原則に従い発展させることを確認し、国境兵力削減問題や経済協力問題に関する文書に署名した。
また、90年3月、モンゴルとの間で92年までに駐留ソ連軍の撤退を完了する旨の協定が署名された。
さらに90年1月、ソ連はソ連軍のカムラン湾からの撤退を開始したこと、89年末にMIG-23戦闘機及びTu-16爆撃機の撤収を完了したことを発表した。
90年には韓国とソ連の関係正常化に向けた動きが見られた。3月、韓国与党・民主自由党の金泳三最高委員が訪ソした。さらに、6月にはサン・フランシスコにおいて、盧泰愚
その他、スハルト・インドネシア大統領の訪ソ(9月)、ルイシコフ首相のタイ、豪州、シンガポール歴訪(90年2月)等、ソ連はアジア・太平洋諸国に対する外交を積極的に展開した。
(4) 対中東関係
ソ連は、ラフサンジャニ大統領の下で現実主義的政策をとるイランとの関係改善を進めた。89年6月、ラフサンジャニ国会議長(当時)はホメイニ師死去の直後にもかかわらずソ連を訪問し、7月~8月にはシェヴアルナッゼ外相がイランを訪問した。
80年代半ばより徐々に修復されていたソ連・エジプト関係は、90年5月にムバラク大統領がエジプト元首として18年ぶりに訪ソしたことにより大きく改善した。
90年に入って、ソ連系ユダヤ人のイスラエル占領地入植問題がアラブ諸国による反発を招いた。ソ連系ユダヤ人出国数は、ゴルバチョフ政権の出国緩和によって急激に増加してきたが、イスラエルは移住者の占領地への居住を推進した。これに対し、ソ連はイスラエルの政策を批判した。
(5) 対中南米関係
シェヴアルナッゼ外相は、89年10月急遽ニカラグァ(ソ連外相として初めて)及びキューバを訪問した。ソ連はニカラグァに対して武器供与の停止を再確認するとともに、ニカラグァは、キューバを始め他のソ連圏諸国からニカラグァへの軽火器、弾薬の搬入を公開することを約束した。この他、コロール・ブラジル次期大統領の訪ソ(90年1月)、チリとの国交正常化(同年3月)を始めとして、ソ連は中南米諸国との関係強化を図っている。
3.わが国との関係
(1)概 観
わが国とソ連との間では、88年12月のシェヴアルナッゼ外相の訪日以来90年7月末までに、5回の外相会談、5回の次官レベルの平和条約作業グループが開催されたほか、89年11月のヤコブレフ政治局員の訪日、90年1月の安倍元外務大臣の訪ソ等も行われ、両国間の政治対話が活発化した。また、89年9月、国連での外相会談においてシェヴァルナッゼ外相から91年にゴルバチョフ議長(当時)が訪日するとの意向が表明され、90年2月には同議長自身の海部総理大臣あて親書の中でこれを確認した。
わが国は、このような状況の下で、89年5月の外相会談において宇野外務大臣(当時)が提示した「北方領土問題を解決して平和条約の締結を最重要課題としつつ、日ソ関係全体を拡大均衡させる」との基本的考え方に基づき、各種交渉における積極的な議論の展開のほか、ペレストロイカの促進に関するソ連経済改革調査団の2次にわたる受入れ、海運、海上保安、渡り烏保護の分野での新たな政府間協議の開催、環境協定、貿易支払協定の準備等、両国関係の改善のために積極的なイニシアティヴをとってきている。また、ソ連も、わが国の在樺太未帰還邦人調査団受入れ、北方墓参地域の拡大等の対応を示してきている。他方、このような対話、交流を通じる両国間の相互理解の深化にもかかわらず、両国間の最大の懸案たる北方領土問題については、ソ連側の態度にこれまでのところ実質的変化は見られず、依然として日ソ間の立場に大きな相違がある。
今後、日ソ間では、ソ連の内外政上の事情により延期されていた日ソ外相間協議が90年9月にわが国で開催される予定であり、その後然るべき時期にソ連で同協議を行い、これらを通じてゴルバチョフ大統領訪日へ向けての準備を進めていく予定である。
米ソ関係、欧州情勢に見られる歴史的な東西間の緊張緩和の動きを背景に、これを真にグローバルなものとして定着させるためには、アジア・太平洋情勢の改善、特に日ソ関係の正常化と抜本的改善が重要であるとの認識が国際的にも広まりつつある。ブッシュ大統領が5月の米ソ首脳会談で東西関係改善の観点から北方領土問題を取り上げたのは、その典型的な例と言えよう。
91年のゴルバチョフ大統領の訪日は、このような意味における日ソ関係改善のための歴史的契機となり得る重要な訪問である。わが国としては、日ソ交渉が正念場を迎える中で、このような国際世論も踏まえつつ、一致した国民世論の下で、従来にも増して粘り強い対ソ外交を進めていく必要がある。
(2) 平和条約交渉
北方領土問題を含む日ソ平和条約交渉は、外相及び外務次官レヴェルでの会談を通じて積極的に進められた。ソ連は、領土問題に関する歴史的・法的議論には応じるものの、議論の実質についてはこれまでの立場を何ら変えておらず、依然として厳しい立場を取り続けている。
89年9月、モスクワで小和田外務審議官は、ロガチョフ外務次官と協議した際、今後の平和条約作業グループの進め方に言及し、日ソ関係に関して両国関係を真に安定した基盤に乗せるためには、平和条約の締結が緊要な課題であること、平和条約の最重要課題は領土問題の解決であり、それを曖昧にしたものには応じられないとのわが国の立場を改めて明確にした。
89年9月の国連総会において、中山外務大臣はシェヴアルナッゼ外相と会談し、最重要問題である北方領土問題につき実質的進展を見出しながら、他の側面における努力をしつつ「日ソ関係全体の拡大均衡」を実現すべきであること、今後の平和条約交渉、平和条約作業グループの中で双方で英知を絞り問題解決の突破口を見いだすべきであること、このようにして「我々の手で我々の時代に日ソ関係に新しいページを開きたい」ことを主張した。
89年12月、東京で行われた第4回日ソ平和条約作業グループでは、第3回作業グループにおける北方領土問題の歴史的、国際法的論点に関する日本の主張に対するソ連の反論を中心に議論が行われた。これに対し日本の反論は次回に譲るとし、必要な反論を行うにとどめた。このような議論の中でソ連は、「平和条約作業グループの作業に積極的性格を持たせるためには、第2次世界大戦の結果生じ、現在も存在している現実を承認する立場を日本がとり、領土確定について根拠のない非難を止めるということもこの目的に資する」と述べ、領土問題につき従来通りのかたくなな態度に終始した。
(3) 経 済 関 係
89年の貿易総額は60億8,600万ドル(前年比3.2%増)と初めて60億ドル台に達した。また、貿易バランスは日本側の7,700万ドルの黒字にとどまり、日ソ貿易はほぼ均衡状態にある。
商品別に見ると、輸出では、繊維製品、加熱冷却用機器、電気機器、輸送機器が増加した反面、従来の対ソ主要輸出品である鉄鋼、金属加工機械、建設・鉱山機械は減少した。なお、最近の傾向として乗用車、複写機、VTR等の輸出急増が目立つ。輸入では、綿花、非鉄金属が増加した反面、非貨幣用金、魚介類が減少した。木材については、88年とほぼ同水準となった。
87年1月にソ連で合弁事業設立に関する大臣会議の決定が施行されて以来、90年4月1日現在でサービス業、木材加工、水産分野を中心に28件の日ソ合弁企業がソ連国内に設立されている模様である。
なお、わが国は、ペレストロイカ(自由化、民主化、市場経済の導入)を支持するとの考え方に立ち、また日ソ関係を拡大均衡させるとの観点も踏まえて、89年11月及び90年4月の2度にわたり、ソ連から次官級の経済改革調査団を受け入れた。同調査団は現在ソ連で進められている国内経済改革の参考とするためわが国経済運営における政府と民間の役割等を調査したが、その受入れはソ連側の高い評価を得た。
(4) 漁 業 関 係
90年の日ソ双方の200海里水域での相手国の漁獲を決めるいわゆる日ソ200海里交渉は、89年11月下旬からモスクワで開催され、12月に一部有償部分を除き妥結した。漁獲割当量は無償部分(双方)18万2,000トン(89年21万トン)、有償部分(日本側のみ)3万5,000トン(89年10万トン)となった。また、妥結できなかった一部有償部分についての追加的協議が90年2月にモスクワで開催されたが、双方の主張の隔たりが大きく、合意に至らなかった。
90年の日本漁船におけるソ連系サケ・マスの漁獲に関するいわゆる日ソ・サケ・マス交渉は、ソ連が88年に出した日本側による公海操業の全面停止を前提声明として、総漁獲量の大幅削減を引き続き主張したため、90年3月にいったん中断した。4月に再開された交渉においてソ連は若干の譲歩を見せ、総漁獲量1万1,000トン(89年は1万5,000トン)となり、漁業協力費は31億5,000万円(89年は33億5,000万円)となった。
(5) 科学技術交流
89年12月、モスクワにおいて科学技術協力委員会が開催され、90年の協力計画として88年に合意された農林業、核融合、放射線医学、人工心臓、波動歯車、環境、地震予知の7分野に加え、エイズに関する協力が新たに加わり、日ソ間の協力は8分野に拡大された。
また、89年12月には日ソ環境協定に関する第1回交渉が開始された。
(6) 文 化 交 流
87年12月に発効した日ソ文化協定に基づき日ソ文化交流委員会が設置され、第1回会合において89年4月1日から91年3月31日までの実施計画が作成された。実施計画は文化の広範な分野の交流を具体的に規定しているが、特に、長年の懸案であった政府レベルの交換留学生の実施及びソ連で初の日本週間(モスクワ)の実施は特筆に値する。
|
89年6月、ウズベク人とメスヘチア人とが衝突し、死者約100名が発生した事件。 |