
第4節 西欧

1.「一つの声」で話す西欧
近年,西欧は政治的にも,経済的にも,一つにまとまろうとの動きを強めており,87年から88年前半にかけても注目すべき動きが見られた。
(1) EC市場統合
87年7月,「単一欧州議定書」が発効した。この条約は,92年末までに財,人,サービス,資本の自由な移動を確保して域内に国境のない領域を完成するとの目標を示し,また,意思決定の方法として従来の全会一致制に代わり,多くの事項について特定多数決を採用することによって政策決定を迅速化しようとするなど,画期的なものである。
EC市場統合の完成は,統合された3億2千万人の巨大な市場の登場を意味する。EC,日本,米国3市場を比較したのが次表である。

統合が完成すると,EC側の調査報告によれば,各種規制の撤廃および統合による域内市場の一体化,合理化,競争の促進等による経済効果は大きく,ECの成長率は少なくとも4.5%上昇するとの試算がある。
EC経済の活性化は,自由主義経済全体の強化にもつながるものであろう。
統合の現状を概観すると,農業,漁業,通商政策の分野では,構成国の権限がECに移行され統合がほぼ完了しているが,他の分野ではさほど統合は進展していない。92年末の市場統合完成を目指して,次のような約300項目に係る作業が予定されている。

これらの作業の進捗状況は,EC委員会の公表した報告書及び報道等によれば,88年6月の時点では,EC委員会は約300項目のうち約200項目について閣僚理事会に提案を提出,同理事会はそのうち91項目を採択した。一時期,当初の計画より相当な遅れが生じたが,現在ではかなりの進捗を見ているといえよう。
ECの現在の最大の課題は,(あ)共通農業政策,農業補助政策からくる生産過剰,(い)これに関連した財政規律問題(EC予算全体の約3分の2が農業支出),(う)EC内の「南北格差」是正,の3点に集約できる。88年2月のECサミットでは,これらの問題につき40時間近くの交渉を経て,予算自主財源の拡大,農業予算の抑制,経済的地域格差是正のための構造基金の増額等を内容とするEC財政改革につき合意した。これは,国内事情を抱える各国が大きな努力を払って到達した妥協の産物であり,EC諸国の統合へ向けての強い政治的意思の表れであると考えられる。
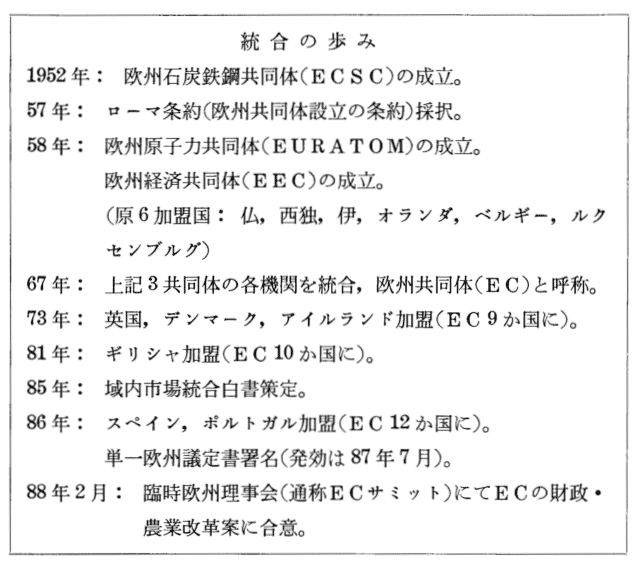
(2) 欧州政治協力
経済分野における統合の努力と並行して,政治分野でのEC諸国間の協力も強化されている。先に述べた「単一欧州議定書」において,従来明文の規定のないまま実体的に行われていたEC政治協力が成文化された。政治統合には常に国家主権の問題が絡み,困難が多いとしても,外交政策面での共同歩調等で政治協力が進展している。例えば,87年にはEC12か国が中東和平に関する声明を発表するとともに,当時の議長国ベルギーの外相が12か国の代表として中東地域を歴訪する等,一部の地域紛争に関しECが旗印を鮮明にするのが見られた。その後も,ECは,東西関係,中東,アフガニスタン,南アフリカ,中米等について共同声明を発表し,ECとしての共通の立場を明らかにしている。今後,世界の主要な問題につき,西欧主要国のみならず,EC12か国が米国及び日本と並んで「一つの声」で発言することがさらに多くなろう。
(3) NATOにおける「欧州の柱」
西欧諸国は安全保障の面でも「西欧の声」を強めている。その背景については後述の通りであるが,具体的には,次のような動きが見られる。

これらの動きは,ド・ゴール元大統領以来の伝統の下,できるだけフリー・ハンドを確保するため,NATOの加盟国でありながらNATOの軍事機構に属しない仏のイニシアティブによるところが大きい。これに対し,英国等の一部にはNATOの結束を損なうのではないか,との警戒心も見られたと伝えられたが,現在ではむしろNATOを補完し,西欧の安全保障を強化するものとして歓迎されるに至った。
2. 欧州における東西関係
(1) INF条約の成立と西欧
過去数年間欧州における最大の安全保障問題はINF問題であった。79年12月NATO二重決定,81年11月米ソINF交渉開始,83年末INFミサイルの西欧配備及びINF交渉の中断,85年3月INF交渉再開を経て,87年12月INF条約署名,88年6月回条約発効に至ったが,その過程において,西欧においては安保論議が繰り広げられた。
87年以降の主たる動きを見ると,87年7月,米国が81年の交渉開始以来提案していたINFのグローバル全廃をソ連がようやく受け入れるに至り,西欧の安保論議は,西独が保有し核弾頭のみ米軍管理となっている短射程INFパーシングIaの取扱いに焦点が当てられた。西独国内の論議を経て,結局8月,コール西独首相はパーシングIaは近代化せず放棄するとの声明を発表した。
12月のINF条約署名後は,INF条約の対象外となっている短距離核の取扱いが焦点となり,その近代化の是非,軍備管理交渉での取扱いが議論された。この問題をめぐってNATO内での意見の相違も伝えられたが,88年3月のNATOサミットまでには,意見の調整が図られ,6年振りに開催された同サミットにおいては,加盟国の結束が示された。
(2) INFミサイル全廃後のNATOの安全保障
INFミサイルの全廃が現実のものとなった現在,NATOにおいては改めて安全保障の在り方が大きな問題となっている。
(イ) NATO核戦力の在り方
NATOの抑止戦略の基本は「柔軟反応戦略」であり,これは,通常戦力及び核戦力によって柔軟に対応できる態勢を確保し,もって,武力行使の発生を未然に防止しようとするものである。NATO諸国は,戦後40数年間欧州の平和が維持されたのは,「柔軟反応戦略」が有効であったためと評価しており,INF全廃後は「柔軟反応戦略」を維持するための核戦力は如何なるものであるべきか,真剣な検討が進められている。
(ロ) 通常戦力の強化
NATOは,ワルシャワ条約機構軍の通常戦力による侵攻に対し,通常戦力で対処できない場合,先に核戦力を使用することも想定している。他方,従来より,このような核への依存度をできるだけ低くするため,通常戦力の強化・改善の施策を推進してきている。INF全廃は通常戦力の必要性を減少させるのではなく,むしろ,通常戦力にはできる限り通常戦力で対処できることが望ましいことを改めて浮彫りにしたと言え,NATO諸国は従来にも増して通常戦力の強化の必要性を認識している。
(ハ) 今後の軍備管理・軍縮の基本方針
NATOでは,INFミサイルを全廃する条約が発効した現在,今後の軍備管理・軍縮の在り方が改めて議論されている。NATOは,87年6月の外相理事会において,軍備管理・軍縮の包括的概念の検討について合意した。同概念は,(あ)米ソの戦略核50%削減,(い)化学兵器のグローバル撤廃,(う)全欧州における通常戦力の安定的かつ安全なレベルの確立,(え)(い)及び(う)との関連における米ソの短距離核ミサイルの削減,を含むものであり,個々の軍備管理交渉を軍備管理全体の中でとらえるための検討を行うことにより,安全保障を高めるには,どの軍備管理交渉をどこまで,どのように進めるべきかの指針を得ることを目指している。
(3) 東西対話の現状
(イ) 要人往来の活発化
INF条約の成立に伴う米ソ関係の改善を背景に,最近,欧州諸国においては,ソ連・東欧諸国との間で要人の往来が活発化した。とりわけ目立つのは西独及びソ連の動きであり,87年7月のヴァイツゼッカー西独大統領の訪ソ,12月のシュトラウス西独バイエルン州首相の訪ソ及び88年1月のシェヴァルナッゼ・ソ連外相の西独訪問等を経て,10月にはコール西独首相が訪ソし,89年前半にはゴルバチョフ・ソ連書記長が西独を訪問する予定となっている。また,ホネカー東独国家評議会議長が87年9月に初めて西独を訪問し,注目された。
(ロ) 欧州安全保障・協力会議
欧州における多国間の対話の場として欧州安全保障・協力会議(CSCE)がある。77年以降,75年に採択されたヘルシンキ最終文書(欧州の安全保障,経済・科学技術・環境の分野での協力,人道その他の分野での協力等につき規定)のフォローアップのため各種会議が開催されている。フォローアップの一環として開催された欧州軍縮会議(CDE)では,信頼・安全醸成措置に関する合意文書が86年9月に採択されている。86年11月よりはウィーンにおいて第3回フォローアップ会議が開催されており,現在はその結論文書の作成が行われているが,人権分野においてソ連の柔軟性が見られないことからその進展は遅々としている。西欧諸国は,一貫して,各分野のバランスのとれた実質的成果を達成することを基本方針として交渉に臨んでいる。
(ハ) 通常戦力軍備管理交渉
欧州における通常戦力分野の軍備管理に関しては,中部欧州(対象が,西側:西独,ベネルクス3国,東側:東独,チェッコスロヴァキア,ポーランド)における通常兵力の削減を目的とする中部欧州相互均衡兵力削減交渉(MBFR)において73年以来既に45回の交渉が行われたが,検証問題をはじめとする東西の対立は根深く,具体的合意は得られていない。このような状況の下,87年2月よりNATO及びワルシャワ条約機構(WP)加盟23か国間で全欧州(大西洋からウラルまで)における通常戦力軍備管理交渉のための準備会合がウィーンにおいて開催されており,交渉目的,交渉開始時期・場所,参加国,削減対象等につき協議されている。
(4) 西欧独自の安全保障強化の動き
西欧諸国が安全保障の面でも「西欧の声」を強めていることについては前述したが,その発端はINF問題とも関係している。83年末のINFミサイル(パーシング1と地上発射巡航ミサイル)の西欧配備に至る期間,西独をはじめとしてミサイル配備反対運動が活発化したが,フランスは,このようなNATOの基本政策に反対する運動は,西欧防衛の基本を揺るがしかねないものとして警戒し,自ら西欧防衛への協力姿勢を強めるに至ったと見られている。フランスは,NATOの加盟国でありながらその軍事機構には属さないとの基本方針の下,西独との2国間協力,西欧諸国(仏,西独,英,伊,ベネルクス)を加盟国とする西欧連合の活性化といった形で,西欧防衛への関与の度合を深めてきた。
さらに,86年10月のレイキャビクでの米ソ首脳会合において,米国が弾道ミサイル全廃を提案したことは,核の重要性を否定しかねないものとして,西欧諸国の中に懸念が生じ,西欧諸国は自らの安全保障問題をこれまで以上に強く認識するに至り,欧州独自の安全保障強化の動きを促進したと言われる。一方,米国は,最近,財政事情の厳しさから同盟国の防衛分担増への期待を強めており,西欧諸国がNATOにおける「欧州の柱」を強化することをむしろ歓迎しているものと見られる。
3. 主要国情勢
(1) 英国―サッチャー首相3選
サッチャー首相は好調な経済情勢を背景に87年6月,総選挙に踏み切り,大勝,3選を果たした。他方,総選挙3連敗を喫した労働党キノック党首は,政策の全面見直しのため,国民との対話集会キャンペーンを開始し,また連合も惨敗,体制建て直しを図るべく自由党及び社民党が88年3月正式に合併,社会自由民主党として発足した。その後5月の統一地方選挙では,保守党は現状維持にとどまったのに対し,労働党は,社会自由民主党を蚕食し,大幅に伸長した。
英国経済は,いわゆるサッチャーリズムといわれる競争原理の徹底,規制緩和等が効を奏し,82年以来の拡大傾向を維持し,87年はGDP成長率4.5%を記録,失業率も88年6月時点で8.4%となり,2年連続して減少傾向にある。一方景気の拡大によりインフレ傾向も出始め,88年7月にはペースレートは10.5%へ引き上げられた。また,景気拡大を受けて,輸入が急増し,87年経常収支の16億8千万ポンドの赤字は88年にはさらに拡大すると見込まれる。
(2) フランス―保革共存政権の解消
86年3月以来の保革共存政権(コアビタシオン)は,国有企業の民営化等による経済の活性化の努力,国内治安回復の成果等により,一定の評価を得つつあったが,88年4月及び5月の大統領選挙でミッテラン大統領がシラク首相等を破って再選され,ロカール内閣成立によって保革共存政権は解消した。しかしながら,6月の総選挙では与党社会党の単独過半数獲得は成らなかった。
87年の仏経済は,消費者物価上昇率は,価格の自由化にもかかわらず年平均3・1%にとどまったが,10%を超える失業率は,大幅な改善を見るに至らなかった。貿易収支は,旺盛な国内需要により314億フランの赤字となった。また,10月の株価大暴落は,それまで順調に推移した民営化を一時休止させる等の影響を残した。
(3) 西独―コール首相3選
87年1月の連邦議会選挙では,コール政権の与党連合が過半数を制し,3月にはコール首相が3選された。その後,コール首相は,連立与党間の意見対立,州選挙におけるキつスト教民主同盟の停滞ないし敗北等に悩まされながらも,長期政権を維持している。
西独経済は,83年以降安定的成長を続けているが,マルク高の影響もあり87年は86年に比べて輸出は振るわなかった。西独経済は貿易依存型であることもあり,86年下期より経済成長率が鈍化しており,87年の経済成長率は1.7%にとどまった。また,消費者物価上昇率は0.6%で物価は安定しているが,雇用情勢は依然として厳しく失業率は8.9%であった。貿易収支は,史上最高の黒字を記録した。コール政権は,税制改革の一環とし,また,経済成長の内需主導を一層進めるため,86年(109億マルク)に引き続き88年に約140億マルク,90年に約200億ルマクの純減税を行う予定である。
(4) イタリア―好調な経済
戦後最長記録を樹立したクラクシ内閣(社会党首班の連立)の下で政治的安定を享受してきた伊政局は,87年3月の同内閣の総辞職を契機として,内政の動きが激しくなった。6月の総選挙後,7月にゴリア内閣(キリスト教民主党を首班とする連立)が成立したが,連立与党の足並みの乱れから88年3月に総辞職し,4月にデミータ内閣(同じくキリスト教民主党を首班とする連立)が発足した。
87年の伊経済は,株式相場,為替相場の変動等の不安定要因があったものの,前年に引き続き良好なパフォーマンスを保った。実質GDPは3.1形(前年2.7%)の伸びを示し,欧州主要国の中では英に次ぐ高い成長率となった。インフレ率も4.6%(前年6.1%)に留まり,政府目標の4%に近づいた。貿易収支は11兆1千億リラの赤字と前年に比し悪化したが,総合収支では1兆6千億リラの黒字となった。失業率は86年の11.1%から12%に上昇,若年層・女性・南部イタリアを中心に雇用情勢の悪化がみられた。
4. 我が国との関係―「日欧新時代の開幕」
(1) 日米欧3極間の協調と日欧関係
西欧諸国は,我が国,米国等他の先進民主主義諸国と共に,自由及び民主主義という基本的価値観を共有し,また自由貿易,市場経済体制の維持,発展に共通の利益を有している。東西関係や国際経済問題を中心に大きな動きが見られる今日の国際情勢の下,我が国が世界の平和と繁栄のために今後一層の国際的役割を果たしていく上で,日米欧3極間の協調は益々重要となっている。日米間の結束を堅持しつつ,日欧関係の強化を図ることは,バランスのとれた3極協調体制を発展させるためにも不可欠である。このような認識の下に,竹下内閣は,西欧諸国との協調は我が国外交の重要な柱であるとし,政治,経済,文化等あらゆる面において日欧関係を拡充しようと努めている。また,西欧諸国においても,我が国の国際社会における役割への期待や我が国との関係に対する関心が高まりつつあり,こうしたことを背景に,日欧協力関係は近年強化されてきている。
我が国と西欧諸国の間の要人往来も益々活発化している。87年5月にはヴェネチア・サミットに先立ちファンファーニ伊首相がサミット参加国中まず我が国を訪れ,その見解を徴した。また,同月にジスカールデスタン前仏大統領,秋には「スカンジナビア・トゥディ」の関連で北欧5か国から国家元首その他の要人が来日し,88年1月にはハゥ英外相が来日し,日英外相定期協議が行われた。我が国からは,87年6月に中曽根総理大臣がヴェネチア・サミット出席に引き続き,我が国総理大臣として初めてスペインを訪問し,88年には,竹下総理大臣が4月末から5月上旬にかけて伊,ヴァチカン,英国及び西独を,さらに6月にはオランダ,仏,ベルギー及びEC委員会を訪問し,ブラッセルではキャリントンNATO事務総長とも会談した。また,87年11月にはベルリン日独センター開所式の機会に浩宮殿下が西独を訪問された。これ以外にも我が方要人がサミット,国連総会,OECD閣僚理事会等の国際会議の機会に西欧諸国の要人と積極的に会談を行い,日欧間の対話の拡充強化に努めている。

(2) 好転した日欧経済関係
87年から88年前半にかけての日欧経済関係は,当初,大幅な貿易不均衡を背景として,EC側の対日姿勢には厳しいものが見られた。EC側の対日認識の根本には,「日本は世界経済システムヘの貢献が少ない」,「日本市場は閉鎖的である」といったものがあったが,その他にもEC側は,日本の対EC輸出が自動車等特定の分野及び市場に集中する傾向,及び対ドルの急激な円高にもかかわらず対欧州通貨切り上げ幅が対ドル切り上げ幅ほど大きくないことによる対米輸出減少分の対欧転換を懸念していた。
このような対日認識を背景に,87年6月のEC外相理事会においては,.部品へのアンチ・ダンピング規則の導入が承認される等,厳しい対日姿勢が示された。また,アルコール問題,半導体問題等に関しては,EC委員会は日本をガットに提訴するに至っている。一方専門家レベルで,自動車,医療機器,化粧品に関し基準認証問題等を話し合うため,EC側よりミッションが2度訪日し,我が国関係省庁と協議が行われた。
こうした状況下で,87年7月,東京で行われた日・ECハイレベル協議においては,EC側は改めて大幅な貿易不均衡及び対米輸出の対欧転換に対して懸念を表明し,一層の市場アクセスの改善や,10億ドルの外国製品政府調達に関する公平な取扱いを要望してきた。これに対し,我が国は,緊急経済対策等を含む我が国の努力を詳細に説明,また,対EC輸入は輸出を上回る伸び率を示していること等を指摘した。
このような日・EC間の建設的な対話の積み重ねに加え,87年春以降,不均衡は依然として大きいものの,我が国の対EC輸入の伸び率が輸出の伸び率を大きく上回る傾向を示していること,自動車等3分野の分野別協議において具体的進展が見られたこと,また産業協力の面でも,日・EC間の直接投資は着実な増加傾向にあること等明るい面も見え始めたため,EC側の対日態度には若干ながら軟化の兆しも現われてきている。ドクレルク委員ECも,87年9月に訪日した際,輸入拡大の傾向が定着するか否かを見極める必要があるとしつつも,このような明るい面を評価し,日・EC双方が協力してさらに拡大均衡に努めるべしとの立場を表明した。
12月には,ドクレルクEC委員及びナルエス副委員長が訪日し,竹下総理大臣,宇野外務大臣等我が国政府要人等と会談した。一連の会談において,EC側は,アルコール飲料問題に関しガット勧告の早期実施を求めたほか,関西国際空港問題及び10億ドルの外国製品政府調達問題に関し,EC企業の参入拡大を求めた。他方,自動車等3分野の分野別協議については,日本の対応は協力的であり喜ばしいとしてこれを評価した。これに対し,我が国は,酒税改正については早期に基本方針を示すこと(その後本件に対する基本方針として,88年1月に「昭和63年度税制改正の要綱」を閣議決定,また,具体案として,6月に「税制改革要綱」を閣議決定),関西国際空港問題及び政府調達問題については公正・無差別な参入機会が確保されていることを指摘した。さらに,日・ECは,両者の関係強化のため協調的努力を行うべきことを確認した。
88年に入っても我が国の対EC輸入は引き続き大きな増加率を示す等,日欧間経済の明るい面が続いていることに伴い,EC側では官民双方において日本市場の重要性に対する認識が改まってきている。この傾向は,3月にヤング英貿易産業大臣が訪日するにあたり,「オポチュニティー・ジャパン」と称する対日輸出倍増キャンペーンを打ち出したことに端的に表れている。また,4月には,EC外相理事会で対日関係報告書が採択されたが,同報告書が日本のマクロ経済における良好なパフォーマンス(内需主導型経済成長,構造調整),日本の対HC輸入の増加を評価し,これが日・EC経済関係の改善に貢献しているとして,日・EC経済関係の積極面をEC自らが認めたこともこうした認識の変化の一例といえよう。
(3) 竹下総理大臣の2度にわたる西欧諸国歴訪
日欧双方において日欧関係を強化しようとする気運が高まっていることを象徴するのが,88年4月末から6月初めにかけて2度にわたって行われた竹下総理大臣の西欧諸国歴訪である。訪欧の基本方針と成果を整理してみよう。
(イ) 日欧関係の強化
日欧関係に厚みと幅を加えるとの総理の意向に各国首脳とも積極的に同調し,西欧側にも日欧関係強化の気持ちが強くなっていることが肌で感じられた。
(ロ) 各国首脳との個人的信頼関係の構築
各国首脳と波長が合い,意気投合する場面が多く,会談の雰囲気も極めて良好であった。トロント・サミットに備えて各国首脳との深い友情と個人的信頼関係を構築するとの目的は十分達成された。
(ハ) 竹下内閣の外交政策の説明
「世界に貢献する日本」及びこれを具体化するための,(あ)平和のための協力強化,(い)国際文化交流の強化,(う)ODAの拡充強化,の三本柱から成る総合的な「国際協力構想」を説明し,各国から歓迎された。竹下外交の基本的姿勢を表明したロンドン市長主催午餐会におけるスピーチ(5月4日)も好評であった。
(ニ) 国際政治,経済問題に関する大局的な意見交換
共通の認識が多いことが確認された。EC市場統合が真剣な動きであることが,首脳レベルで直接確認された。竹下総理大臣からは,EC市場統合を評価しつつ,域外国に対して開かれたものとなるべきであるとの我が国の基本的立場を伝えた。
(ホ) 文化交流,心の交流の重視
「心で結ぶ日欧文化交流計画」(囲み参照)を提唱し,積極的な評価を得た。
3. 日欧協力関係に一層の厚みと幅をもたらす方策 (1) 文化面の協力 文化の相互交流を通じ,異質な文化に対する寛容な心を培う ことは,開かれた国際社会,ひいては国際協調と世界平和の 構築につながる。多様な文化の相互交流は,国際社会の活発 化と発展への活力を生む。 欧州と日本の文化の交流は新しい東西の「心の道」を開き, 21世紀に向けた新時代の文化の創造に大きく役立ち得るもの。 当面の具体策としての「心で結ぶ日欧文化交流計画」 (イ)人的交流の拡大 ・欧州の科学者や研究者に対する1年程度の日本でのフェロー シップ新設。 ・JET計画を仏,独語等へ広げる。 ・日欧間にワーキングホリデー制度を提案。 ・科学技術の分野における協力の方法の探究。 (ロ)日本研究や日本語教育への助成の増加。 (ハ)日欧交流・日欧対話の組織の拡充,各種文化行事への助成。 ユーロバリア日本祭,日英2000年委員会,ベルリン日独センタ、 日仏文化会館等。 (2)政治対話の深化,国際平和のための協力強化 (3)経済面での協力 (イ)経済構造調整,内需拡大,市場アクセス改善,蓄積された黒字 を世界に役立てること等による世界経済のバランス回復への協力。 (ロ)開発途上国への支援(第三世界における日欧協力を含む)。 (ハ)自由貿易体制の維持・強化(ウルグァイ・ラウンドでの協調, 開放的な欧州統合の達成)。 4.日欧新時代の開幕 (1)21世紀を目前にした日本は,経済発展を真の豊かさに結びつけ, 大きく世界に開かれた社会を築く要。創造性に富み活力ある文化 国家の建設。「ふるさと創生」。 (2)世界に貢献する国家を造るため,欧州諸国民との交流を役立たせたい。 (3)日欧が力を合わせ新時代への幕を開ける絶好の時。 |