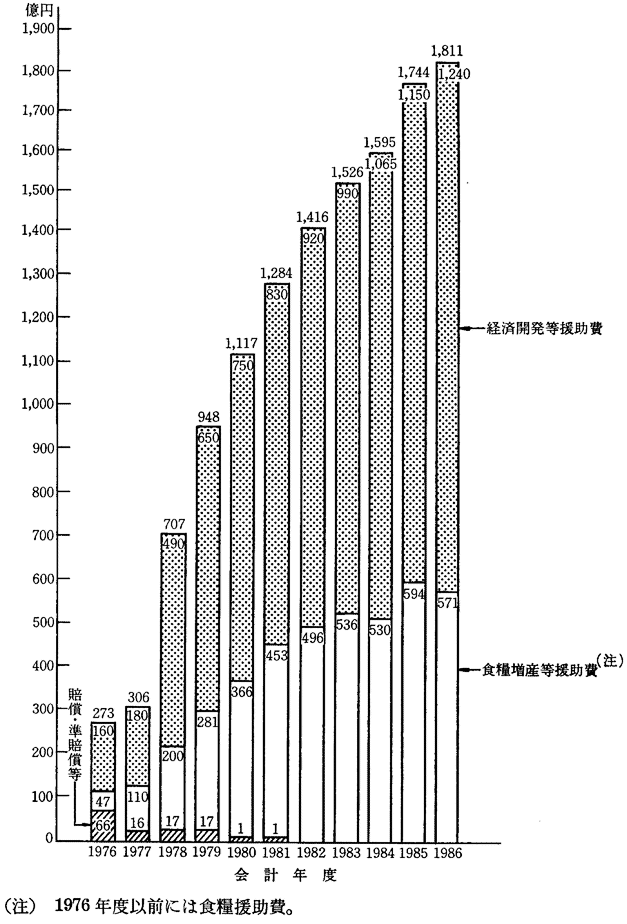
第3節 無償資金協力
1. 概要
無償資金協力は,開発途上国に対する資金協力のうち,相手国に返済義務
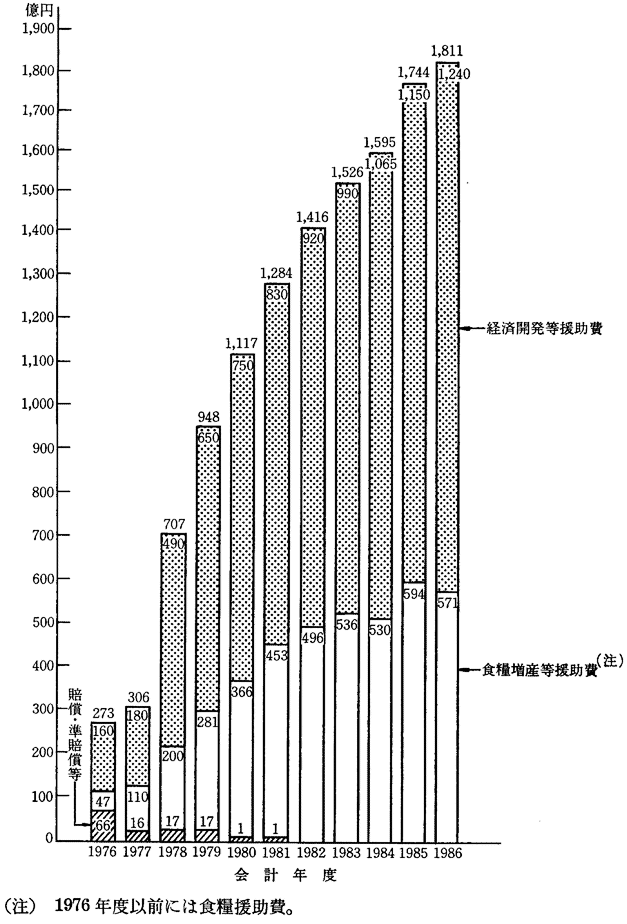
を課さずに資金を供与する形態の援助である。わが国の無償資金協力は68年度に開始され,今日に至るまでその資金量は年々大幅な増大を続けており,わが国のODAの拡充,特にその質の向上を図る重要な柱となっている。
わが国の無償資金協力は,(1)一般無償援助,(2)水産関係援助,(3)災害関係援助,(4)文化関係援助,(5)食糧援助及び(6)食糧増産援助から成っている。86年度予算(補正後)における無償資金協力事業予算の総計は1,800億円を超えており,10年前の予算額と比較すればその規模は8.7倍に拡大している。
2. 経済開発等援助費による協力
(1) 一般無償援助
経済開発等援助費の主要な部分を構成する一般無償援助は,開発途上国がその経済・社会の発展のための計画を実施する上で必要な施設・資機材及び役務を調達するために必要な資金を供与するものであり,経済的収益性が低く,開発途上国が自己資金により実施することが困難な案件を中心として,基礎生活分野での援助及び人造り援助にその重点を置いている。
86年度の予算ベース(当該年度の予算からの援助実施を決定した)一般無償援助実績は,供与対象国54か国,供与総額約1,041億円に達している。
86年度の予算ベースの一般無償援助実績を分野別に見ると次のとおりである。
(イ) 医療・保健分野
中国の肢体障害者リハビリテーション研究センター,インドのサンジャイ・ガンジー医学研究所,ザイールのキンシャサ大学病院等における医療機材整備計画等総計18件の事業に対し,130億1,900万円を供与した。
(ロ) 教育・研究分野
スリ・ランカの青少年教育訓練センター,ザンビアのメヘバ難民キャンプ中学校及びパラグァイ・日本人造りセンター等の建設計画等総計21件の事業に対し,270億2,000万円を供与した。
(ハ) 民生・環境改善分野
フィリピンのマニラ首都圏環境衛生改善計画,イエメン・アラブの地方水道整備計画,マーシャルのマジュロ環礁水道設備改善計画等総計32件の事業に対し,202億7,600万円を供与した。
(ニ) 農業分野
インドネシアの稲病害虫発生予察防除計画,スーダンの食糧倉庫建設計画,ザンビアの農地開発計画,ホンデュラスの農村総合開発モデル事業計画等総計18件の事業に対し,総額152億4,100万円を供与した。
(ホ) 運輸・通信分野
ネパールの地方電気通信網整備計画,セネガルの放送施設整備計画,パプア・ニューギニアのラジオ放送網改良計画等総計36件の事業に対し266億300万円を供与した。
(ヘ) その他
他にタイの金属・機械工業開発研究所建設計画に対し,19億1,100万円を供与した。
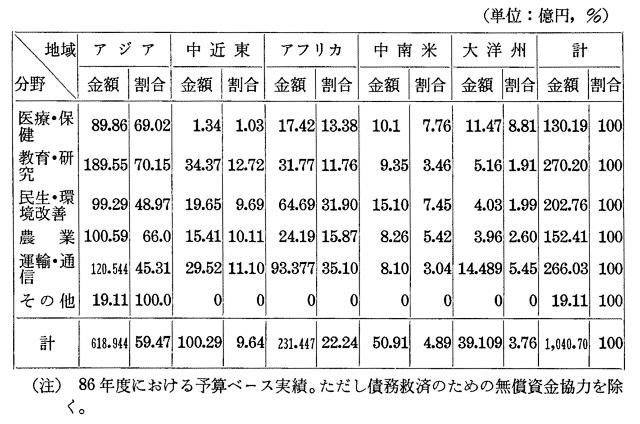
また,我が国は,78年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)貿易開発理事会(TDB)閣僚会議の決議に基づき,77年度以前に我が国に対して公的債務を有していた後発開発途上国等(18か国)を対象に,債務救済のための無償資金協力を78年度から実施しており,86年度には13か国に対し,約71億2,213万円を供与した。
(2) 水産関係援助
水産関係援助は,開発途上国の水産振興に寄与するために,漁業訓練,水産研究等の施設及び漁港等漁業関連施設・資機材並びに役務調達に必要な資金を供与するものである。86年度には,フィジーのラオトカ漁港整備計画,ペルーのパイタ水産訓練センター建設計画等総計12件の事業に対し,94億5,000万円の協力を実施した。
(3) 災害関係援助
災害関係援助は,風水害,地震,旱魃などの自然災害を被った国に対する緊急援助及び紛争等により発生した難民・被災民に対し人道上の観点から行われる援助からなる。86年度には,カメルーンの有毒ガス噴出事故,エル・サルバドル及びエクアドルの地震被害,カンボディア難民等に対し,総計21件,13億5,715万円を供与した。
(4) 文化関係援助
文化関係援助は,開発途上国における教育及び研究の振興,文化財及び文化遺跡の保存活用,文化関係の公演・展示などの開催等のために使用される資機材の購入に必要な資金を供与するものであり,文化交流に関する国際協力の一環として75年度から実施されている。86年度には合計52件,総額20億円の協力を実施した。
3. 食糧増産等援助費による協力
(1) 食糧援助
食糧援助は,「1967年の国際穀物協定」及び同協定を引き継いだ「1986年の国際小麦協定」を構成する「1986年の食糧援助規約」に基づいて実施されており,通称ケネディ・ラウンド(KR)援助とも呼ばれている(上記規約は86年3月に作成され,わが国では,同年11月の国会承認を経て,12月に受諾書寄託を行った)。
我が国は,同規約に基づき,毎年小麦換算で30万トンの最低拠出義務を負っており,食糧不足に苦しむ開発途上国が穀物(米,小麦,その他86年度については,85年度に引き続き,アフリカでの域内調達を図るためジンバブエ産メイズをも使用)及びその輸送役務の購入に必要な資金を無償で供与している。86年度の予算ベースの食糧援助実績は,34か国,2国際機関に対し,総額184億9,600万円であった。食糧援助を供与先別に見ると,アフリカ地域が全体の69.6%と大部分を占め,その他,アジア地域20.0%,中南米地域7.6%,中近東地域2.5%,大洋州地域0.3%となっている。
(2) 食糧増産援助
我が国は,開発途上国の食糧問題の解決は,基本的には自助努力による食糧増産によるべきであるとの認識の下,77年度から「食糧増産援助費」について新たに予算措置を講じ,開発途上国が食糧増産プロジェクトを遂行する上で必要とする肥料,農薬,農機具等の購入のために必要な資金を無償で供与している。86年度の予算ベースの食糧増産援助実績は,51か国に対し総額386億円であった。その内訳は,アジア地域55.7%,アフリカ地域32.1%,中近東地域3.4%,中南米地域8.3%,大洋州地域0.5%となっている。
4. 最近の動向
(1) 効果的実施・適正な援助
無償資金協力の規模の拡大の下でもいっそう効果的かつ適正な援助を確保するため,主に国際協力事業団(JICA)の担当事項として,被援助国政府による案件形成に対する支援,協力実施決定に先立つ事前の各種調査,各案件の所要経費積算精度の向上,相手国政府による事業実施の促進のための協力,実施状況に関する事業完了後の確認,必要フォロー・アップ協力の実施,さらにわが国の無償資金協力のしくみに関する各開発途上国政府の啓発,各種制度改善等のための種々の基礎的な調査等,援助実施のあらゆる段階にきめ細かい制度を設けて,援助の効果及び適正さを高めることに努めている。
また,無償資金協力にかかわる政策の企画・立案及び実施の際の専門的な見地からの意見・助言の有用性が高まっていることから,77年度から経済協力局長の下に各界有識者の参加を得て無償援助実施懇談会を開催しており,87年3月までに計18回の会合を持ってきている。上記数々の制度の構築も,同懇談会での議論・提言が基になったところが大きい。
(2) その他の最近の特徴
近年の食糧不足以降,アフリカ地域向けの協力が大幅に拡大されてきている。86年度には,長期的な生産力向上,民生改善のための援助が強化され,総額で540億円を上回るとともに,無償資金協力全体に占める割合で初めて30%台に乗った。また,小規模国家の多い大洋州地域に対してもきめ細かく援助を実施することに努め,全体予算額の3.6%(85年度には2.9%)を同地域に供与した。
なお,実施に際しては,技術協力等他の形態の援助との連携,既実施案件のフォロー・アップ,他国あるいは国際機関との協調,供与対象国の拡大等,無償資金協力予算の運用効果を最大とすべく,様々の機動的執行の努力を行っている。