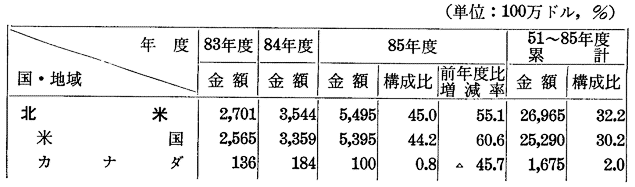
第3節 国際投資問題
1. 我が国の投資概要(貿易から投資へ)
85年度の我が国の対外直接投資(届出ベース)は122億1,700万ドルに達し,過去最高であった前年度(101億5,500万ドル)に比べ20.3%の増加となった。
(1) 地域別に見ると(表1),先進国向け投資は,欧州向け投資(19億3,000万ドル)が前年度並みであったほかは,北米向け投資が前年度比55.1%増の54億9,500万ドル,大洋州向け投資が同134.4%増の5億2,500万ドルと好調であったため,前年度比41.0%増の79億5,000万ドルとなり,構成比も54.5%から65.1%に上昇した。
他方,途上国向け投資は,中南米向けが前年度比14.2%増の26億1,600万ドルであったが,アジア向けが同11.9%減の14億3,500万ドルとなったほか,中近東,アフリカがそれぞれ同83.5%,同47.2%減少したため,同5.5%減の42億6,800万ドルにとどまった。
(2) 次に業種別に見ると(表2),製造業にあっては,機械,輸送機,電機部門が好調であったが,鉄・非鉄部門をはじめ他部門すべて大幅減少であったため,全体では前年度比6.1%減となった。他方,非製造業にあっては,金融・保険業向け投資が前年度に引き続き好調で同82.5%増の38億500万ドルとなったほか,不動産業向け投資が同180.7%増の12億700万ドルと大幅に伸びたため,全体では同28.4%増となった。
(3) 85年度の対外直接投資の増加要因は,(i)我が国金融機関の国際業務の拡大に伴い,金融・保険業向け投資が北米,中南米,大洋州向けを中心に引き続き大幅に増加したこと(全投資額に占めるシェア,80年度8%,84年度21%,85年度31%),(ii)貿易摩擦等を背景として北米向け輸送機,機械,電機の製造業投資がかなり増加したこと(それぞれ,対前年度比53.9%,195.9%,66.5%増),(iii)北米向けを中心として不動産業投資が大幅に増加したこと(北米向けは対前年度比3倍増の11億2,100万ドル),等が挙げられる。
他方,対アジア投資は前年度に引き続き減少したが,この減少傾向の要因としては,大型資源開発案件の減少,労働コストの上昇等が指摘される。
(4) 我が国の対外直接投資のパターンは,従来の開発途上国での製造業向け投資に代表される低賃金追求型中心の投資から先進国製造業向け投資に代表される貿易摩擦回避型の投資へと変化を見せてきているが,昨今の円高により,投資先としてNICsを中心とするアジアが再び注目を集めつつある。
海外直接投資の推進は,経常収支黒字が定着している我が国経済を国際的に調和のとれたものにするために必要であるはか,開発途上国等相手国の経済発展のためにも必要である。
特に,債務性が少ない直接投資の性格から累積債務問題解決にも資する開発途上国向け投資の増加も期待されている。
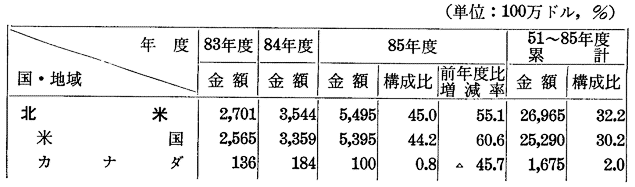
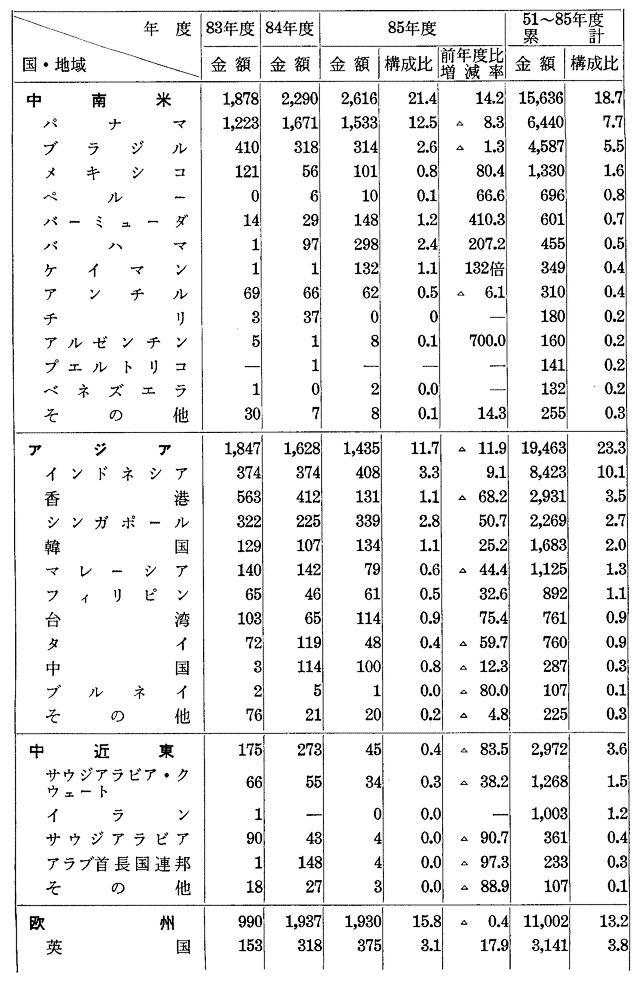
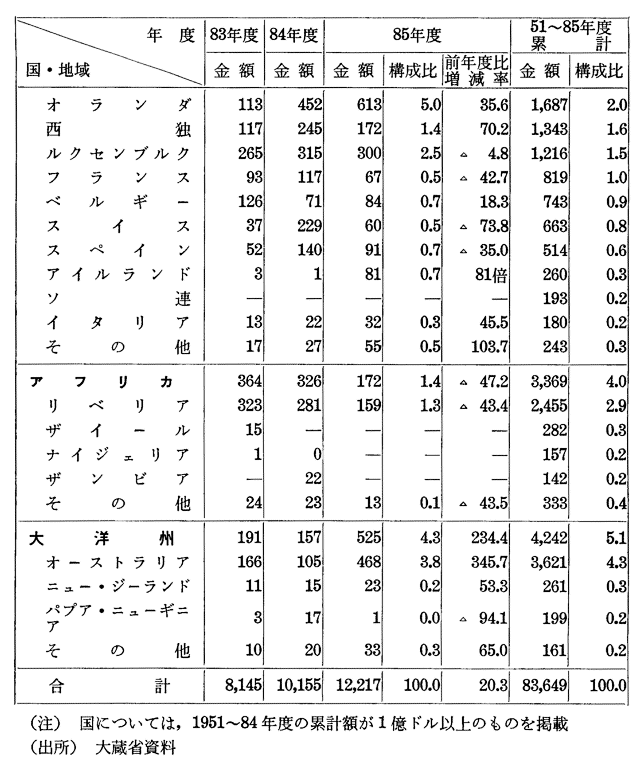
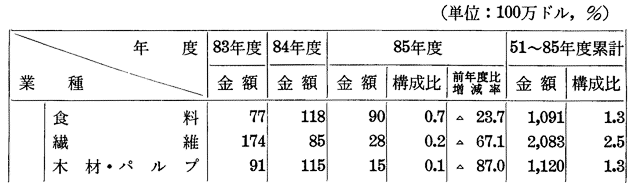
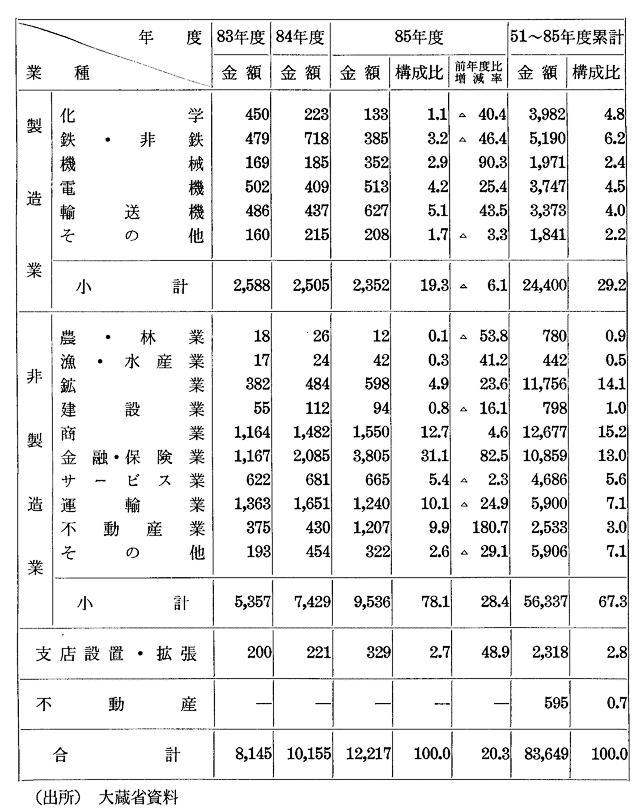
2. 投資保護協定の締結の促進
(1) 我が国の対外直接投資は増加傾向にあり(図参照),今後とも一層活発に行われることが予想される(86年4月から87年2月までの届出総額194億6,900万ドル)。
そもそも海外投資は,投資母国の経済に貢献するのみならず,資本・技術・経営手法の移転,雇用創出効果等により投資受入国の経済発展に資するとともに,経済的・人的交流を通じて両国関係を緊密化し,また貿易摩擦を緩和する役割をも果たし得るものである。昨今の貿易摩擦の激化等に鑑み,政府は86年5月「経済構造調整推進要綱」を策定し,その一施策としてかかる効果を有する海外直接投資の推進を図ってきている。
(2) 海外投資は一義的には民間企業の責任と判断に委ねられているものであるが,民間企業のみでは解決困難な問題もあり,投資母国及び投資受入国が協力して投資環境をできる限り良好なものに整備し,投資を推進する必要がある。
例えば投資受入国の政策が一定しない場合等は,投資家にとって予見可能性及び法的安定性が十分確保されないため投資阻害要因となる。投資保護協定は,事業活動に対する待遇,投資財産の保護に対する待遇等を規定しており,民間投資家に投資についての予見可能性及び法的安定性を与えるもので,投資保険,税制等の施策と並んでこうした投資環境の整備のための諸施策の一環として重要である。近年,我が国の海外投資が急増する
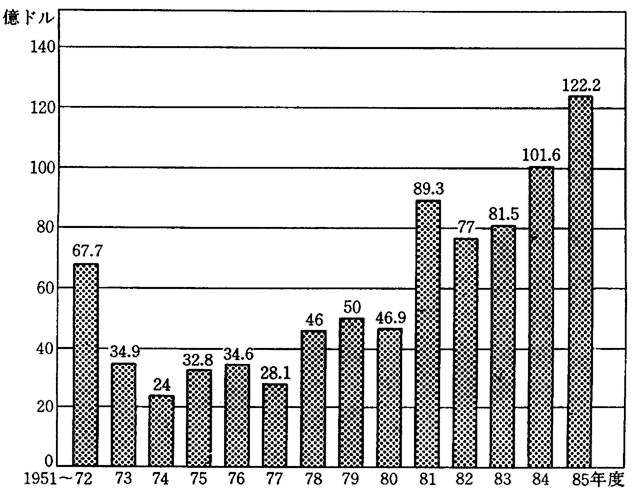
中で,投資のみを対象として実体的及び手続的規定を詳細に定める投資保護協定の必要性が認識されるに至ったが,昨今の我が国を取り巻く経済環境もあって,投資促進の一方策として同協定の重要性はさらに高まってきているといえよう。
(3) 我が国は,現在までにエジプト及びスリ・ランカとの間に投資保護協定を有しているほか,中国及びASEAN諸国(ブルネイを除く)と鋭意交渉を行ってきている。また,新たに,トルコ(87年2月),パキスタン(87年3月)とも交渉を開始したところである。