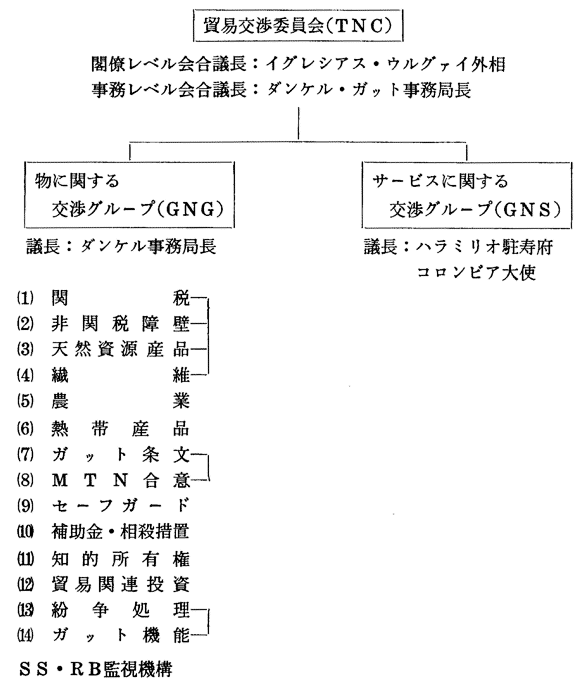
第2節 国際貿易
1. 国際経済の現状と新ラウンド
86年の国際経済の現状を見ると,インフレ率低下や原油価格の下落等の要因を反映して全体的には経済成長が持続しているものの,78年の第2次石油危機以来高まりつつある保護主義圧力は依然として衰えをみせていない。先進国の一部には財政赤字,深刻な雇用状況,構造的な国際収支の悪化に対応するため,二国間または,一方的な国内立法により貿易制限措置(輸出自主規制,報復的輸入制限)をとる傾向が特に顧著になってきた。特に先進国間の貿易不均衡は,輸出サイドの国内価格引下げ,ドルの実質的引下げが期待より小さかったこと,マクロ経済要因,Jカーブ効果等の要因により86年に至ってさらに拡大し,これを背景としてECのいわゆる利益の均衡論にみられるような管理貿易を志向する動きが台頭してきた。他方,途上国経済は先進国における保護主義の高まりや累積債務に起因する多くの困難を克服するに至っておらず,外貨準備不足のため依然として多くの輸入制限的措置をとることを余儀なくされている。
このような保護主義圧力を防圧し,多角的自由貿易体制を維持・拡大することを目的として83年末以来準備が進められてきた新ラウンドは,各国の努力がようやく実を結び,86年9月20日,ウルグァイ,プンタ・デル・エステにおける閣僚宣言の採択によりその発足が正式に決まり,翌87年1月に各交渉項目に応じ15の交渉グループを設置,2~3月にかけてそれぞれのグループは実質交渉に入ったが,交渉の進め方・優先項目をめぐり参加国の足並みは完全にはそろっていない。このように,新ラウンドの将来にはなお予断を許さぬものがあるが,ガットを中心とする多角的自由貿易体制の維持・強化がその繁栄に不可欠である我が国としては,新ラウンドの5つの目標(自由無差別な多角的貿易体制の再構築・強化,貿易障害の一層の軽減・撤廃,途上国の貿易環境の改善,世界貿易の構造変化へのガットの効果的対応の確保,ガット機能の強化)を再確認しつつ,新ラウンド交渉を通じ,さらに保護主義に対する闘いを継続していかなければならないといえよう。
2. ウルグァイ・ラウンド(新ラウンド)の発足
ガット新ラウンド(新たな多角的貿易交渉)については,86年1月,新ラウンド準備委員会が発足,7月末まで閣僚宣言のドラプディングを行った後その作業を終了した。これを受けて9月15日から5日間,ウルグァイのプンタ・デル・エステにおいて新ラウンド発足のためのガット関僚会議が開催(我が国よりは,倉成外務大臣,田村通商産業大臣が出席)され,ここにおいて新ラウンド(倉成外務大臣の提唱により,開催国にちなみウルグァイ・ラウンドと命名)発足の閣僚宣言が全会一致で採択された。
続いてジュネーヴにおいて交渉計画策定のための協議が開始され,難航の末,87年1月末に合意が成立,2月より各交渉グループ会合が開始された。なお,我が国との関係では,小林智彦国際経済問題担当大使が貿易関連投資グループの議長に選ばれた。
(1) 準備委員会から閣僚宣言の採択まで
新ラウンド準備委員会は86年1月に発足した後,個別交渉項目のレヴュー,閣僚宣言案のドラプディング作業を行ってきた。準備委員会の討議においては,サービス等新分野の扱いをめぐり先進国と途上国強硬派(インド,ブラジル等)が対立,先進国内部では農業問題をめぐりECと豪等農産物輸出国が対立,またECは「利益の均衡」を主張していわゆる「日本問題」を提起するなど数々の対立がみられ,討議の行方は予断を許さなかったが,途上国の一部穏健派(韓国,ASEAN諸国等)が新分野の扱いにつき7月初旬より先進国側に歩み寄りを示し始めた。この結果,先進国と途上国穏健派から成る多数の国の支持を集めた閣僚宣言案(いわゆる合同グループ案)が成立したが,途上国強硬派の抵抗のため準備委員会は閣僚宣言案の一本化に成功しないまま7月末日その幕を閉じた。
新ラウンド発足を討議する閣僚会議は9月15日より5日間,ウルグァイのプンタ・デル・エステにおいて,イグレシアス・ウルグァイ外相を議長として開催された。討議は,合同グループ案をベースに行われたが,途上国強硬派の抵抗もあり,結局,物とサービスの交渉を分け,前者を扱う「物に関する交渉グループ(GNG)」の設置のみをガット総会の決定とし,新ラウンド自体は総会の機会に会合した閣僚が決定するという形でようやく妥協が成立,新ラウンド発足を決める閣僚宣言が9月20日全会一致で採択された。
(2) 交渉組織の設定
閣僚宣言では新ラウンド全体を統轄する機関として貿易交渉委員会(TNC)を設置し,この下にGNGとサービスに関する交渉グループ(GNS)を置くことを決定したのみであり,個別交渉項目に応じた交渉の組織づくりについては,86年12月19日までに別途決定することとなっていた。交渉の組織づくりをめざす協議は,各国の利害関係の対立の再燃のため予定された12月19日までには合意を成立させることができなかったが,翌87年1月末に至ってようやく合意をみた。
(別表)
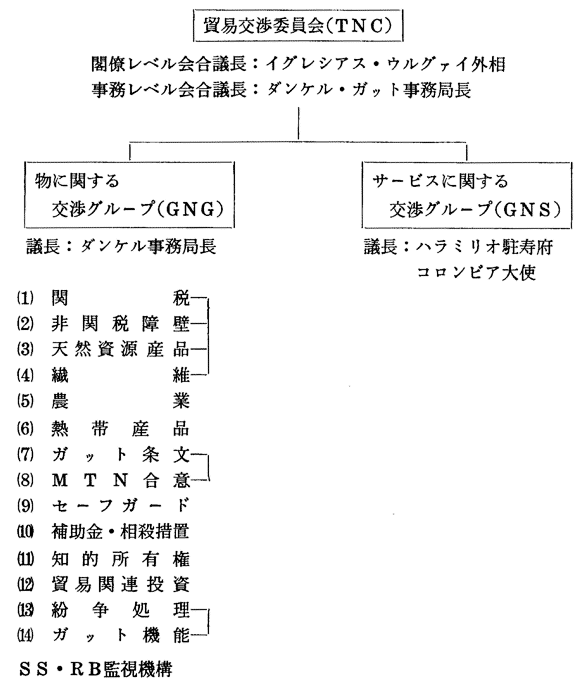
その結果,GNGの下に14の交渉グループ(関税,非関税障壁,天然資源,繊維,農業,熱帯産品,ガット条文,MTN合意,セーフガード,補助金・相殺措置,知的所有権,貿易関連投資,紛争処理,ガット機能)を設置し,これと別にスタンドスティル,ロールバックの監視機構を設けることが決定され,各グループは2~3月にかけそれぞれの活動を開始した(別表参照)。このうち最初の4グループは当面は,市場アクセス・グループというひとつのグループで扱うほか,ガット条文・MTN合意,及び紛争処理・ガット機能はそれぞれ当面は単一のグループで扱うこととなった。ウルグァイ・ラウンドの期間は閣僚宣言において4年と定められているが,他方で場合によっては早期に交渉が終了したものについてはその早期実施についても可能性を閉ざしておらず,今後の進展が期待されるところである。