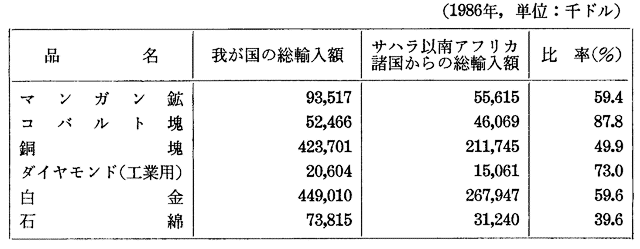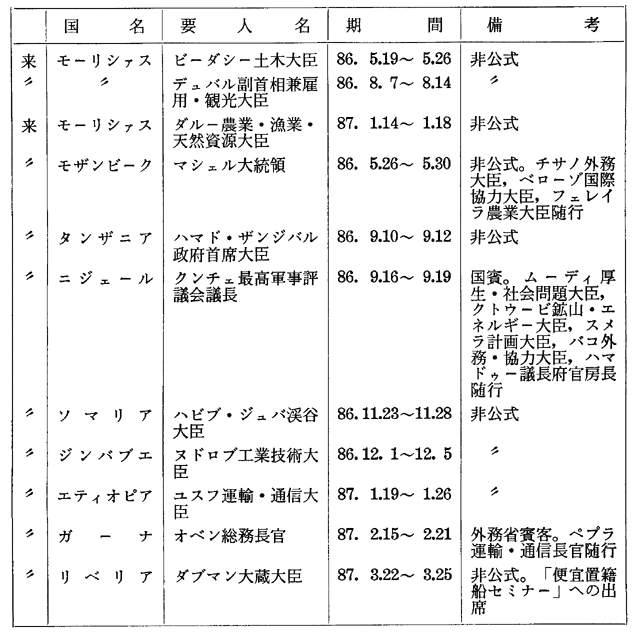
1. 内外情勢
(1) 概観
(イ) 86年のアフリカにおいては,チャド問題,南部アフリカ問題等政治問題で種々の動きが見られたものの,問題の根本的解決には至らなかった。
(ロ) 一方経済面においては,天候に恵まれたこともあり,農業生産は回復し,緊急食糧援助を必要とする国はモザンビーク,アンゴラ,ボツワナ,エティオピア,レソト等の数か国に減少した。しかしながら,アフリカ諸国の多くは,依然構造的食糧不足や食糧の輸送,貯蔵等ロジスティックス上の問題を抱えているほか,一次産品価格の低迷,累積債務,人口増加等のため,経済困難は依然深刻である。
(ハ) このような経済困難を背景にして・86年5月には国連アフリカ特別総会が開催され,今後5年間のアフリカ経済復興開発に向けての「国連行動計画」が採択された。
(ニ) またアフリカにおいても,経済危機から脱却するため,世銀・IMFと協調し,経済構造調整に着手する国が増加しており,約25か国が構造調整計画を実施中あるいは実施予定である。ただし,象牙海岸,ガーナ,セネガル等既に数年問にわたりとれを実施し成果が上がりつつある国もある一方,ザイール,ザンビア等構造調整計画による緊縮政策を採った結果,国内での反発が強まっている例もあり,今後とも構造調整計画をめぐる動向には注目を要する。また,かかる経済危機も一因となり,幾つかの国で政情不安が強まりクーデター未遂等が発生した。
(ホ) チャドにおいては,リビアの支持するグクーニ前大統領の反政府軍とハブレ政権軍との間に86年10月停戦協定が成立した結果,従来の紛争は様相を変え,現在,チャド政府軍とチャド北部を占領するリビア軍との間で戦闘が続けられているが,チャド軍は87年3月下旬,チャド北部のリビア軍重要基地を奪回し,戦況はチャド軍に有利に展開している。
(ヘ) 南部アフリカ地域においては,南アフリカ(以下「南ア」)情勢の一層の悪化,及びこれに伴い南ア経済に大きく依存している南ア周辺諸国,特に国内に反政府ゲリラを抱えるモザンビーク,アンゴラ,また構造調整が軌道に乗らないザンビア等の経済悪化がさらに深刻化した。
南アは,5月にボツワナ,ザンビア,ジンバブエを同時に越境攻撃し,8月には周辺諸国への逆制裁措置をとる一方,国内的には,治安情勢の悪化を理由に6月非常事態宣言を全土に発布し,黒人解放運動に対する弾圧を強化した。
かかる南ア政府の態度に対し,国際社会は反発を強め,我が国をはじめとし,EC諸国,米国は南アに対する追加的制裁措置を発表した。
他方,南ア周辺諸国に対する国際的な支援強化の気運が高まり,第41回国連総会において,「フロントライン諸国に対する特別援助」決議が採択された。
(2) 域内協力関係
(イ) 第22回アフリカ統一機構(OAU)首脳会議は86年7月アディス・アベバで開催され,コンゴのサスンゲソ大統領が議長に選出された。同首脳会議では,対南ア制裁が討議の焦点となり,包括的強制的南ア制裁を呼びかけた「南部アフリカの危機的情勢に関する声明」が採択され,「南部アフリカ問題に関する首脳委員会の設置」が決議された他,86年5月の国連アフリカ特別総会で採択された「アフリカ経済復興開発のための国連行動計画1985~1990年」を承認し,これを遂行する決意が再確認された。
(ロ) このほか,西アフリカ諸国経済共同体(ECOWAS)首脳会議が86年6月アブジャ(ナイジェリア)で,南部アフリカ開発調整会議(SADCC)年次協議会が87年2月にハボローネ(ボツワナ)で開催された。また,86年1月に発足した旱魃開発政府間機構(IGADD)の第一回援助国会議が87年3月にジブティで開催された。
(3) 東部アフリカ
(イ) エティオピア
87年2月,政府の新憲法草案が国民投票の結果圧倒的多数で承認され,メンギスツ政権は安定を保ったが,86年10月にはゴシュ外相が,また87年3月には,アベベ在京大使が米国に亡命する等,政府要人の西側亡命があいついだ。
経済面では,旱魃被災の状況は各国の援助,天候の回復等により,改善されたが,依然食糧不足状況が続いた。
外交面では,86年1月,9年ぶりにソマリアとの間で首脳会談を実施し,その後3度にわたり外相会談を行ったが両国間に具体的な合意がみられるには至らなかった。
(ロ) ソマリア
内政面では,86年5月,バレ大統領が交通事故に遭ったため後継者問題が起ったが,12月末,7年ぶりに行われた大統領選挙で同大統領が再選され,1993年までの任期をつとめることとなった。
外交面では,86年1月のエティオピアとの首脳会談に引き続き,3度にわたり外相会談を実施したが,具体的合意がみられるには至らなかった。また,86年10月,ソ連との間で,1977年以来冷却化していた両国関係を正常化させることで合意をみた。
(ハ) ウガンダ
86年1月のクーデターにより,ムセベニ政権が成立し,3月には全国をほぼ掌握したが,8月頃より北部を中心に旧政府軍によるゲリラ活動が活発化し,小規模戦闘が繰り返された。
ムセベニ政権は混合経済,非同盟外交を打出しているが,たび重なる内乱による経済の混乱は継続した。外交面では,ムセベニ大統領が86年11月英国等の欧州各国を訪問したが,リビア,キューバ等とバーター貿易を開始する等東側との関係も維持された。
(ニ) タンザニア
ニエレレ大統領引退の後,選出されたムウィニ大統領は,それまでの社会主義経済に自由化政策を導入するとともに,IMFの勧告による平価切下げ等を実施し経済再建に努力した。
外交面では,同大統領は86年,モザンビーク,ケニア,ブルンディ,ルワンダを公式訪問し地域協力,善隣友好の促進に努め,さらに87年3月にはインドネシア,中国,北朝鮮を歴訪するなど,幅広い外交活動を行った。
(ホ) ケニア
モイ大統領は就任以来大統領の権限強化に努めてきたが,86年にはさらに権限を強化する動きがみられたため,キリスト教会等からのモイ政権に対する批判が起った。
ケニア経済は,86年には国際的なコーヒー,紅茶価格の急騰等により貿易収支が改善され,また好天に恵まれたこともあって農業生産も上昇し,好調に推移した。
外交面では,従来からの路線である善隣友好,OAU重視,非同盟,親西側外交を維持した。
(ヘ) マラウィ
86年もバンダ大統領は,政情の安定を維持したが,高齢(1906年生まれ)であることによる後継者問題も浮上してきている。
(ト) マダガスカル
内政面では,地方都市での商店略奪事件,大学紛争,若干の事件があったものの,おおむね安定的に推移した。
経済面では,1990年の食糧自給達成を目的とした5か年計画(86~90年)の遂行に努める一方,IMF,世銀の指導の下構造調整を進めている。
外交面でも,全方位外交・非同盟主議という基本的路線に変更ないが,近年経済困難克服のため現実的な政策を推進し,西側との結びつきを強めている。
(チ) コモロ
87年3月末の総選挙で大統領派が議席を独占し,アブダラ政権の安定ぶりを印象づけた。
(リ) モーリシアス
86年前半は,与党内部の対立が表面化し,4閣僚が辞任する等,政局の混乱がみられたが,ジュグノート政権は8月内閣を改造し,事態を収拾した。
経済面は世銀の構造調整計画を遂行したことにより順調な回復振りを示した。
(ヌ) ジブティ
アプティドン大統領指導の下,内政は引き続き安定しているが,82年以来の経常収支赤字の拡大,エティオピア,ソマリアからの難民の流入により経済状況は厳しい。
(4) 中部アフリカ
(イ) ザイール
既に20余年の統治を行っているモブツ大統領の統治の基盤は依然堅固であり,反政府活動は存在するものの政府の抑圧により無力化している。他方,83年以来の緊縮政策は国民生活を圧迫していたが,86年は緊縮から成長への飛躍の年として国民生活の向上が目標とされていたところ,資金流入不足,主要輸出産品の価格の低迷等により成長政策はうまく始動せず,インフレの昂進により国民各層の不満は高まっている。経済危機克服のためMPR(国民革命運動,ザイールの唯一党)中央委員会は86年10月,(a)IMF調整プログラムを見直し,ザイールの経済発展に見合ったものに変更する,(b)対外債務支払いに上限を設ける等を骨子とした新経済政策を採択した。
(ロ) ルワンダ
政権獲得以来13年目を迎えたハビリヤリマナ政権は83年の大統領選挙を経て,その土台はますます固まりつつあるとみられる。86年はコーヒー(輸出の9割)市況の好調により経済は好影響を受けた。
(ハ) ブルンディ
政権獲得後10年を経たバガザ政権は安定しており,86年においても部族問題を背景とする政府・教会の緊張関係は依然継続したものの,政権の基盤に揺ぎはみられなかった。
(ニ) コンゴー
サスンゲソ大統領は86年7月,OAU(アフリカ統一機構)議長に選出され,その政治的威信を高め,その指導体制は基本的に安定的に推移したが,石油収入の減少による経済困難に直面しており,国民の間では85年からの緊縮経済政策に対する不満が高まっている。
(ホ) ガボン
67年以来政権の座にあるボンゴ大統領は,9月の党(PGD)大会及び11月の大統領選挙で圧倒的支持を受け,長期安定政権としての基盤はますます強固になった。
経済面では,石油価格の下落及びドル安による輸出収入の減少により,財政危機に直面したため,大幅な予算削減措置及び対外公的債務の繰延要請を実施するに至った。
外交面では,仏及び近隣諸国との協力関係を中心に穏健な平和外交を展開した。
(ヘ) 赤道ギニア
7月のクーデター未遂事件でヌゲマ大統領は,部族内の実力者を逮捕し,結果的には政権基盤を強化することとなった。
経済面では,85年のフラン圏加盟以来,仏をはじめ西側との協力関係が進展している。
(ト) カメルーン
82年以来政権の座にあるビア大統領の権力基盤は,党(PDPC),行政機構の人事刷新を通じて一層強化され,ビァ政権は安定している。
他方,順調な成長を遂げて来た同国経済には・石油価格低迷により若干かげりが見えた。外交面では,西側先進国との間に活発な外交活動が展開されたほか,イスラエルとの間に外交関係が樹立された。
(チ) 中央アフリカ
81年9月の軍事政権樹立以来停止されていた憲法に代わる「新憲法」が採択され,また同時に軍事政権成立時から5年にわたって国家元首を務めてきたコリンバが大統領に選出され,民政化に向かっての前進がみられた。
(リ) チャド
リビアが支持するグクーニ前大統領の率いる反政府派と仏・米が支持するハブレ政権軍との間に86年10月停戦協定が成立し,グク一二派の拠点をめぐるリビアとチャド政府軍の戦闘が行われ,紛争は拡大化の様相を呈していたが,87年3月末チャド軍がチャド北部のリビア軍重要拠点を奪取し,戦局はチャド軍に優勢裡に推移している。現在,OAU(アフリカ統一機構)等を中心に調停努力が続けられている。
(ヌ) サントメ・プリンシペ
内政はおおむね平穏裡に推移した。
経済面では,経済再建のため,5か年開発計画を策定し,昨年に引き続き5月に援助国会議を開催した。
(5) 西部アフリカ
(イ) ナイジェリア
ババンギダ政権が,内政面では回教徒とキリスト教徒との衝突等の問題を抱えつつも,86年を無難に切抜け同政権の体制は徐々に固まり安定性が増しつつある。経済面では85年10月の経済非常事態宣言により厳しい輸入制限,公務員の給与削減等を実施してきたが,86年7月より世銀の指導をうけ構造調整計画(1988年6月まで)を導入し,輸入承認制度の廃止等輸入制限の緩和,ナイジェリア通貨を適正価格にすること(実質的ナイラ貨の切下げ)等の措置を順次実施している。他方,83年以来未解決のままであった累積債務問題に進展がみられ,86年9月中長期民間銀行債務の繰り延べ及び同12月中長期公的債務及び中長期及び短期付保商業債務の繰り延べが合意された。
(ロ) ガーナ
ローリングス現政権は,84年以降5%以上の経済成長を達成してきた実績を背景に,政権の基盤は一層強化された。政権発足当初は,東側寄りの外交を展開していたが,83年後半以降,経済再建を推進する上で,西側諸国の経済援助が不可欠であるとして,西側重視の外交姿勢を強めている。87年2月にオベン総務長官(首相格)を団長とする経済使節団が来日した。
(ハ) 象牙海岸
内政面では6期目に入ったウフェ・ボワニ大統領の指導の下,極めて安定的に推移した。経済面では,一次産品(特にコーヒー,ココア)の国際市況の低迷及びドル安による輸出所得の減少により厳しい状況にある。
外交面では,フランスを中心とした西側寄りの穏健かつ現実的な外交政策を継続しているが,東側諸国を含めた,外交の多角化に努めている。
(ニ) リベリア
87年2月ドウ大統領暗殺計画が発覚し軍人約30名が逮捕され,3月下旬,閣僚を含む政府高官149名の大幅な人事異動が行われた。
外交面では,86年7月ソ連との外交関係が復活し,11月にはギニア,シエラ・レオーネとの間に3か国不可侵条約が締結された。
(ホ) シエラ・レオーネ
87年3月モモ大統領失脚を狙ったクーデター未遂事件が発生した。経済面では,IMFの意見を採り入れ,レオンの変動相場制を実施し商業の活発化をめざしている。
(ヘ) ギニア
社会主義を標傍していたセクトゥーレの旧体制から,民主主義・自由経済を基本とするコンテ現政権への移行が進められた。具体的には,世銀・IMFの指導の下,構造調整計画が着実に実行された。コンテ政権に対立する勢力はほとんど存在せず,同政権は比較的安定した状態にある。
外交面でも,セクトゥーレ時代の東側寄り路線が改められ,西側寄りへの方向転換が行われている。
(ト) ギニア・ピサオ
85年11月のクーデター未遂事件発生後の政権は一応安定してはいるものの楽観は出来ない状況にある。
経済的には依然困難な状況にあるが,第2次4か年開発計画(1988~91)を策定した。
(チ) セネガル
内政は安定的に推移しており,1988年の大統領選挙,総選挙を控え,野党の活動が活発化するきざしがみられる。
経済面では第7次4か年計画(86~89年)の遂行に努力する一方,援助国の協力を得て,中長期財政・経済調整計画の下に,経済体質の改革に取り組んでいる。
ディウフ大統領はOAU議長(85~86年)としての活躍によりアフリカのみならず諸外国における評価を高めた。外交面では,仏との協力関係が基本であるが,米国との友好関係も緊密化した。
(リ) ガンビア
87年3月の選挙でジャワラ大統領は5選を果たし議会選挙でも与党である人民進歩党が過半数を獲得した。経済は依然困難な状況下にあり,IMF,世銀からの資金導入を図っている。隣国セネガルとのセネガンビア国家連合は,経済,金融制度の統一により進展がみられなかった。
(ヌ) モーリタニア
内政面では種族問題に端を発する騒擾事件が発生したが,タヤ政権は全体的には安定的に推移し,民主化に努力している。
経済面では,世銀,IMF勧告による経済再建計画を推進している。
(ル) マリ
長年にわたる干ばつ等の影響により経済困難を抱えており,IMFの支援を得て経済再建に努力している。内政は一応安定的に推移している。
(ヲ) ニジェール
クンチェ議長による軍事政権が18年目を迎え,深刻な経済困難や部族問題を抱えながらも食糧対策等地道な政策によって,安定した政権を保っている。
経済的には農業生産が好調であったがウラン市況が低迷を続けており,依然困難な状況にある。
外交面では,仏をはじめとする西側諸国との関係緊密化に努めており,9月にクンチェ議長が訪日した。
(ワ) ブルキナ・ファソ
3年目に入ったサンカラ政権は8月に第4次内閣改造を行い,その政権基盤を固めた。他方,8月第1次5か年経済開発計画を発表したが,IMFとのスタンドバイ交渉が失敗し,今後とも経済困難が予想される。
(カ) トーゴー
内政面では,クーデター未遂事件(9月)があったが,無難に処理され安定を取り戻している。
経済面は依然不振であるが,世銀,IMFの支援を得て構造調整に努力しており,成果を見せ始めている。
(ヨ) ペナン
ケレクー政権はマルクス・レーニン主義を提唱しているが,経済近代化のため仏等西側諸国への接近を強めている。
内政は,平穏に推移した。
(タ) カーポ・ヴェルデ
85年の総選挙で三選されたべレイラ大統領のもと国民の支持を得て第二次国家開発計画(86~90)を策定し,経済復興に努力している。
(6) 南部アフリカ
(イ) ザンビア
カウンダ政権は安定を保ったが,経済の悪化は回復をみせなかった。カウンダ大統領は,86年4月及び87年1月経済閣僚を中心とする内閣改造を行うと共に,経済困難克服のためIMF・世銀の構造調整計画に取り組んだが,外貨オークション制度の実施,補助金の撤廃等は,インフレ,失業の増大などをもたらした。このため86年12月,主食であるメイズの値上りに反対する住民の暴動が発生,その後もストライキが発生した。
外交面では,英連邦内において対南ア制裁の必要性を主張するとともに,フロントライン諸国の議長として南ア問題につき他のフロントライン諸国との協議を行う等,南部アフリカの平和と安定に努力した。
(ロ) ジンバブエ
ムガベ首相の率いるZANU-PF党が85年の総選挙で勝利を収めたこともあり86年,内政は安定的に推移した。86年4月ムガベ首相は,現行憲法を改正し白人議席を廃止する意向を明らかにするとともに,野党第一党ZAPUとの統合の話し合いを行った。
経済面では86年5月,経済の構造改革等を中心とする第一次5か年計画を策定した。
外交面では86年9月,ハラレにおいて第8回非同盟首脳会議を開催し,ジンバブエは議長国として会議を成功裡に終えた。
(ハ) 南アフリカ
(a) 内政面では,南アフリカ政府は非常事態宣言の解除(86年3月),パス法・都市流入規制法の廃止(6月)等の改革措置を実施したが,これらの改革は,アパルトヘイト撤廃にほど遠かったことから5月1日(メーデー)及び6月16日(ソウェト暴動10周年記念日)に全国的な職場・学校放棄が行われる等黒人側の反アパルトヘイト暴動は継続した。
これに対し,ボ一夕政権は86年6月,全土に非常事態宣言を発布し,また,12月には報道規制の強化を行う等強権で対応した。
(b) 国際社会の対南ア制裁強化の動きが強まり英連邦幹事国による追加措置発表(86年8月),EC外相理事会での規制措置決定(9月),我が国の追加措置発表(9月)に続き,10月には,米国が対南ア制裁法案を可決した。
(c) 経済面においては,86年第3四半期より国内需要にようやく回復がみられ,輸出もランド安に支えられ好調で,全体的にはやや明るいきざしがみえ始めた。
しかしながら,南ア経済の先行きに対する不安感,インフレ・失業の増大が依然として継続し,また,国際的南ア非難もあって米国系を中心に有力企業が次々と撤退を発表した。
(d) 周辺諸国との関係では,86年5月に南ア軍がボツワナ,ザンビア,ジンバブエのANC拠点に同時越境攻撃を行い,12月にもスワジランドのANC拠点に対し攻撃を行ったため国際的非難を招いた。
(ニ) アンゴラ
内政面では,政府MPLA・PT(アンゴラ人民解放運動・労働党)と反政府団体UNITA(アンゴラ全面独立民族同盟)との交渉は行われず,ドス・サントス大統領も11月,UNITAとの交渉の意思がないことを明らかにした。またMPLA軍とUNITAとの内戦も膠着状態のまま推移した。
経済は,輸出の95%を占める石油価格が下落したこともあり,一層悪化した。また86年9月からIMF・世銀への加盟に関する話し合いを開始した。
外交面では86年12月ムビンダ外相は,アンゴラ外相として初めて旧宗主国であるポルトガルを訪問した。
(ホ) モザンビーク
86年10月建国の父であるマシェル大統領が飛行機事故により死亡したが,11月には,新大統領にチサノ前外相が選ばれマシェル路線の踏襲を表明した。
同国の経済活動はたび重なる旱魃とモザンビーク民族抵抗運動(MNR)の破壊活動により回復をみなかった。
なお,故マシェル大統領は,86年5月訪日し,日・モザンビーク関係強化に貢献した。
(ヘ) ナミビア
86年3月,ポータ南アフリカ大統領は,キューバ兵のアンゴラ撤退計画につき同年8月1日までに何らかの合意が得られれば,南アとしては国連安保理決議435の実施を行う用意がある旨を表明したが,アンゴラ側が応じなかったため事態の進展にはつながらなかった。
86年9月20日,国連ナミビア特別総会が開催され,南アのナミビア不法統治非難,南アのナミビアからの即時撤退要求,安保理決議385及び435の無条件・即時実施要求,南アによるナミビア内暫定政権樹立非難,安保理に対する対南ア包括的強制制裁の採択要請を骨子とした決議案が採択された。
2. 我が国との関係
(1) サハラ以南
アフリカの独立国は,現在45か国(国連加盟国の約3分の1)を数え,国際場裡において大きな影響力を持っている。また,この地域は稀少金属を含む豊富な資源を有し,世界経済上も重要な役割を担っている。
アフリカ諸国の大部分は,経済の基盤が未だ弱く,構造的な食糧不足をはじめ,低成長,累積債務問題などの深刻な経済困難に直面している。
我が国は,アフリカの重要性とその国際的役割の増大,また相互依存関係の深まった今日の国際社会における我が国の国際的責務を果たすとの観点から,これら諸国との人物交流を促進して相互理解を深め,またこれら諸国の国造りのために幅広い分野で経済・技術協力を行うことにより,その経済社会開発に寄与するよう努めている。
(2) 人物交流
9月にクンチェ・ニジェール最高軍事評議会議長が国賓として・また・87年3月には,オベン・ガーナ総務長官が外務省賓客として,それぞれ訪日したほか,86年5月にマシェル・モザンビーク大統領が非公式に訪問する等計20名の閣僚級の要人が我が国を訪れた。
(3) 経済
(イ) 貿易
86年の我が国のサハラ以南アフリカ諸国に対する輸出は,31億3,400万ドルであり,対前年比5.3%の増となった。
これに対し,我が国のサハラ以南アフリカ諸国からの輸入は,32億3,500万ドルで対前年比21・5%の大幅増となったため僅かながら我が国の入超となった。
貿易の国別構成については,輸出では南ア,リベリア,ナイジェリア,ケニア,カメルーンが上位5か国で全輸出量の73%を占め,また,輸入では南ア,ザンビア,モーリタニア,リベリア,ガーナが上位5か国で全体の85%を占めた。
(ロ) 投資
86年3月末の我が国の対サハラ以南アフリカ直接投資許可実績は、累計で36億900万ドルとなっており,我が国対外直接投資総額の34%のシェアを占めた。
また,86年度は3億100万ドル(シェア1.4%)で対前年比79.2%と大幅に増大した。
(4) 経済・技術協力
我が国は特に70年代後半から対アフリカ援助の拡充に努めてきており,我が国二国間ODAに占めるアフリカのシェアは75年の6-9%から85年の10.9%へと約1.6倍に,ドルベースの絶対額では約4.7倍になった。86年度においても,我が国は,86年5月の国連アフリカ特別総会で採択された「国連行動計画」を尊重しつつ,アフリカ諸国の中長期的な食糧自給達成が必要との観点にたち,食糧・農業分野に対する援助を中心とした援助の拡充に努め,85年5月のボン・サミット・フォローアップとして提唱している「アフリカ緑の革命構想」の一環として「アフリカ緑の平和部隊」をセネガル及びタンザニアに派遣したほか,アフリカ諸国の構造調整を支援するため,85年度に引き続き世銀「アフリカ基金」との特別協調融資を実施した。この結果86年のサハラ以南アフリカ向け二国間政府間援助は4億1,846万ドルとなり,前年を上回る実績を上げた。
なお,南ア情勢の展開により経済的困難を被っている南ア周辺諸国に対する援助強化の一環として,87年2月,南部アフリカ経済協力調査団をこれら諸国に派遣した。
<要人往来>
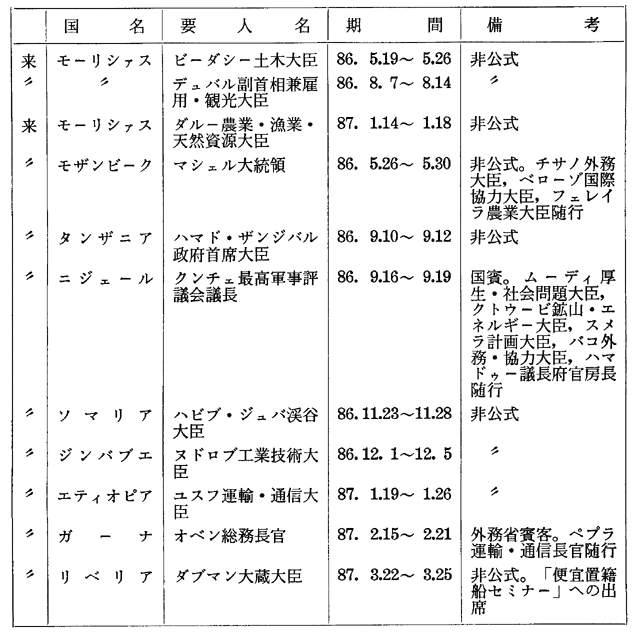
<貿易関係>
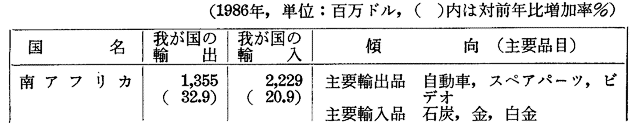
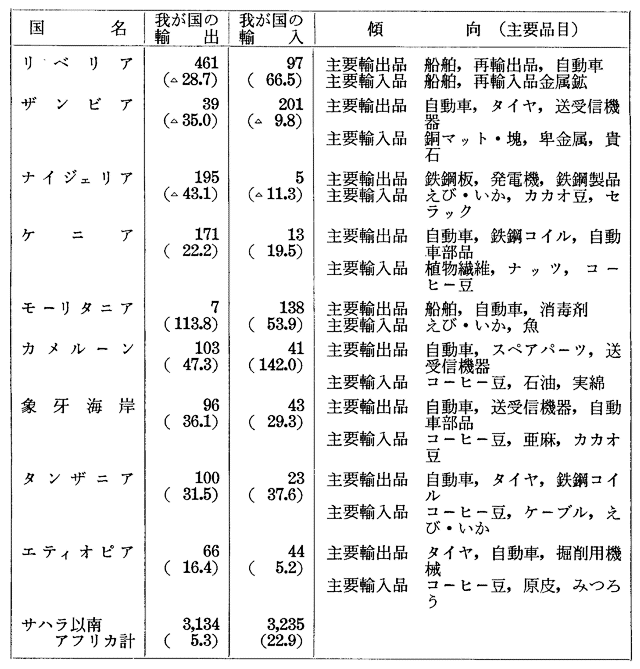
<民間投資>

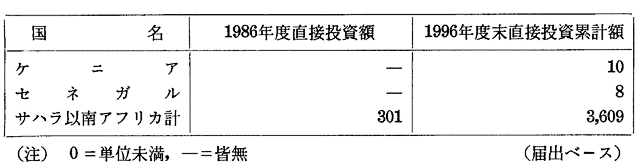
<主な鉱物の輸入品>