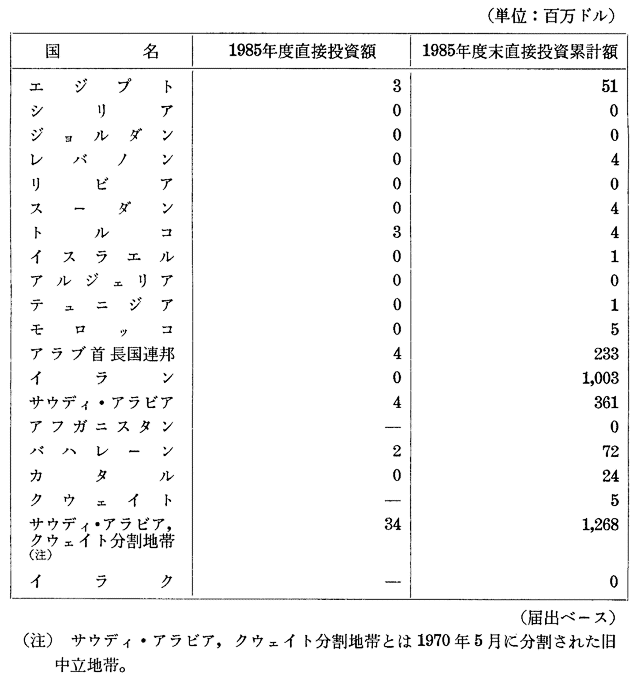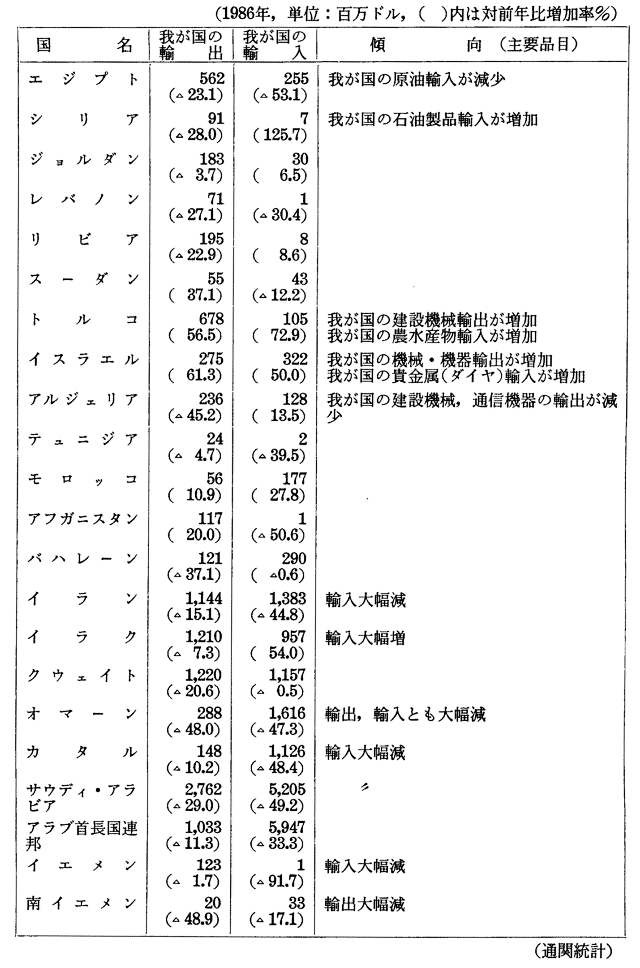
第7節 中近東地域
1. 内外情勢
中近東地域は,世界の主要な原油供給源として戦略的重要性を有している。特に我が国は,原油必要量の7割近くを依存しているのみならず,貿易及び投資先としても中近東諸国と極めて密接なかかわりを持っている。しかし,この地域はイラン・イラク紛争,中東和平問題,レバノン紛争,各種テロ問題等の政治問題のほか,急激な経済発展により生じた経済・社会問題,石油価格の低下に伴う財政収入の減少等種々の問題を抱えている。こうした諸問題が域内の不安定要因となり,ひいては,国際社会全体に大きな影響を及ぼす可能性もあるので,その動向には不断の注意を要する。
このような状況のなかで,我が国は,経済・技術協力を通じ中近東諸国の国造り,人造りに積極的に協力するとともに人的交流,文化交流の強化を通じ相互理解の増進にも努めている。
我が国の国際的地位の高まりとともに,近年,中近東諸国から我が国に対し単に経済分野だけでなく政治面でも積極的な役割を果たすことを要望する声が強まっている。このような期待に応えるべく,我が国は,86年においても,中東平和問題及びイラン・イラク紛争の早期平和解決に向けての環境造りのため,当事者に対し働きかけを行うなど,機会あるごとに関係者との協議を重ねた。
(1) 中東和平をめぐる動き
(イ) 86年2月19日,フセイン国王は「PLOが信頼性と一貫性を回復するまで,PLO指導部との政治的調整は行わない」との演説を行い,85年2月の「フセイン・アラファト合意」に基いて1年間にわたって進められてきた和平へ向けてのPLOとの共同政治行動を停止した。
さらに7月には,ジョルダン政府は同国内のファタハ(PLO主流アラファト派)事務所の閉鎖を決定し,ジョルダン・PLO関係の冷却化が印象づけられた。
(ロ) 7月,ミッテラン仏大統領の訪ソの際,ゴルバチョフ書記長は従来から主張している中東和平に関する国際会議開催の準備段階として国連安保理5常任理事国を基礎とする準備委員会の開催を提案し,フランスはこれに原則賛成したが,米国は同提案を直ちに拒否した。
(ハ) ペレス・イスラエル首相は7月21日モロッコを訪問し,フェズ憲章を中心に中東和平問題につき,ハッサン国王と会談を行った。右会談は純粋な意見交換に終ったが,エジプト以外のアラブ諸国がイスラエル首脳と公式に会談したのはこれが初めてである。
(ニ) 9月11日,ペレス・イスラエル首相はエジプトを訪問し,ムバラク大統領と会談を行ない,1987年を「和平のための交渉の年」と宣言するプレス・ステートメントを発表した。
(ホ) 87年2月,シャミール・イスラエル首相が訪米した際,米国側は,中東和平に関する国際会議開催構想に反対する同首相に対し,国際会議の開催を含む,直接交渉につながるあらゆる可能なアプローチを検討する必要性を強調した。
(ヘ) 他方,2月23日にはベルギーにおいてEC外相政治協議が開催され,EC12か国は中東和平国際会議を国連の枠内で支持するとの「中東に関するEC12か国宣言」を発出した。
(ト) かかる状況下同月25日,ペレス・イスラエル外相はエジプトを訪問し,エジプト,イスラエル両国は全当事者間の直接交渉につながる国際会議の87年開催を提案する旨の,共同声明を発表した。
(チ) 一時失われていた中東和平へのモメンタムが昨年以降活性化してきているが,アラブ側はいまだに中東和平の進め方をめぐり分裂しており,またイスラエル側も国際会議に反対しているシャミール首相と国際会議を支持するペレス外相の間に対立があり,それぞれ和平プロセス進展への障害となっている。
(2) レバノン情勢
(イ) 85年12月,シリアの主導の下,アマル(イスラム教シーア派),PSP(イスラム教ドルーズ派)及びレバニーズ・フォース(LF:キリスト教マロン派)三派閥でレバノン問題解決のための国民合意(ダマスカス合意)が調印された。
しかしながら,キリスト教徒マロン派内部で右合意はキリスト教徒の権限を大幅に縮小するものであるとの反発が強まり,内部で戦闘が発生し,結局同合意はキリスト教徒マロン派の受け入れるところとはならなかった。
(ロ) 一方,かかるキリスト教徒の動きに対しアマル及びPSPは反発し,両者間で86年5月にはベイルートで大規模な戦闘が発生した。このような状況下,7月シリア軍兵士150~200名がベイルートに進駐し,市内の治安維持活動を開始,ベイルート情勢は一時改善の兆しを見せた。
(ハ) 他方,85年のイスラエル軍撤退以降,PLOの戦闘員がシドン,.ティール及びベイルート南部のパレスチナ人難民キャンプを中心に再び勢力を伸張させ,これに対しイスラエル軍は,86年1月以降PLO基地に攻撃を重ねた。
(ニ) また,アマルはPLOの戦闘員放逐を狙い,9月末以降,パレスチナキャンプにおいてアマル,PLO間の戦闘が激化し,アマルは各パレスチナキャンプを包囲し,各キャンプ難民を,飢餓状態に落とし入れた。
87年2月16日にはかかるアマルのPLOに対する強硬姿勢,アマルの西ベイルートにおける支配権確立に反発するPSP等とアマルとの間で大規模な戦闘が展開された。各派指導者はダマスカスにて会談を行い,西ベイルートの治安回復に向けてのシリアの軍事介入を要求し,右に基づき,21日,シリア軍7千~1万人が西ベイルートに進駐し,状況は改善しつつある。
(3) イラン・イラク紛争と湾岸情勢
(イ) 86年2月の南部戦線における攻勢以来,イランはイラクの石油・工業都市ファオの占領を継続している。これに対しイラクは,5月17日,中部戦線でイラク領内に侵攻しメヘラン市を占領し,同市とファオの交換を示唆したが,6月30日のイランの反撃を受け7月3日撤退した。
(ロ) 夏よりイランはこれまでのイランの原油積出し基地カーグ島空襲に加えイラン側の製油所,発電所等の経済施設に対する空襲を強化した。また,これまでイラク軍機の航続距離外とみられていたイランの原油積替え地点であるシリー島,ラバン島,ホルムズ・ターミナルを相次いで空襲した。イランは,このようなイラクの経済施設攻撃を文民地域攻撃であると非難し,バグダッドに対する地対地ミサイル攻撃等で報復した。
(ハ) 春以降イラン指導者は本年を戦争の運命を決する年とする旨を繰返し発言しつつも,限定的攻勢を繰返すに止まっていたが,87年1月9日より,イラン軍はイラクの第2の都市バスラに向けて攻勢をかけたため南部戦線を中心に戦況が激化した。イランはバスラ東方約10キロの地点まで進出したが,イラク側の防戦により戦闘は再度膠着した。
(ニ) また,このような地上戦闘の激化に伴って相互都市攻撃も再燃し,イラクはテヘラン,コム等のイラン側の主要都市を空襲し,これに対しイランもバグダッドに対しこれまでにない頻度で(1月間に11発)ミサイルによる報復攻撃を行った。しかし,2月19日のフセイン大統領の対イラン攻撃停止宣言を契機に,事態はとりあえず鎮静化した。
(ホ) 86年を通じて湾内を航行する船舶に対する攻撃件数の増加も見られ,前年の約2倍以上の100隻あまりの船舶が被弾した。特に86年10月以降クウェイトを目的地とする船舶に対する攻撃が頻発し,87年1月7日にはコスモ・ジュピター号が日本船籍船として初めて被弾した。また,3月には米国はイランが中国製の地対艦ミサイルをホル?ズ海峡に配備したことを公表しており,湾内情勢の緊張が高まった。
(ヘ) この間,本件紛争解決のための種々の努力がなされ,10月8日には同年2月に採択された戦闘の即時停止等を求める決議582号の履行を求める安保理決議588号が採択されている。
また,8月2日,フセイン・イラク大統領はイランの為政者に対して5項目からなる和平提案を行った。
(4) アフガニスタン情勢
(イ) 86年になって,ソ連・アフガン政権側において平和攻勢とみられる動きもあったが,ソ連軍(11万~12万人)は同国に依然として居すわり,ソ連軍・アフガン政権側と反体制勢力との戦闘は続いており,同国の情勢は改善していない。
(ロ) ソ連・アフガン政権側の目立った動きとしては,7月にゴルバチョフ書記長がウラジオストックにおける演説でアフガニスタン駐留ソ連軍6個連隊の撤退に言及し,右が10月に行われた(撤退規模は約8,000人といわれる)こと,また,12月末に,5月にカルマルにかわり,人民民主党の新書記長に就任していたナジブラ書記長が,ゲリラ側との一方的停戦を含めた国民和解の方針を打ち出したことがあげられる。こうした一連の措置によりソ連・アフガン政権側は,問題の解決に積極的に対応しているとの姿勢を打出そうとしたものとみられているが,ソ連軍6個連隊の撤退は,ソ連がそもそもアフガニスタンで必要とはしない高射砲連隊等から成っており,質的にも,量的にも実質的な意味があるものとは言い難く,またアフガン政権側の国民和解の呼びかけも,反体制勢力の大勢はこれを拒否する姿勢を明らかにしている状況にある。
こうした一連の平和攻勢の一方で,ソ連・アフガン政権はパキスタン国境地帯への爆撃等を強化しており,アフガン政権軍機がパキスタン領空を侵犯し越境爆撃を行うとの事態も続いている。
(ハ) 本問題の解決をめざして,コルドベス国連事務次長の仲介によるパキスタン・アフガン政権間の間接交渉が引き続いて,86年5月及び7~8月,87年2~3月にジュネーヴにて行われたが,交渉の中心課題たるソ連軍撤兵のタイム・テーブルについては双方の立場が依然隔っていると言われ,合意に至っていない。
我が国は,ソ連軍の即時全面撤退を含むアフガニスタン問題の早急な解決の必要性を機会ある毎に訴えてきているほか,パキスタン,イランへ流入した450万人にのぼると言われるアフガン難民に対して国連難民高等弁務官(UNHCR)及び世界食糧計画(WFP)を通じ積極的な援助を行っている(61年度の援助総額は約38億5,000万円)。
(5) 各国の情勢
(イ) エジプト
(a) 内政面ではムバラク大統領は85年に引き続き民主化を推進し,86年12月に野党勢力より従来からその合憲性につき疑義が呈されていた人民議会選挙法を一部改正した後,87年2月には人民議会の解散の是非を問う国民投票を行い約90%の賛成票を得て議会を解散した。4月6日に行われた選挙で与党国民民主党は3分の2の安定多数を占めたが野党も議員数を倍増させている。
国内治安面では86年2月25日徴兵年限の1年延長という誤ったうわさから中央治安警察隊の暴動が発生・77年の食糧暴動以来約9年振りの大規模な騒擾に発展し,約10日後ようやく事態は正常に復すという事件があったが,それ以降はイスラム原理主義者等による小規模な騒擾等がみられたが,国内での大きな騒動,混乱は回避されている。
(b) 86年11月にはルトフィ首相が辞任,後任にはシドキ会計検査院長が就任した。辞任原因の一つは経済情勢の改善の面で成果をあげ得なかったこととされている。なおエジプトの経済情勢は対外累積債務経常収支赤字,財政赤字の面で依然として厳しい状況が続いている。
(c) 外交面では,イスラエルとの関係を進展させる一方,中東和平プロセスの進展にも寄与した。まず,9月11日にはイスラエルとの間で1982年のシナイ半島返還以来,両国間の象徴的懸案であったタバ問題に関し仲裁裁判付託合意書に署名,これを受けて同日ペレス首相(当時)はカイロを訪問し両国間で5年振りの首脳会談が行われた。さらに87年2月にはペレス外相はエジプトを訪問しムバラク大統領等と会談,中東和平に関する国際会議の開催を提案した。
また,ブラブ世界への復帰も徐々にではあるが進展させており,ムバラク大統領は87年1月クウェイトにて開催されたイスラム会議機構(OIC)首脳会議にエジプトのOIC復帰後初めて参加し,今なお公式には断交状態にあるシリアのアサド大統領,サウディのファハド国王等と会談を行った。
対米欧関係ではアブ・ガザーラ国防相,ガンズーリ経協相等の訪米,7月と12月の2度にわたるムバラク大統領の欧州諸国歴訪等を通じ良好な関係を維持した。また,ソ連との関係は,7月のガーリ外務担当国務相の訪ソ等徐々に進展している。
(ロ) シリア
(a) 86年3月をもって就任16周年を迎えたアサド大統領は84年後半以降健康を取り戻して内外の問題に積極的に取り組んでいる。86年2月には国民議会議員(任期4年)の選挙が施行され,全議席195のうち,与党バース党を中心とする進歩国民戦線が160議席を占めた。
(b) 経済面においては,石油価格の下落に伴う出稼ぎ労働者からの送金の減少及び産油国からの財政援助の低下により,農・工業とも生産が伸び悩む一方で外貨準備の不足が深刻化しており,物価の急騰,物資の入手難が伝えられている。
このため政府は厳しい外貨規制を行いつつ,財政・金融面での引締め,私企業部門の活性化等経済再建に取り組んでいる。
(c) 外交面では,86年5月国内で大規模な戦闘が発生し,7月にシリア軍をベイルートに派兵して治安維持活動を開始,87年2月にはさらに戦闘が激化したため,西ベイルートの治安回復のため,シリア軍7千~1万人が同地域に進駐し,状況は改善しつつある。
(d) 近隣諸国との関係ではジョルダンとの関係改善が進み,5月アサド大統領のジョルダン訪問が実現し,フセイン国王も85年末以降頻繁にシリアに来訪している。
また,アサド大統領は87年1月,クウェイトにおいて開かれたイスラム会議機構首脳会議に出席し,その際公式には断交状態にあるエジプトのムバラク大統領とも会談を行った。
PLOについては82年以来対立を強めているアラファト議長との関係は依然として改善されなかった。
またイラン・イラク紛争については,シリアは引き続きイランを支援しており,イラクとは緊張関係が続いている。
(e) なお,86年10月,英国はエル・アル航空機爆破未遂事件にシリアが関与したとして,シリアと断交し,米国,カナダが大使を召還したほか,また,米国及びEC諸国はそれぞれ対シリア措置を発表した。
(ハ) ジョルダン
(a) 現体制はフセイン国王の個人的魅力及び現実的かつ着実な政策により,広く国民的支持を得ており,86年も内政は比較的平穏に推移した。
(b) また,85年4月に成立したリファイ内閣は経済活動の活性化及び国内治安対策を主要課題として取組み,86年には第三次経済開発5か年計画及び被占領地開発5か年計画を発表した。
(c) 外交面では,86年2月19日フセイン国王はPLOが信頼性と一貫性を回復するまでPLO指導部との政治的調整は行い得なくなった旨表明し,85年2月のフセイン・アラファト合意に基づいて進めてきた和平へ向けてのPLOとの共同政治行動を停止した。さらに7月には国内のPLO・ファタハ事務所の閉鎖を決定し,PLOとの関係の冷却化を印象付けた。
(d) 他方,シリアとは85年以来の関係改善が進展し,86年5月にはシリアのアサド大統領が8年振りにジョルダンを訪問した。次いで同月フセイン国王はイラクを訪問し,シリア・イラクの和解を試みたが,具体的な成果は上がらなかった。
(ニ) リビア
(a) 80年代初頭以来事実上断交状態にあった米国との関係は,86年1月の米国による対リビア措置の発表及び3月のシドラ湾における米軍との間の戦闘発生により一層悪化し,ついに4月には米国は同月の西ベルリンのディスコ爆破事件へのリビア関与が明らかになったとして,リビアの国際テロ活動予防のための自衛行動であるとの理由のもとにトリポリ及びベンガジの軍事基地等を爆撃するに至った。
(b) 内政面では,カダフィ大佐は同爆撃直後から約4か月間公衆の前に姿を現さず,その間同大佐の消息に関する様々な憶測が飛びかったが8月末より同大佐は公開の場に頻繁に出現するようになりカダフィ体制が引き続き維持されていることを印象づけた。
87年2月の全国人民会議において全国人民委員会(内閣相当機関)の改造が決定され,同委員会メンバー11人中7人の新書記が任命された。対外連絡担当書記(外相格)は就任1年足らずで更迭され,前書記長(首相格)が右書記に任命された。
(c) その他外交面では,アラブ・アフリカ地域でのリビアの孤立が一層深まっており,86年8月リビアが,ハッサン・モロッコ国王とペレス・イスラエル首相との会談を非難したのに対し,モロッコは84年以来のリビアとの連合協定破棄を宣言した。
(d) また,チャド紛争については,引き続き反政府軍を支援しているが,86年10月に起きた反政府軍内のグク一二派とオマール派の内紛に際してはオマール派を支援してリビア軍が直接介入し,これに対してグクーニ派はチャド政府軍側について両者の間で戦争が再発した。87年3月末,リビア軍は,政府軍との戦闘に敗れ,チャド北部の重要拠点を放棄し,リビア・チャド国境地域への撤退を余儀無くされた。
(e) 対ソ関係では米軍の対リビア爆撃後直ちに5月カダフィ大佐に次ぐ実力者ジャルード少佐がソ連を訪問しており,また9月のリビア革命記念日にはソ連からはデミチェフ最高会議幹部会第1副議長を団長とする代表団がリビアを訪問する等関係の維持,強化が見られた。
(f) 経済面においては,86年から第3次5か年経済開発計画が開始され,人工大運河計画及び石油化学工場の建設等が国家最優先プロジェクトとして推進されている。しかし86年初以来の石油価格暴落による国家収入の急減により政府発表によれば86年度予算の執行率は約35%で計画を大幅に下回っており,経済情勢は困難な状況にある。
(ホ) スーダン
(a) 内政面では85年4月のダハブ将軍によるクーデターから1年たった86年4月上旬実施された総選挙の結果・ウンマ党及び民主統一党がそれぞれ第1党,第2党を占めるに到り,同年5月6日ウンマ党党首マハディが新首相に就任し,15日に文民内閣が発足した。しかし,ニメイリ前大統領失脚の主因であった困難な経済情勢並びに最大の政治課題である南部問題については解決の見通しは未だ立っておらず,マハディ首相は反政府勢力のスーダン人民解放戦線(SPLA)との話し合いの姿勢を示しているが,SPLAの反政府攻勢は依然継続している。
(b) 外交面では,マハディ政権は発足以来,周辺国特にリビア,エティオピアとの関係改善に努めているが,SPLAを支援していると言われるエティオピアとの関係は改善されていない。他方リビアとの関係はマハディ首相が就任後最初の外遊先として86年8月リビアを訪問し,同年9月リビアのカダフィ大佐がスーダンを訪問する等,両国の関係改善が急速に進展してきたが,87年3月に至りスーダン西部にチャド紛争との関係からリビア軍が駐留し,これに対しスーダン側が抗議してリビアは同軍隊を撤収させるという事件が発生した。一方エジプトとの関係は,クーデター後冷却化していたが,87年2月マハディ首相がエジプトを訪問し,両国の経済などの分野での協力促進をうたった同胞憲章に調印し,関係は改善した。米国,ソ連との関係については,マハディ首相は86年8月ソ連を,同年10月米国をそれぞれ訪問し,いずれにも偏しない姿勢を示している。
(c) 経済面では,多額の債務返済に絡んで86年2月1MFから新規融資資格を停止されたが,これに対し新政権は有効な解決策をいまだ示していない。
(へ) トルコ
(a) 内政面では83年の民政移管及びオザール政権の成立後3年を経過し,国内治安も安定を増し,民政移管時に67県全県に施行されていた戒厳令は86年末には東南部の5県を対象とするのみとなっている。86年9月の中間選挙で与党祖国党は選挙対象となった11議席中,6議席を獲得し,その後解散した野党自由民主党の一部を取り込んで,議席数を400議席中255議席(前回総選挙時237)と増大している。
(b) オザール政権下,経済面でのパフォーマンスはおおむね順調であり,インフレ率は一時の100%を越えるレベルから約30%まで低下し,経済成長率は84年以降年率5%を上回っており,輸出も伸び,財政面でも体質の強化が見られている。ただし86年の経常収支は輸出が伸びなかったのに対し,輸入は石油価格の低下にもかかわらず高水準を維持し,また利子支払も増大したため,悪化した。
(c) 外交面では,トルコはNATOの一員として穏健かつ現実的な西側寄りの路線を基調としつつもソ連を中心とする東側諸国との経済交流及びアラブ諸国や日本を含めたアジア諸国との関係強化を図る等多角的な外交を積極的に展開している。
87年4月にトルコはECへの加盟を申請し,また米国とは懸案の防衛経済協力協定の改訂につき合意が成立し,87年3月回協定の改訂が行われた。またオザール首相は86年8月にはソ連を訪問し,ソ連からトルコに至る天然ガスパイプラインの建設に合意した。なお同首相は86年中にイラン,イラク,サウディ等の中東諸国を歴訪した。
他方,ギリシャとはサイプラス問題をめぐり対立しているのに加え,87年3月にはエーゲ海大陸棚の油田探査権をめぐり両国間で一時緊張が高まった。またブルガリアとは同国に居住する少数派トルコ系住民問題で対立している。
(ト) イスラエル
(a) 84年9月成立した挙国一致内閣の当初の取極に基き,86年10月,ペレス労働党党首からシャミール・リクード党首へ首相交替が行われた。
(b) ペレス内閣は,イスラエルの大きな課題であったレバノンからのイスラエル軍撤退及び経済の建て直しの面で成果を収めた。経済面でも,85年7月より実施された,抜本的民需抑制,物価・賃金の凍結を柱とする第4次緊急措置により,86年の物価上昇率は19.7%にまで収束し(85年は185%),輸出は前年比約10%増加した。
(c) 外交面では,86年7月ペレス首相が,モロッコを訪問し,ハッサン国王と会談を行ったが,これはエジプト以外のアラブ首脳がイスラエル首相と公式に会談した初めての例であり,注目された。エジプトとの間では,9月に両国間の国境問題であったタバ問題に関し仲裁付託合意文書が成立し,これを受けてペレス首相はエジプトを訪問しムバラク大統領と会談,サダト・ベギン会談以来5年振りに両国間の首脳会談が実現した。この他,8月にはカメルーンとの外交関係が再開され,8月ソ連との間でも67年の断交以来初の領事に関する政府間協議が行われ,また9月ニューヨークにおいて両国外相会談が行われる等活発な外交が展開された。
(d) 中東和平問題に関しては,「直接交渉に導く国際会議」の開催にむけて国際的気運が高まるに従い,これを積極的に進めようとする労働党と,国際会議はイスラエルが困難な要求を押しつけられる場となるだけであるとしてこれに反対するリクードの間の立場の違いが明白となり,国内政治の面でも複雑な様相を呈している。
(チ) アルジェリア
(a) シャドリ大統領は,内政前において従来通り堅実かつ現実的な政策を維持し,また治安面でもイスラム原理主義等の不穏な動きも見られず,その内政は,おおむね平穏に推移した。
(b) 外交面では中東における紛争の解決に向け,活発な調停,仲介に乗り出し,PLO全諸派会議のアルジェでの開催提案,レバノン紛争解決に向けての調停,レバノンの仏人人質解放のための仲介等を行った。
また,リビアとの関係では86年1月末アルジェリアでシャドリ大統領がカダフィ大佐と会談し更に12月には同大統領がリビアを訪問する等,関係改善が見られた。
(c) 経済面では,86年1月制定された新国民憲章により,従来の重化工業優先の政策から,中小規模の軽工業の重視,農業,水資源開発及び民間部門の積極的活用といった今後のアルジェリアの基本的な経済政策を定めた。
しかし,この新たな経済政策にもかかわらず,86年のアルジェリア経済は原油生産の縮小政策の他,原油価格の下落,天然ガス輸出価格の下落により輸出収入が減少し,厳しい状況が続いた。
(リ) チュニジア
(a) ブルギバ大統領は84歳の高齢にもかかわらず,依然として第一人者として国政をリードした。
86年7月,6年余りにわたりその地位にあったムザリ首相が汚職等の理由で解任され,その後任にスフアール財務経済大臣(当時)が就任した。また,ムザリ首相の解任に先だって,多数の閣僚が更迭されており,86年のチュニジア内政は混乱の様相を呈した。
(b) また,9月半ばにはムザリ前首相の下で長期間外交を担当したエセブシ外相も更迭され,後任にマブルーク駐仏大使(当時)が就任したが,従来のチュニジアの穏健な外交路線に大きな変化はなかった。
(c) 経済面については,86年は第6次経済・社会開発5か年計画の最終年にあたり,政府は,右計画の遂行に努力を傾注したが,国際石油市場の軟化に伴う石油収入の減少,地中海における一連の国際テロ事件等による観光収入の減少,天候不順による穀物生産の減少と食糧輸入の増大により,86年のチュニジア経済は,財政収支及び国際収支の面で深刻な問題に直面した。
(ヌ) モロッコ
(a) ラムラニ首相は病気療養のため86年9月29日首相を辞任し,後任にララキ副首相兼教育相が任命された。ララキ新首相は基本的にはラムラニ前首相の政策を維持し,内政はおおむね平穏に推移した。
(b) 外交面では,86年7月21日,ハッサン国王がペレス・イスラエル首相(当時)をモロッコに迎え入れ,中東和平問題につき協議を行った。シリアはこれに強く反発し,モロッコとの外交関係を断絶し,その他ソ連,アルジェリア,PLO等もモロッコを非難した。また,リビアもモロッコを強く非難したが,これに対しモロッコは84年8月に締結されたモロッコ・リビア連合協定を破棄した。
(c) 経済面では,81年来の旱魃が終えんし,穀物生産が史上最高の豊作を記録したこと,また石油価格の値下げ,対ドルレート及び金利の低下等モロッコにとり有利な環境が生じたことから86年には国内総生産は5.7%と高い伸びを示すと共に貿易赤字も前年比約25%の縮小が見込まれている。
(ル) アフガニスタン
(a) 現在も11万人のソ連軍が駐留しており,依然,各地でソ連,アフガン政権軍と反体制ゲリラ勢力との戦闘が続いている。
(b) 内政面では,5月,カルマルに代わりナジブラ元秘密警察(KHAD)長官が人民民主党書記長に就任し,注目された。同書記長は,12月末に国民和解の政策を打ち出し,反体制ゲリラ側との一方的停戦を宣言したが,反体制ゲリラ側の大勢はこれを拒否する方針を明らかにした。また,政権内部にはパルチャム派とハルク派間の派閥抗争というソ連に大きく依存している。
(ヲ) イラン
(a) 現イスラム共和国体制は,イラクとの紛争をかかえ,また体制内では内外諸政策をめぐって種々の意見対立もあるものの,基本的には引き続き安定的に推移した。
(b) 経済面では,86年初よりの石油価格下落は戦時下の同国の経済に深刻な影響を及ぼした。政府は,これに対処するため非石油産品の輸出拡大による外貨獲得を含む新経済計画を発表した。
(c) 対外面では,仏及びソ連両国と関係改善を図る動きが見られ,また,石油価格の安定をめぐってサウディ・アラビアとの協調関係を重視する姿勢が注目された。
また,米国が関係改善を意図して秘密裡にイランと接触していた事実が公けになったが,対米関係に基本的変化はなかった。
(ワ) イラク
(a) 内政面では,イラン軍の攻勢による戦況の一時的悪化及び石油価格下落に伴う経済状況の悪化が,イラクの戦争,経済運営に影を投じているが,86年7月,4年ぶりの与党バァス党大会の開催を通じ党及び軍の態勢の建て直しを図る等の動きもあり,フセイン政権は安定を維持している。
(b) 外政面では,汎アラブ,非同盟,反シオニズムを基本方針としつつ,当面最大の課題であるイランとの紛争の早期終結を目指して,12月のフセイン大統領のサウディ・アラビア訪問等アラブ穏健派諸国,ソ連,西側諸国と幅広い外交を展開している。
(c) 我が国との関係では,国連における倉成外務大臣のアジーズ外相との会談(86年9月),アルワーシュ厚生大臣(9月)及びザハウィー外務次官(87年2月)の来日等ハイ・レベルの対話が続けられた。
(カ) サウディ・アラビア
(a) 石油収入の大幅な減少に伴い国内経済が一層低迷(86年3月に予定されていた新年度予算は同年末まで延期)する中で,政府は主要インフラ・プロジェクトの完成を背景に全般的な財政削減を行い,その一方で,各種補助金の支出を継続する等民生に配慮した慎重な政策運営を行っており,国内政情は安定的に推移した。
(b) 外交面では,GCCを中心とした域内諸国との関係緊密化に努めるとともに,イラン(86年9月アガザデ石油相の訪サ),ソ連(87年1月ナーゼル石油相訪ソ)との対話のチャネル維持にも努める等引き続き幅広い外交を展開した。
(c) 国際石油情勢に関しては85年秋以降スウィング・プロデューサーの役割を放棄し,市場原理を反映した原油販売価格を採用していたが,石油市況の一層の軟化を受け同年末のOPEC総会に際しては協調減産と価格体制の建て直しに向け重要な役割を演じた。
(ヨ) クウェイト
(a) 経済政策をめぐる政府と議会の対立が深まり,議会の動向が国内政治の混乱を惹起しかねない状況となったことを背景として,86年7月,ジャーベル首長は議会を解散した。
(b) 86年2月のイラン軍のイラク領ファオ進攻に伴い,同国をめぐる情勢も緊張の度を深め,クウェイトは紛争の終結を強く訴えるとともにイラク支援の姿勢を強めた。また87年1月同国はイスラム諸国首脳会議を主催したが,これに先だち同会議への参加を求めるべく各国に特使を派遣する等の積極外交を展開した。
(c) 経済面では国際石油価格の大幅な下落や,国家財政の赤字等が影響し国内経済活動は前年同様,引き続き低迷した。
(タ) アラブ首長国連邦
(a) 内政面ではザーイド大統領,ラーシド副大統領がともに再選され,アブダビ,ドバイ両首長国を中心とする連邦体制の維持が図られた。
(b) 外交面では,11月にGCC首脳会議がアブダビで開催され,ホスト国としてGCCの連帯強化に積極的な役割を果した。
(c) 経済面では,原油価格低迷のため石油収入が大幅に減少し,赤字財政となっており,こうした事情を背景として種々のプロジェクトは凍結ないし中止され,また貿易量も減少する等,同国経済は全般的に低迷した。
(レ) オマーン
(a) カブース国王のもとでの政治体制は安定しており政治情勢も平穏に推移した。
(b) 経済面では,石油価格下落による石油収入の急減のため政府は通貨問題も存在している。
(c) 現政権は非同盟主義を標傍しているものの,実際にはあらゆる面で切下げ,歳出の10%削減,5億ドル・ローンの借入れ等の諸措置を講じてきているが,かかる経済情勢を背景として86年から始まった第3次5か年計画の改訂を余儀なくされている。
(c) 外交面では,従来通り穏健な西側諸国との関係を基調とした路線が堅持されている。
(ソ) カタル
(a) イラン・イラク紛争の継続と急激な石油価格の下落による厳しい経済情勢にもかかわらず,国内政情はハリーファ首長の下で平穏に推移した。
(b) 対外関係では4月,バハレーンとの間で小島の領有権をめぐる紛争が発生したことが注目された。
(c) 同国は石油価格の下落の中で,OPEC生産枠を遵守しており経済的には厳しい状況にあり,これを背景として,国家予算の発表も行われていない。また製鉄,肥料,石油化学といった同国の主要産業も深刻な影響を受けている。
(ツ) バハレーン
(a) 国内情勢は,全般的には目立った動きはなく.平穏に推移した。11月にはバハレーンとサウディ・アラビアとを結ぶコーズウェイが開通した。
(b) 対外面では4月にカタルとの間で小島の領有権をめぐり紛争が発生したことが注目される。
(c) 同国経済は石油価格の下落による湾岸諸国経済の不振の影響を受け,全般的に厳しい状況にあった。
(ネ) 南イエメン
(a) 86年1月の内紛後,旧政権派の一部は北イエメンに避難したままであるが,新政権下の同国の政情は一応落ち着きを取り戻した。同年10月末には最高人民会議及び地方人民会議の選挙が行われ,アッタース議長が正式に最高人民会議議長(国家元首)に選出されたほか,ノウマーン首相の再任が承認された。
(b) 経済面では,戦災復旧のための出費に加え出稼ぎ労働者の送金激減により苦しい状況にある。
(c) 対外面では,ソ連等東側に大きく依存する基本政策にかわりはないが,湾岸諸国との関係にも意を用いている。
(ナ) 北イエメン
(a) 同国の内政は基本的には安定的に推移したが,86年1月の南イエメン政変後同国旧政権派の避難民が多数流入するとの問題もかかえている。
(b) 経済面では近隣産油諸国からの援助減少,出稼労働者からの本国送金減退により財政ひつ迫,外貨不足,インフレ高進といった事態が生じ,輸入がほぼ停止したほか工場生産活動も低滞する等,苦しい状況にある。これに対し,政府は緊縮経済措置を打出している。
(c) また,最大の外交問題である対南イエメン政策については,旧政権擁護の立場を堅持しつつも,新旧両政権間の和解を仲介する等イエメン情勢の安定化に努めた。
2. 我が国との関係
(1) 我が国は,従来より国際政治・経済に占める中近東諸国の重要性,我が国との間に存在する相互依存関係等にかんがみ・中近東諸国との友好協力関係の強化を積極的に進めてきた。86年においては,この友好協力関係を一層幅広いものとすべく,イラン・イラク紛争の早期平和的解決に向けての環境造りを継続するとともに,中東和平の推進を支援した。人的交流も活発であったが,就中モロッコ皇少子の公賓招聰を行い,マグレブ諸国との交流を深めた。さらに我が国は中近東諸国の工業化を含む国造りや人造りのための経済・技術協力を推進してきており,かかる観点から第5回日本・サウディアラビア合同委員会が開催されるとともにまた,これら諸国との相互理解を増進すべく,トルコ・エジプトにおいて日本週間を開催するなど文化面という新分野での中近東諸国との交流が促進された。
(2) 86年の我が国の中近東諸国との貿易は,輸出が106億ドル,輸入が188億ドルで,我が国の入超は82億ドルとなった。対前年比では輸出が18%減,輸入は38%減であり,我が国の入超額は52%と大幅に減少した。これは石油の需給緩和の下で産油国を中心に財政事情が悪化し,我が国からの輸出が低迷するとともに,石油価格の下落により我が国の輸入が減少したためである。
<要人往来>
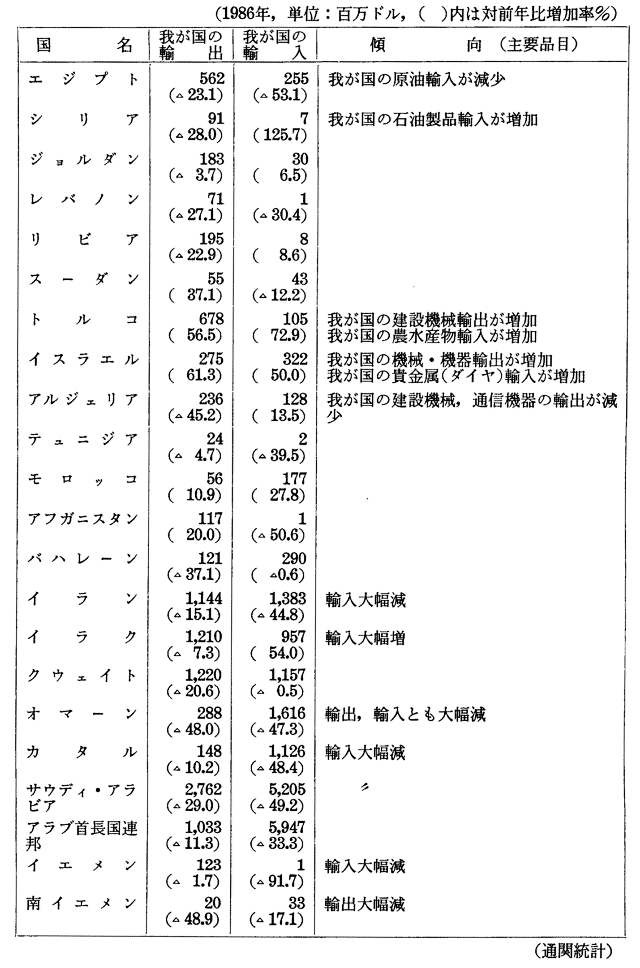
<貿易関係>
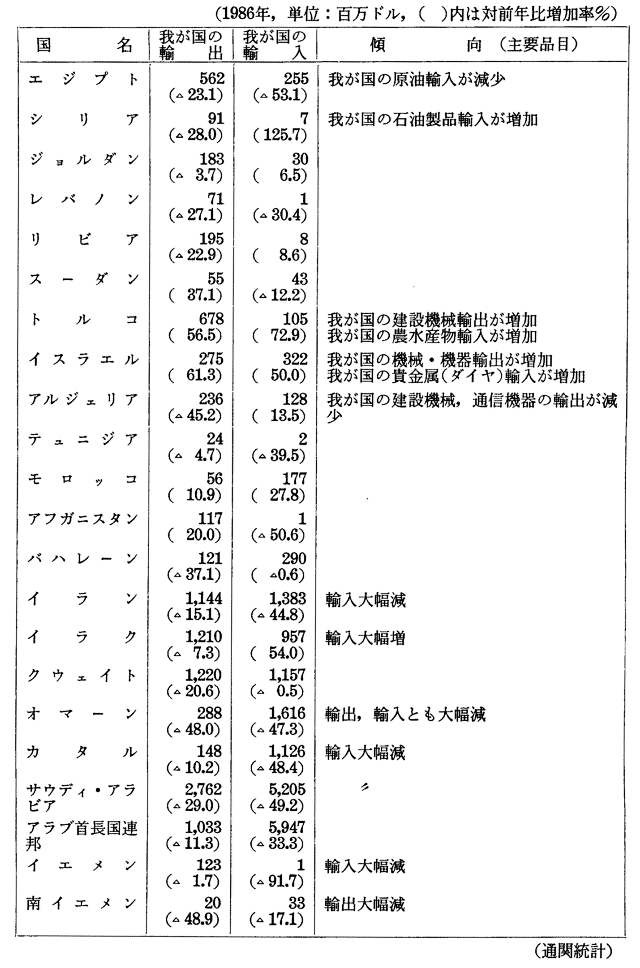
<民間投資>