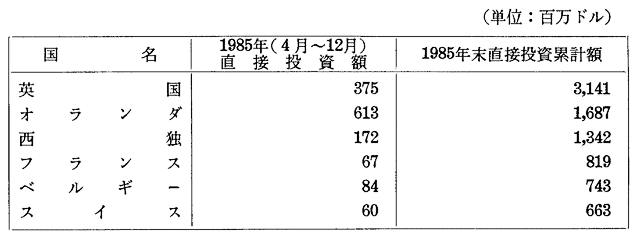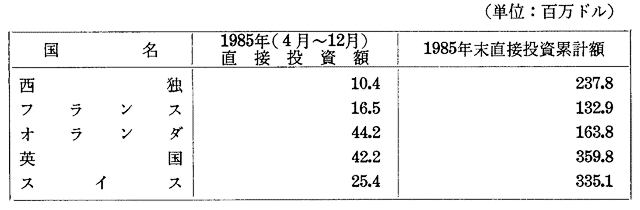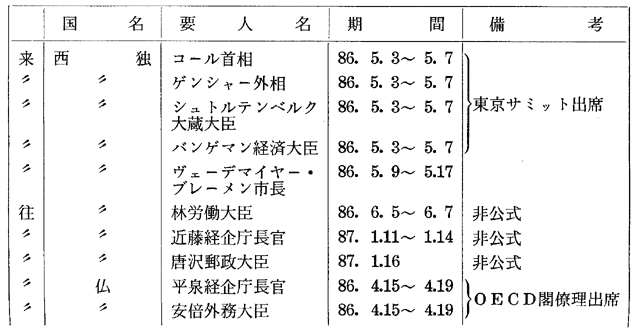
第5節 西欧地域
1. 西欧地域の内外情勢
(1) 概観
西欧諸国は,86年1月よりのスペイン,ポルトガルのEC加盟及びECの機構改革,欧州政治協力の強化へ向けての活発な動き,ユーレカ計画の推進等に見られるように加盟国の一致した強い政治意思の下に,「強い欧州」の建設を積極的に進めている。安全保障面では,NATOの結束強化に努めるとともにこれを補完するものとして,WEU(西欧同盟)の活性化を図るなど欧州独自の安全保障を図るための努力をも行っている。
86年9月にストックホルムにおける欧州軍縮会議(CDE)で信頼醸成措置に関する合意文書が採択されるなど進展がみられたこと,及びゴルバチョフ政権が西欧重視のジェスチャーを示していることなどから・西欧においては,ソ連,東欧諸国との対話を推進しようとの動きがみられ,86年7月から87年3月までの間にフランス,英国,西独,デンマーク,スウェーデン,オランダ・スペイン・イタリアなどの諸国とソ連の間では要人の往来が行われた。また,現在ウィーンで行われているCSCE(欧州安全保障協力会議)フォローアップ会議,あるいはNATOとワルシャワ条約機構(WP)との間の全欧州における通常戦力軍備管理交渉のための準備会合の成り行きが注目される。
西欧各国の国内政治情勢の主要な動きとしては,フランスでは,86年から,社会党出身のミッテラン大統領の下に保守のシラク首相が任命され,保革共存の政権となっているが,86年末から87年初めにかけて学生のデモ,労働者のスト等シラク首相の施策に反対する動きも国内においてみられた。西独においては,87年1月に総選挙が行われ,コール首相率いる与党は伸び悩んだものの,政権を維持した。英国においては,サッチャー首相が数々の問題に直面しながらもこれを乗り切り,世論調査における保守党のリードを背景に87年中に解散総選挙を行うとみられている。イタリアにおいては,86年6月に連立与党内のキリスト教民主党と社会党の対立を原因としてクラクシ内閣が総辞職したが,その後,87年3月までの存続を目途に再任された。しかるに,同月に至って,連立与党内の足並みの乱れから,クラクシ内閣は再び総辞職した。新内閣成立は難航し,4月には,ファンファーニ上院議長を首相とするキ民党単独内閣が成立したが・議会は解散され,6月に総選挙が行われることとなった。このほか,86年5~6月にはオーストリアで大統領選挙が行われ,ワルトハイム大統領が選出された。また,86年5月にはノールウェーで政権交代により労働党内閣が成立し,さらに同年中には,オランダ,スペイン,オーストリアで,87年にはアイルランド及びフィイランドでそれぞれ総選挙が行われ,オーストリア,アイルランドにおいて政権交代が行われた。さらに,87年にはアイスランド,マルタで総選挙が予定されているのに加え,デンマーク,ポルトガルにおいても選挙が行われる可能性が高い。
86年の西欧経済情勢は,緩やかではあるが85年に引き続いて回復傾向を示している。物価上昇率はドル安及び原油価格の低下もあり,顕著な鎮静化を示している。また貿易収支,経常収支については,英国,ノールウェーといった産油国は原油価格の低下のためにいずれも悪化を見たが,それ以外の国々では,貿易収支,経常収支のいずれについても改善ないし黒字幅の増大をみたところが多い。また,失業率は全体的にみて依然として高水準のまま推移しており,今後ともインフレを引き続き抑制する一方で,雇用を増大させるため,産業構造の硬直性の除去等経済の活性化をいかに図っていくかが西欧各国の重要な課題である。
(2) 欧州における東西関係
(イ) 北大西洋条約機構(NATO:North Atlantic Treaty Organization)
86年における東西関係は,その前半においては米ソ関係を中心に東西関係改善の雰囲気に陰りが見られたが,同年後半は,9月の欧州軍縮会議(CDE)における合意,10月のレイキャヴィクにおける米ソ首脳会合,87年2月のソ連によるINF切り離し提案等,欧州における東西関係は新たな段階に入りつつあるといえる。他方,ソ連を中心とするワルシャワ条約機構(WP)軍の軍事力増強が継続され,特に短射程中距離核戦力(SRINF)及び通常戦力分野における東西のインバランスに対する懸念が強まっている。こうした状況下,NATO諸国は種々の機会をとらえて同盟諸国,特に米欧間の緊密な協議を行い,同盟としての結束を維持しつつ,米INFの欧州配備及び通常戦力強化の努力を継続し,「抑止と対話」を二本柱とするNATOの基本政策を一貫して堅持している。
(ロ) 欧州安全保障・協力会議(CSCE:Conference on Security and Co-operation in Europe)(アルバニアを除く全欧州諸国及び米国,カナダの35か国が参加)
83年9月のマドリッド・フォローアップ会議結論文書に基づき,欧州軍縮会議(CDE)が85年に引き続き行われ86年9月に信頼・安全醸成措置の合意がなされたほか,86年4月には「人的接触に関する専門家会議」が
ベルンで開催され,安全保障及び人間・情報等の交流の分野でCSCEのフォローアップが行われた。
また,86年11月4日より,87年7月末を終了目標としてウィーンにおいて第3回目のフォローアップ会議が開催されている。
(ハ) 欧州軍縮会議(CDE:Conference on Disarmamentin Europe)(参加国はCSCEと同じ,開催地はストックホルム)
欧州軍縮会議は,第1段階で信頼・安全保障措置につき協議し,その成果を受けて第2段階で軍縮について協議することになっている。同会議は,85年末までに8回,86年には4回の会議が開催され,同年9月,軍事活動の事前通告,軍事活動へのオブザーヴァーの招請,現地査察を含む検証等の措置に関する合意文書が採択された。この合意は87年1月より実行に移されており,欧州の軍事活動の透明性,予測可能性を高めることが期待されている。また,今回の成果は,CSCEウィーン・フォローアップ会議に報告され,同会議により評価及び欧州軍縮会議の第2段階への移行につき協議されている。
(ニ) 欧州における通常戦力分野の軍備管理
本件に関しては,中部欧州(対象が,西側:西独,ベネルクス三国,東側:東独,チェッコスロヴァキア,ポーランド)における通常兵力の削減を目的とする中部欧州相互均衡兵力削減交渉(MBFR:Mutual and Bal-anced Forces Reduction)(オブザーヴァーを含め,西側12か国,東側7か国,開催地はウィーン)において1973年より既に41回(86年4月から87年3月までの間には3回)の交渉が行われている。同交渉においては,双方の兵力削減目標(陸:70万人,空:20万人の計90万人になるまで削減)については東西の合意が達成されているものの,検証措置及び削減対象に装備を含めるか否か等の諸点については依然東西間で大きな意見の対立があり,その進展は遅々としている。
このような状況下,ワルシャワ条約(WP)諸国は86年6月,「欧州における兵力及び通常兵器削減に関する軍縮アピール」を採択,これを受け,同12月NATOは「通常戦力軍備管理に関するブラッセル宣言」を行い,87年2月よりNATO及びWP加盟23か国間で全欧州(ウラルから大西洋まで)における通常戦力軍備管理交渉のための準備会合がウィーンにおいて開催されている。同準備会合では,交渉目的,削減対象等につき協議されているものの,欧州の通常戦力の現状(西側は不均衡,東側は均衡と主張)及び削減対象(西側は通常戦力のみ,東側は戦術核戦力を含むと主張)等に東西の見解の相違があり,今後の成り行きが注目される。
(3) 欧州統合問題
86年1月1日よりスペイン,ポルトガルが加盟したことでECはその規模を12か国に拡大した。また,86年2月末をもって全加盟国が署名を行った「単一欧州議定書」により,92年までの域内統合市場の完成,EPC(欧州政治協力)の正式認知及びそのための事務局の設置等が決定され,かつ,これら経済及び政治の両分野を統合し,EC諸国の関係全体をヨーロッパ・ユニオン(欧州連合)に移行させる意志を条約上確認し,ECは質的にも統合が強化されることとなった。もっとも,87年1月からと見込まれていた「単一欧州議定書」の発効実施が現在(87年3月末)でも遅延しており,EC委が描いた通りのスピードでは進んでいないという面もあるが,欧州統合自体は着実に前進しているといえよう。
(4) 各国の情勢
(イ) ドイツ連邦共和国(西独)
(a) 86年の西独内政は翌87年1月に予定された連邦議会選挙へ向けての各党の動きを中心に展開した。82年10月以来政権にあるコール内閣は,安定した経済情勢を背景に政局運営に自信を深めていたが,86年4月のソ連チェルノブイリ原発事故を契機として国民の間に原発の安全性をはじめ環境問題一般に対する関心が急速な高まりをみせ,原発政策を維持する政府は一時苦境に陥った。しかし最大野党である社会民主党は基本路線をめぐる党内対立の深刻化から統一的な選挙戦略をたてることが出来ず,コール政権の動揺をつくには至らなかった。その後6月のニーダーザクセン州選挙において連立与党が1議席差で辛勝し,また,コール政権が新たに連邦環境省を設置するなど環境問題にも積極的な対応姿勢を見せる中,社会民主党は劣勢に陥り10月のバイエルン州,11月のハンブルグ州選挙でいずれも惨敗し,コール政権優勢の内に連邦議会の選挙戦が繰り広げられていった。87年1月の同選挙においては前回選挙(83年3月)に比較し保守政党は得票数を落としたが,連立を組んでいる中道の自民党が票を伸ばし,連立政権が引き続き維持されることとなった。これによりコール政権は次期4年,成立以来8年を越える長期政権を担当することとなった。
(b) 西独経済は83年以降引き続き安定回復基調で成長を続けているが,86年は第3四半期以降成長速度が減速し,同通年では当初政府見通し3%を下回る2.4%の実質成長率にとどまった。消費者物価上昇率マイナス0.2%と物価は極めて安定しており,109億マルクにのぼる所得減税政策の効果もあって内需は堅調な伸びを示したが,設備投資は年後半伸びが鈍化し,輸出もマルク高の影響もあって伸び悩んだ。他方,貿易収支・経常収支は輸出の不振にもかかわらず,輸入価格の低下に伴い史上最高の黒字を記録した。失業問題は改善の傾向にはあるものの失業者数は依然200万人を越える高水準で推移している。
(c) コール政権は外交政策において米国との関係緊密化,独仏関係の強化を中心とする西側同盟諸国との強固な関係に立脚しつつ,ソ連・東欧諸国との対話路線の維持発展に努めている。特に西独による米INFの配備決定後冷却化していたソ連との間において,86年には7月にゲンシャー外相の訪ソ,科学技術協定の締結等関係修復のきざしが見られ,87年の西独総選挙後,要人間の往来も活発化してきている。両独関係は難民流入問題,東西両ベルリン間通過規制問題等で一椏Iには影がさしたものの,文化協定締結,環境協定交渉の進展など実務関係を中心に緊密化が図られた。
(ロ) フランス
(a) 86年3月の総選挙後,ミッテラン大統領は保守のシラク氏を首相に任命,第5共和制下において初めての保革共存(コアビタシォン)政権が発足した。政権は86年中おおむね平穏に推移したが,他方,大統領が選挙制度改革,企業私有化,労働時間の弾力化の諸法案への署名を拒否する等,少なからず不協和音も見られた。シラク首相は,テロ対策等の治安政策,あるいは経済政策である程度の成果は挙げたものの,86年11月から87年1月にかけての文教政策に反対する学生デモ及び公営企業ストによる社会的混乱の収拾ぶりにつき国民の不満をかうに至った。こうした国民1の不満及び88年の大統領選挙に向けてもともとコアビタシオンに反対しているバール元首相の人気が高まってきたこともあって,87年になってからは大統領と首相の間の対立が表面化することは少なくなってきている。
(b) 経済面では,シラク首相は,ファビウス前社会党政権末期の政策を基本的に継承し,失業問題,インフレ抑制,対外均衡の達成,財政再建を目標としているが,他方,その独自の政策として自由化による経済活性化政策を推進した。原油価格の下落等の国際環境にも恵まれたため,インフレは鎮静化して主要先進国の水準に近づき,また貿易収支においても大幅な改善が見られて均衡をほぼ達成した。しかしながら,求職者数は86年末で257万人となり,失業率も10.7%まで上昇した。
他方,シラク政権は,国有企業を民営化する方針を打ち出し,一部は既に実施されている。
(c) 外交面でまず注目されるのは,コアビタシオンの成立により,従来大統領の「専管分野」とみなされていた外交及び国防を大統領と首相の間で分担するようになったことである。この関連で,東京サミット,欧州理事会,さらに2国間の首脳会談等に大統領と首相の双方が出席するケースも多くなっている。
外交路線そのものについては,シラク政権が発足してからも大きな変化は見られない。東西関係においては,核抑止力を保持し,米国との間で大西洋同盟の忠実な一員として連帯の維持・強化に努める一方でソ連,東欧との「特権的対話者」としての地位確保に努める等独自の役割を果たそうとしている(ミッテラン大統領が86年7月に米ソを相次いで訪問したのもその現われ)。欧州においては,欧州統合に積極的な姿勢を示している。第三世界との関係では,南北問題重視の姿勢を見せるとともに,アフリカ諸国(特に仏語圏との歴史的結び付きの強化に努め,さらに南太平洋地域にも強い関心を示している。
(ハ) 英国
(a) 与党保守党は,年初来ウエストランド社救済問題の取り扱い,米国のリビア爆撃の際の英国内米軍基地使用許可に対する批判等の中で,世論調査の支持率が低迷した。
しかし,86年9~10月開催された各党大会で,キノ,ク党首の率いる労働党が非核政策を打ち出し,自由・社会民主連合が核政策をめぐり不統一を露呈(自由党はポラリス・ミサイル後,予定されているトライゲント・ミサイル導入は行わない旨主張)したのに対し,保守党が社会保障,教育等の面で「思いやりのある政策」色を全面的に打ち出す中で,11月以後の世論調査では保守党がほぼ首位を占めるに至っている。各党とも早ければ87年6月にも選挙はあり得べしとの認識の下に,それぞれ選挙体制作りを進めている。
(b) 英国経済は緩やかな拡大を続け(実質GDP2.6%),物価上昇率も低水準で推移している(3-4%)。失業者数は依然300万人台という高水準ながら,86年夏をピークに以後減少傾向を示している。しかし,石油収入の減少,製品輸出の不振により,経常収支は7年振りに赤字となった。
(c) 外交面では,86年後半にはEC議長国として,シリア制裁問題等につき積極的に対応した。東西関係では,7月,シェヴァルナッゼ・ソ連外相が訪英,87年3月にはサッチャー首相が英国首相の公式訪問としては12年振りに訪ソした。
軍備管理・軍縮の面では,サッチャー首相は,レイキャヴィク米ソ首脳会談後,11月に訪米し,軍備管理交渉のプライォリティーは,(i)短距離兵器の抑制を伴うINF合意,(ii)戦略攻撃兵器の5年間50%削減,(iii)化学兵器の禁止,に置かれるべきことで米国の同意を取り付け,また87年の訪ソにおいては,ゴルバチョフ書記長との間でINF交渉を優先すること等で意見の一致を見るなど,積極的な動きを示した。
(ニ) イタリア
(a) イタリア政局は,クラクシ首相を首班とする5党連立政権により86年6月まではおおむね安定的に推移(クラクシ首相は85年11月イタリアにおける戦後最長政権を実現して以来,その記録を更新しつつあった)したが,同月末,一部与党議員の造反により,地方財政法案が否決されたのを理由にクラクシ内閣は総辞職した。これを受けて,連立5党間で,87年3月末の社会党大会を契機としてクラクシ首相が党務に専念し,政権をキリスト教民主党に譲る旨の合意が成立したと伝えられ,その結果8月初めには第2次クラクシ内閣が発足した。しかし,その後も連立政権内で最大政党でありながら首相を出していないキリスト教民主党とクラクシ首相の率いる社会党の主導権争いが再燃,87年3月,クラクシ内閣は総辞職するに至った。
(b) イタリア経済は,非常な好調を示しており,欧米経済紙の中には,イタリア経済の奇跡と表するものまである。GDP成長率は86年は2.7%が見込まれており,インフレも,85年以来のスカーラ・モービレ(賃金物価スライド制)改正による賃金政策の成功に加えて最近のドル安・原油安の影響により86年では6.1%の水準まで低下した。また,86年には貿易収支の赤字を前年の6分の1に縮小し,経常収支では7兆リラ程度の黒字への転換が予測されている。さらに,企業の合理化・労使関係の安定により企業収益は改善したが,他方失業率は改善されず戦後最悪の水準となっている。
(c) 外交では,西側民主主義国の一員として米国,NATO及びECとの協調を基本外交方針とし,この基本的な枠組みの中で東西関係及び地中海・中近東地域に対し独自の外交を展開した。東西関係では,87年1月にはポーランドのヤルゼルスキー国家評議会議長が西欧諸国への初めての公式訪問としてイタリアを訪れ,また,同2月にはファンファーニ上院議長及びアンドレオッティ外相が訪ソし,それぞれゴルバチョフ書記長と会談した。中東との関係では,86年4月の米国のリビア攻撃に対しては,アラブ側の反発を招きテロ増加につながるとして米国に同調せずECの枠内でテロ対策を実施し,対リビア関係を縮小しつつも最小限の話し合いのパイプは維持るとの方針をとっている。ECとの関係では,その強化に積極的姿勢を示しており86年2月には,ECの単一議定書に署名した。また,クラクシ首相は日本・中国・インドを公式訪問してアジアに対する関心も強めている。
(ホ) アイルランド
87年度予算をめぐり,87年2月に下院の解散,総選挙が実施され,その結果・共和党のホーヒー政権が誕生した。今後,同政権が財政赤字・高失業率といった経済状況を再建すべくいかなる施策を打ち出すか注目される。
(ヘ) 北欧
フィンランドでは,87年3月の任期満了の総選挙が実施され,その結果,与党・社民党が第1党の地位を保ったものの,野党・保守系国民連合党が大きく議席を伸ばし,4月ソルサ内閣は総辞職した。
スウェーデンでは,86年2月のパルメ首相暗殺後政権を継いだカールソン首相が対話を旨とする穏健な政局運営を行っている。外交面でも,同首相は就任直後長年の懸案であったソ連訪問を実現するなど着実な成果を挙げている。しかし,社民党は少数単独政権であり,原子力発電停止問題,税制改革問題,防衛費問題等をめく"り,88年秋の総選挙に向けての各党の動向が注目される。
ノールウェーではヴィロック保守連立政権が石油価格の急落による財政難を理由に86年5月,総辞職し,ブルントラント労働党政権が誕生した。同政権は,少数にもかかわらず野党中道2党との歩み寄りにより,政権を維持している。
デンマークでは,86年はシュルター保守党連立政権にとり発足以来(4年目)初めて外交・安保政策に煩わされることなく経済政策に全力を傾注し得た年であった。もっとも,財政収支は黒字に転じたものの,国際収支赤字は改善せず,10月には消費削減,貯蓄振興を目的とした経済引き締め法を導入した。今後,87年中に見込まれる総選挙に向けての各党の動向が注目される。
アイスランドでは,86年5月の統一地方選挙で政府・与党が伸び悩み,野党が伸長した。かかる傾向は夏以後の世論調査にも表われ,87年4月の総選挙が注目される。
(ト) ベルギー,オランダ
ベルギーでは,第6次マルテンス内閣が国家財政再建及び企業の競争力強化による経済再活性化を最大の課題とし,特別権限法に基づき大幅な財政支出削減による緊縮政策を実施した。86年10月には,オランダ語系住民とフランス語系住民の間の根深い言語問題(フーロン市の市長資格問題)に端を発し,内閣総辞職願いをボードワン国王に提出するという内閣崩壊の政治危機に直面したが,内務大臣辞任等の連立与党間の妥協によりこれを回避した。86年の経済は,大幅な財政赤字,高水準の失業率という問題を抱えているが,鉱工業生産投資の上昇,物価の下落,経常収支の改善等前年に引き続き緩やかながら回復基調にある。
オランダでは,86年5月,下院総選挙が実施され,連立与党(キリスト教民主同盟,自由民主人民党)が勝利を収めた結果,7月,第2次ルッベルス内閣が成立した。同内閣にとり,一層の財政赤字削減,失業問題の解決,安楽死立法問題の決着をいかに進めるかが最重要課題である。86年の経済は,成長率1.6%,失業率11.6%(85年15.6%),物価上昇率0.2%と比較的明るい徴候をみせた。
(チ) 中欧
オーストリアでは,86年5~6月の大統領選挙の結果,ワルトハイム前国連事務総長(野党国民党支持)が選出された。一方,与党社会党は,自由党(連立与党)党首が保守派に交替したため,連立を解消,86年11月に下院総選挙を実施した。その結果,87年1月社会党・国民党による大連立が21年ぶりに復活した。経済面では総じて安定的成長を示したが,国営企業財政赤字が依然大きな課題となっている。
スイスの内・外政は引き続き安定的に推移した。内政面では,難民問題,チェルノブイリ原発事故を契機とした原子力政策のあり方が取り上げられた。経済面は安定成長を維持した。
(リ) 南欧
スペインでは,EC加盟後も現実的な穏健路線を採ってきたゴンサレス社会労働党政権が,86年7月の総選挙でも過半数を維持し,引き続き政権を担当することとなった。しかし,失業問題は依然深刻で,同政権の抱える主要問題となっている。また,86年3月の国民投票においてNATO残留が決定されたのを受けて,同国は,駐西米軍の規模に関し,米国と協議を進めている。
ポルトガルではドル安,石油価格等の外的要因も手伝って,経済は比較的好調であり,シルバ社民党政権は安定的な内政運営を行っていた。しかし,87年3月に至り,急拠提出された内閣不信任案が与野党の数々の思惑の中で成立し,議会が解散,7月に総選挙が実施されることとなった。
ギリシャでは,全ギリシャ社会主義運動(PASOK)政権は85年総選挙以降,経済的には,社会福祉政策重視から緊縮財政政策,民間部門の役割重視等へと政策を転換し,また,対外的には,ECはじめ西側世界との結び付き強化等従来の政策の軌道修正を行い,86年においても引き続き国内における数々の非難を乗り越え,その姿勢を堅持しつつ,定着化を図った。
マルタでは,87年5月の総選挙を控え,与野党が内政,外交,経済のあらゆる施策で対立するなど,選挙一色の一年であった。
サイプラスでは,ギリシャ・トルコ両系住民に対する国連事務総長の仲介努力が続けられ,86年3月には事務総長提案の第2次修正案が双方に提示されたが,まだ全面解決のための交渉に入れない状況にある。
(ヌ) ヴァチカン
ローマ法王は,86年においても,正義に基づく世界平和の実現を目標として活発に行動した。
86年10月末には,アッシジにおいて世界平和祈願集会を開催し,世界一日休戦の日とせんとの法王の呼びかけに,世界の主要宗教の代表者が参加するとともに,アフガニスタンを除き,イラク,レバノン,アジア,中南米の抗戦団体も停戦に応じた。
法王は,86年にも欧州,アジア,大洋州,中南米の多くの国を歴訪し,現地教会,信者大衆への宗教活動を行うとともに各国政府首脳と会談した。10月のレイキャヴィクの米ソ首脳会談に際しては,その会談直後,ソ連はスメルチンク外務次官を派遣してシルヴェストリ一二法王庁外相に会談内容を説明せしめ,また米国はワインバーガー国防長官が,フィレンツェで司教訪問中にあった法王に謁見した。さらに南アフリカにおける暴動,その他各地でみられる自由と人権抑圧,パリでの爆弾テロによる無差別殺傷事件などが起るたび,ローマ法王は傷心と遺憾の意を表明している。このような平和と隣人愛を説く法王の真摯な姿は多くの人々の共感を呼び,ヴァチカンの国際的イメージの向上に貢献した。
2. 我が国と西欧諸国との関係
(1) 日・西欧関係全般
西欧諸国は,我が国・米国等の他の先進民主主義諸国と共に自由と民主主義という基本的価値観を共有し,自由貿易・市場経済体制の維持・発展に共通の利益を有している。東西関係や国際経済問題を中心とした現下の厳しい国際情勢の下,我が国が世界の平和と繁栄のため,国際社会において果たすべき役割に対する西欧諸国の期待は高まっており,こうした背景の下,日欧協力関係,特に日欧政治関係は近年緊密化しつつある。
我が国と西欧諸国の間の人的交流もますます強化されており,86年には,西欧諸国から,東京サミットにフランス,西独,イタリア,英国,オランダ,EC委員会の各首脳が出席し,またコイヴィスト・フィンランド大統領が国賓として,クラクシ・イタリア首相及びチャールズ英国皇太子が公賓としてそれぞれ訪日したのをはじめ,多数の要人が我が国を訪れている。他方,我が国からは,86年5月に安倍外務大臣(当時)がOECD閣僚理事会出席の機会にフランスの要人と会談し,また12月に倉成外務大臣が日・EC委員会閣僚会議に出席するとともにベルギー,イタリア,ヴァチカン,フランスを訪問したし,87年1月には中曽根総理大臣がフィンランドを訪問した。西欧主要国との外相定期協議(86年4月から87年3月までの間にフランス,イタリアとそれぞれ2回),日・EC議長国外相協議(86年5月及び9月),倉成外務大臣とキャリントン・NATO事務総長との意見交換(86年12月)等も行われた。さらにこれ以外にも我が方要人が国際会議等の機会をとらえて西欧諸国の要人との積極的に会談を行って日欧間の対話の拡充強化に努めている。
(2) 日・西欧経済関係
86年の日欧経済関係には,85年来の厳しさに変化は見られず,3月に行われたEC外相理事会でも厳しい対日要求のラインが確認されたが,その後貿易不均衡が一層拡大し,特に日本の対EC輸出が急増していることが明らかになるにつれEC側は懸念を強め,7月の外相理議長結論文書で右懸念を改めて表明した。また,同文書においてEC側は特にアルコール飲料問題についてガット23条提訴の可能性を示唆しつつ,差別的障壁の除去を求めた。結局,この問題については10月の外相理においてガット23条2項手続に付記することを決定した。他方,我が国政府も本件の解決に鋭意努力した結果,12月23日に決定した税制改正で酒税に関しウィスキーの級別制度の廃止,ワインに関する従価税の廃止,大幅税率引き下げ等が決定され,関係国の評価を得たが一部の国は右決定になお不満の意を示したことから,本件は結局ガットの場で協議が行われることとなった。
この間9月に行われたウルグアイでのガット閣僚総会においてEC側はいわゆる「利益の均衡」論を展開,日本問題を徹底的に追求する構えを見せるなど,ECの対日姿勢の厳しさが改めて浮き彫りにされた。これに対し,我が国はEC側の考え方は本来ガットの目指す自由な,多角的貿易体制と相容れない管理貿易体制を志向する危険がある等と反論した。
こうした状況の下,12月にブラッセルで行われた日・EC委閣僚会議においては,我が方より倉成外務大臣,田村通産大臣,三ツ林科学技術庁長官が出席し,核融合協定締結交渉の開始,産業協力センターの設立等我が方の積極的意向を表明したことから,協力の気運が高まり,また,幾つかの個別問題についても解決をみる等の前進がみられた。
しかし,86年全体でECの対日貿易不均衡が167億ドルと前年より約45%増えたこと,及び対ドル円高による対米輸出の欧州へのシフトに対する懸念などから,87年3月16日のEC外相理では再び貿易不均衡の継続的な悪化を遺憾とする旨の厳しい対日結論文書が採択された。これに対し我が方より,ECとの貿易を拡大均衡の方向においてよりバランスのとれたものとするために我が国の行っている努力を説明しつつ,他方,EC側が,議論ずみの利益の均衡論や輸入数量目標に言及していることは遺憾,EC側が対日差別輸入数量制限,問題等従来から我が国が指摘してきた重要な問題について適切な対応を行うことを期待する等の反論を行った。
しかしながら,日本側の大幅な出超という状況が変わらない以上,欧州側の不満も解消されないため,87年の日欧経済関係の推移には予断を許さないものがある。
<要人往来>
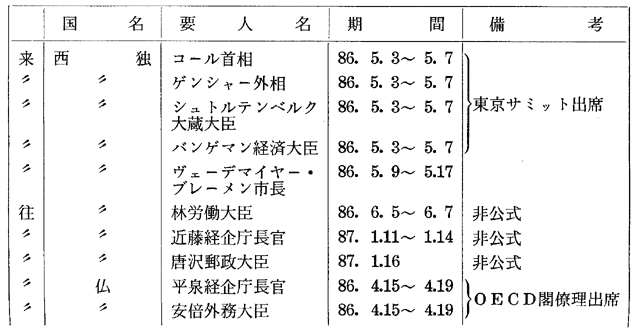
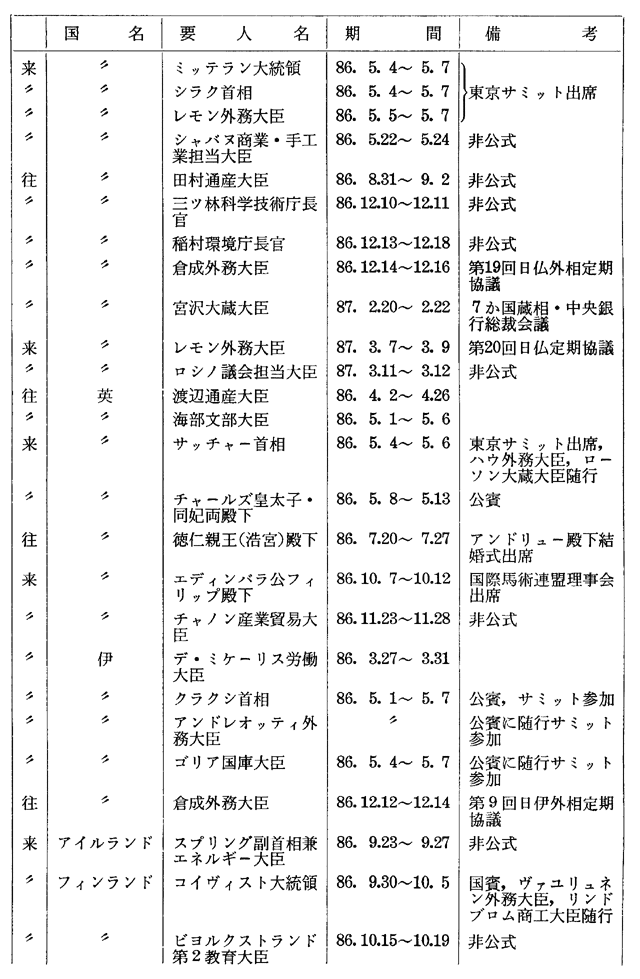
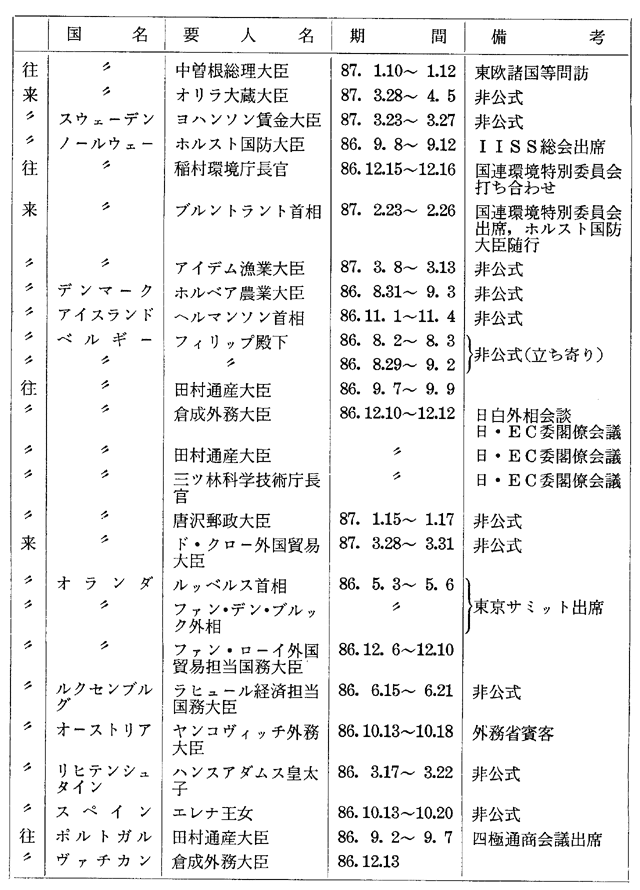
<貿易関係>
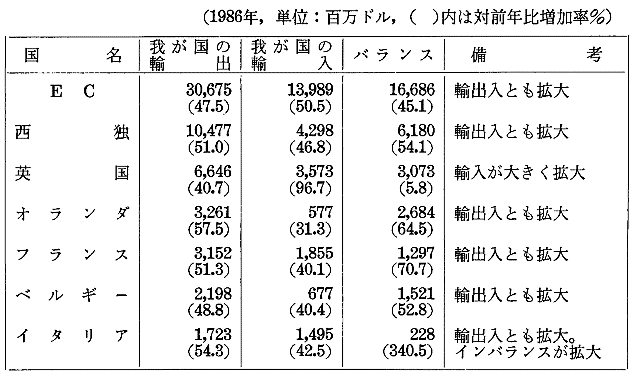
<民間投資>