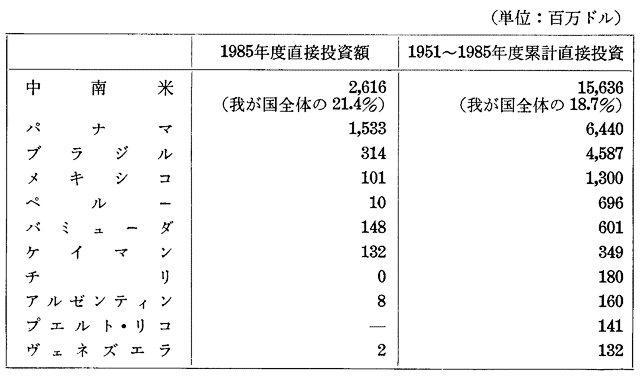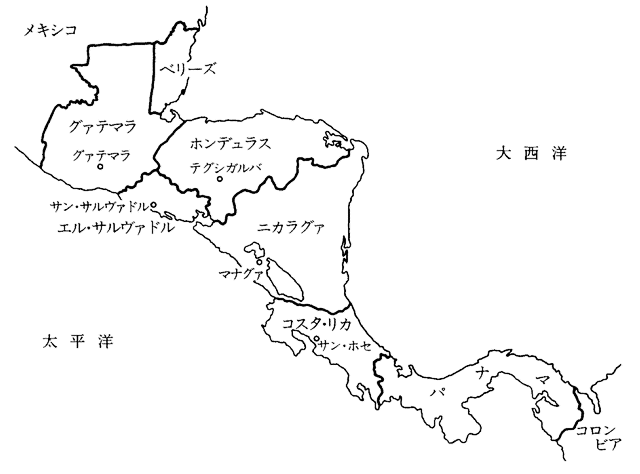
第4節 中南米地域
1. 内外情勢
(1) 全般
中南米地域は,約4億人の人口を有し,開発途上国の中にあっては,「中進国」に位置付け得る比較的所得水準の高い国を含む33の独立国から成り,広大な土地と豊富な天然資源,人的資源にも恵まれ将来に向けて大きな発展の可能性を秘めた地域である。その国際社会における政治,経済的な地位も近年ますます増大している。
現在中南米地域においては,中長期的趨勢として民主化の進展が見られる一方,中米紛争,累積債務問題は引き続き同地域の重要な課題となっている。
(2) 中米紛争
コンタドーラ・グループ(メキシコ,パナマ,コロンビア,ヴェネズエラ)等域内の和平努力は忍耐強く継続されているが,86年6月パナマで開催された「中米和平協力協定」への署名会議では最後まで中米諸国間で軍縮,軍事演習の実施方法,及び民主化等の問題につき合意が得られず,署名は実現しなかった。7月にはニカラグア政府がホンデュラス,コスタ・リカ両国をニカラグアの反政府勢力(コントラ)を擁護しているとして国際司法裁判所に提訴し,10月にはニカラグアの民主化を促進するとしてレーガン米大統領が議会の承認を求めていたコントラに対する総額1億ドルの援助実施が最終的に承認された。
このような情勢下,87年1月にはコンタドーラ・グループ及び同支援グループ(ブラジル,アルゼンティン,ウルグアイ,ペルー)8か国外相は国連及び米州機構事務総長と共に中米諸国を訪問し,中米和平につき各国首脳と意見を交換した。
さらに,2月にはこれまでのコンタドーラ和平プロセスを補完する形でコスタ・リカ大統領より新たな和平提案が提示され,新提案につき協議する
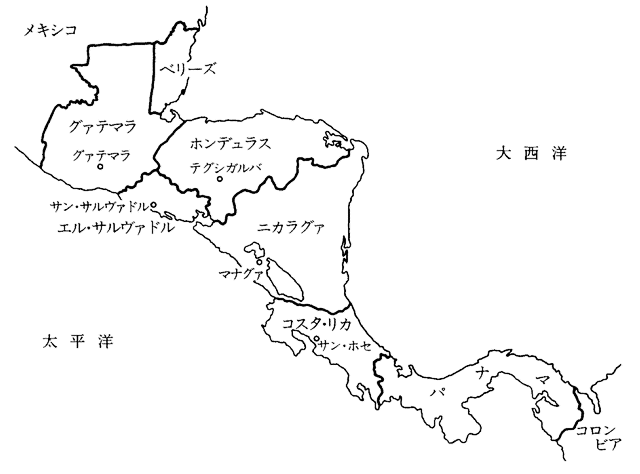
目的で近くグァテマラにて中米5か国首脳会議が開催される運びとなった。
(3) 経済情勢(債務問題を含む)
(イ) 86年の中南米地域全体の国内総生産の伸びは3.4%と85年の2.7%を上回り,84年と同程度の水準に回復した(国連ラ米経済委員会資料)。1人当りGDP成長率も85年の04%から86年の1.2%へと上昇した。また中南米諸国の内,非石油輸出国がおおむね高い経済成長率を達成した(平均6.5%)のに対し,メキシコをはじめとする石油輸出国の多くにおいて経済成長率がマイナスに陥った(平均マイナス1.9%)。
(ロ) 86年の中南米全体のインフレ率は69%と史上最高であった85年の275%を大きく下回り,4年ぶりに2ケタの上昇にとどまり沈静化の傾向を示したが,インフレ抑制は中南米の経済にとって引き続き重大な課題であるといえよう。
(ハ) 石油価格の低下,一次産品価格の低迷が86年の中南米地域の対外収支の悪化をもたらした。輸出額は対前年比15%減と落ち込み,貿易収支黒字額は,85年の335億ドルから86年の185億ドルヘと45%の減少となった。
(ニ) 中南米諸国の累積債務額は86年末で,前年末比2.4%増の3,820億ドルに上った。86年には金利の低下により債務利子返済額は前年比約45億ドル減少したが,依然利子負担は307億ドルに達しており,全体的な輸出低調の中で,輸出額に対する利子返済率は前年並みの35.1%となった。累積債務問題は,これまで当事国の自助努力,IMF等国際金融機関,債権国政府,民間銀行等の協力により当面の危機は一応回避されてきており,86年7~9月にはメキシコヘの金融支援パッケージが具体化した。しかし,87年2月にはブラジルが民間債務利払停止措置を発表し,国際金融界に衝撃を与えた。
債務問題をはじめとする中南米諸国経済の低迷に伴う政治的・社会的困難は重大なものがあり,中南米の主要債務国を代表し,サンギネッティ・ウルグァイ大統領が,東京サミット直前及びヴェネチア・サミット直前にサミット参加国首脳宛親書を発出する等債務国は政治対話,金利の引下げ,途上国への資金流入の拡大等を求めている。
(4) 主要国の動向
(イ) メキシコ
(a) 86年,メキシコは,革命以来最大とも言われた経済危機に直面し,また内政面は北部の地方州選挙において与党(立憲革命党)が依然圧倒的な勝利をおさめたものの,一部には与党が同選挙において不正を行ったとして教会勢力をも巻き込んで議論が行われた。5年目を迎えたデラマドリ政権は,かかる状況下経済再建及び政治改革を推進している。
(b) 外交面では,総じて内政をにらみつつ,外交政策を実施している。即ち,8月には,核軍縮6か国首脳会議を招致,10月にソ連外相のメキシコ訪問といった独自の外交路線を内外に示すとともに,中米紛争に関してはコンタドーラ・グループの一員として引き続き和平実現に向け努力した。また,86年11月から12月にかけて行った大統領の日本及び中国訪問並びに外相のブラジル,アルゼンティン訪問は貿易,投資の拡大及び南米との経済関係強化という長期的視点に立ったものである。
(c) 86年の経済は,年初来の石油価格急落等により資金繰り及び財政赤字が悪化したが,対外債務問題では,IMFとの合意(7月)を契機としてパリ・クラブでの公的債務繰延べ及び民間銀行による新規融資・債務繰延べ合意がなされた結果,当面の資金繰り不安は回避された。また,8月にGATTに正式加盟し,貿易の自由化を進めるとともに非石油関連輸出及び対メキシコ投資促進を図った。なお,86年のインフレ率は史上最高の106%を記録し,実質成長率はマイナス3.8%となった。
(ロ) パナマ
(a) 86年は,85年9月のバルレタ大統領辞任により発足したデルバイエ(第1副大統領より大統領に昇格)政権が、安定政権となりうるか否かが注目された年であった。発足当初,与党連合中議会にわずか1議席のみを有する共和党出身である同大統領の政治的基盤のぜい弱さが懸念されていたが,野党,労働組合等の強力な反対のため前政権が実現し得なかった経済関係の改正法案(労働法,産業法,農牧業法)を成立させるなど政治力を発揮した。また与党連合中の最大政党民主革命党及び軍部との関係も良好であった。
(b) 外交面では,85年9月のバルレタ大統領辞任により悪化していた米国との関係が,米政府の新政権に対する信頼の回復等により改善された。
(c) 経済面では,依然財政赤字,対外債務等の問題が?るものの,金利低下,原油価格の下落,周辺諸国経済の回復傾向等により,86年はプラス成長となった。
(ハ) コロンビア
(a) 86年5月の大統領選挙で,自由党のビルヒリオ・パルコが圧倒的支持を得て当選し,8月に就任した。国内では,新政権発足後よりゲリラや麻薬マフィアの動きが再び活発化してきた。政府は,それに対して貧困と麻薬の撲滅を内政の最大の課題とするほか,地方分権化を進めており88年3月には初めて全国市町村で第1回首長選挙が実施される予定である。
(b) 外交面では,パルコ大統領は実利尊重と隣国との関係調整を重視している。
(c) 経済面では,経済調整政策の効果,コーヒー価格の好調,石油の増産等によりこれまでの低迷状態から上昇軌道に転じ,86年成長率も5.3%(暫定)を達成した。
(ニ) ヴェネズエラ
(a) ルシンチ政権は,(i)与党民主行動党が議会で安定多数を占めていること,(ii)党内の支持も基本的に堅固であること,(iii)大統領個人に対する国民の信望が厚いことなどにより無難に政局を運営した。
(b) 外交の重点は対外債務問題の処理,OPECを舞台とする石油価格の安定化努力に置かれたが,中南米諸国との対話の充実にも努力が払われ,大統領はブラジル,アルゼンティン,ウルグアイを訪問した。
(c) 経済面では,石油収入の減少による財政収支の悪化がみられたが,優遇為替レートの切下げ,税制改革等を断行しつつ公共投資の実施等景気浮揚のための政策を実施した。そのため,経常収支では20億ドルの大幅赤字を記録したものの,経済成長面では8年ぶりのプラス成長(3.1%)を達成した。消費者物価上昇率は11.5%,失業率は10.5%となった。債務問題では,86年2月に調印した公的対外債務にかかわるリスケ協定の見直しにつき,87年2月国際民間銀行団と基本的な合意に達した。
(ホ) キューバ
(a) 86年2月の第3回共産党大会における党人事の大幅刷新により,カストロ首相を頂点とする指導体制がますます強固になる一方,カストロ首相は折にふれ,経済活動の非能率や官僚主義の弊害を批判した。86年5月には農産物自由市場を廃止するなど,市場経済原理を一層導入するよりも,経済の中央集権化と革命精神の発揚によって国内経済の苦境をのり切る方針を打ち出している。
対外経済面でも砂糖国際価格と石油価格(ソ連から輸入される石油の再輸出が主要な外貨収入源)の低迷で外貨事情もタイトになっており,カストロ首相は87年の西側諸国からの輸入を半減させると発表した。
(b) 対米関係に改善の兆しはなく,両国の出入国正常化合意も米国の対キューバ宣伝放送問題をめぐり停止に至ったままである。
一方でキューバは中南米外交を活発に展開しており,86年6月の22年ぶりのブラジルとの復交が特筆される。
ソ連との関係では86年11月,カストロ首相がコメコン・サミット出席のために同年2度目の訪ソを行った。
(ヘ) カリブ諸国
この地域の一次産品(砂糖・石油)価格の低迷による厳しい経済状況が続く中で,3か国で与野党逆転による政権交替があった。
86年5月,バルバドスではバロウ首相が10年ぶりに政権を担当することになり,ドミニカ(共)では同年8月にキリスト教社会改革党のバラゲール大統領が就任した。トリニダッド・トバゴでは同年12月の総選挙で独立以前から30年にわたり政権を担当してきた人民国家運動党が大敗し,ロビンソン首相の率いる国家再建連合党が与党となった。
セント・ルシアでは87年4月の総選挙でコンプトン首相の与党統一労働党がかろうじて過半数を制したが,与野党迫仲の時期を迎えている。
デュバリエ大統領国外亡命(86年2月)後のハイティでは,一部に政権を担当する国家評議会に対する反対デモも生じたが,同評議会の下で,86年10月の制憲議会選挙,87年3月には各種基本的諸権利や大統領の任期・権限を明確に規定した新憲法案の国民投票が実施され,100%近い圧倒的支持を得て同憲法案が承認された。大統領選挙に至るまでの今後の日程も示されており,民主化は着実に進んでいるものの,未だ情勢については予断を許さない。
(ト) ブラジル
(a) サルネイ政権は,86年2月発表したクルザード計画(物価凍結,賃金抑制,為替レート固定等)の成功により国民的支持を得,11月行われた総選挙(上下両院議員兼制憲議会議員選挙,州知事及び州議会議員選挙)において,与党民主同盟は地滑り的勝利を収めた。しかし,同選挙において与党の内ブラジル民主運動党(PMDB)は大勝したが,サルネイ大統領の出身政党である自由戦線党(PFL)は後退した結果,サルネイ大統領は勢力を増大したPMDBとの間で,従来にも増して緊密な政策調整を迫られる結果とならた。また,政府が総選挙直後に発表したクルザード計画II(公共料金・凍結価格引上げ等)が国民にとって極めて不人気な内容であったため,国民の政府に対する不満が増大し,賃上げ要求スト等が続発した。経済情勢の急激な悪化を背景に,政府内では,経済政策をめぐる意見の対立が表面化し,企画大臣の更迭にまで発展した。
(b) 外交面では,サルネイ政権は,現実主義的かつ多角的外交を展開し,86年6月,22年振りにキューバとの国交を再開した。他方近隣諸国との関係強化にも努め,特に86年7月にはアルゼンティンとの間で経済統合のための宣言に調印し,注目を集めた。
(c) 86年の経済は,クルザード計画の実施により内需の大幅拡大がみられ,GDPは対前年比8.2%増,消費者物価指数は58.7%(前年は230%台),完全失業率は2.2%(12月)に低下するなど好調に推移した。反面,ヤミ取引の横行,品不足の深刻化等物価統制によるゆがみが同年後半より深刻化し,貿易収支黒字は対前年比23%減(95.3億ドル)を記録した。87年に入り,クルザード計画の形骸化が見られ,政府は政府・労使間の社会協約で難局を乗り切ろうとしたが失敗し,インフレ・賃上げの悪循環が懸念され始めた。
(d) 対外債務問題については,87年1月IMFとのスタンド・バイ取極めなしにパリクラブにおいて公的債務の繰延べにつき基本的合意が成立した。他方ブラジルは,貿易収支の悪化,外貨準備の大幅減少等を背景に,87年2月外国民間銀行団の中長期債務にかかわる利払い停止措置を発表した。右発表を受け,フナロ蔵相は,2月末より3月上旬にかけ日米欧諸国を訪問し,債権国政府の理解と支援を要請したが,債権国側の反応は概して厳しいものであった。
(チ) アルゼンティン
(a) 86年は,政治面では,アルフォンシン政権発足以来の内政上の大きな課題である民主主義の定着がさらに進展した。特に,旧軍事評議会メンバーに対する人権侵害裁判は,86年12月,最高裁判決が下ったほか,その他の軍人の訴追に関しては,いわゆる終止符法が国会で可決され軍事政権の人権侵害問題は一応の結着をみた。
(b) 外交面では,アルフォンシン大統領は,86年7月,我が国を含む6か国を歴訪したほか・10月及び11月にはソ連及び米国を訪問するなど活発な訪問外交を展開した。また,フォークランド(マルビーナス)諸島問題については,86年10月末英国が同諸島周辺150カイリに「暫定保存管理水域」の設定を宣言したことで英ア間の対立が深まった。
(c) 経済面では,アウストラル・プラン(85年6月発表,物価賃金凍結等)を適宜修正,弾力的運用を図ることにより,86年のインフレ率を12年ぶりの2ケタ台である81.9%に押えることに成功した。また,86年の国内総生産は,農業部門の不振にもかかわらず,工業建設部門が大幅に増加したため,5.7%の成長となった。
(リ) ペルー
(a) ガルシア政権は,国内経済活性化及び民生向上を優先課題としており,かかる政策の一定の成果を背景として高い支持率を維持し,86年2月の統一地方選挙に圧勝するなど政権基盤を固めた。他方,都市部での治安が悪化し,86年2月よりリマ市及びカヤオ市に非常事態宣言及び夜間外出禁止令が発令された。
(b) 外交面では,86年も引き続き非同盟・第三世界重視の外交を進め,特に,アラブ・アフリカ諸国との関係強化に努めた。
(c) 経済面では,経済活性化及びインフレ抑制を目的とした緊急経済政策を継続し,経済成長率8.9%を達成,またインフレ率も62.9%に低下した。
しかし・経済活性化に伴う輸入増もあり・貿易黒字が大幅に縮少し,86年第4四半期には外貨準備が急激に減少した。対外債務政策では,86年7月,支払を年間輸出額の10%以内に制限する政策をさらに一年間延長した。
(ヌ) チリ
(a) 86年9月反政府テログループによるピノチェット大統領暗殺未遂事件が発生し,戒厳令が再布告されたが,87年1月には全面解除された。ピノチェット政権は80年憲法にそって選挙人登録制度法,政党法を公布するなど民主化へのプロセスを進行させている。
(b) 外交面では,ペルー,ボリヴィア等近隣諸国との関係改善と国際的イメージの回復に努めた。
(c) 経済面では,適切な経済運営に加え,石油価格と金利の低下という対外要因もあり,5%の経済成長を達成したほか,前年にし失業率(84%),インフレ率(17.4%)ともに低下した。
(ル) ボリヴィア
(a) パス政権は86年も引き続き,民主体制の基盤強化と国際協調に努めた。政情は与党民族革命運動党(MNR-H)と最大野党の民族民主行動党(ADN)の連携関係の存在もあり,比較的安定していたが,86年8月中旬の鉱山労働者ストに端を発し,同28日より90日間全土に戒厳令が布告された。
(b) 外交面では,86年7月の麻薬撲滅対策実施のための米軍派遣要請以後米国との関係改善が顕著となった。
(c) 経済面では,インフレは沈静化傾向をみせたが,錫及び天然ガスの国際価格の低落が国内経済に大きな打撃を与えるなど困難な状況が続いている。対外債務問題については,86年6月1MFとスタンド・バイ・クレジット供与に合意したほか,7月にはパリ・クラブで公的債務繰り延べの合意が成立した。
2.我が国との関係
(1) 全般的関係
(イ) 我が国と中南米諸国は伝統的に友好協力関係にあり,経済的にも相互補完関係にある。また約100万人に上る邦人移住者,日系人の活躍が我が国と中南米諸国の結びつきを一層緊密にしている。近年我が国の国際的地位の向上に伴い,中南米諸国の対日期待が高まっており,我が国は従来より経済交流及び経済技術協力を強化し,累積債務問題等中南米諸国が直面している経済困難の克服のための努力にも協力してきている。さらに,要人等人的往来,文化交流も活発化し,友好関係の増進に寄与している。
(ロ) 86年にはアルフォンシン=アルゼンティン大統領(7月),デラマドリ=メキシコ大統領(11~12月) がそれぞれ訪日したが,これらの訪問は,単に我が国とこれら諸国の関係緊密化のみならず,我が国と中南米全体との関係の増進に大きく寄与するものであった。
また,86年9月には我が国外務大臣として初めて倉成外務大臣が,ガット閣僚総会の機会にウルグァイを訪問し,同国首脳のみならず中南米各国閣僚とも意見交換を行った。
内中米紛争については,我が国はその平和的解決のためのコンタドーラ・グループ等域内の和平努力を強く支援するとともに,中米・カリブ地域の経済的・社会的発展のために協力を行っている。
(ニ) 我が国は,中南米諸国の民主化の定着は,中南米の政治情勢の長期的安定に資するものと歓迎しており,さらにこれにより,我が国とこれら諸国との対話・協力が一層促進されることを期待している。
(2) 経済関係
(イ) 貿易
我が国の86年の対中南米貿易は,輸出が対前年比11・9%増の94億9,455万ドルと回復傾向を示したのに対して,輸入は対前年比マイナス0.8%の61億9,356万ドルと若干ながら前年度実績を下回った。輸出の増加は機械機器,特に自動車輸出の増加によるところが大きく,他方輸入では石油価格下落により,鉱物燃料が対前年比25.6%の大幅減少となった。
(ロ) 投資
我が国の対中南米直接投資実績は,86年3月末累計で156億3,600万ドルであり,我が国の対外直接投資全体に占めるシェアは18.7%で北米・アジア地域に次いで第3位となっている。
(ハ) 金融
我が国民間銀行の対外貸付残高に占める中南米向け比率は高く,国際的金融支援に応分の協力を行ってきているが,特に86年にはメキシコに対し,国際協調の下,10億ドルの輸銀融資の表明など官民による協力を行った。
(ニ) 民間レベルの経済交流
86年9月,日本・アルゼンティン経済合同委員会(於ブエノスアイレス),日本・チリ経済委員会(於サンチャゴ)がそれぞれ開催され,二国間の貿易・投資促進等について意見交換が行われた。
また87年4月には,南米経済使節団が官民合同のミッションとしてアルゼンティン,ウルグァイ,チリに派遣され,貿易・投資の拡大を通じ,これら諸国との経済交流を活発化するため,調査を行った。
<要人往来>
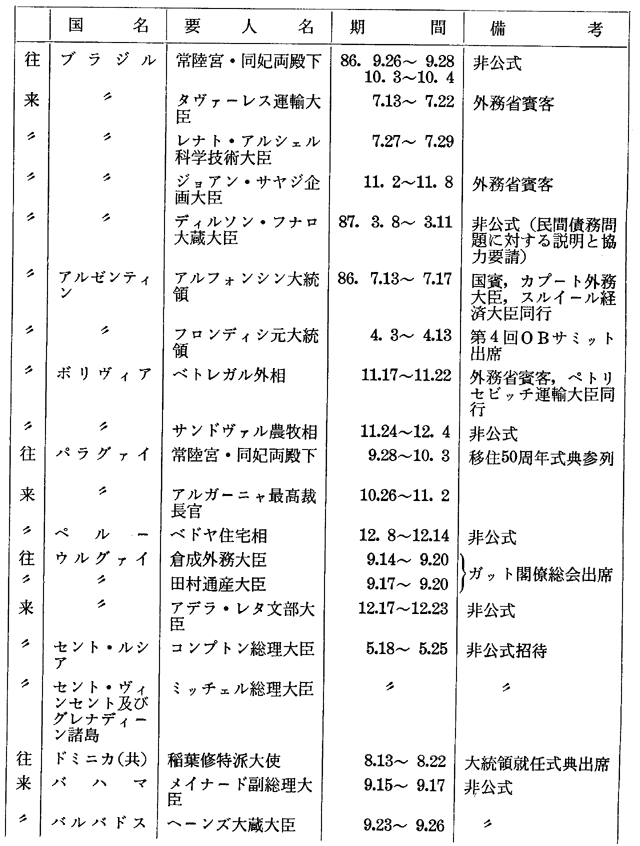
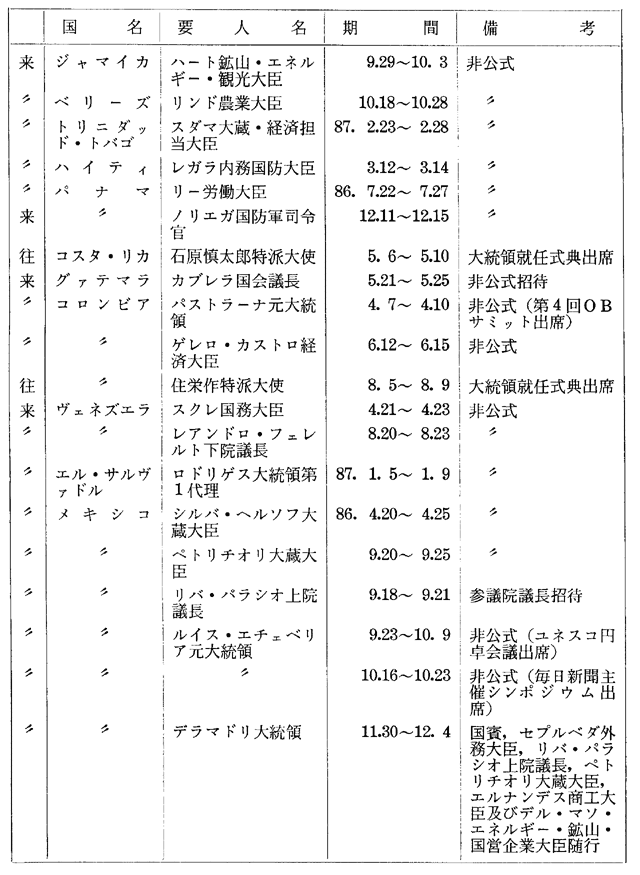
<貿易関係>
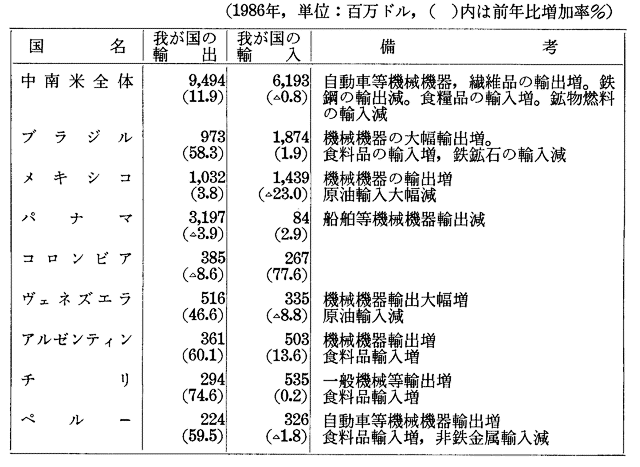
<民間投資>