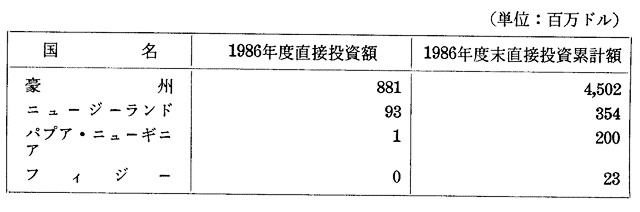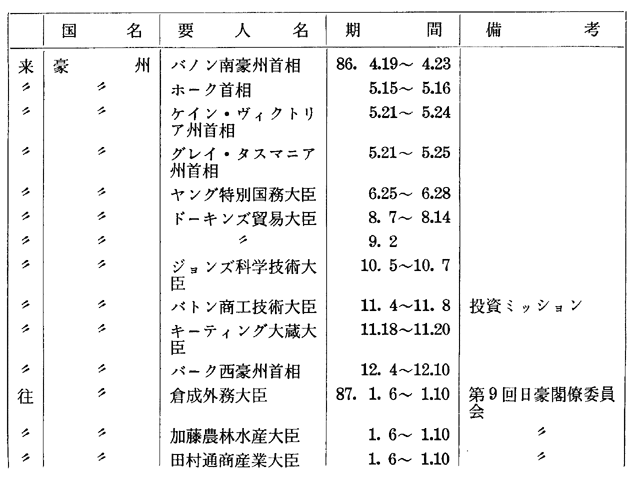
第2節 大洋州地域
1. 内外情勢
(1) 豪州
(イ) 内政
4年目のホーク労働党政権は,全国党大会(86年7月)を無難に乗り切り,党内左派を抑えつつ自由主義的な規制緩和措置等現実的施策を着実に積み重ねていった。しかし好転せぬ国際一次産品市況,国際収支の悪化,膨大な対外累積債務等悪化する経済パーフォマンスを背景に国民的人気の低下が懸念されだした。また,同年中頃より台頭した全国賃金裁定制度の廃止等自由競争に基づく社会制度を標傍するニューライト・グループから思想的挑戦を受ける一面もあった。ただし,全体としては,労働党は団結を保ちつつ柔軟な対応を示し,86年末に豪州経済が底を打つとともに,国民的人気も回復してきた。
他方,野党側は,85年9月に保守連合(自由党・国民党)党首として登場したハワード自由党々首の指導力が問題視され,加えて87年に入りビョーキ・ピーターセン・クイーンズランド州首相(同州国民党々首)による同党首批判,次期連邦首相の座への出馬運動を契機に保守連合解消問題が表面化するに至った。また,自由党内部でもハワード党首が,ピーコック影の外相(前自由党党首)を更迭(87年3月)する等主導権争いが起き混迷の様相を呈した。
(ロ) 外交
ホーク政権は,従来同様,ANZUS条約の維持等対米関係,最大の貿易相手国たる日本との関係及び中国,ASEAN諸国等のその他アジア・太平洋地域諸国等との関係を重視する姿勢を堅持した。
米国との関係では,同国の対ソ補助金付き小麦輸出問題でいら立ちを示す一面もあったが,豪米閣僚会談(86年8月)でANZUS枠内での同盟関係の堅持が再確認された。対ソ関係では87年3月シェヴァルナッゼ外相が訪豪,豪はソ連の南太平洋進出に明確な形で懸念を表明したが,他方豪ソ定期協議設置等が合意された。NZとの間では,ANZUS問題での見解の相違はあるも,引き続き防衛を含む幅広い分野で緊密な関係を維持,その他の南太平洋諸国ともヘイドン外相の訪問(86年5月)等を通じ友好協力関係強化に努めた。対フィリピン関係では,ホーク首相の訪比(86年5月)等アキノ政権との友好協力関係促進を図った。対中関係は,ホーク首相の訪中(86年5月),万里副首相の訪豪(同年9月)等順調に発展した。対中東関係では,ホーク首相のジョルダン,イスラエル及びエジプト訪問(87年1月下旬~2月上旬)を通じ外交の幅を拡大した。
(ハ) 経済
83年後半以降高い成長を示していた豪州経済は,86年に減速過程に入った。経常収支の大幅な赤字,対外債務の増大,豪ドルの下落等すでに顕在化しつつあった対外経済関係の不調が86年に大幅に悪化したことを背景に,実質GDP成長率は85/86年度(7-6月)3.6%,86年暦年で1.1%に落ち込んだ。物価も輸入インフレの影響から消費者物価指数は85/86年度8.4形,86年10~12月期には対前年同期比9.8%に上昇,失業率も10~12月期8.4%と上昇傾向にある。
こうした情勢下,ホーク政権は経済政策において対外不均衡の改善を最重要課題として努力を払ってきた。
まず財政面では,歳出の伸び率をゼロに抑え,増税により歳入の伸びを確保する財政赤字削減型の86/87年度予算を発表した(8月)。
また賃金問題については,ホーク政権の経済運営の支柱であった「物価・所得合意」(アコード)に基づくフル・インデクセーション方式に代わり,二層式賃金決定方式が新賃金決定方式として採用されることとなった(12月)。
産業面では,引き続き構造調整を推進し,保護水準を引き下げるための諸政策が実施された。また製造業振興のための外国からの投資促進を図るため,外資規制の緩和や投資ミッションの派遣が行われた。
貿易面においても,対外不均衡改善を目指して輸出振興のために種々の措置がとられた。また,農業貿易の自由化を主張する豪州は農産物輸出14か国閣僚級会議(ケアンズ会議)の開催を主唱し,ガット新ラウンドにおいて農業貿易問題が十分取り上げられ,補助金を排した公正な自由貿易体制が確立されるよう「ケアンズ宣言」が採択された。(8月)
(2) ニュージーランド(NZ)
(イ) 内政
ロンギ労働党政権は84年7月の誕生以来,自由民主主義の維持,国民生活の向上等を基本としコンセンサス重視の政治を指向している。内政面では特に経済再建を重視し,政権2年目の86年も短期的には国民に忍耐と犠牲を要求しつつも中長期的にはNZ経済の体質強化に資する諸改革を積極的に推進し,おおむね国民の間で歓迎されてきた。しかし,87年に至っても経済不況から脱せず,世論調査では与党労働党と野党国民党の支持率が伯仲している。
またANZUS問題と密接に絡んでいる非核法案は85年12月以来国会で審議されていたが,87年6月成立した。なお同法案との関連で政府は,国防政策の見直し作業を行ってきたが,87年2月今後の指針となる国防白書を発表し,自国周辺地域により限定した国防政策への転換を明らかにしている。
(ロ) 外交
ロンギ政権は,アジア太平洋の重視,農産品自由化・輸出市場の開拓等経済・貿易外交を推進する中で,自由民主主義陣営の一員であるとの立場を維持しつつも同国の国際環境から反核の姿勢を強調する等86年も引き続いて独自の外交路線を進めている。
特に85年2月の米艦船のNZ寄港拒否に端を発したANZUS条約をめぐる米国との緊張関係は,86年8月米国がANZUSに基づく対NZ防衛義務の停止を表明するに至った。その後,NZは豪州との軍事協力関係の強化等に努めている。
なお,85年7月に発生した仏による反核船舶「レインボー・ウォリア号」爆破事件は,両国が86年7月国連事務総長の和解裁定案に合意し決着した。
(ハ) 経済
ロンギ政権は,発足当初より国内経済をインフレ体質から脱出させるとともに生産性を上昇させ国際競争力獲得による安定成長を目標とし,市場原理に基づく自由経済主義政策を積極的に推進している。これまでに諸規制の緩和,関税引下げ,財政金融引締政策を実施しているが,86年度においても,財政支出抑制に努めるとともに税制改正,国営企業の資産売却
及び一部民営化,農業補助金の撤廃等を実施した。
かかる一連の緊縮的政府経済政策も背景として成長率の鈍化(86暦年,前年比1.1%),高い失業率(86年度平均5.3%),インフレの高進(86暦年,前年比13.2%の上昇)等86年度も総じて経済パフォーマンスが芳しくないが,短期的に必要な過渡的措置との好意的見方が財界の中でも支配的である。
対外貿易・経済の分野においては,貿易収支は黒字基調が続いているものの,対外借入債務に対する利払い負担から経常収支は大幅赤字(86暦年2,750百万NZドル)となった。
(3) 南太平洋島嶼国
南太平洋には9の新興独立島興国が存在,いずれも積極的に国造りに励んでいるが,一般に,国土,人口,資源等に恵まれず経済的にぜい弱であり,その発展は海外よりの援助に依存している。他方,旧宗主国ないし域内先進国たる豪州,NZ,英国等よりの援助は先細りないし伸び悩み傾向にあり,これら諸国は我が国を含む援助ソースの多角化を求めるようになっている。政治的には,この地域は今までは平和で安定した地域として,世界の関心を引くこともほとんどなかったが,近年ソ連等新しい域外勢力の進出の動き,南太平洋非核地帯条約の発効(86年12月)や仏の核実験をめぐる核問題,ニューカレドニアの独立問題,まぐろ漁業をめぐる米国との関係不調(ただし,この問題は87年4月,米国と南太平洋諸国との間の多数国間漁業協定が署名され解決)等の動きがあり,国際政治の上でも注目されるようになってきている。
同地域の主要諸国の動向次の通り。
(イ) パプア・ニューギニア(PNG)
(i) 内政
1年目を迎えたウィンティ政権は,経済成長促進,雇用創出の政策を進める一方,行財政改革による歳出削減を実行した。
同政権は連立に伴う不安定な一面があったものの,チャン副首相の株券大量購入問題,TV放送開始時期延期等の政府に対する野党批判も一時的なものであった。
また,比較的治安が良いとされていた地方都市の犯罪が増加した。
(ii) 外交
86年のウィンティ政権の外交政策は,外交を内政の延長として明確に位置づけた上で、PNGの国益に直接結びついた外交活動を行なうことの重要性を強調し,活発な外交を展開した。
大きな特徴としては,豪州の援助が削減傾向をたどり,両国関係が従来の「特別な関係」から単に「緊密な関係」に移行しつつあるとの認識を深める一方,インドネシアとの友好協力条約締結をはじめ,ASEAN諸国及び日本をはじめとする先進諸国に対し,より積極的かつ自主的な外交を展開した。
(iii) 経済
コーヒーを除く一次産品市況の低迷,豪州の経済不振,インフレと高金利等の外的要因のため,必ずしも活発な経済状況ではなかった。
その反面,鉱業投資は特に金及び石油に関して活発化し,林業では木材市況が順調に回復し,また,貿易収支は金とコーヒーの輸出に支えられ,好調に推移した。
(ロ) フィジー
(i) 内政
これまでの政治は,マラ党首率いる同盟党(AP)が政権を担当し,これに対し野党の国民連邦党(NFP)が対抗するという図式で行なわれてきたが,86年労働党(FLP)が設立され,87年4月に行われた総選挙においてはおおかたの予想に反しインド系住民等の支持を受けたNFP・FLP連合が勝利を収め独立以来17年間続いたフィジー系主体のマラ同盟党政権に代わりバパンドラ首相率る連合政権が誕生した。
しかしながら同年5月インド系住民の台頭に反発した軍部によるクーデターが発生,ババンドラ政権は失脚し,代わってガニウラ総督が当分の間暫定的に政権を担当することとなった。
(ii) 外交
同盟党政権下のフィジーの外交路線に変更はなく,ヘイドン豪州外相の訪問に代表される豪州,NZを中心とする英連邦諸国との緊密な関係の維持を基調とし,米国,ソ連,中国,日本その他アジア諸国等の友好
関係強化にも力を入れた。
他方,ババンドラ政権は,非同盟,非核政策等を標傍していた。クーデター後の外交政策の方向については今だ不透明な部分が多い。
(iii) 経済
86年のフィジー経済は,民間投資の伸び悩み,歳入不足等の問題はあったが,砂糖生産量が過去最大となり,低迷していた観光客も14%増と上向きになり,経済は昇り調子といえた。
また,貿易収支は改善し,消費者物価上昇率は下降し,インフレ鎮静化傾向が続いている。しかし,クーデターに引き続く国内の混乱が,今後の経済の先行きに暗雲を投げかけている。
(ハ) その他南太平洋島興国
ヴァヌアツは,5月30日リビアと,また,6月ソ連,9月には米国との間で各々立て続けに外交関係を樹立するとともに,9月からソ連との間で漁業交渉を開始し87年1月に二国間漁業協定が署名された。また,85年以来,200海里経済水域内でソ連漁船に1年間の操業を認めたキリバスは,年央にソ連と入漁延長交渉を行ったが,合意に達せずソ連漁船は10月をもって同国経済水域内での操業を終了することとなった。
2. 我が国との関係
(1) 豪州
日豪関係は,各層にわたる対話を通じ貿易経済面のみならず幅広い分野で拡大発展してきたが,86年5月のホーク首相の訪日,87年1月のキャンベラでの第9回目豪閣僚委員会開催,政府間の各種協議実施等を通じ両国関係の一層の緊密化が進んだ。
経済面では,先の日豪首脳会談における基本合意を受けて,投資ミッションの相互派遣(85年11月,豪側投資ミッション(バトン商工技術大臣団長)訪日及び本年2月日本側投資環境査調団(天谷通産省顧問団長,広江丸紅副社長副団長)訪豪)が行われる等,伝統的な相互補完貿易関係のみならず新たな協力関係が進展した。
政治面では,日豪二国間関係強化のみならず,第9回目豪閣僚委員会において,太平洋島興国に対する協力について緊密な連絡を行うこと等が合意された。
(2) ニュージーランド(NZ)
両国は,相互補完的な貿易関係を中心に順調に発展してきており,日本はNZにとり往復で最大の貿易相手国の地位を占めるに至った。
政府レベルにおいては,倉成外務大臣,加藤農水大臣がNZを訪問し,パーマー副首相が訪日するなどの要人往来が頻繁で,二国間関係にとどまらず,国際政治経済情勢,とりわけ南太平洋情勢等についても意見交換が行なわれるようになっている。また両国間の各種政府間協議においても,広く対話が行なわれており,両国はアジア太平洋地域のパートナーとして関係を深めている。
こうした動きに加え今後人的交流,文化交流,地方自治体交流等の分野においても一層緊密化の動きが見られる。
(3) 南太平洋地域
南太平洋島興国は,前述の通り援助ソースの多角化を求める傾向もあり,近年同じ太平洋国家の一員である我が国との関係強化を求めている。
南太平洋フォーラム(SPF:South Pacific Forum)は,85年の第16回会議において我が国との関係強化を訴える決議を採択したが,86年の第17回会議においても,一項をさいて同様の決議を採択,特に電気通信,域内海運,トゥヴァル等小規模島興国開発の分野で我が国から従前にも増した援助も得るよううたった。我が国はかかる南太平洋島興国の期待に応え,これら諸国との関係の一層の緊密化を図るべく,その一環として86年7月浦野外務政務次官(当時)がパプア・ニニーギニア,バヌアツ,フィジーを訪問した。
さらに87年1月倉成外務大臣が豪州及びニュージーランドに引き続き上記3島嶼国を訪問した。また,フィジーにおいて我が国の太平洋島興国政策に関する演説を行ったが,「太平洋未来社会を目指して」と題するこの演説において倉成外務大臣は,今後の我が国の対太平洋島興国政策のポイントを(1)島嶼国の独立性と自立性の尊重,(2)地域協力の側面的支援,(3)太平洋地域が「平和で安定した地域」であり続けるよう努力,(4)経済的繁栄のための支援,(5)人的交流の促進の5点に置くことを表明し,域内国のみならず関係各国より大きな支援を得た。
<イ> 要人往来
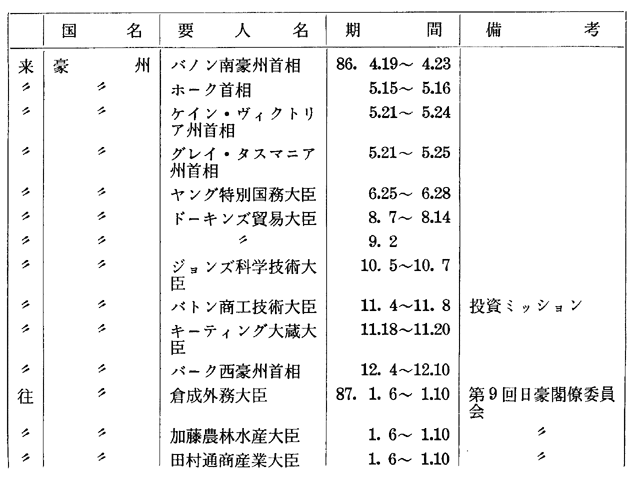
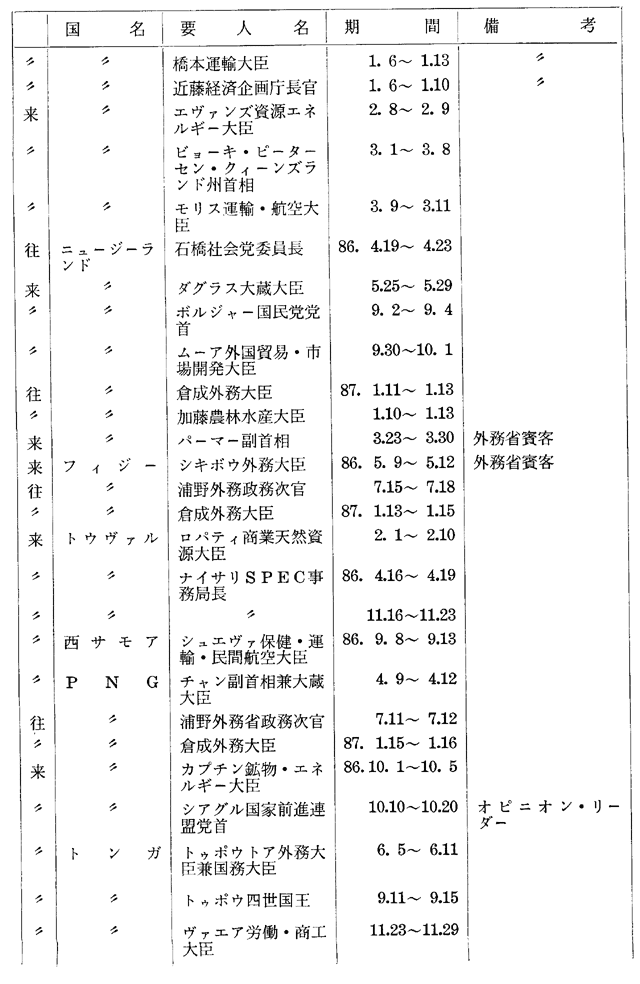
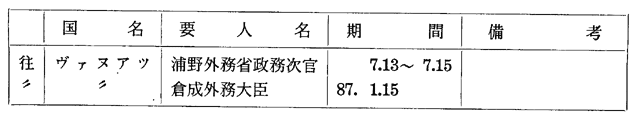
<ロ> 貿易関係
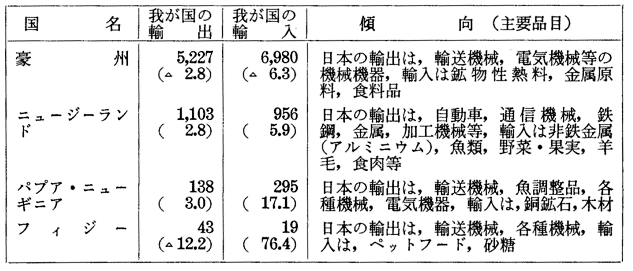
<ハ> 民間投資