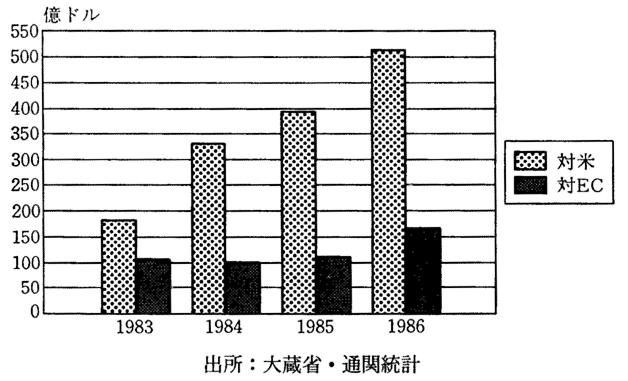
第1章 我が外交の基本課題
世界に貢献する日本へ―歴史的転換の時
1. はじめに
我が国を取り巻く現下の国際環境は,我が国の大幅な対外不均衡を背景とした諸外国との経済摩擦,就中,米国とのかつてないほど深刻化した貿易不均衡問題等を中心に厳しさを増している。
また,世界経済は主要国における大幅な経常収支不均衡,保護主義の増大,急激な為替変動,累積債務問題などの諸困難に直面しており,現在の国際経済秩序は,その根幹を揺るがしかねない深刻な局面に至る可能性があると言っても過言ではない。
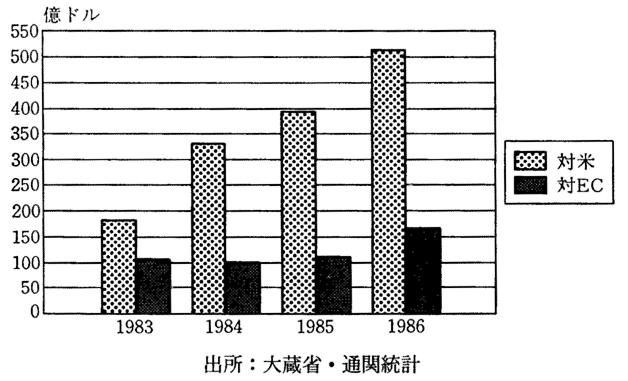
他方,国際政治分野では,東西関係が軍備管理交渉を中心に一定の進展を見せているものの,その長期的趨勢は予断を許さないものがあり,世界各地の地域紛争は,引き続き解決の目途が見られない状況にある。
このように厳しくかつ変動しつつある国際社会において,我が国の果たすべき役割はとりわけ重要となってきている。これまで我が国は,自由貿易体制を中心とする恵まれた国際環境の下で比較的順調に発展してきたが,今日,その国際秩序自体が,各国の協調と不断の努力なくしては維持できない状況に至っている。今後,我が国としては,長期的視野に立って国際協調を重しじ,国際秩序を支える重要な担い手としての責任と役割を負担することにより,世界の平和と繁栄に積極的に貢献する国家となるよう努めることが肝要である。我が国は,まさに大きな歴史的転換期に差しかかっており,今日ほどその姿勢が内外から問われている時はないであろう。
2. 国際社会の変貌と我が国の役割
我が国としては,まず,現在の国際情勢とその根底にある時代の潮流をより的確に把握することが重要である。
相互依存の増大した今日の国際社会において,米ソ両国は,依然として巨大な軍事力を背景に大きな影響力を有しているが,日本,西欧,中国等の比重も着実に増大している。経済分野においては,第二次大戦後圧倒的な経済力を有し,国際秩序の形成・維持に寄与してきた米国の相対的地位の低下が生じ,自由貿易体制及びドルを基軸通貨とする国際通貨体制が新たな局面を迎えている。
このように国際社会は,ますます流動的様相を深めるに至っているが,米国が,依然,国際政治・経済において中心的な役割を果たしていることは明らかである。しかし,現在の国際秩序をより円滑に維持し,世界の平和と繁栄を確保するためには,主要自由民主主義諸国がそれぞれ応分の国際的責任と役割を果たすとともに,相互間の対話や政策協調を強化していくことが一層重要となってこよう。
また,現在の国際関係において,安全保障の観点から軍事力の持つ意味が大きいことは否定出来ないが,他方,経済,科学技術,社会・文化の比重も顕著に高まっている。米ソ両国をはじめとする主要国が,経済面での競争力強化や活性化を大きな課題とし,さらに,科学技術開発に精力的に取り組んでいるのもこの端的な表われと言えよう。
このような大きな潮流の中,我が国が,未来を展望しつつ,政治,経済,文化等の各面でバランスのとれた国家を目指し,国際社会に対し建設的な貢献を行っていくためには,例えば次のような役割を念頭に置いていくべきではないだろうか。
第一に,平和国家として他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの立場を堅持しつつ自らの安全保障に努め,グローバルな視野から世界の平和と安定に貢献するため,一層の政治的役割を担っていくこと。
第二に,国際経済秩序の維持・発展のため,主体的にその責任と役割を果たしつつ,我が国経済の活力を生かし,また南北問題解決に向けての一層の経済協力の拡充を通じ,世界経済全体の健全な発展に寄与すべきこと。
第三に,文化,学術及び科学技術を重んじ,国際交流を促進するとともに,環境・医療・食糧等の人類共通の問題解決にも努め,新しい文明の創造に貢献していくこと。
第四に,良識とヒューマニズム等の普遍的価値を重んじ,相手国の立場に十分配慮しつつ,世界各国の信頼を得るよう努めること。
3. 我が国外交の基本的立場
以上のような我が国の将来に向けての役割を実現していく上で,外交の果たす使命が極めて重要であることは言うまでもない。
我が国は,自由民主主義諸国の一員としての立場及びアジア・太平洋地域の一国であるとの認識に立って,自国の安全と繁栄を確保するとともに,世界の平和と繁栄に貢献することを外交の基本としている。
(1) 自由民主主義諸国の一員としての外交
我が国が現在享受している平和と繁栄は,戦後日本が選択した自由及び民主主義という共通の価値観を有する諸国との連帯と協力なくしては実現し得なかったものであり,自由民主主義諸国の一員として自らを位置づけることは日本外交の基本である。
これら諸国との関係のうち,とりわけ日米安全保障体制を基盤とした日米関係は,我が国外交の基軸である。日米関係は戦後一貫して強化されてきており,最近の両国間の経済摩擦はかつて経験したことのないほど深刻なものになっているものの,両国は,経済問題のゆえに全体として良好な関係が損われてはならないとの観点から,問題解決のため緊密に協力している。本年4~5月の中曽根総理大臣の米国公式訪問を通じ,かかる日米間の協力は一層促進された。日米関係は今や単に二国間関係にとどまらず,世界的視野に立った協力関係にまで発展しており,我が国としては,米国との協力関係の維持・強化を図り,広く国際社会に寄与していかねばならない。
西欧諸国は,今日,その統合の進展に伴い新たな活力を発揮しつつあり,また,我が国との関係も,経済分野のみならず,政治,文化,科学技術等幅広い分野にわたり緊密の度を加えつつある。最近,これら諸国の対日姿勢も経済摩擦をめぐり一段と厳しくなっているが,我が国としては,欧州を含めたグローバルな経済面での対応を図っていくとともに,政治面等での日欧協力関係の一層の緊密化に努めていくことが重要である。
自由民主主義諸国の連帯と協調は,今後一層重要になってこようが,かかる意味において,先進民主主義工業国7か国によるサミットの果たす役割は大きく,本年6月のヴェネチア・サミットにおいても,現下の国際経済問題,東西関係,地域問題等に関し緊密な協議が行われ,具体的協力姿勢が打ち出されたことは評価される。我が国としては,今後とも,サミット,さらには,OECD等を通じ,積極的な貢献を行うとともに,先進諸国との協力を一層強化することが肝要である。
(2) アジア・太平洋地域の一国としての外交
アジア・太平洋地域は,政治的には,朝鮮半島の緊張,カンボディア問題,一部諸国の政情不安等があり,経済的にも一次産品価格の低迷,累積債務問題の深刻化など諸困難を抱える国が多く見られる。他方,この地域はダイナミズムに満ち,国際社会の中でその比重を一段と高めつつある。
我が国は,アジア・太平洋地域に位置するのみならず,歴史的,文化的にもこの地域と深い関わりを有している。また,この地域の平和と安定は日本の安全を確保する上で極めて重要であり,経済関係も,近年,貿易,投資,観光等を通じ一層緊密化している。
これら諸国との関わりにおいて,我が国が古くから文化的恩恵を受けてきたこと及び過去において不幸な経緯があったことは,今日においても謙虚に受け止め,銘記しなければならないことである。また,我が国が近代化のプロセスにおいて,概して欧米より学ぶ姿勢をとってきたことは否めないが,そのことは日本にとってのアジア・太平洋地域の重要性をいささかも減ずるものではない。
我が国としては,より良き関係を目指すため絶えず自らの姿勢を問い続け,歴史とその教訓に学ぶという対アジア外交の原点を踏まえた平和・友好の関係を構築していくことが重要である。そしてこれら諸国の自主性を尊重するとの基本的立場に立ち,平和国家として同地域の安定に貢献しつつ,広範な分野における交流と対話を進めて相互信頼を深めていくことが肝要である。アジア・太平洋諸国との友好協力関係を強化することは,日本及びこの地域,ひいては国際社会全体の平和と繁栄に寄与することを意味し,我が外交を進めていく上で不可欠な要素と言えよう。
また,21世紀へ向け進展しつつある太平洋協力の諸活動に対し,我が国としても一層協力していく必要がある。
4. 日本外交の課題
我が国は,以上のような基本に立ち,平和と繁栄を維持しつつ,積極的に国際的責任と役割を果たすため,次のような課題に真剣に取り組んでいくことが必要である。
(1) 世界の平和と安定に向けての努力
世界の平和と安定を確保することは人類の長年の悲願であるが,現実には戦争の脅威,地域紛争,テロ問題等,不安定要因は夥しい。我が国としては,平和国家としてその国力にふさわしい役割を,以下の各分野において一層積極的に担っていくべきである。
また,86年に国連加盟30周年を迎えた我が国は,本年より2年間,国連安全保障理事会の非常任理事国を務めているが,国連における責任をより積極的に果たしていくことが重要である。
(イ) 東西関係及び軍備管理・軍縮
東西関係,就中,世界の平和と安定にとり基本的要素である米ソ関係においては,86年10月のレイキャヴィク首脳会談,本年4月の米ソ外相会談,6月のNATO外相理事会等を通じ,紆余曲折はあったものの,軍備管理・軍縮問題で中距離核(INF)に関し注目すべき動きが見られた。このINFに関して我が国は,グローバルな全廃が西側の安全にとり最善の解決策であるとの基本的立場をとっている。
ヴェネチア・サミットにおいて,安定的で建設的な東西関係の構築を目指した西側の平和意思及びその協調と結束が確認されたが,我が国としても,日米安保体制を堅持し,自由民主主義諸国との連帯を強化しつつ,より安定した東西関係の構築のため積極的な努力を傾けていくことが必要である。また,我が国自身,軍縮の促進に積極的に貢献すべく,国連及び軍縮会議などの場において,核実験の全面禁止,核不拡散体制の維持・強化,化学兵器禁止の早期実現等を引き続き各国に訴えていかねばならない。
他方,我が国がソ連及び東欧諸国と自ら対話を促進していくことは,二国間関係のみならず,東西間の相互理解を深めるという意味でも重要である。
ソ連との間では,86年の二度にわたる外相間定期協議において北方領土問題を含む平和条約交渉が再開され,さらに両国の政治対話の一層の強化につき合意をみた。北方領土問題については,ソ連は依然頑な立場をとっているが,同問題を解決して平和条約を締結し,真の相互理解に基づく安定した二国間関係を確立することは我が国の不動の基本方針である。
また本年1月,中曽根総理大臣は,日本の総理として初めて東欧諸国等を公式訪問し,東西間の政治対話と相互理解の促進に寄与した。
(ロ) 地域問題
現在,世界各地では,朝鮮半島,カンボディア問題,アフガニスタン問題,イラン・イラク紛争,中東和平問題,南部アフリカ問題,中米紛争等,多くの緊張や紛争が見られる。これらは,歴史的経緯,民族や政治体制の相違,第三国の干渉等,各々複雑な要因を抱えており,未だ必ずしも解決の目途は立っていない。我が国としても,紛争の拡大を阻止し,早期平和的解決を目指し,また緊張緩和を図るべく,そのための環境造りに一層の外交努力を行うことが重要である。
イラン・イラク紛争の継続を背景として,湾岸情勢は緊張の度合いを高め,船舶の安全航行確保が大きな問題となっている。かかる状況の下,ヴェネチア・サミットで本問題に関する政治声明が発出された。我が国は従来よりイラン・イラク双方と緊密な対話を維持している独自の立場に立って,紛争の解決へ向けての環境造りのため外交的努力を積極的に展開しており,倉成外務大臣が,イランを訪問した際にも,同紛争の早期終結を強く働きかけた。今後も紛争解決のためできる限りの努力を続ける必要がある。
(ハ) テロ問題
近年,爆破事件,航空機等のハイジャック事件,誘拐・暗殺など,一般市民を巻き込む凶悪なテロ行為が多く生じている。このようなテロ行為は,市民の平和と安全を脅かすのみならず,国際社会に対する挑戦でもある。また,海外の在留邦人の安全を確保するとの観点からも看過し得ない問題である。我が国としてはいかなるテロ行為にも断固反対との立場から,その防止のため国際協力を強化することが重要である。
(2) 世界経済の健全な発展への貢献
(イ) 世界経済は,成長の持続,低インフレ率,金利の低下,あるいはウルグァイ・ラウンド交渉の開始等の明るい動きがあるものの,依然多くの不安定要因を抱えている。かかる状況の下,各国が自らの課題に主体的に取り組むとともに,各国間で政策協調を進めていくことがますます重要となっている。その意味において,東京サミットに引き続きヴェネチア・サミットにおいて,政策協調の強化の重要性が確認されたことは有意義であった。
貿易,金融,投資の各分野における我が国の比重は,近年著しく増大しており,その国際経済面での貢献に対し,各国からの期待と関心が高まっている。他方,我が国経済は,一国としては未曽有の年間860億ドル(86年)もの巨額な経常収支黒字を生みだすに至り,世界経済の撹乱要因となっているとの批判が生じている。我が国が対応を誤まれば,自由貿易体制,国際通貨制度等,世界経済発展の共通の基盤及び枠組み自体を危うくすることにもなりかねない。このことは,とりもなおさず日本経済自身の発展を危うくすることにもなりうる。
今日,我が国にとり焦眉の問題は,深刻な様相を呈している諸外国との経済摩擦を緩和し,世界各国で台頭しつつある保護主義を防圧することで
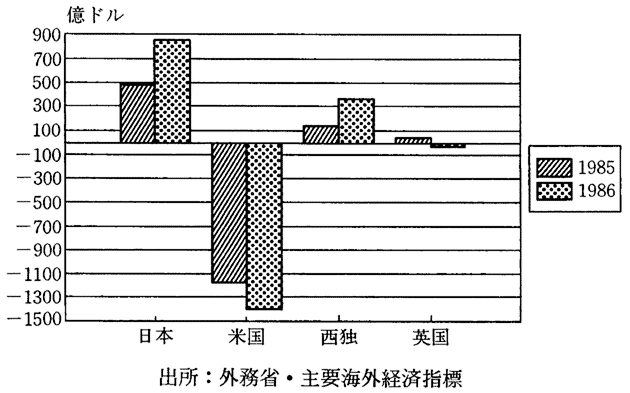
ある。特に,日米経済関係は,貿易不均衡問題を中心に,本年に入り緊張の度合いを一層高めた。日米経済関係の世界経済に及ぼす影響は極めて大きく,両国とも各々の責任を自覚し,摩擦の緩和に努め,もって保護主義を防圧していくことが肝要である。
もとより経常収支不均衡の是正は,我が国一国の政策対応や為替レートの調整のみで達成することはできず,米国の財政赤字削滅と産業競争力強化への諸努力をはじめとする主要国間の政策協調が不可欠であるが,我が国としては以下に述べるような諸施策を積極的に実行していかねばならない。
(ロ) まず,我が国は,自らの責任を自覚し,国際的調和を図るため,その経済構造を従来の輸出依存型から内需主導型に積極的に転換させるとともに,世界経済の健全な発展のため積極的に貢献すべく,あらゆる努力を果敢に実行していくことが重要である。かかる観点から,本年4月の総理訪米,5月のOECD閣僚理事会,6月のヴェネチア・サミットに向けて,我が国としての具体的な政策努力をとりまとめるべく,内需拡大,輸入拡大,国際社会への貢献を柱とする緊急経済対策の策定のため政府・与党を通じて精力的に検討が進められた。
5月末に政府が決定した緊急経済対策は,その結実であり,政府の政治的決断により,具体的数字を示しつつ,我が国の強い決意を表明したものとなっている。すなわち,内需拡大については,公共投資等の追加と所得税等の減税先行を併せ6兆円(約430億ドル)を上回る財政措置を伴う思い切ったものとされ,輸入拡大については,総額10億ドル規模の政府調達による追加的な外国製品輸入を行うため,補正予算で臨時異例の財政措置を講ずることなど,政府が率先して努力することが明らかにされた。また,国際社会への貢献についても,後述するように,政府開発援助の繰り上げ実施,途上国に対する積極的な資金の還流等を行うことを謳った。この対策に対しては,ヴェネチア・サミットにおける各国首脳を含め,各国より積極的な評価とその実行に対する強い関心が示されており,今後,対策の決定事項を確実に実行に移していくことが必要である。これらの諸政策は中長期的な政策方向の核をなすべき課題であり,一過性の措置に終わってはならず,今後とも継続的に努力を傾注しなければならない。
また,各国との個別懸案については,引き続き公正かつ迅速な解決を図ることが不可欠である。さらに,我が国の農業についても,本年のOECD閣僚理事会及びヴェネチア・サミットでの合意を踏まえ,食糧の安定供給確保の必要性にも配慮しつつ,バランスのとれた形での改革を遂行すべきである。
他方,産業構造の転換や輸入拡大の過程においては,雇用問題をも含め,国内的困難が生ずることは避けられず,また,最近の急激な円高に伴い,多くの産業,特に重厚長大型産業や輸出依存型の企業が,厳しい状況に陥っていることも事実である。こうした現状の下では,内需拡大を基本に,新たな雇用機会の創出,地域経済振興等が強く求められているが,同時にかかるプロセスを通じ,日本経済を国際的に調和のとれたものとしていくことこそ,日本経済全体の活力と繁栄を中長期的に確保し,国民の生活を豊かにするために不可避なものであることを認識する必要がある。
海外直接投資については,一部に産業の空洞化を生むと懸念する向きもあるが,日本企業の国際化という観点から,さらには相手国の雇用創出及び技術移転に寄与し,かつ経常収支不均衡の是正にもつながることが期待されるため,基本的には一層促進すべきである。但し,海外進出にあたっては,地元の人々を積極的に登用するとともに,企業が地域社会の一員として溶け込んでいくことが必要である。
(ハ) 国際貿易面において,86年9月のガット閣僚会議でウルグァイ・ラウンドが発足したことは,保護主義を防圧し,自由貿易体制の将来に確固たる展望を切り開いていく上で大きな前進であった。我が国としては,今後とも同交渉の成功に向けて積極的な役割を果たし,同時に,自らなすべきことを果断に実行しなければならない。
国際通貨問題に関しては,85年秋の5か国蔵相会議に続き,東京サミットにおいて7か国蔵相会議が創設され,為替レートの安定を目指した先進国間の政策協調は一層の進展をみた。しかし,急激な円高は日本経済に多大な影響を及ぼしており,また,ドルの急激な下落は世界経済を混迷に陥れかねない危険をはらむものであることにも鑑み,今後とも通貨価値の安定のため,主要国が一層協調していくことが肝要である。この観点から,ヴェネチア・サミットにおいて,為替相場の安定の必要性につき,主要国首脳間で政治的な意思が宣明されたことは大きな意義を有する。
(ニ) 技術革新の著しい今日において,我が国は優れた応用技術力を持ち,エレクトロニクス,光ファイバー,人工知能,バイオ・テクノロジー等,高度先端技術の分野でも世界有数の先進国であると言えよう。我が国としては,今後,基礎研究を含む科学技術全般の発展に一層の努力を傾注し,その総合的な科学技術力をもって,世界経済の活性化ひいては人類の福祉と新しい文明の創造のため貢献していくことが重要である。そのためにも諸外国との産業協力,科学技術協力,学術交流等を一層積極的に促進していく必要がある。
(3) 開発途上国の安定と発展への協力
(イ) 現在,開発途上国では,新興工業国・地域の目覚ましい経済発展がある一方,その多くは,一次産品価格の低迷,経済成長の鈍化等の経済的諸困難に直面している。また,中南米諸国及びアフリカ諸国を中心に累積債務問題が深刻化しており,債務国のみならず国際経済全体にとっても大きな不安定要因となっている。さらに,都市のスラム化,砂漠化等の社会及び環境問題を抱える国も多く,世界には未だ一千万人を超える難民と栄養不足に苦しむ数億の人々が存在する。
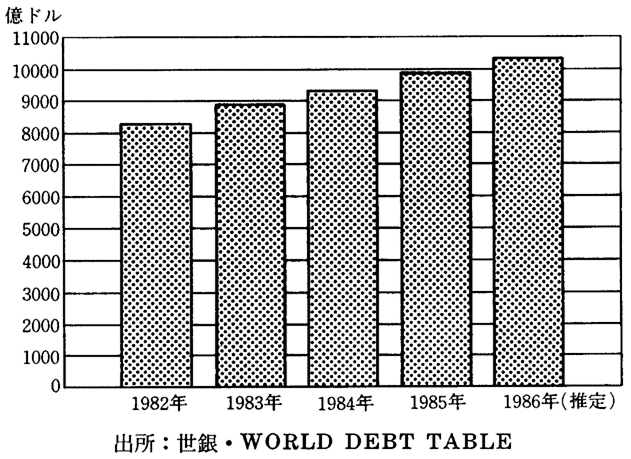
開発途上国の経済・社会開発に対する協力は,単に人道的観点から重要であるだけでなく,当該国及び地域さらには世界全体の安定と発展に貢献するものである。また,今日自由世界第二の経済力を有する我が国にとり,経済協力の積極的推進は重要な国際的責務であると言えよう。
(ロ) 日本の役割に対する諸外国の期待は,近年著しく高まってきており,我
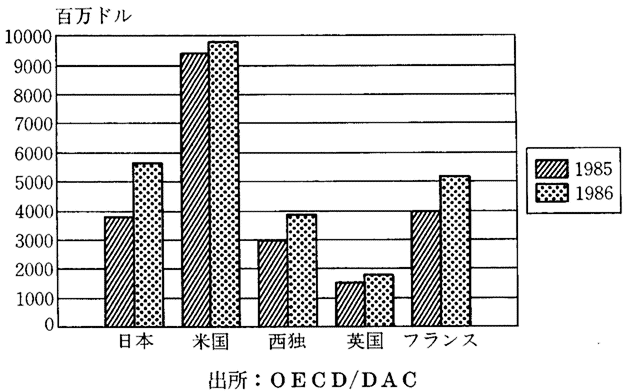
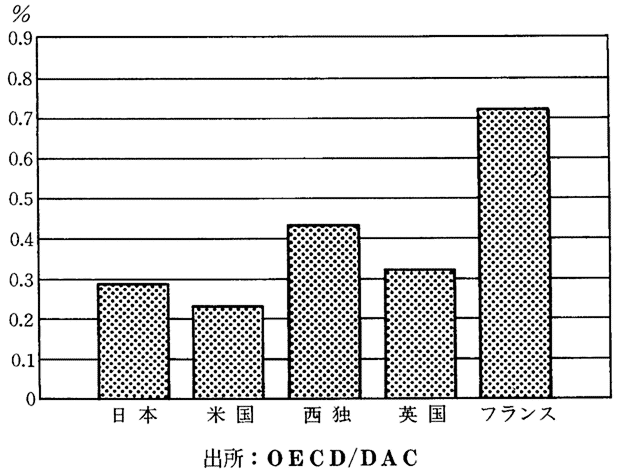
が国はかかる期待に積極的に応えるため,第三次中期目標を掲げ,政府開発援助(ODA)の拡充に努めるとともに,本年5月の緊急経済対策において,7か年倍増目標の2年繰り上げ実施,今後3年間で新たに200億ドル以上の完全アンタイドの資金を途上国に還流させること,及びアフリカ諸国等への3年間で5億ドル程度のノンプロジェクト無償援助を含む贈与の拡大等の積極的支援を決定した。また,今後とも適正かつ効果的な援助を実施し,円借款を含め援助の質の改善,被災国に対する国際緊急援助体制の整備など,開発途上国のニーズの多様化に弾力的に対応できるよう努力していくとともに,途上国の人造りと国造りに寄与するため,研修員の受け入れ,専門家派遣等の技術協力についても,一層の推進を図ることとしている。さらに我が国は,世界的に依然深刻な状況にある難民問題に対しても,資金・食糧援助やインドシナ難民の受け入れなどを通じて,引き続き取り組んでいく必要がある。
このような協力と同時に,開発途上国経済をより活性化させるために,二国間及び国際機関を通じた途上国との対話の積極的推進,途上国産品の輸入の一層の拡大,民間直接投資とそれに伴う技術移転の促進等を図り,新たな分業関係を築いていくことが極めて重要である。
(4) 国の安全の確保
(イ) 我が国は,第二次大戦後から今日に至るまで,顕著な復興と発展を遂げてきたが,その間享受してきた平和と繁栄が,国家の安全の基礎の上に実現してきたことは言うまでもない。安全保障に万全を期することは,国民の生命・財産を守り,国家の独立を維持するための必要不可欠な条件であり,外交の基本的課題でもある。
日本を取り巻く国際情勢は,極東地域におけるソ連の一貫した軍備増強とその活動の活発化,朝鮮半島での緊張の継続などに見られるように厳しいものがあり,我が国として安全保障の確保のため,より一層の努力が肝要である。
我が国の安全は,当然のことながら,周辺の国際環境が平和で安定していることに大きく依存している。この章で述べた諸般の積極的外交努力も,究極的には平和で安定した国際環境を築くことを目指すものであり,今後ともそのために絶ゆまざる努力を積み重ねていかなければならない。
同時に,今日の国際社会の平和が,基本的には力の均衡と抑止の上に成り立っていることは冷厳な現実であり,我が国は,自由と民主主義という基本的価値観を共有する米国との安全保障体制の堅持と,節度ある有効な防衛力の整備を通じて安全の確保に努めている。
(ロ) 我が国の安全の確保にとり米国の抑止力は不可欠であり,日米安全保障体制は国の安全保障の基盤である。従ってこの体制を円滑かつ効果的に運用し,その信頼性を高めるため絶ゆまぬ努力を行うことは極めて重要である。
かかる観点から,我が国は,米国との間で緊密な協議を続けるとともに,日米防衛協力のための指針に基づく研究の推進,共同訓練の実施,対米武器技術供与の枠組みの整備等の日米防衛協力を推進している。また,日米安全保障体制の基礎を成す米軍の駐留が,円滑かつ効果的なものとなるよう,施設・労務の両面で在日米軍駐留に対する支援を強化させるとともに,空母艦載機の夜間着陸訓練場の確保,米軍家族住宅の建設及び米軍艦船の寄港についても地域社会の理解を得るべく努力してきている。本年6月には,在日米軍従業員の労務費追加負担を可能とする在日米軍労務費特別協定が締結されたが,これにより,同従業員の安定雇用とともに,在日米軍の効果的活動の確保が図られることが期待されている。
さらに,86年9月,政府は現在米国の進めている非核の防御システムによって弾道ミサイルの無力化を図る戦略防衛構想(SDI)の研究への参加に関する決定を行い,現在,参加が円滑に行われるよう具体的諸措置について米国と協議を行っている。
(ハ) 日米安全保障体制の堅持とともに,自らの防衛力を保持することも極めて重要である。我が国は,平和憲法の下,専守防衛に徹し,他国に脅威を与えるような軍事大国にならないとの基本理念に従い,文民統制,非核三原則を堅持しつつ,節度ある有効な防衛力の整備に努めてきている。そして現在,防衛計画の大綱に定める防衛力の水準の達成を図ることを目標とする中期防衛力整備計画の着実な実施に努めている。その防衛力は,日米安全保障体制とあいまって,国の安全の確保に不可欠であるのみならず,結果的に自由民主主義諸国全体の安全保障の維持に寄与し,アジアひいては世界の平和と安定にも貢献していると言えよう。
(5) より世界に開かれた日本の実現
(イ) 近年,我が国の大幅な経常収支黒字を背景として,諸外国との経済摩擦は厳しさを増しているが,相互依存の深まった今日の国際社会では,繁栄も苦難も共に分かち合うべきであり,自分の利益のみを追求するという自己本位の行動をとることは許されない。
また,最近は日本人の意識や行動に傲慢さが見られるとの指摘も見られるが,異なる文化や価値観を受け入れ,多様性を尊重するという謙虚さなくしては,我々自らを高めていくことも各国からの信頼を得ることもできない。さらに,偏狭なナショナリズムが高まることとなれば,国際社会からの孤立化を招くことになろう。
我が国は,古来,朝鮮半島,中国などから様々な文化を採り入れ,明治の開国後も,欧米諸国の諸制度等を採り入れてきた。また,第二次大戦後,日本は貿易立国を目指して,積極的に海外から技術を導入しつつ,輸出の拡大と企業の海外進出を図ってきた。このように,我が国は古代から他国の優れた文化・技術を採り入れたり,熱心に海外進出を行ってきたが,他方,日本から外国に向けての文化や情報の発信は,その流入に比し弱く,また,外国からの人や物の受け入れの面においても,まだまだ不十分であると言わざるを得ない。
これら人的往来,貿易,文化など様々な分野における「出」と「入」の不均衡な状況は,我が国の貢献及び国際社会との調和の観点から是正すべきであると言えよう。そのためには,国として社会としてのおおらかさと包容力を備えるべく,各分野における諸改革を国際的視野から大胆に推進し,経済・社会面の制度や慣習,さらには我々の意識をより世界に開かれたものにしていくことが重要である。
(ロ) 我が国が経済・社会面での閉鎖性を克服していく過程においては,国内の様々な分野に少なからぬ影響が及び,場合によっては短期的に相当の犠牲を払わざるを得ないことも事実である。しかし,外からの異なる人や物及び価値観を受け入れることは,国際社会に対する我が国の責務であると同時に,我が国経済・社会を活性化させ,中長期的な繁栄を確保する上で不可欠な要素と言え,さらに,国民一人一人の生活を豊かにし,自らが国際社会の一員であるとの自覚を深めることにも寄与するものと考えられる。
また,一部には日本の国際化が,我が国自身の文化的・社会的特質を損うものではないかとの懸念があるが,より世界に開いていくことは,日本がその優れた伝統と近代化において発揮した長所を維持・発展させる一方我々の行動・社会規範を世界に向けて一層普遍的な価値を有するものに変えていく,まさにその過程と言えるのではないだろうか。
より開かれた日本を実現するための分野は,広範にわたっており,ここ数年経済面等で進展を見せているものの,多くの改善すべき余地が残されている。政府及び民間が相携えて,今後ともその動きを一層促進させていくことが肝要であろう。
また,制度や慣習を改善するとともに,国民一人一人が意識を変革していくことが何よりも重要である。そのためには,国内のあらゆるレベルで諸外国との相互理解を図り,国際交流を深めていくことが必要である。その意味で近年,地方自治体,民間団体などにおいて,人物交流,国際的行事の開催等の対外的活動が活発化していることは歓迎すべきことである。
(ハ) 他方,欧米諸国やアジア諸国などにおいて,我が国の映画・服飾・音楽・建築デザイン・日本食などが受け入れられつつあり,現代日本についてのイメージの形成に寄与している。また,特に欧米においては,歌舞伎・相撲等の公演の成功などを通じ,伝統的文化に対しても従来以上に理解が深まっており,さらに近年海外の日本語学習者も著しく増加している。このように日本文化は,以前にも増して普遍性を高め,諸外国から多くの関心を集めつつあり,我が国としては,その高まる関心に一層積極的に応えていくべきである。その際,日本の国際化が,諸外国とりわけ近隣諸国の文化・社会発展等に及ぼす影響についても十分配慮しなければならない。
他方,諸外国との関係において,未だ相互理解の不足に基づく誤解が多く見られ,我が国に対する認識のずれが,様々な摩擦の大きな要因となっていることが指摘されている。諸外国との相互理解と友好関係を促進するため,青少年交流,留学生交流,国際問題研究等をはじめとする文化交流,及び広範な広報活動を一層促進することが重要である。また,高度情報社会の到来を迎え,高度通信システムの利用等を通じ,情報発信能力を強化していくことも必要である。
現在,世界は,21世紀を担う新しい世代が人類の歴史的遺産を引き継ぎつつ,豊かな未来を実現し得るか否かという,極めて重要な時期を迎えている。このような国際社会の現状にあって,その影響力と果たすべき役割を著しく増大させている我が国は,今まさに,責任ある国家への歴史的な転換期を迎えていると言えよう。