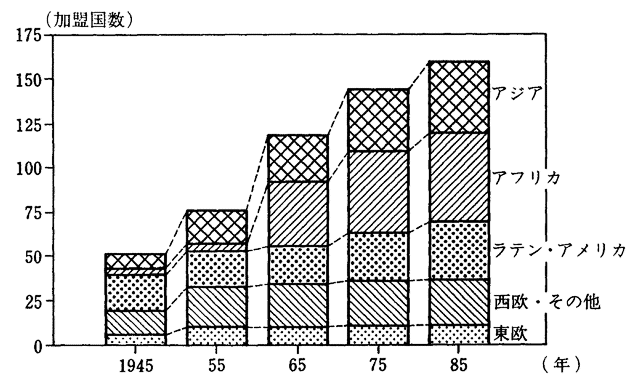
第4節 国際連合の諸活動に対する協力
1.創立40周年を経た国際連合(国連)
(1)国連は,国際の平和と安全の維持及び諸国民の経済的・社会的・文化的・人道的発展を目的とする国際協力促進を図るための最も普遍的な国際機関である。
1945年に誕生した国連は85年創立40周年を迎えたが,この間,加盟国数が当初の51か国から159か国に増大した(図1)のみならず,その活動も国際政治経済情勢の変化に伴い非常に広範囲にわたるものとなり,規模・機能の両面ともに普遍的国際機関の名にふさわしい成長を遂げた。
10月,創立40周年記念会期が国連にて開催され,我が国を代表して中曾根内閣総理大臣が記念演説を行った。
(2)他方,国連の現在の姿は国連憲章にうたわれた理想とは程遠いとの批判が根強くあることも事実である。
図1:国連加盟国数の地域別推移
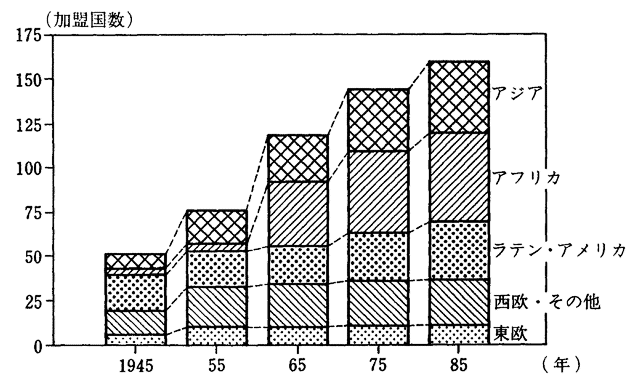
第1に,国際の平和と安全の維持に関し,国連憲章の起草者が想定した,安全保障理事会を中心とする集団安全保障体制が,東西冷戦を背景として機能していないとの点があげられる。
第2に,先進国中心の国際経済体制の変革を主張する途上国の動きにより,70年代に入って「新国際経済秩序」の概念が導入され,途上国側の多数の力によって,現実離れした議論が展開されるとの事態が生じた。
第3に,最近のユネスコ問題に代表される過度の政治化傾向や機構の肥大化という国連システムに内在する問題が顕在化してきており,加盟国が厳しい財政状況に直面している今日,国連に対する諸国民の信頼が揺らぎ始めている。
(3)このような批判に対し,国連としても解決のための現実的方途を模索し続けている。また,徐々にではあるが,国連の抱える問題はとりもなおさず加盟国自身の問題でもあるとの意識が芽生えつつあり,理由のない楽観視はできないのと同様,過度の悲観視,もしくは国連不要論も当たっていないと言えよう。
たとえば,国際の平和と安全の維持に関しては,当初の集団安全保障構想にかわり,国連のプレゼンスが領域国の同意を得て紛争地域に介在し,停戦の監視,武力衝突再発の防止にあたるという「平和維持活動(PKO)」構想が登場した。同構想は中東地域を中心に紛争の再発・拡大防止のため
図2:主要国の通常予算分担率の推移

(*)ウクライナ,白ロシアを含む。
重要な役割を果たしており,国際社会の現実に定着してきている。また,紛争の解決に際し,総会・国連事務総長がより重要な役割を果たしつつある。
次に,経済問題に関しても,途上国側に表決による決議の採択自体に意味はなく,問題解決には先進国を含む関係国すべての同意が必要であるとの認識が深まりつつあり,決議採択に際し「コンセンサス方式」が用いられることが近年増加していることにも,それがよく表われている。
さらに,国連組織に内在する問題についても,事務局・加盟国が相互に協力して財政の引締めや機構の活性化を図るべきであるとの気運が高まっ
図3:国連機関に対する財政的寄与率(*1)
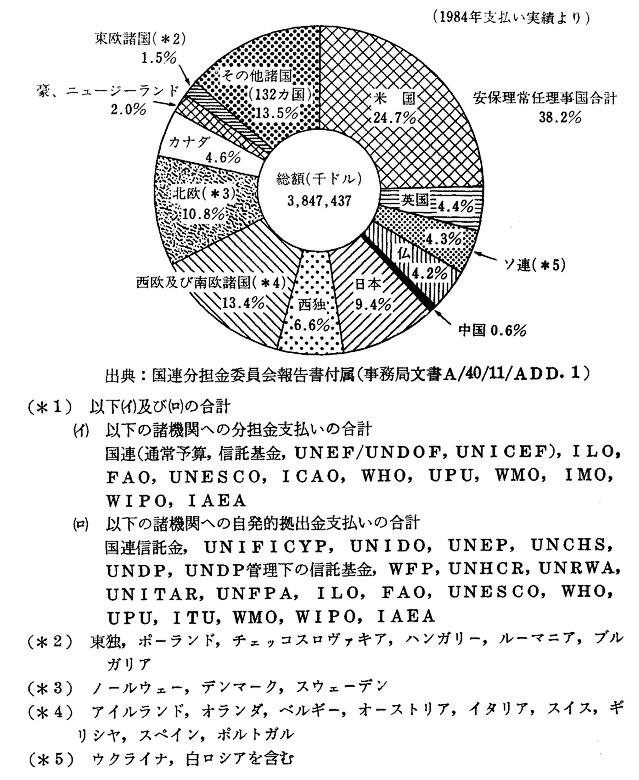
てきており,85年の第40回国連総会においては,各方面より具体的提案が相次いだ。
(4)国際的な取組みなしには解決し得ない問題が多々生じてきている今日,普遍性を備えた国際組織としての国連の存在それ自体が,今や国際社会の
図4国連機関に対する財政的寄与(1983~84年支払い実績)
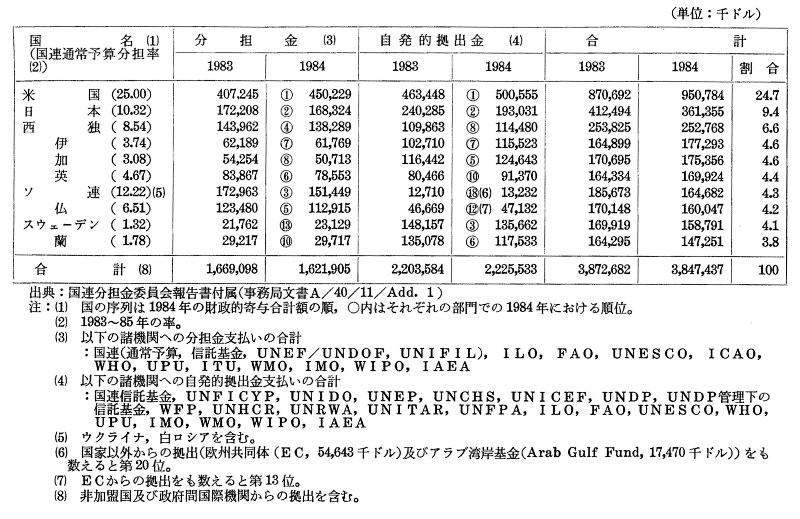
共通利益になっていると言える。国連がその機能を強化し,諸国民の期待と時代の要請に応えて行くためには,国連自身と加盟国による努力を,長期的観点から一層推進して行くことが必要であろう。
2.我が国と国連
(1)我が国は1956年の国連加盟以来一貫して国連を通じての国際協力を重視しており,米国に次ぐ第2位の大口財政負担国に成長した今日(図2)国連の再活性化のために果たすべき責任は大きい。
(2)そのために我が国が緊急に取り組むべき課題として,国連の行財政改革がある。限られた資源を有効に利用し国連の組織としての効率性を高め諸国民の期待に応えるよう努力することが急務であるとの観点から,安倍外務大臣は第40回国連総会において「国連効率化のための賢人会議」設置を提唱した。本件決議案は85年12月,コンセンサスで採択され,86年2月,「賢人会議」第1回会合が開催され発足した(メンバーは18人。我が国よりは斉藤元国連大使が参加)。同会議は今後,効率の改善,予算及び資金手当,実施確保措置等につき討議を重ね,第41回総会開会までに,総会に対し勧告を提出することになっている。未曾有の財政危機に際し国連の行財政問題が注目を集める中,各加盟国とも,「賢人会議」が具体的成果をあげることを強く期待している。
(3)他方,国連の諸活動に対し我が国が今後一層の協力を行っていくためにも,国連機関に,より多くの日本人職員が採用されるよう働きかけを強化していく必要がある(国連事務局に勤務する日本人職員は,85年末現在で122名であり,国連通常予算の分担率等を基に設定されている我が国の望ましい職員数171~232名を大幅に下回っている)。