
第1章 我が外交の基本課題
-国際社会への積極的貢献と一層の国際化の推進-
1.はじめに
今日,科学技術の著しい進歩による情報通信・交通手段の発達に伴って,太平洋,大西洋などで隔てられた世界は一体化し,人的・経済的交流や情報の流れも地球的規模で飛躍的に増大した。その結果,一地域の政治・経済・文化の動向が他の地域に与える影響はますます大きくなっている。
国際社会の相互依存関係がこのように深化する状況の下,国際政治・経済の枠組みにも質的・構造的変化が生じている。米ソ両国が,圧倒的な軍事力を背景として,世界の平和と安定にとり依然決定的な影響力を有しているこ
世界のGNPに占める主要国の割合(1984年)

とは事実である。しかし,同時に,西欧・日本の相対的地位の向上,中国の対外開放政策の推進,アジア・太平洋地域の著しい発展,第三世界の発言力の増大といった国際社会における構造の変化も進行している。さらに,二度の石油ショックや新技術の導入による経済構造の変化,高度情報社会の到来などによる国際社会の質的変化に伴い,ガット,IMFなどを中心とする国際経済システムは,新たな対応を迫られつつある。
戦後,我が国は国民の絶えざる努力と恵まれた国際環境によって未曾有の経済発展を遂げ,今や世界第二位に迫ろうとする経済力と世界有数の対外資産を持つに至った。
主要国の対外純資産残高
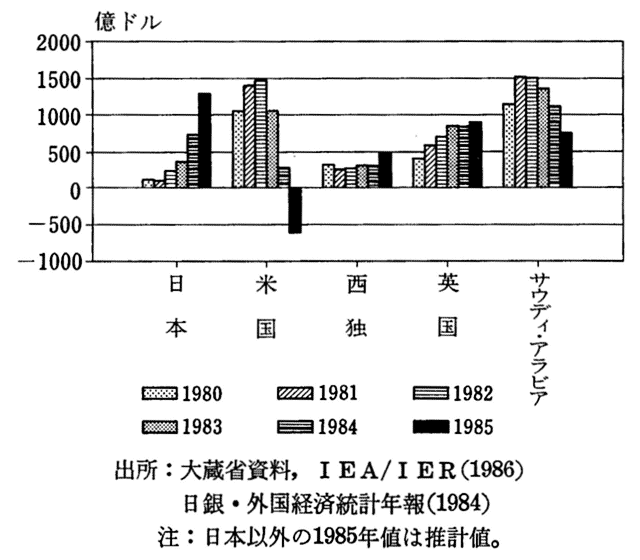
我が国が今日銘記すべきは,我が国が,特に経済の分野において,我々が意識している以上に大きな国際的影響力を持つに至っていることである。その結果,我が国が国際経済システムの円滑な機能を維持していく上で果たさなければならない役割と責任も著しく増大した。
さらに,我が国の国際社会における地位の向上に伴って,我が国が果たすべき政治的役割と責任も増大しつつあり,世界の平和と繁栄の維持のために積極的に貢献することは,我が国の重大な国際的責務となっている。
今や,国際社会との調和を図ることなくして,我が国の平和と繁栄の存続はあり得ず,我が国が,世界的視野に立ち,自ら積極的に一層の国際化を推進し,世界に開かれた日本を実現することは,我が国の重要な課題である。
2.我が国の基本的立場
我が国は,世界の平和と繁栄のために積極的に貢献する外交を推進するに当たって,政治的・経済的理念を共有する自由民主主義諸国の一員としての立場と,地理的・歴史的・文化的に緊密な関係にあるアジア・太平洋地域に属する国としての立場を基本としてきた。
(1)自由民主主義諸国の一員としての外交
我が国は,今日,安定した民主主義国の一つとしての地位を確立し,自由と平和及び繁栄を享受している。このような平和と繁栄は,自由・民主主義及び市場経済という価値観を共有する米国及び西欧諸国を中心とした自由民主主義諸国との政治的・経済的協力なくしては,実現し得なかったものである。我が国として,今後ともこれら諸国との協力関係を一層強化しつつ,我が国外交を推進していくことが肝要である。
日米安全保障条約は我が国の安全保障の基盤であり,米国との緊密な協力関係は我が国外交の基軸である。この安全保障体制の円滑かつ効果的運用を確保し,その抑止力の信頼性を高めることは,我が国の自衛力の着実な整備とあいまって,我が国の安全にとって不可欠である。
現在の日米関係は,貿易の不均衡などをめぐり,経済分野で難しい局面もあるが,全般的に良好な状態にある。日米関係を揺るぎない基盤の上に置くため,今後とも,米国との政治・経済・文化・科学技術を含めた広範で奥深い緊密な協力関係を一層増進することが重要である。
米国と並んで自由民主主義諸国の重要な柱である西欧は,その経済的・政治的統合に向けて努力し,新たな活力を発揮しつつある。我が国は,西欧諸国との間にも経済問題を抱えているが,これら諸国との関係を,経済のみならず,政治・文化・科学技術などの分野でもより緊密なものにしていくことは,自由民主主義諸国全体の発展のためにも重要な意義を持つものである。
こうした自由民主主義諸国との協力関係を一層緊密化する上で,政府・民
世界の輸出に占める主要国の割合
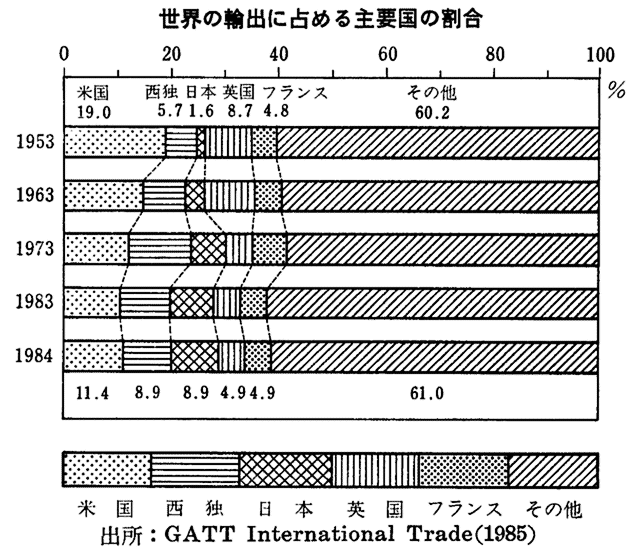
間のレベルで進められている種々の対話と政策協議はますます重要となっている。
世界経済のインフレなき持続的成長を達成し,為替相場の安定を図るため,我が国と同じく市場経済原則に基づく経済運営を図る諸国との間で政策
世界の一入に占める主要国の割合
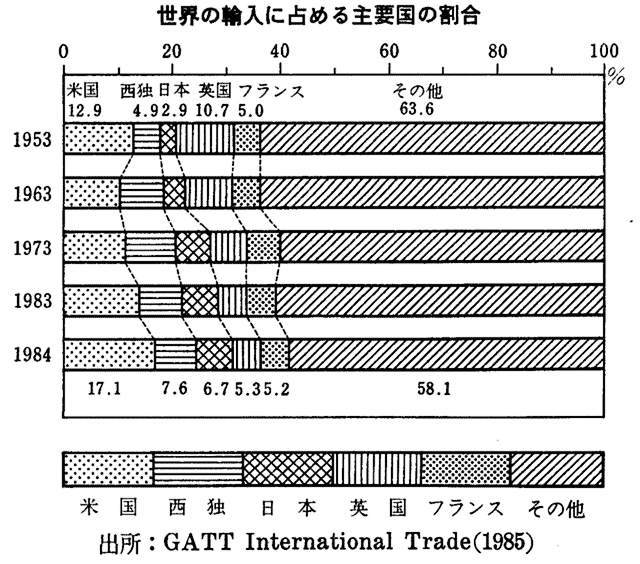
協調を図ることは,極めて重要である。この意味において,OECD,IMF等の国際機関と並んで主要先進民主主義諸国の指導者が一堂に会するサミットの果たす役割は大きい。
86年5月東京で行われたサミットでは,より安全かつより豊かで,自由かつ平和な世界の実現のために各国が協力することの重要性を強調した「東京宣言」,世界経済の持続的成長のための政策協調の強化,世界的視野からの構造調整の推進,保護主義の防圧と新ラウンドの早期発足,開発途上国に対する支援などをうたった「東京経済宣言」などが採択され,サミット参加国間の協力と協調が確認された。
(2)アジア・太平洋地域の国としての外交
近年,アジア・太平洋地域は,全体として世界で最もダイナミズムに富み,顕著な発展を遂げてきており,将来の発展に向けて大きな潜在力を持つ地域として注目を集めている。我が国が,民族的・歴史的・文化的側面などで多様性に富むアジア・太平洋地域の特色を踏まえながら,この地域の平和と繁栄に寄与することは,この地域を重要な構成要素とする世界全体,ひいては我が国の安全保障と繁栄にとって不可欠である。
この地域の諸国との関係を推進するに当たって,我が国として,歴史とその教訓に学ぶという我が国の対アジア外交の原点を踏まえた平和・友好の関係を増進することが重要である。その意味で,国と国との関係のみならず,人と人とのつながり,心と心の触れ合いを大切にした外交を展開し,相互理解を深めることが肝要である。
この地域における我が国の外交努力の主要な課題は,域内諸国との友好協力関係を引き続き増進し,その経済・社会的な安定と発展に寄与し,地域の平和と安定を確保するための努力を進めることである。86年6月のASEAN拡大外相会議において安倍外務大臣は,このような我が国の対アジア政策を次の三本柱に集約して表明した。
(あ)平和国家としての日本の貢献
(い)間断なき対話と,心と心のふれ合いを通ずる相互理解の促進,及びこれによる相互信頼の確立
(う)変動する情勢に効果的に対応するASEANと日本の協力関係の確立
中国との友好協力関係は,アジアのみならず世界の平和と安定にとって肝要であり,長期にわたって維持・発展させていかなければならない。韓国との間では善隣友好協力関係を一層推進するとともに,南北間の対話促進とソウル・オリンピックの成功などに積極的に協力することが重要である。
ASEAN諸国については,その安定と発展のための努力を一層支援することが重要であり,特に,フィリピンに対して,その新政権が国内の諸改革を円滑に進めながら,安定化の基礎を築こうとする努力を出来る限り支援することは緊急な課題である。また,カンボディア問題の包括的政治解決へ向けてのASEAN諸国の和平努力を支持していくことも重要である。
さらに,近年アジアと政治的にも経済的にも関係が緊密化している大洋州諸国との友好協力関係の一層の増進を図っていくことも重要である。
ダイナミックな経済成長を示してきたこの地域においても,85年に入り,輸出の不振,一次産品価格の低迷などの要因から,経済成長に陰りを見せた国が多く見られた。我が国としては,民間直接投資と技術移転の促進による新しい分業関係の樹立と製品輸入の増大を始めとする貿易の円滑な拡大を図るとともに,経済・技術協力を促進し,各国の経済発展と民生向上に寄与することが引き続き重要な課題である。
さらに,我が国は,二国間の枠組み及びASEAN拡大外相会議などの場における協力に加えて,各種民間レベルにおいて進められている太平洋協力に積極的に貢献している。こうした地域協力の努力が,21世紀に向けて,この地域の発展を一層促し,ひいては世界の繁栄にも寄与していくことが期待される。
3.日本外交の課題
(1)世界に開かれた日本を目指して
相互依存関係の深まった今日の国際社会において,以前にも増して,自国の利益のみを追求するという自己本位な行動は許されず,また,一国だけが繁栄することも不可能となっている。各国それぞれが国際社会の責任ある一員として,国内の施策の実施に当たって,国際社会との調和を図ることが強く求められており,このような意味の国際化を一層推進し,我が国を真に世界に開かれたものとしていくことは,我が国にとって緊急の課題である。
我が国においては,今や,人的往来・貿易・金融などの面で海外に積極的に進出するという意味においての国際化は相当に進んでいると言える。
また,明治維新以来,海外の文物を取り入れるという課題にも,我が国は,総じて積極的に取り組んできた。しかし,国際社会における位置付けが高くなってきた今日,世界の平和と繁栄のシステムを維持し発展させるため,たとえそうすることが当面の利益と結びつかない場合であっても,主体的に,かつ,率先して,その責任と費用を負担することが強く求められている。
同時に,相互依存の深まった今日の国際社会における我が国の重さが増すにつれ,我が国の社会と経済を外に向かって開くことが,我が国の発展のため必要であり,また,そうすることが世界経済の健全な成長のためにも不可欠である。
我が国の経常収支黒字は85年約500億ドルにも達し,我が国と諸外国との経済摩擦は厳しさを増している。このような状況が続くことは,諸外国との関係で極めて深刻な事態と言わざるを得ない。我が国としては,自国が世界経済に占める重要な地位と責任を自覚し,国際経済環境とより調和した経済社会の実現に向けて積極的に努力していくことが急務である。こうした努力は,我が国経済の持続的成長の基盤を培う上でも必要である。市場アクセスの改善,内需の拡大などを通じ輸入の増大を図ることは,国民の選択の幅を広げ,また,国際的に自由・無差別な競争を貫くことは,経済の効率化・活性化を促すものである。国際分業の進展に即した経済構造の改革も,中長期
主要国の貿易収支
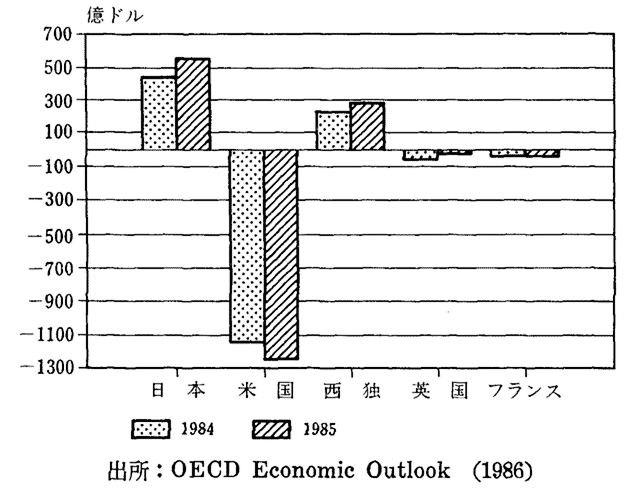
的観点から我が国経済の活力を保っていく上で不可欠の課題である。こうした努力は種々の国内的困難を伴うものではあるが,これを克服することにより,将来にわたり我が国の経済の安定的発展が確保できるのである。
このような世界に開かれた日本を目指す上で肝要なことは,国際化を推進することは我が国自身の社会的・文化的特質,とりわけ同質性の高い我が国民の長所と美点を損うものではないことを正しく認識することであり,そのために,我が国自身の特質を的確に理解し,より世界的視点に立って,国として,社会としてのおおらかさと包容力を身につけることである。
我が国の伝統や社会のあり方に基づくものとしてこれまで許容されてきた制度や慣行についても,我が国がその国際的地位と役割にふさわしい国際性・普遍性を得ることによって国際的な協調を図り,諸外国との交流,特にその受け入れにおいて一層の国際化を進めることが必要となっている。これらの根底にある外からの異質なものを受け入れるという意識の面における国際化,言わば「内なる国際化」が重要となっている。
このような国際化を推進するに当たっては,地方自治体,民間などあらゆるレベルで,諸外国との正しい相互理解を図り,これを深め合うとともに,国際交流や国際協力活動を展開していくことが重要な課題である。近年,地方自治体,民間団体などの国際化への関心が高まり,その対外的な活動が活発化していることは歓迎される。これまでの大阪及び北海道への担当大使の出張や「一日外務省」などの開催に加え,最近,「国際化相談センタ,の設置,地方自治体との人事交流の拡大など一連の措置がとられているが,今後とも国際化に対する地方の熱意と活力を積極的に支援していくことが肝要である。
(2)世界の平和と安定への積極的貢献
世界の平和と安定の確保は今や人類共通の悲願であるが,現実には核戦争の脅威,地域紛争,頻発する国際テロなど,依然世界の平和と安定を脅かす不安定要因が数多く存在している。国際社会の責任ある一員として,これら諸問題の解決に向けて積極的な貢献をしていくことは,我が国の外交の重要な課題である。
(イ)東西関係
世界の平和と安定にとり基本的な要素である東西関係,とりわけ米ソ関係については,その安定化のため絶えざる努力が払われなければならない。
その意味で,85年11月,米ソ首脳会談が実現し,両国間の相互理解が深められたことは有意義であったが,11月の合意に従って第2回首脳会談が早期に実現され,軍備管理交渉の進展と束西関係の安定が図られるよう,我が国としても働きかけていくことが重要である。
また,自由民主主義諸国が,抑止力を維持しつつ,東西間の力の均衡をできる限り低い水準で安定させるよう努力することは,安定的な東西関係を構築する上で重要である。このような観点から,我が国は,米ソ軍備管理・軍縮交渉などの軍備管理交渉が実効ある成果を上げ,グローバルな解決が行われるよう,米国を始めとする自由民主主義諸国と緊密な協議を行うとともに,日ソ外相会談などの機会をとらえて,ソ連がこれらの交渉に真剣かつ建設的態度で臨むよう引き続き呼びかけている。
我が国は,従来から国連,軍縮会議などの場において核軍縮を中心とする軍縮の促進に積極的に貢献してきており,今後とも,核実験の全面禁止,核不拡散体制の維持・強化,化学兵器禁止の早期実現などを目指し,より一層の努力を払うことが内外から期待されている。
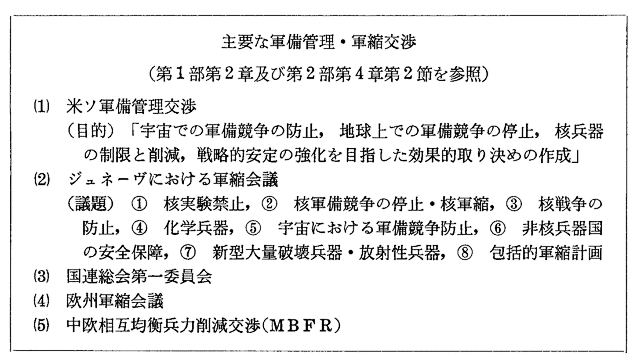
我が国自身が,東側諸国と対話を促進していくことも重要である。86年1月,シェヴァルナッゼ=ソ連外相が訪日して,8年振りに日ソ外相間定期協議が開催され,領土問題を含む日ソ平和条約交渉が再開された。5月には安倍外務大臣がソ連を訪問し,シェヴァルナッゼ外相との間で,1月に再開された領土問題を含む平和条約交渉を継続するとともに,ゴルバチョフ書記長とも会談して,両国間の対話の定着に努めた。しかし,北方領土問題は依然未解決であり,我が国としては,領土問題を解決して平和条約を締結し,日ソ関係を真に安定した基盤の上に置くという不動の方針を貫き,今後とも粘り強い努力を続けていくことが肝要である。
(ロ)地域紛争
現在,世界各地では地域的な紛争や緊張・対立状態が存在している。朝鮮半島,カンボディア問題,アフガニスタン問題,イラン・イラク紛争,中東和平問題,中米,南部アフリカなどにおける対立は,未だ地域的なレベルに留まっているが,米ソ両大国の直接の対立にエスカレートする危険性をはらんでおり,世界の平和にとり大きな不安定要因となっている。
我が国としても,これらの紛争や対立の拡大の阻止と早期平和的解決のため,我が国としてなし得る限りの努力を続けていくことが重要である。
特に,アジアにおける紛争と緊張は,我が国の平和と安全に大きな影響を与えるだけに重視すべきであり,我が国は,朝鮮半島における南北対話の動きを歓迎し,半島における永続的平和の実現のための環境造りに努め,また,カンボディア問題については,問題解決のための4原則を明らかにし,共存のための対話を訴えるなど,和平への環境醸成に寄与すべく積極的努力を続けている。
(ハ)国際テロ
近年,無辜の一般市民をも巻き込むハイジャック・暗殺・爆破などの国際的テロ事件が頻発し,国家の関与が問題となるに至っている。国際テロは,市民生活の平和と安全を脅かす人間の尊厳に対する挑戦であるのみならず,民主社会と世界の平和への脅威として許すべからざることであり,その防止のための国際協力を一層強化することは緊急な課題である。このような見地より,東京サミットにおいて「国際テロリズムに関する声明」が発出された。
また,海外に滞在している邦人が安心して活動できるよう,緊急時にこれら邦人を保護することも,これまで以上に重要になっている。
(ニ)国際的協力
国際連合は平和のための国際協力の組織として創立されて以来,40周年を85年迎えたが,これまで地域的な平和維持活動,開発途上国の発展など多くの分野で一定の成果を収めてきた。しかし,その国際平和維持機能については依然所期の目標を達成するに至っておらず,また,国連機構の肥大化・非能率など多くの問題点が指摘されている。
我が国が,米国に次ぐ第二の財政負担国として,国連の行財政改革の推進を積極的に働きかけ,その活性化を図ることは,国連を将来にわたって有効な国際協力の機構として維持していく上で極めて重要である。この意味で,85年,安倍外務大臣の提唱に基づき設置された「国連効率化のための賢人会議」は,我が国の国連における積極的態度の表れである。86年は我が国の国連加盟30周年であるとともに,国際平和年でもある。我が国として,世界の平和と繁栄のために国連などを中心に積極的な多数国間外交を推進していく必要がある。
また,86年4月,ソ連でチェルノブイリ原子力発電所の事故が発生し,事故直後の東京サミットで,原子力の安全性確保のための国際的協力の重要性に関する声明が発出された。国境を越えて多くの国に影響を及ぼしたこの事故は,原子力の平和的利用について世界的観点からの国際協力の重要性を再認識させるものであったと言えよう。
我が国は,85年後半のメキシコ地震,コロンビア火山噴火の大災害を契機として緊急救助隊の創設を含む国際緊急援助体制の整備を進めてきた。被災国に対するこのような積極的・能動的な支援の推進も,我が国の国際的協力を真に有効で評価されうるものとしていく上で重要である。
(3)世界の繁栄と発展のために
世界の貿易,投資,金融などにおける我が国の影響力の増大に伴い,我が国が国際経済システムの維持において果たす役割も否応なく増大している。
我が国が,単に自国の利益だけでなく,広く国際経済全体の円滑な機能を考えて行動することが,我が国のみならず世界の繁栄と発展にとっても不可欠である。
(イ)世界経済の健全な発展への貢献
85年,世界経済は景気拡大3年目に入り,インフレの鎮静化,金利の全般的低下,先進国の成長見通しの改善など,明るい動きが見られた。
しかし,同時に,我が国の大幅な経常収支黒字を背景として,諸外国との経済摩擦が一段と厳しさを増した。また,世界経済は,財政赤字,経常収支不均衡,深刻な雇用情勢,増大する保護主義的圧力など引き続き多くの問題を抱えているほか,為替レートや石油価格の動向など先行きの不透明さも存在している。
このような状況の下,東京サミットにおいて,参加国首脳及びEC代表は,忌憚のない意見交換を行い,インフレなき経済成長の達成,為替レートの安定などを目的とした各国の政策協調の一層の強化と,構造調整の推進の重要性を確認する「東京経済宣言」を発出した。また,この宣言では,一次産品への依存度の高い開発途上国の輸出の必要性への配慮が指摘されるとともに,アフリカの経済復興開発努力への協力の継続も表明された。
今日の世界経済にとって,最も緊要な課題は,世界中で蔓延しつつある保護主義を防圧し,自由貿易体制の維持・強化を図ることである。そのためには,各国が自主的に市場の開放・アクセスの改善を図るとともに,現在準備作業が進められている新ラウンドを成功させることが不可欠である。我が国として,引き続き新ラウンド交渉の86年9月開始に向けて積極的に準備作業を推進するとともに,同交渉が実り多いものとなるよう全力を尽くすことが重要である。
我が国は,85年7月「市場アクセス改善のためのアクション・プログラム」を決定した後,その繰り上げ実施に努めるとともに,円高の定着,民間活力の活用などを通ずる内需拡大にも大きな努力を払ってきた。
また,86年4月に発表された「国際協調のための経済構造調整研究会」の提言を受けて5月に決定した「経済構造調整推進要綱」にもあるように,内需主導型の経済成長の達成,国際的に調和のとれた産業構造への転換などに積極的に努力することが,国際協調を促進する上で極めて重要である。
さらに,相手国の雇用を創出し,経常収支不均衡の是正にも寄与するため,海外への直接投資を一層促進することも必要である。
国際通貨問題については,85年9月の5か国蔵相会議(G-5)を契機として政策協調による為替レートの是正に成果が見られたが,その後86年4月のIMF暫定委,5月の東京サミットなどの場で各国の政策の多角的監視(サーベイランス)の強化が合意された。我が国としても,こうした国際協調の努力に対し積極的に参加していくことが重要である。
我が国は,今日,ロボット,新素材,バイオ・テクノロジー等の先端技術においても世界有数の水準にある。政府間の科学技術協力,投資に伴う技術移転,並びに企業間の技術提携などを通ずる科学技術分野での我が国の積極的な協力は,21世紀に向けての各国の新しいニーズに応える上で重要であり,世界経済の活性化にも寄与しうるものである。
(ロ)開発途上国の安定と発展への協力
開発途上国の経済・社会開発に対する協力は,単に人道的観点から重要であるだけでなく,当該国・地域の安定と発展に貢献し,ひいては世界の平和と繁栄にも資するものである。このような協力の推進は,世界第2位に迫る経済力を有し,平和国家であり,かつ,対外依存度の高い我が国にとって最もふさわしく,重要な国際的責務である。
現在,開発途上国の多くは,累積債務問題,一次産品価格の低迷,経済成長の鈍化などの経済的諸困難に直面している。また,世界には未だ一千万人を超える難民がおり,さらに,アフリカを中心として多くの国が飢餓・旱ばつなどの問題に悩まされている。
このような状況の下,我が国としては,開発途上国に対し政府開発援助(ODA)を引き続き着実に拡充し,85年9月に設定したODA第三次中期目標の達成に向けて一層努力することが必要である。同時に,厳しい財政事情に鑑み,効果的・効率的援助の実施がますます重要であり,我が国の援助が相手国の経済・社会開発と民生向上のため真に有効な支援となるよう,我が国としても可能な限り努力していかなければならない。
また,難民に対する資金・食糧援助などの支援,飢餓・旱ばつの抜本的克服に資する「アフリカ緑の革命構想」などの協力も,一層強化していかなければならない課題である。
同時に,援助だけではなく,開発途上国産品に対する市場の一層の開放,民間直接投資とそれに伴う技術移転の促進により新たな分業関係を
主要国の政府開発援助(ODA)(1985)
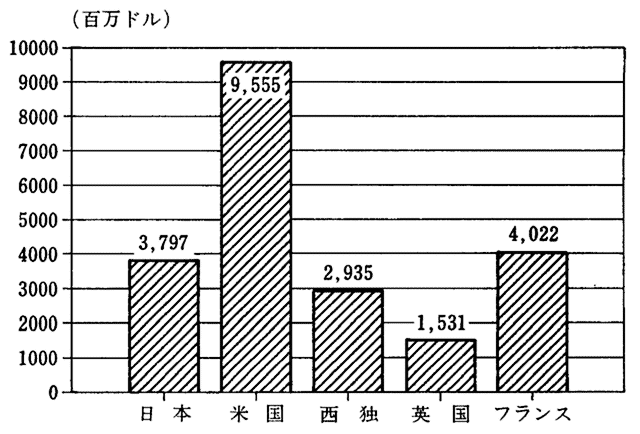
ODA対GNP比率(1985)
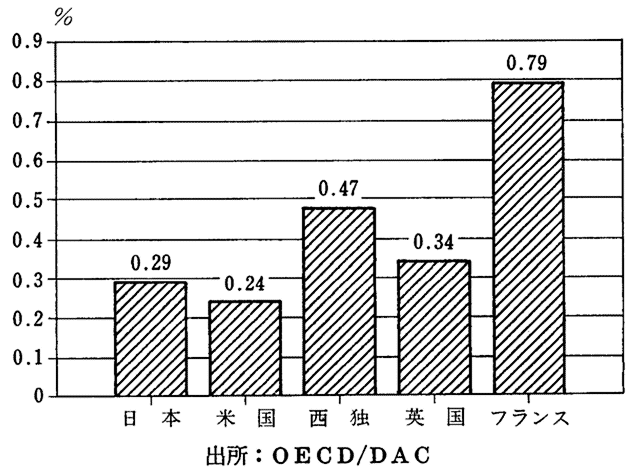
出所:OECD/DAC
築いていくことも極めて重要であり,開発途上国への我が国の協力を,このような総合的なものとしてとらえ,かつ強めていくことが従来以上に必要となってきている。
我が国は,基礎から応用に至るまで幅広い分野で秀れた技術を有しており,このような技術の移転に対する開発途上国からの期待は大きい。我が国として,今後とも途上国の人造りと国造りに寄与するため,政府ペースの技術協力を一層推進するとともに,民間の技術についても,相手国のニーズに応じ技術移転が進められるような環境を醸成していくことが重要である。
また,累積債務問題は,債務国の経済のみならず,国際金融にとっても大きな不安定要因となっている。特に,最近の石油価格の下落による石油収入の減少は,多額の債務を抱える一部の産油国の債務問題を一層深刻なものとしている。債務問題の解決に当たって,債務国の自助努力が必要であることは当然であるが,我が国としても関係債権諸国,国際機関などとの協力を積極的に進め,債務国支援を強化していくことが要請されている。
(4)安全保障の確保
国の安全保障を確保することは,外交の基本的課題である。また,国の安全に不安なきを期してこそ,平和と軍縮のための努力や世界の繁栄と発展のための活動を積極的に進めていくことが可能となるという意味で,安全保障の確保はすべての外交活動の前提条件であると言える。
今日の国際社会の平和が,究極的に力の均衡と抑止の上に成り立っていることは冷厳な現実である。我が国の平和と安全を確保するためにも,脅威の現実化を未然に抑止する不断の努力を行うことは当然である。我が国周辺地域におけるソ連の質量両面にわたる一貫した軍備増強とその活動の活発化に見られるように,我が国を取り巻く国際情勢は厳しさを増しており,我が国として安全保障の確保のため,より一層の努力が必要となっている。
我が国は,自由と民主主義という基本的価値観を共有する米国との安全保障体制の堅持と,節度ある有効な防衛力の整備,及びより安定した国際環境を構築するための積極的な外交努力の展開を通じて安全保障の確保に努めている。
まず第一に,我が国の安全保障にとって,あらゆる種類の侵略に対する米国の抑止力の持つ意義は依然として大きく,日米安全保障体制は我が国の安全保障の基盤である。この体制を円滑かつ効果的に運用し,その信頼性を高めることは我が国の安全保障にとって不可欠である。
このため,我が国は,米国との間で,防衛問題に関して緊密な協議を続けるとともに,「日米防衛協力のための指針」に基づく研究の推進,共同訓練の実施,対米武器技術供与の枠組みの整備などに代表される日米防衛協力を推進している。また,日米安全保障体制の基礎を成す米軍の我が国駐留が効果的なものとなるよう,空母艦載機の夜間着陸訓練場の確保や米軍家族住宅の建設について地域社会の理解を得るべく努力してきている。個人の自由と尊厳に立脚する民主主義を守り,繁栄した市民生活を確保していくことは,このような努力を通じて日米安全保障体制を維持することにより初めて可能となっている。
第二に,防衛力の整備について,我が国は,平和憲法の下,専守防衛に徹し,他国に脅威を与えるような軍事大国にならず,非核三原則と文民統制を堅持するとの方針の下に,節度ある有効な防衛力の整備に努めている。85年9月には,「防衛計画の大綱」に定める防衛力の水準達成を図る見地から中期防衛力整備計画を閣議決定した。我が国の防衛力整備は,日米安全保障体制とあいまって,我が国の安全の確保に貢献しているのみならず,結果的に,束西両陣営間の軍事バランス面において自由民主主義諸国の安全保障の維持に寄与するとともに,アジアひいては世界の平和と安全にも貢献している。
第三に,我が国の安全は,当然のことながら,我が国を取り巻く国際環境が平和で安定していることに大きく依存している。この章で述べた世界の平和と安定を求めての諸般の積極的外交努力も,究極的にはこのような平和で安定した国際環境を造る努力の一環であり,今後ともたゆまざる努力を積み重ねていかなければならない。
依然,多くの課題を含み流動的な現下の国際情勢の下で,来たる21世紀へ向けて,次の世代へ明るい希望を与え,より良い世界を構築するために,現在我が国が果たすべき国際的責務は重大である。
このような認識の下,我が国は,相互依存の深まった国際社会の責任ある一員として,積極的に一層の国際化を促進するとともに,創意をもって能動的に行動する外交を展開しなければならない。