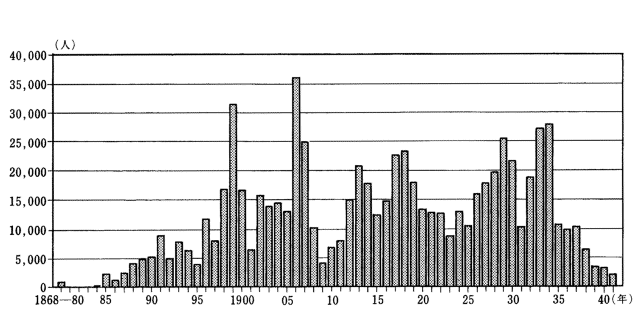
ダヘの移住は次第に制限されるようになっていった。
北米への門戸を狭められた我が国民の海外移住の流れは,その向きを南米,特にブラジルへ転じた。1908年6月サントス港へ到着した笠戸丸の781人を第一陣として,ブラジルヘの移住者は陸続と続き,その数は1941年までに約19万人に達した。
明治以降第二次大戦による中断までの間の邦人移住者の総数は,当時の満州への移住を除いても77万人を超え,地域別に見ると,北米地域(ハワイを含む)約37万人,中南米地域約24万人,東南アジアその他が約16万人となっている。
3.戦後における海外移住
第二次世界大戦による中断の後,我が国の海外移住は,1952年に,17家族54人のアマゾン移住をもって再開された。移住再開は,敗戦により半減した国土に閉じ込められて苦しい生活を余儀なくされていた我が国民の眼を再び海外に向かって開かせた。政府が移住者の大量送出を言わば国策として取り上げたことともあいまって,1950年代の我が国の海外移住の流れは,奔流とも言うべき勢いで,ブラジルからパラグァイ,ボリヴィア,アルゼンティンそしてドミニカ共和国へと拡大していき,年間移住者数は再開後4年目の55年には1万人を超え,その後も逐年増加を続けた。この時期の海外移住は主として農業移住であり,移住者は農業雇用者として既成の日系農場へ雇用されるか,又は後述の移住会社等が南米各地に設定した移住地に開拓農として入植したものである。
政府は,狭い国土に過大な人口を抱え,これらを労働力として吸収すべき産業の復興が未だ十分に進んでいなかったこの時期に,海外移住の推進を重要な政策として取上げ,種々の振興策を講じた。すなわち,55年に,移住者の募集,送出,渡航費貸付け等に当たる財団法人日本海外協会連合会(海協連)を設立し,次いで54年に移住地の購入・分醸及び移住者への融資に当たる日本海外移住振興株式会社(移住会社)を設立して,移住者に対する援護・支援を強化した。海協連及び移住会社の業務は,その後63年に設置された海外移住事業団の事業に発展的に吸収され,更に,74年設置された国際協力事業団に継承されて現在に至っている。政府は,また,海外移住に関する重要事項を審議する諮問機関として海外移住審議会を55年に設置した。移住先諸国との関係においても,ボリヴィア(56年),パラグァイ(59年),ブラジル(60年)の各国と移住協定を結び,これらの諸国への移住を安定した軌道へ乗せるとともに移住者保護の強化をはかった。
57年の1万6,620人を戦後の最高に,55年以降1万人台を維持してきた移住者数は,我が国経済の安定とそれに伴う雇用の拡大にしたがって減少し始め,62年には1万人を切り,近年においては年間3,000人前後で推移している。また,移住の形態も最近は中南米への農業移住に代わって,カナダ,豪州,米国等への技術者の移住,商工業自営を目指す移住の占める率が高くなっている。戦後の移住者数は,84年までに約25万人であり,これを地域別に見ると,中南米約10万人,北米(カナダを含む)約14万人,豪州その他約1万人となっている。
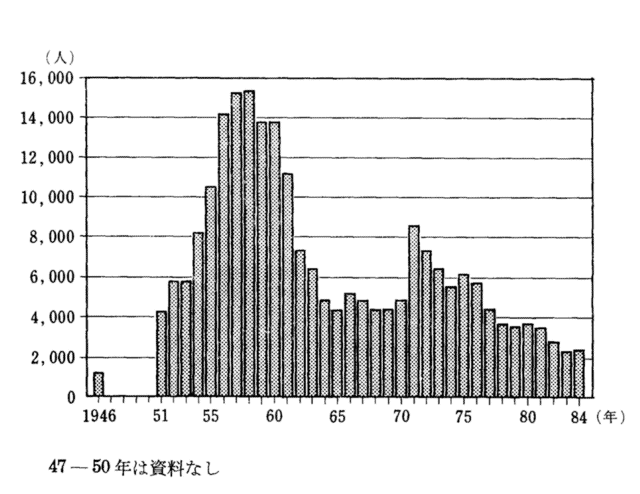
4. 海外移住の評価と課題
現在,海外には約25万人の邦人移住者と移住者の子孫である約150万人の日系人が在住している。これら移住者や日系人は,その居住国に対する貢献を通じて,我が国と居住国との友好親善に寄与しているのみならず,企業の海外進出等我が国民の海外活動に際しても重要な貢献をしている。また,開発途上国への邦人の移住は,技術移転という面からも,また移住に伴う投資の面からも国際協力として優れた効果を持っている。他方,移住者の中には,移住地を取り巻く厳しい環境などのため,いまだ自立安定するまでに至っていない者もあり,これらの者に対しては,生活基盤確立のための援護を更に強化し,その自立安定の早期達成を図っていく必要がある。
前述のように,近年移住者数は必ずしも多いとは言えないが,他方,商用,留学その他の目的で海外で生活する我が国民は逐年増加しており,その中にはそのまま海外に定住してしまう者も多い。言わば新しいタイプの移住者とでも言うべきこれらの人々への対応は移住政策上の新たに取上げられるべき課題の一つであろう。また,移住の成果とも言うべき150万人の日系人に対する対応も今後真剣に検討されるべき課題と言えよう。