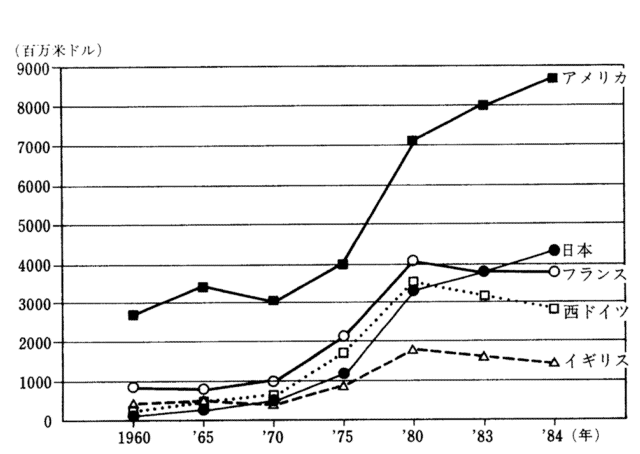
1.我が国経済協力の理念
我が国の経済協力は,輸出振興という側面に重点を置いて開始されたが,その後,我が国の経済発展に伴い,経済協力においても経済力にふさわしい貢献をなすべきであるとの認識が次第に定着してきた。更に,石油危機の経験が示すように,我が国がエネルギーをはじめとする各種資源,食糧等の面で開発途上国に大きく依存していることから,経済協力を通じて開発途上国との良好な関係を維持,強化し,もってこれらの資源,食糧の確保を図ることを期待する考え方もある。また,国際的に見ても,人道的・道義的援助の考え方,あるいは「南の繁栄なくして北の繁栄なし」との表現に端的に示される南北間の相互依存関係を重視する考え方等,援助理念については種々議論が展開されてきた。
80年代半ばの今日,我が国は人道的考慮と相互依存の認識という南北問題の根底にある基本理念に立脚して,開発途上国の経済・社会開発,民生の安定,福祉の向上を支援するため経済協力を行っている。加えて,平和国家であり,自由世界第2位の経済力を有し,かつ対外経済依存度が他国に比して高い我が国にとって経済協力は我が国が国際社会において果たすべき責務であり,同時に,このような協力を通じて開発途上国の政治的,経済的,社会的強靱性の強化を支援することは,当該国・当該地域,更には世界の平和と安定に貢献し,ひいては我が国の総合安全保障に資するものである。
2.我が国経済協力の形態と実施体制
(1)賠償・準賠償
我が国は54年にビルマとの間で最初の賠償協定を締結したのを皮切りに,フィリピン,インドネシア,ヴィエトナムと逐次賠償協定を結び,更に,ラオス,カンボディア,タイ,ビルマ,韓国,マレイシア,シンガポール及びミクロネシアの8か国・地域については賠償に準ずる経済協力(「準賠償」)を実施する協定を締結した。賠償・準賠償はそれ自体としては戦後処理の一環であったが,同時にそれは相手国の経済・社会開発に役立つ資金の供与という意味で我が国政府ベース資金協力の端緒を開くものであった。
(2)技術協力
対ビルマ賠償協定の締結と同じ54年,我が国はコロンボ・プラン(50年に発足した,アジア・太平洋諸国に対する援助計画)に加盟した。これによって我が国は研修員の受入れや専門家の派遣等を開始し,本格的に政府ベース技術協力に踏み出すこととなった。その後,60年代半ばにかけて海外技術訓練センター事業(プロジェクト方式技術協力の一環),機材供与事業,青年海外協力隊等が順次発足し,技術協力の内容は格段に拡充された。現在,技術協力は我が国が重視する「人造り協力」の推進に当たって中心的な役割を果たしている。
技術協力に係わる業務は当初「(社)アジア協会」等により実施されたが,62年には政府ベース技術協力の一元的実施機関として「海外技術協力事業団(OTCA)」が設立され,更に74年にはOTCAと海外移住事業団(63年設立)とを統合して「国際協力事業団(JICA)」が発足した。
(3)政府直接借款
58年2月,我が国にとって初めての政府直接借款(円借款)を供与する取極がインドとの間で締結された。円借款は義務的,戦後処理的な性格を有する賠償とは異なり,明確な政策的意図に基づく本格的な経済協力として,商業ベースの融資よりはるかにゆるい条件で供与されるものであり,円借款の開始は政府ベース資金協力にとって画期的な意義を有するものであった。我が国の借款の形態は当初からプロジェクト借款を主体としているが,60年代半ばには,商品借款や債務救済のための「再融資」,「債務繰延べ」も相次いで導入された。
円借款に係る業務については開始当初は日本輸出入銀行がこれを行ったが,61年に「海外経済協力基金(OECF)」が設立されてからは,双方が円借款に携わることとなった。その後75年に輸銀・OECFの業務分野調整が行われ,以後の新規円借款は原則としてOECFが一元的に供与する体制が整備された。
(4)無償資金協力
60年代半ばまで我が国資金協力の中心であった賠償・準賠償は67年をピークとして減少に転じたが(終了は77年),これに対応して,69年には,開発の遅れた国を中心に借款で実施することが困難な公共的社会開発分野の案件を対象とする新たな資金協力の形態として二国間一般無償資金協力が開始された。一般無償資金協力はその後着実に拡充され,現在では無償資金協力全体の2分の1強を占めるとともに,我が国が経済協力の重点分野としている「基礎生活援助」の主要な担い手となっている。
なお,一般無償資金協力開始の前年の68年には,食糧援助規約に基づく食糧援助(通称「KR援助」)が開始されており,以後も水産無償(74年),文化無償(75年),食糧増産援助(通称「第2KR援助」)(77年)等が相次いで導入された。
(5)多国間援助
二国間援助体制の確立と併せて,経済協力を行う国際機関への参加も進展した。我が国は既にIDA(「国際開発協会」,通称「第二世銀」。60年設立)に当初から援助国として参加し,また,61年にOECDの下に主要援助国の協議機関として発足したDAC(開発援助委員会)についてもその原加盟国となっていたが,その後もアジア開発銀行(66年),アフリカ開発基金(73年),米州開発銀行(76年)等の地域開発銀行に加盟するとともに,国連諸機関の活動に対する協力の拡充に努めた。
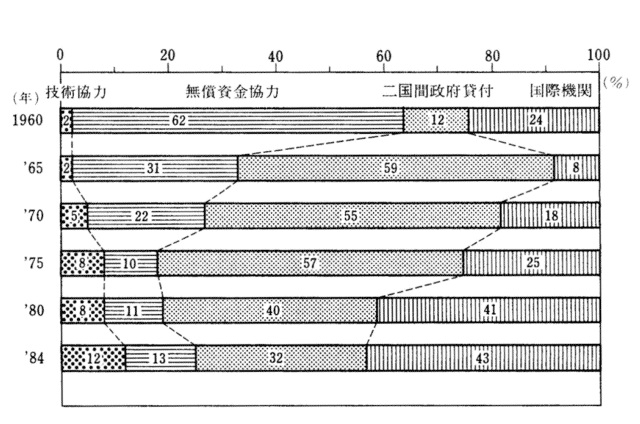
3.我が国経済協力の実績
(1)量の増大
前述の通り,援助開始から間もない60年代初期の我が国のODA実績は1億ドル程度に過ぎなかったが,84年の実績は43.2億ドルで米国(87.0億ドル)に次いでDAC17か国中第2位の規模にまで増大した。この20余年間には他の先進国もODAの拡充に努めているが(84年実績と60年実績とを比較すると,米国3倍,仏4.5倍,西独12倍,英国3.5倍),我が国ODAの伸長振り(84年実績は60年実績の41倍)は他国を遥かに上回るものであり,この点は通貨レート変動の影響を除くために各国通貨ベースで比較しても同様である(84年実績と60年実績との比較では米国3倍,仏8倍,西独8倍,英国7.5倍に対し,我が国は27倍)。
このようなODA拡充に大いに貢献したのは,二度にわたる,ODAに関する中期目標の設定であった。即ち,我が国は78年のボン・サミットにおいてODAの3年倍増を表明し,80年には目標(78年実績14.24億ドルの倍の28.48億ドル)を大きく上回る33.04億ドルの実績を達成した。更に81年には新たな中期目標を設定し,80年代前半(81~85年)のODA実績総額を70年代後半(76~80年)の総額(106.8億ドル)の倍以上とするよう努めることを決定した。81年及び82年の実績は円安,国際機関への増資交渉の遅れ等の原因によって夫々,対前年比4.0%,4.7%の減少となったが,83年には24・4%,84年には14・8%と高い伸びを見せている。5年倍増の中期目標は85年末をもって終了するが,我が国は国際的な期待に応えるため,86年以降も新たな中期目標を設定して引続きODAの着実な拡充に努め,その際,質の面でも可能な限りの改善に努めることとしている。
他方,ODAの量は国際的には対GNP比率によって比較されることが多いが,我が国の場合,この比率は84年に前年の0.32%から0.35%に上昇したもののDAC17か国中第11位と低位にあり,この点からもODAの一層の拡充が期待されている。
(2)質の改善
ODAの質に関する指標としては贈与比率(ODA全体のうち,二国間の無償資金協力及び技術協力並びに国際機関に対する出資・拠出等の合計が占める割合)及びグラント・エレメント(G.E.)が用いられるのが通例であるが,我が国は従来からこのいずれにおいても他の多くのDAC諸国を下回っている。即ち,60年代半ば以降,円借款が我が国ODAの中心的地位を占めるに至ったことの結果として,贈与比率は概ね40~50%程度の水準で推移しており(81年43.6%,82年39.6%,83年55.2%,84年46.2%),DAC諸国の平均(81年75.2%,82年76.1%,83年79.7%)には達していない。
また,G.E.についてDACは72年,ODAのG.E.を全体で84%以上とすることを勧告し,更に78年にはこれを86%に引き上げることとした。我が国はこれら勧告を受けて,G.E.の改善に努力してきているものの(72年61.0%,76年74.9%,80年74.2%,84年74.2%),国際目標あるいはDAC諸国平均(83年91.2%)には及んでいない。
このようにODAの質の改善は我が国にとって大きな課題となっており,先に述べた通り,我が国は86年以降の新たな中期目標の下,今後も可能な限り質の改善に努めることとしている。
(注)グラント・エレメントとはODAの条件の緩和度を示す指標のことであり,個別の援助のグラント・エレメントを加重平均して算出する。個別の援助のグラント・エレメントは,金利が低くなり,据置期間及び償還期間が長くなるほどパーセントが高くなり,贈与は100%と定義され,逆に,商業条件(金利10%)の借款は0%と定義されている。
なお,ODAの質に係わるもう一つの問題であるアンタイイングについては,我が国は72年に円借款のアンタイイングを積極的に拡大する方針を打ち出したが,74年にDACにおいて「開発途上国(LDC)アンタイイングに関する了解覚書」が締結された後はLDCアンタイドを原則とすることとし,更に,78年1月の日米通商交渉の共同コミュニケを受けて,78年度新規意図表明分より一般アンタイドを基本原則とすることとした。我が国円借款の一般アンタイド率は近年50%から60%前後にまで増大しているが,我が国は国際経済環境等内外にわたる諸般の事情をも考慮の上,引続きアンタイド化の着実な実行に努める方針である。
(注)援助のアンタイイングとは,一般的に財貨及び役務の調達先を援助供与国に限定しないことを意味する。
LDCアンタイドとは調達先を全ての先進国及び開発途上国に開放する(いわゆる一般アンタイド)ための中間的措置として考えられたもので,調達先を援助国及び開発途上国とするものである。
(3)対象地域の拡大
我が国の政府ベース経済協力がアジア諸国に対する賠償によって開始されたことに象徴されるように,我が国の二国間ODAの供与先としては当初よりアジア地域が極めて大きな地位を占め,特に70年代初めまではアジア地域が我が国の二国間ODAに占めるシェアは90%から100%に近い水準にまで達していた。これは,我が国がアジアに位置し,アジア地域と歴史的,政治的,経済的,文化的に緊密な関係にあることを反映するものと言えよう。その後,我が国とアジア以外の諸国との関係の深まりと我が国のODAの拡充に伴って,これら諸国に対する援助の比重も次第に増加し,近年は二国間ODAの約7割がアジア地域(ASEAN諸国のシェアは約3分の1),残りが中近東,アフリカ及び中南米の3地域に概ね均等に供与されている。
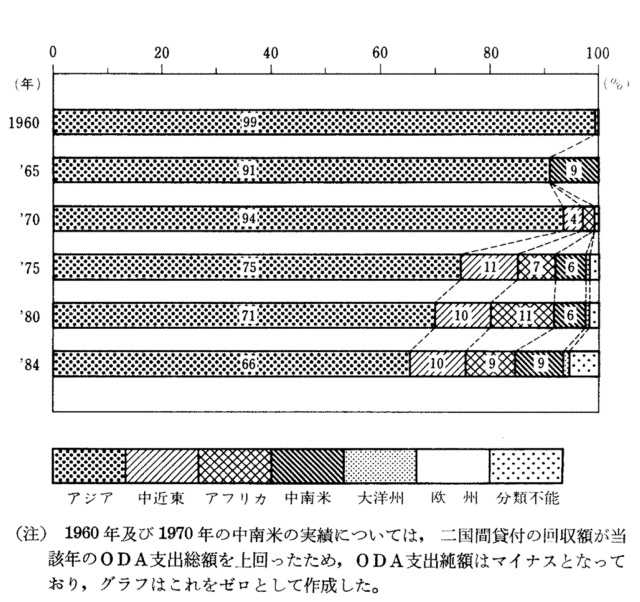
現在,我が国は二国間援助供与の決定に当たっては,先に述べた経済協力の基本理念に基づき,相互依存の度合い(我が国にとっての当該国の総合的な重要性)及び人道的要素(援助対象国の援助要請の大きさ,あるいは貧困の度合い)等を総合的に勘案することとしている。
我が国は,81年5月の日米共同声明において「世界の平和と安定の維持のために重要な地域」に対する援助の強化を表明した。これは,開発途上国の経済的混乱は政治的・社会的不安定を惹起し,国際的な紛争の引き金ないし国際的緊張の原因ともなりかねず,従って経済協力を通じ開発途上国の経済社会開発を支援し,民生の安定,福祉の向上に貢献することは,これら諸国の政治的・社会的安定をもたらすとともに,広く国際間の緊張を緩和することに貢献することになるとの認識に基づいている。具体的にどの地域がこれに該当するかは,その時々の国際情勢に応じて我が国が自主的に判断することとしている。
(4)対象分野
我が国の援助の対象分野としては従来より,円借款を中心に経済インフラストラクチャーの比重が高いが,近年,特に無償資金協力及び技術協力の拡充を背景に,これに加えて「基礎生活援助」及び「人造り協力」に重点を置いている。「基礎生活援助」とは開発途上国の住民の福祉に直接稗益する農村・農業開発,保険・医療,水資源等の分野を対象とするもので,70年代において国際的に打ち出されたBHN(Basic Human Needs,「人間生活の基本的要請」)援助と軌を一にしている。また,「人造り協力」は,開発途上国における人材の不足が開発を妨げる大きな要因となっているとの認識に基づくものであり,その典型としては鈴木総理が81年のASEAN諸国訪問の際に提唱した「ASEAN人造りプロジェクト」(各国に「人造りセンター」を設け,我が国では沖縄に国際センターを開設するもの)が挙げられる。
4.効果的・効率的援助
近年の厳しい財政事情の下,経済協力に対しては特段の配慮が払われてきたが,今後も国内における広範な支持と理解の上に立って経済協力の拡充を図っていくためには,経済協力が所期の効果を挙げるとともに効率的に行われるよう努めていくことが不可欠である。このため,我が国は,(あ)被援助国との協議を通じての開発ニーズの的確な把握,(い)事前調査の充実による優良な案件の選定,(う)他の援助国との政策協議,(え)援助評価の実施,等に努めており,今後もこれらの諸措置の充実を通じて,一層効果的・効率的な援助の実施を図っていくこととしている。