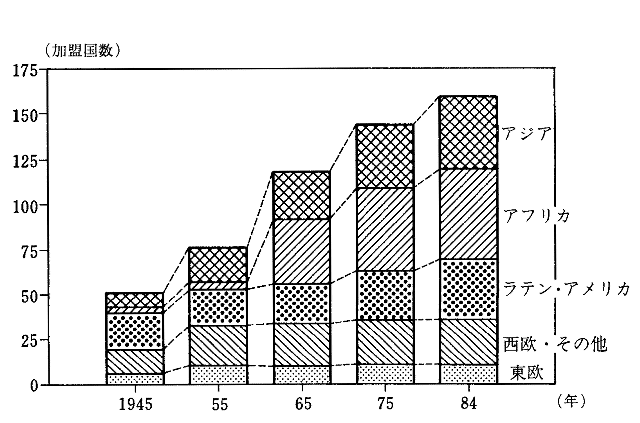
国際連合(以下国連)は,本年40周年を迎える。40年という歳月とともに,国連はその創設に参画した人達が予想もしなかった著しい変貌を遂げた。
(1)加盟国数は創立当時の51か国から159か国に膨らみ(第39回国連総会でブルネイが159か国目の加盟国となった),加盟国の地域別構成も大きく変化した(図1参照)。世界のほとんどすべての国を網羅した普遍的な国際機構へと国連が成長するにつれ,その活動も非常に広範にわたるようになった。国連の意思表示である総会決議の数・対象の変遷及び国連活動の「足腰」である事務局予算(国連通常予算)の40年間の伸び(図2)は,このことを如実に物語っている。
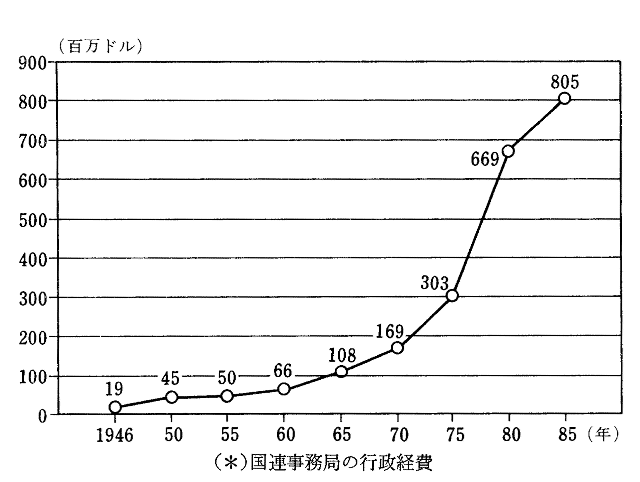
(2)国連憲章第1条に掲げられている「国際の平和と安全を維持する」という面での国連の機能も過去40年の間に大きく変化した。憲章の起草者は,「安全保障理事会」を国際平和と安全確保の任を果たす主要な機関とし,米,英,ソ連,中国,仏の5か国を常任理事国として拒否権を与えることにより,五大国の協調による国際平和と安全の維持という世界秩序安定の構図を描いていた。しかし,米ソ対立が東西冷戦として顕在化するにつれ,大国の利害が衝突する紛争の場合に常任理事国の拒否権の行使により安保理での
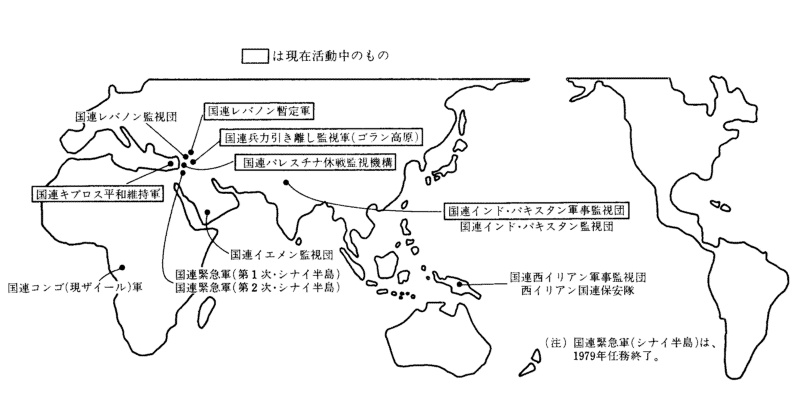
合意が得られず,国連が有効な紛争処理を果たし得ない事態が多発するに及び,当初の構想は破れるに至った。(60年代半ば以前はソ連が加盟問題を中心に拒否権を行使し,それ以降は米国が中東問題を中心に拒否権を行使して,84年末までにソ連は120回,米国は38回の拒否権行使を行っている)。
このような状況に対応するため国連が創り出した新しいメカニズムがいわゆる「平和維持活動(PKO)」である。武力行使を目的としない「国連軍」が,紛争当事者間の同意を得て紛争地域に介在し,停戦の監視,武力衝突再発の防止にあたり,平和の回復と維持を行うというこの構想は,米ソ対立の狭間で国際社会の現実に定着してきている。現在,このような平和維持機能は,イスラエル・レバノン間の「国連レバノン暫定軍(UNIFIL)」,イスラエル・シリア間の「国連兵力引離し監視軍(UNDOF)」等,紛争の再発防止のために重要な役割を果たしている(図3参照)。
(3)「平和及び安全の維持」が,上記(2)のように限定的な形でしか実現されないことが明らかになっていく一方で,その多くが開発途上国である新規加盟国の増大により,それら諸国の重要関心事項である経済社会問題の比重が高まってきた。1960年代は,ケネディ大統領提案により「国連開発の10年」と定められ,国連貿易開発会議(UNCTAD),国連開発計画(UNDP),国連工業開発機関(UNIDO)といった重要な経済関連機関が次々と設立された。
70年代に入ると,先進国中心の国際経済体制の変革を主張する途上国の動きにより,「資源と開発」国連特別総会において「新国際経済秩序(NIEO)」の概念が導入され,その後の国連の経済論議における主要なイデオロギーとなった。しかし,近年,経済実体と乖離したNIEO的アプローチに開発途上国が固執し,現実的な議論の進展が見られない状況が続いた結果,「国連離れ」,「マルチ(多数国間協力)離れ」の現象も一部に見られてきた。
一方,事務総長以下国連全体がアフリカ支援において示したイニシアティブや,専門機関による地道な協力実績等経済社会分野での国連への期待には依然根強いものがあり,経済社会分野においても国連の実効的機能の強化が強く求められている。
(4)国連において多数派たる開発途上諸国は,グループ77等として結集し,先進国側にとり受諾困難な決議を数の力で採択させるという事態が屡々見られた。しかし,途上国側も表決の勝利自体に意味はなく問題の解決には関係国全ての同意が不可欠との認識に徐々に近づきつつあることは,決議採択に際し「コンセンサス方式」(事前に十分な非公式協議を行い投票によらず採択する)が用いられる率が近年増加していることに良く示されている。
(5)このように,国際環境の大きな変化の中にあって国連が対応への努力を払って来たことは事実ではあるが,国連の現状は,創立40周年を機に,国連のあり方について真剣な問い直しが行われることを求めている。即ち,前述の通り国連の平和維持活動はそれなりの効果をあげているものの,創立当初の国連の理想からは程遠く,他方,経済面においても国連における南北問題に解決への積極的展開は未だ見られない。更に,最近のユネスコ問題に象徴される過度の政治化傾向や機構の肥大化といった全国連という組織に内在する問題が顕在化している。アフリカの干魃,砂漠化,環境・人口問題等々国際的な取組なしには解決し得ない問題が多々生じてきている今日,普遍性を備えた国際組織である国連を再活性化させる必要性が以前にも増して高まっていると言える。
2.我が国と国連
(1)我が国は1956年の国連加盟以来一貫して国連を通じての国際協力を強化してきた。今日,我が国は米国に次ぐ第2位の大口財政負担国(図4,5参照)として国連の活動を支える主要国の一つに成長しており,国連の再活性化のために果たすべき責任と役割は大きい。そのために我が国が緊急に取り組むべき課題として,国連の行財政改革が挙げられる。限られた資源を有効に利用し国連の組織としての効率性を高めるには,優先順位の低い事業や政治的に偏向した事業を削除することが必要であり,そのためには,定員増の抑制や人件費等の行政経費の圧縮を通じて機構の肥大化を防ぐことが緊要である。
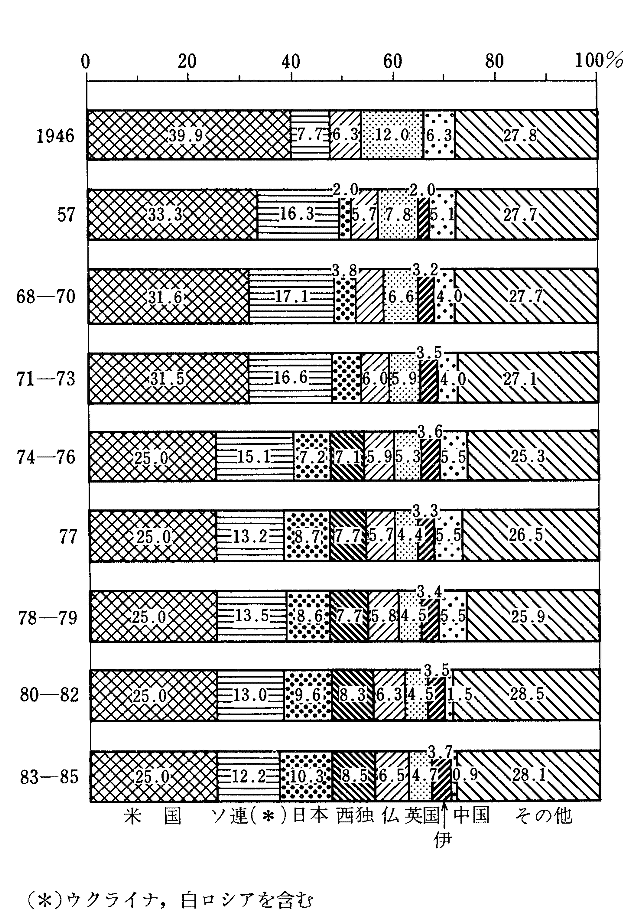
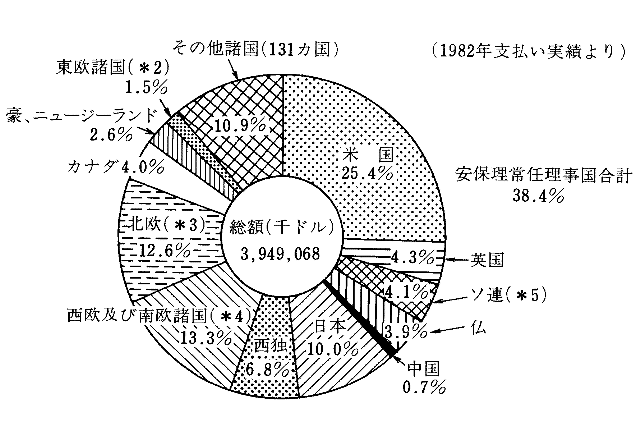
出典:国連分担金委員会報告書付属(事務局文書A/38/11/ADD.1)
(*1)以下(イ)及び(ロ)の合計
(イ)以下の諸機関への分担金支払いの合計
国連(通常予算,信託基金,UNEF/UNDOF,UNICEF),ILO,FAO,UNESCO,ICAO,WHO,UPU,WMO,IMO,WIPO,IAEA
(ロ)以下の諸機関への自発的拠出金支払いの合計
国連信託金,UNIFICYP,UNIDO,UNEP,UNCHS,UNDP,UNDP管理下の信託基金,WFP,UNHCR,UNRWA,UNITAR,UNFPA,ILO,FAO,UNESCO,WHO,UPU,ITU,WMO,WIPO,IAEA
(*2)東独,ポーランド,チェッコ,ハンガリー,ルーマニア,ブルガリア
(*3)ノールウェー,デンマーク,スウェーデン
(*4)アイルランド,オランダ,ベルギー,オーストリア,イタリア,スイス,ギリシア,スペイン,ポルトガル
(*5)ウクライナ,白ロシアを含む
(2)また,国連の諸活動に対し我が国が今後一層協力していくためにも,国連機関に,より多くの日本人職員が採用されるよう一層働きかけていく必要がある(国連事務局に勤務する日本人職員は,1984年6月末現在で113名であるが,国連通常予算の分担率等を基に設定されている我が国の望ましい職員数172-233名を大幅に下まわっている)。
(3)1984年においても我が国は,上述の我が国に与えられた責任と課題を認識しつつ積極的な国連外交を展開した。その主要なものは以下のとおり。
(イ)第39回国連総会は,「アフリカの危機的経済情勢」に関する討議を最重要事項に指定した。我が国は安倍外務大臣の一般討論演説においてアフリカ支援を強く訴え,同総会での本件討議に弾みをつけ,各国の力を本件に集中せしめた。またアフリカ諸国も救済の早期実施を優先させた現実的対応を示したため,「アフリカの危機的経済情勢に関する宣言」が全会一致の採択として結実した。この間,アフリカ・グループの一致した要望を受けた総会議長の要請により我が国は本件についての「調整役」の役目を引き受け,国連事務局に対し強く働きかけ,安倍外務大臣の提唱した「国連機構を総動員した構想計画」をアフリカ緊急支援タスク・フォースとして実現させた。
(ロ)近年注目を集めている行財政問題に関しても我が国は積極的な対応を行い,第39回総会における行財政問題の焦点となった国際公務員について妥協案を提出して決着せしめた。
(ハ)また,ICJ選挙,経社理選挙など我が国にとり重要な各種選挙に当選を果たした。