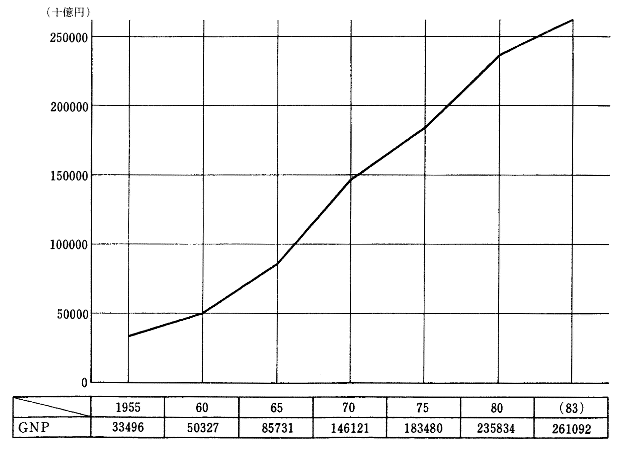
資料:I.F.S.1980年を基準とする実質値
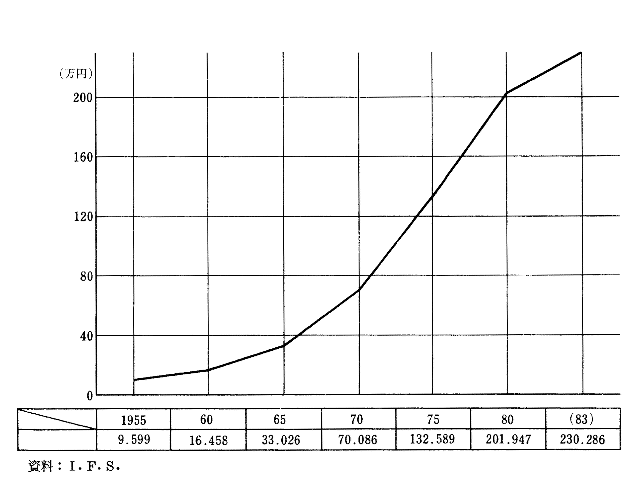
されたのである。
60年6月に定められた貿易自由化大綱は速やかに実施に移され,63年2月には我が国は国際収支を理由とする輸入制限国(GATT12条国)から,輸入制限を行わない国(同11条国)に移行した。他方,為替・資本の自由化も着実に進められ,64年4月,為替の自由化を実施,IMF14条国(為替制限を行う国)から同8条国(為替制限を行わない国)に移行した。このような自由化への動きを背景に,我が国は64年経済協力開発機構(OECD)に加盟,名実ともに先進国の仲間入りを果たした。
(3)経済繁栄と世界経済の激動(1965~75年)
我が国経済は65年不況を迎えたが,その後70年夏までの57か月間記録的な好況を続けた。この長い好況と成長持続の中で,我が国の経済力は著しく強まり,68年には自由世界第2位の経済力を有するに至った。同年には,我が国の経常収支も黒字に転じたが,他方,米国の貿易収支赤字が71年,72年と急速に拡大し,深刻な経済摩擦を惹起することとなった。
このような状況下,我が国は米国との間で協議を重ね,71年1月,輸入自由化の促進を目的とする総合対外経済対策を発表,以後,数次にわたる円対策を決定し,経常収支の黒字拡大基調への対処に努めた。
また,国際場裡では,世界の保護主義を抑え自由貿易主義の発展を図るとの観点から,ガットの下の多角的貿易交渉を提唱,73年9月,東京でガット閣僚会議を開催し,東京ラウンドを発足させた。
70年代の世界経済の激動は,国際通貨危機を発端として始まった。71年8月,ニクソン米大統領は緊急経済政策を発表,金ドル交換を停止し,輸入課徴金を導入した。その4か月後合意に至ったスミソニアン体制も短命に終わり,73年2月には円を含め世界の主要な通貨は変動相場制に移行した。
更に,同年10月には第四次中東戦争が勃発,湾岸OPEC(石油輸出国機構)6か国は原油公示価格の大幅引き上げを断行した。第一次石油危機である。石油価格の4倍増という事態は先進国経済を「高インフレ・国際収支悪化・不況」といった三重苦に陥れ,我が国も74年度には戦後初のマイナス成長を記録,75年度にかけて戦後未曾有の厳しい不況を経験することとなった。
戦後海外からの安価で豊富な石油その他の資源に依存し,加工貿易立国として成長を遂げてきた我が国にとり,これは大きな衝撃であり,これ以後,資源供給国との関係強化の必要が改めて強く認識され,政策の根本的変革が求められた。
このような状況下,ジスカールデスタン仏大統領は,西側主要国首脳が一堂に会し世界経済の再建について忌憚のない意見交換を行う必要があるとして,主要国首脳会議(サミット)の開催を提唱し,75年11月ランブイエ城で第1回サミットが開催された。この会議への我が国の参加は,我が国の国際社会での地位の向上を象徴する出来事であったと言える。
(4)変貌する国際経済環境(1975~84年)
70年代前半に世界経済を揺るがせた二つの危機は,戦後約30年間を通じ世界経済の発展を支えてきた二本の柱―強い米国経済と安価な石油―の崩壊とIMF・GATT体制の風化を意味するとともに,世界経済の相互依存の認識を強くした。以後,世界経済は混迷と不確実性の時代に入ることとなる。
我が国は,75年にはプラス成長に転ずる等,比較的早期に第一次石油危機からの立ち直りを示し,世界経済も,76年以降景気回復過程に入った。
しかし,79年のイラン革命を機に,イランの原油輸出が激減し,第二次石油危機が発生した。これを機にOPECが再度石油価格の大幅引き上げに踏み切ったため,世界経済は再び,長期不況に陥ることとなったが,その中で日本経済は,第一次石油危機の経験をも生かしつつ,その適応力を遺憾なく発揮した。即ち,第一次石油危機後続けられてきた省エネルギー,代替エネルギー開発,供給源多角化等,資源の安定供給のための努力を強化するとともに,エネルギー高価格時代に適応した産業構造への転換を達成した。その結果,我が国は他の先進諸国に比し,相対的に高い成長率を維持するとともに,経常収支も81年には再び黒字に転じた。
他方,省資源による輸入の停滞と,自動車,電子工業製品,工作機械等特定商品の輸出の急増は,欧米諸国との間に二国間の貿易不均衡を生ぜしめ,我が国とその貿易相手国の間に,再び経済摩擦が発生した。
70年代後半以後,諸外国から厳しい要求が寄せられる中,我が国は外交努力を重ね,二国間では,例えば牛場・ストラウス共同声明(78年1月),牛場・ハーフェルカンプ合意(同年3月)というような成果を挙げ,また,多国間の場では,東京ラウンドの終了(79年4月)に向けて,積極的な貢献を行った。
第二次石油危機を乗り越えた80年代前半(84年末まで)には,我が国は,自由貿易体制の維持・強化,調和のある対外経済関係の形成及び世界経済の活性化を図るとの観点から,6次にわたる対外経済対策を決定・実施した。
我が国経済の戦後40年間の歩みを振り返る時,開発途上国とのつながりを忘れてはならない。「南の繁栄なくして北の繁栄なし」といわれるように,開発途上国との間の相互依存関係は緊密なものとなってきている。また,途上国の経済発展とそれを基礎とした平和と安定の下に,我が国の繁栄があることも事実である。我が国は今後とも,経済・技術協力に止まらず,市場アクセスの改善,直接投資の増大等を通じ,途上国の工業化に大きく寄与しなければならない。
戦後40年を経て今や,世界経済の重要な一翼を担うに至った我が国は,現在,まさに,世界経済の安定的発展のために何をなし得るかを自らに問う段階に来ている。我が国が,そして世界が,その発展と繁栄を将来の世代に引き継いでいくためにも,国際社会が自由で拡大する交流と協力の途を歩み続けることが必要であり,我が国としても,その過程で積極的な役割を果たしていくべきである。
2.1984年の世界経済
(1)先進国経済
1984年の先進国経済を概観すると,インフレの鎮静化の中で,着実な景気拡大が見られた。特に,国際経済の動向に大きな比重を占める米国経済は実質GNP成長率6.8%と,51年以来最も力強い回復を示した。西欧諸国の景気も全般的に回復基調を示した。
雇用情勢は,米国では改善を見せたが,西欧諸国では依然厳しい状況が続いた。米国の国際収支は,ドル高の影響もあって,1,015億ドルという大幅な経常収支赤字を記録した。
(2)開発途上国経済
82年及び83年に1%台という戦後最低の経済成長率を記録した開発途上国経済は,84年には,先進諸国の本格的な景気回復の影響を受けて,実質経済成長率及び国際収支の両面で顕著な改善を示した。
実質経済成長率
83年1.5%→84年3.7%
経常収支
83年▲705億ドル→84年▲439億ドル
他方,一次産品市況の低迷,累積債務問題,アフリカの飢餓等,途上国経済は依然として多くの困難に直面しており,経済回復のテンポにも大きな跛行性が見られた。
累積債務問題については,ロンドン経済宣言に謳われた多年度にわたる返済繰延べ等の適切な対応,景気回復定着の中での債務国自身の経済調整努力等により,最悪の局面は回避された。しかし,債務国の輸出収入の多くの部分が債務返済に充てられ,経済発展に向けられないこと等多くの困難があり,この問題の真の解決には,なお多大の努力と時間が必要である。
(3)世界貿易の動向
1983年より回復基調にある世界貿易は,84年,数量ベースで9%増加し,金額で1,995兆ドルとなった。この世界貿易の拡大は,80年代初頭の景気後退から世界経済が回復したことを示すものである。
他方,84年の世界貿易の急速な回復にも拘わらず,貿易問題をめぐる緊張は持続しており,一層各国間の協力に基づく努力が必要となってきている。特に,自由で多角的な貿易体制の再構築を図っていく上で新たな多角的貿易交渉の早期開始が急務となっている。
(4)インフレなき持続的成長へ向けての努力
このような世界経済情勢を背景にして,84年5月のOECD閣僚理事会,6月の第10回主要国首脳会議(於,ロンドン)では,先進国経済のインフレなき景気回復の持続と,その恩恵の開発途上国への均霑のための方途などに関し,幅広い合意が達成された。
その後の国際経済情勢としては,それまで世界経済を牽引してきた米国経済の成長が1984年後半から鈍化してきたことを背景に,財政赤字及びドル高,失業及びその背景にある構造的硬直性,対外収支不均衡及び保護主義圧力の高まり等持続的成長に対する制約要因への懸念が増大することとなった。これら不確実性の除去のため,OECD,IMF,世銀等で積極的な討議が行われている。特に,85年5月のボン・サミットでは,協調と団結の精神の下,インフレなき持続的成長のためのこれまでの合意を踏まえつつ,サミット参加国がそれぞれ抱える問題に責任を持って取組む積極的な姿勢を打ち出したことが特筆される。
(5)我が国経済の動きとその役割
83年春より回復に転じた我が国経済は,物価安定が続くなかで,84年に入っても景気回復を持続した。雇用情勢にも改善の動きが見られたが,国際収支面では,経常収支の大幅黒字と,長期資本収支の大幅赤字が持続した。
こうした中で,我が国の当面の経済運営の基本的課題は,インフレなき持続的安定成長を達成し,雇用の安定を確保する一方,行財政改革を着実に推進し,また,自由貿易体制の維持・強化,調和ある対外経済関係の形成及び世界経済活性化への積極的貢献を図ることである。
この観点から,政府は,84年12月「対外経済対策」として,関税率の引き下げ(85年度から農産品につき一年分,鉱工業品につき二年分,各々前倒し,及び特恵制度の改善等)を行うことを決定した。更に,政府は,同月,対外経済問題閣僚会議を設置するとともに,民間有識者から成る「対外経済問題諮問委員会」を設置し,我が国経済の一層の国際化を進めるための中期的政策提言等につき,検討を求めた。同委員会は,85年4月9日報告を提出したが,これを受け,政府は,対外経済問題に関する最近の決定と今後の政策方向をとりまとめた「対外経済対策」を発表した。
この「対策」において,政府は,対外経済諮問委報告に示された政策(対開発途上国政策を含む)提言を最大限尊重し,実施に移していく考えを明らかにした。特に,市場アクセスの改善については「原則自由・例外制限」の基本的視点に立ち,「例外」の内容も必要最小限のものに限定するとの提言を受け入れ,出来る限り早期に市場アクセス改善のための行動計画(アクション・プログラム)を策定し,遅滞なく実施していくことを決定した。
これら一連の措置は,我が国存立の基盤である自由貿易体制の維持・強化のために,その責任とコストを負担するとの立場からとられたものであり,また,ガットの新ラウンド推進にモメンタムを与えるとの我が国の一貫した姿勢を示すものである。