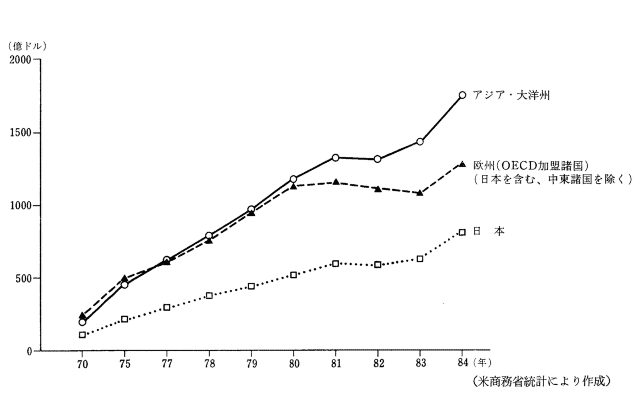
これに加えて,ソ連が極東における核・通常戦力の増強を続け,その太平洋艦隊が,ソ連艦隊の中でも北洋艦隊と並び,質・量ともに最大規模に成長しているという背景も指摘し得よう。近年の太平洋艦隊増強の動きは,ソ連がSLBM(潜水艦発射弾道ミサイル)の重要性を認識し,極東海域を対米戦略上SLBM配備に適した地域として重視していることに深くかかわっているとみられる。ソ連のかかる動きに対し,米国においても,極東が米国自身の安全保障に直結した地域であるとの認識が深まっている。現在極東は,米ソ両国にとって戦略上極めて重要な地域となっている。
このような情勢の変化を受け,また中国の自主独立路線等も相まって,70年代後半以降,米中及び中ソ関係は微妙に変化してきている。
(2)米中関係
84年の米中関係は,趙紫陽総理訪米(1月)とレーガン大統領訪中(4月)の実現に示されるように,基本的には順調に推移した。
両国首脳の相互訪問の結果,産業技術協力協定,租税協定等の調印が行われ,かかる関係の安定化を背景として,米中間の経済交流(貿易・投資)は一層の発展をみた。また米中間の軍事面での交流も,張愛萍国防部長訪米(6月),レーマン海軍長官訪中(8月),ベッシー統合参謀本部長訪中(85年1月)等が行われ着実な進展をみせている。
米中関係における最大の障害としては,やはり台湾問題が挙げられよう。中国は,「台湾関係法」と米国の台湾武器供与に対して再三不満の意を表明し,米中間の三つのコミュニケ(上海コミュニケ,国交正常化コミュニケ,82年8月17日の台湾への武器売却に関するコミュニケ)の遵守を要求している。中国は,台湾問題が主権にかかわる問題であるとの立場を堅持しているので,その歩み寄りには限度もあろうが,米中関係の進展を大幅に後退させることは,避けんとしているやに見受けられる。最近,中国は,香港問題を解決した「一国家二制度」の構想が,台湾問題についても適用可能との考えを明らかにしており,米国の対応が注目される。
米中関係を展望する上で重要なことは,中国の安全保障にとりソ連が看過すべからざる要素であるという状況に変化がないこと,及び,中国の現代化にとって米国を含む西側から得る利益が大きいとの基本的認識に立ち,今後も西側諸国との関係で,より協調的な路線をとってゆくと予想されることである。このため,自主独立外交を掲げる中国と,米国の外交政策との間には,幾つかの相違点が残るにしても,基本的には米中関係は良好に推移していくものとみられる。
(3)中ソ関係
中ソ関係の改善を目的とする外務次官級会談(82年10月再開)は,84年も継続され,第4次(3月),第5次(10月),第6次(85年4月)の会談が北京とモスクワで交互に開催された。実務面では,貿易量の拡大,留学生相互交換枠の拡大,スポーツ交流,文化交流等の他,各種専門家間の交流等に見られる如く,徐々にではあるが関係拡大傾向が認められた。
2月に故アンドロポフ書記長葬儀参列のため,万里副総理が訪ソし,アリエフ第一副首相と会談した。9月には国連総会に際して中ソ外相会談が実現し,グロムイコ・呉両外相は,「種々のレベルにおける政治対話の継続」への賛意を表明した。
当初5月に予定されていたアルヒーポフ第一副首相の訪中は,12月になって実現をみた。同副首相は,趙総理等中国側首脳と会談し,経済技術協力協定,科学技術協力協定,経済・貿易・科学技術協力合同委員会設置に関する協定の3協定を調印した。
85年3月ゴルバチョフ新書記長は,党中央委臨時総会での就任演説において,「ソ連は中国との真剣な関係改善を希望する。このことは相互性が存在すれば完全に可能である」と発言し,対中関係改善へ向けての積極的姿勢を表明した。
中国からは,李鵬副総理が,故チェルネンコ書記長葬儀参列のため訪ソし,ゴルバチョフ新書記長と会談を行った。その際,胡総書記のゴルバチョフ新書記長へのメッセージが伝達されたこと,李副総理が新書記長との会談で,いわゆる「三条件」に言及しなかったこと,ソ連を中ソ対立以来初めて「社会主義国」と呼んだこと,政治関係改善への希望を表明したこと等にみられる如く,中国の対ソ姿勢に若干の変化がみられた。
しかし,その後の外務次官級会談では,中国側提示のいわゆる「三条件(カンボディア侵略の越に対する支援停止,アフガニスタンからのソ連軍撤退,中ソ国境付近のソ連軍の削減及びモンゴル駐留ソ連軍の撤退)」をめぐり,依然として,中ソ間には基本的立場の相違があったものとみられる。また,カンボディアの抗越勢力及びアフガニスタンの抗ソ勢力への支援を継続する,中国の姿勢にも変化はみられていない。
3.地域情勢の動向
東西関係は国際情勢の基軸を成しており,その他の大国間関係と共に,その推移は,国際情勢の諸動向に大きな影響を及ぼしている。同時に,各地域情勢は,東西関係とかかわりを持ちつつも,その程度には差があり,また,それぞれの地域の独自性の故に,国際情勢全般に不安定要因を形成している状況にある。
イラン・イラク紛争については,例えば,両国によるタンカー攻撃に見られるごとく,単なる二国間の問題にとどまらず,周辺諸国や域外諸国に対して波及する危険性を示した。また,ニカラグァ等中米情勢の緊張と流動化については,地域紛争が地域を越えて東西関係の文脈で認識された面もあった。
カンボディア,アフガニスタン,イラン・イラク紛争等,ここ数年来の軍事的対立については,84年も紛争当事国ないし当事者のみならず,関係国の間にも事態打開への様々の動きが見られたが,紛争解決への展望が得られることなく推移した。国際的紛争においては,紛争解決を望む勢力があることは当然であるが,逆に紛争を継続させる種々の要因もあり,問題解決への道程には多大の困難を伴うとも言えよう。
(1)アジア・大洋州情勢
(イ)朝鮮半島においては,83年に大韓航空機撃墜事件(9月),ラングーン爆弾テロ事件(10月)等,緊張の様相を呈したが,84年は南北間の対話が再開される等,南北当事者間に新しい動きがみられた。
北朝鮮による韓国への水害援助物資提供(9月),南北経済会談(11月),赤十字予備会談(11月)の開催等がそれである。
朝鮮半島と関係国間の動きとしては,先ず全斗煥大統領の韓国国家元首としての初めての本邦公式訪問(9月)がある。同訪問は,日韓両国が成熟した確固たる関係に向けて踏み出す象徴であり,その実質的な契機となったのみならず,朝鮮半島の緊張緩和に向けて,両国が努力するとの方向を打ち出したことにおいても意義があった。韓米関係も,レーガン大統領の訪韓(83年11月),全斗煥大統領の訪米(85年4月)等を通じて強化が図られた。
中国と北朝鮮の間でも,胡ヨウ邦総書記の訪朝(84年5月),金日成主席の訪中(同11月)等,要人往来が頻繁にみられた。ソ連と北朝鮮との間も,金日成主席の訪ソ(同5月)等を通じて関係が緊密化している。
また韓中関係が,スポーツ交流,国際会議参加等の非政治的分野で進展をみたことも注目された。
内政面をみると,韓国では,学園自律化措置の実施,政治活動被規制者の解除等,全斗煥政権の手堅い政策の下で,基本的には平穏に情勢が推移した。85年2月の総選挙では,新しく結成された新韓民主党が野党第一党に進出した。与党民正党も安定多数を確保し,内閣改造が行われた。
北朝鮮では,引き続き金正日後継体制作りの動きが顕著であり,経済面では合弁法制定(9月)の動きが見られた。
南北対話については,南北朝鮮間の相互不信が根深いことから,急速な進展は困難とする向きが多い。しかし,今後当事者間で対話が積み重ねられ,関係国の努力も相まって,具体的成果が生まれ,同地域の緊張緩和に貢献することが期待されている。
(ロ)中国では,84年も引き続き,トウ小平・胡ヨウ邦・趙紫陽を中心とする指導部により,「四つの現代化」を目指し,経済建設を最優先とした諸政策が進められた。
10月1日には建国35周年祝賀式典が開催された。また,数年来の農業体制改革の成果を踏まえて,党12期3中全会(中央委員会第3回全体会議)で,「経済体制の改革に関する中共中央の決定」が採択され,都市を重点とした経済体制改革が開始されることとなった。83年末から行われていた「整党」は,84年末より第2期として順次地方レベルで開始された。
香港問題に関しては,「一国家二制度」構想に基づいて解決が図られ,12月中英合意文書に両国首相が正式に署名した(85年5月発効)。
(ハ)カンボディア情勢は,84年も膠着状態が続いた。
ASEAN側は,外交面で,ヴィエトナム軍の撤退及びカンボディアの民族自決を柱とする「包括的政治解決」を追求した。これに対し,ヴィエトナム側は,84年11月からの乾期に,タイ・カンボディア国境地帯で大規模な攻勢を開始し,85年3月までに民主カンボディア派の本拠地を軒並み攻略する等,カンボディアの既成事実化(「ヘン・サムリン政権」の存続)を追求した。
中越間では,国境地帯で緊張が続いており,関係改善へ向けての動きは見られなかった。また,ソ連は,カムラン湾における軍事プレゼンスを引き続き増強した。
フィリピンの政情は,84年も注目を浴びた。5月の国民議会議員選挙では,与党が最終的に過半数を維持したものの,野党も大幅に進出した。10月には,アキノ暗殺事件について,軍部の関与を指摘する調査報告書が公表され,85年1月に起訴が行われた。秋には一時マルコス大統領の健康の悪化がみられた。共産党勢力が,農村地域を中心に活動を活発化したことも注目された。
(ニ)南西アジアでは,インディラ・ガンジー印首相の暗殺(10月)にかかわる諸情勢の展開が注目された。
ラジーブ・ガンジー新首相(前首相の長男)は,12月下旬,懸案の総選挙を実施した。そして,新首相への同情,清新なイメージ,強力且つ安定した中央政府への期待等を背景に,空前の勝利を収め確固たる地位を築いた。
対ソ関係では,ウスチノフ国防相の訪印(84年3月),ガンジー新首相の訪ソ等,頻繁な要人往来が見られた。対米関係では,新首相就任後,米国国防省幹部,ボルドリッジ商務長官(同長官訪印時,技術移転に関する了解覚書調印)等が相次いで訪印した。ガンジー首相も85年6月訪米した。
印パ関係は,84年後半以降シク教徒の動き等をめぐり冷却化した。ガンジー首相は,就任演説で近隣諸国との関係増進に前向きの姿勢を示してはいるが,パキスタンの核兵器開発,高性能武器入手等に対する印の懸念も依然大きい。
パキスタンでは,84年12月ハク大統領が国民投票で圧倒的な信任を得て,引き続き5年間政権を担当することとなった。しかし,85年3月ハク大統領が故チェルネンコ書記長葬儀に参列した際,ソ連のゴルバチョフ書記長は,パキスタンのアフガニスタンに対する干渉がなくならない限り,両国関係に否定的影響が出る旨,厳しい態度を示した。
(ホ)豪州では,84年12月総選挙が行われ,ホーク首相率いる労働党が引き続き政権を維持することになった。ホーク首相は,香港,日本,中国,韓国,シンガポール,マレイシアを訪問する等,アジア・太平洋重視の外交を展開した。
ニュージーランドでは,7月の総選挙で8年ぶりに労働党政権が誕生したが,米国との間で核艦船の寄港問題をめぐり,ぎくしゃくした関係が続いた。
(2)米州情勢
(イ)米国では,11月6日大統領選挙で,レーガン大統領が民主党のモンデール候補を大差で破り,再選を果たした。
レーガン再選の要因として,景気回復,力と威信の回復というテーゼへの共鳴,レーガン大統領の個人的人気の高さ等が挙げられている。第2期レーガン政権は,かかる国民世論の支持を背景に,財政,貿易,税制等の経済問題,及び,対ソ軍備管理交渉等外交上の諸問題に取組みはじめた。
(ロ)カナダでは,通算15年余政権にあったトルドー首相の辞意表明を受けて,6月自由党党首選で,ターナー元蔵相が新党首に選出された。
ターナー首相は9月総選挙を実施したが,変化を求める国民の気運,選挙戦でのミス等が重なり,マルルーニー党首率いる進歩保守党の歴史的圧勝となった。マルルーニー首相は,外交面では対米関係,NATO重視の姿勢を示すと共に,内政面では連邦と州の関係改善,財政赤字削減,経済の活性化等の経済問題に取組んでいる。
(ハ)中米情勢は84年全体として厳しさを増した。
メキシコ,パナマ,コロンビア,ヴェネズエラからなるコンタドーラ・グループは,84年も中米問題の平和的解決のための努力を継続し,9月に「中米和平協力協定案(改訂版)」を中米5か国(グァテマラ,ホンデュラス・エル・サルバドル,ニカラグァ,コスタ・リカ)に提示した。
これを受け,10月には,ニカラグァを除く中米4か国が,安全保障面等においてさらに改正すべき点があるとして,「見解文書」を提示する等の動きを示した。85年に入ってコンタドーラ・グループ及び中米5か国の代表によって全権代表会議が開催され,和平協定案に関する最終的な調整が行われている。
シュルツ国務長官のニカラグァ訪問(6月)を契機に,米・ニカラグァ間で直接交渉が9回開催された(85年1月中断)。84年末から,ニカラグァの大統領選挙,米国のニカラグァ反政府勢力への支援問題等を巡って,両国間の緊張が高まった。米国は,85年5月に対ニカラグァ経済制裁措置を発表した。
(ニ)84年,中南米諸国全体としては,経済回復の兆しがみられたものの,累積債務,インフレ等困難な経済問題が存在することに変わりはなかった。
中南米諸国は3回にわたり中南米債務国会議を開き,累積債務問題が単なる経済問題にとどまらず,政治的社会的困難を惹き起こしているとの観点から,「債務国と債権国との政治的対話」を呼び掛けた。
84年11月にウルグァイが,また85年1月にブラジルが21年振りに,それぞれ民選大統領を選出する等,中・長期的趨勢として,南米諸国で民主化の進展がみられた。
(3)欧州情勢
84年東西関係が流動的に推移する中,欧州諸国の動きは一様ではなかった。
(イ)米1NFの西欧配備は,西独,英,伊各国においては,ほぼ予定通り進捗している。ベルギーでは,85年3月になって巡航ミサイルの配備が開始された。他方,オランダは84年6月になって,議会決議を受けて巡航ミサイルの蘭内配備開始の最終決定を,85年11月まで延期する旨発表した。
レーガン大統領が提唱したSDI構想に関しては,西欧各国は,米国をはじめとする同盟国と緊密に協議を行いつつ,政治面・戦略面での意味合い,研究参加の可能性等,種々の観点から,対応ぶりにつき検討を開始した。なお先端技術に関して,85年4月仏は,西欧独自の「ユーレカ計画(欧州先端技術共同体構想)」を西欧各国に提示した。
(ロ)東欧諸国においては,米INFの西欧配備,ソ連の東独・チェッコヘの核ミサイル追加配備に伴い,危機意識が高まり,緊張緩和への願望が強まった。
かかる情況を背景に,東欧諸国は,平和な国際環境の醸成をめざし,また経済不振等の困難を打開するため,自主的な対西欧外交を進める姿勢を強めた。とはいえ,84年9月ホネカー東独書記長とジフコフ=ブルガリア書記長の西独訪問が,相次いで無期延期されたことは,東欧諸国の自主外交も,ソ連の許容範囲内でのみ可能であることを改めて示すものであった。
(ハ)85年3月チェルネンコ書記長が,就任後僅か13か月で死去した。ブレジネフ,アンドロポフ,チェルネンコと,指導者が短期間に相次いで死去したことから,世代交替の観点からも,後任書記長人事が内外の関心を集めた。そして,チェルネンコ書記長死去発表後,異例の早さで,若いゴルバチョフ政治局員(54歳)の新書記長選出が発表された。
ゴルバチョフ新政権は,内外政策において,従来の基本路線を継承する旨宣言している。内政面では,人事刷新,規律強化及び経済実験等,アンドロポフ路線を継承しつつ,最大懸案である経済再建を図ろうとするものとみられる。外交面では,就任演説において,「最近の中央委諸総会にて作成された戦略路線は従来通り不変である」旨述べ,対外路線に基本的変化がないことを明らかにした。ゴルバチョフ政権は,当面内政面に重点を置きつつも,外交上は,対米関係の再構築,及び,東欧,アフガニスタン,中国,インド等周辺諸国との関係に力点を置くものとみられる。
(4)中近東・アフリカ情勢
(イ)PLO内紛により軍事的敗北を喫したアラファトPLO議長は,84年に入ると主導権回復を狙って,ジョルダン及びエジプトとの関係強化を図った。84年11月には,中間派及び反アラファト派の参加を得ないまま,アンマンでパレスチナ民族評議会(PNC)の開催に漕ぎ着けるまでに至った。
85年2月には,アラファト議長とフセイン国王との間で,パレスチナ問題の解決に向けての所謂「フセイン・アラファト合意」が成立した。これは,国連諸決議に基づく領土と和平の交換を主眼とした和平を目指したものである。PLOが黙示的ながらも,初めて公式に安保理決議242号を認めたとも解釈し得る点が注目される。
ムバラク大統領は,同合意を踏まえ,2月末「まずジョルダン・パレスチナ合同代表団と米国とが対話を行い,次いで同合同代表団とイスラエルとが交渉を行うことを求める」との提案を行い,3月米国を訪問した。
(ロ)レバノンでは,84年4月各派指導者を取り込む形で,カラミ挙国一致内閣が成立した。同政権は,治安の維持・回復及びイスラエル軍の撤退に取組んだ。しかし,9月には米大使館爆発事件が発生する等,治安は悪化の一途をたどり,イスラエルとの撤退交渉も行き詰まった。85年1月には,イスラエルがレバノンからの3段階撤退を一方的に決定したが,その第1次撤退が開始された直後から,予想される撤退後の軍事的空白をめぐり,各派の主導権争いが激化した。4月にはベイルートにも戦火が拡大し,一時はカラミ首相が辞意を表明する(後に撤回)事態までに発展した。こうした中,シーア派の勢力拡大が見られた。
(ハ)イラン・イラク紛争では,84年2月のイラン軍の地上攻撃を皮切りに,3月末以降のタンカー攻撃(5~6月にピークを迎え,以降徐々に鎮静),6月の相互都市攻撃等が見られたが,戦況は総じて膠着状態のまま推移した。
85年に入り,イラク軍は限定的ながらも積極的攻撃に転じ,3月4日のアフワズ攻撃を機にイラン諸都市に対する空爆を敢行した。これに対し,イランもバグダッド・ミサイル攻撃等の報復措置をとり,両国間で激しい相互都市攻撃が展開された。4月に,国連事務総長の両国訪問が実現し,事態は鎮静化に向かった。しかし,イラクが,クウェイト首長暗殺未遂事件(5月25日)の背後にイランが存在するとし,かつイランがラマダン停戦を拒否したとして,再びイランを空爆したことから,事態は再び緊迫の度を増した。
(ニ)アフリカにおいては,干魃による食糧危機が深刻化した。
今次干魃は,従来の干魃がサハラ砂漠南縁地域に集中して発生していたのに対し,東部アフリカ及び南部アフリカをも含む,アフリカ全域に及んでいることを特徴としている。アフリカでは,約1.5億人が飢餓ないし栄養失調の危険にさらされていると,国連等で報告されている。
ナミビアをめぐっては,84年2月に南アとアンゴラ間で事実上の停戦合意がなされ,アンゴラ領内に侵攻していた南ア軍は,南ア・アンゴラ合同監視委員会の監視の下に撤退することとなった。南ア軍は徐々にナミビア国境に向け撤退を開始し,85年4月に至り,南ア軍のアンゴラ領からの撤退が実現した。
84年9月に,南アでは新憲法が発効し,人種別三院制議会が発足した。しかし,新憲法体制の下でも,国民の7割以上を占める黒人には,依然として参政権が付与されていない。
チャド問題については,仏・リビア軍の撤退合意(9月),ブラザビル和平準備会合(10月)等があったが,依然解決の目途は立っていない。
84年11月にアディス・アベバで開催された,第20回OAU首脳会議で,モロッコはOAUからの脱退を宣言した。
4.国際経済の動向
84年は,先進国経済が,83年に始まった世界的な景気回復を基礎に,第二次石油危機が残した不況とインフレから脱却する足掛かりをつかんだ年であった。また景気回復(OECD加盟国実質GNP成長率4.9%見込)が,国際政治の動向に安定感を与えた面もあった。
今次景気回復に主導的役割を果たしてきた米国経済については,当面緩やかな拡大基調が持続すると見込まれているが,大幅な財政赤字,経常収支赤字を抱える中で,拡大スピードが減速してきており,先行き警戒感もみられる。欧州経済も,全般的に回復基調にあるが,雇用情勢は依然厳しく,構造調整の遅れという問題がある。
開発途上国経済も,84年は先進諸国の景気回復基調の下,アジアのNICs等を中心に輸出が増大する等,やや明るさを増した。中南米諸国等の累積債務問題も,多年度リスケ等の債務救済や債務国側の努力もあり,最悪の事態を乗り切っている。とはいえ,途上国経済の回復には大きな跛行性がみられ,特に低所得アフリカ諸国は,一次産品輸出の停滞,干魃の影響深刻化に苦しむ等,依然として多くの困難に直面している。
国際石油市場では,非OPEC産油国の着実な増産もあり,84年も需給緩和基調で推移した。スポット取引の大幅な拡大,先物市場の発達,精製設備高度化による原油需要構成の変化,産油国の石油製品輸出等,市場原理の高まり,ないし市場の構造的変化とも言い得る動きも顕著となった。これに対し,OPEC諸国は,10月の総会で生産上限を引き下げ(1,750万→1,600万B/D),12月及び85年1月の総会で,油種間価格差の調整,加盟国監査制度の設立等を以て対処した。しかし,自由世界の石油供給に占めるOPECのシェアは,依然低下傾向にある(84年40.3%)。
世界貿易は84年に9%増(数量ベース)と急速な拡大を示したが,経常収支の不均衡も大幅に拡大した(84年米国経常収支赤字1,016億ドル)。また,景気回復の地域別・産業別の跛行性,失業問題等も相まって,保護主義的動きには根強いものがあった。これに対し,OECD閣僚理事会(85年4月),ボン・サミット(同5月)等の場においては,適切なマクロ政策,構造調整,市場開放努力等,各国が協調しつつ諸施策を確実に実施すること,及び,自由貿易体制の維持・強化のため,新ラウンドを早期開始することにつき合意された。