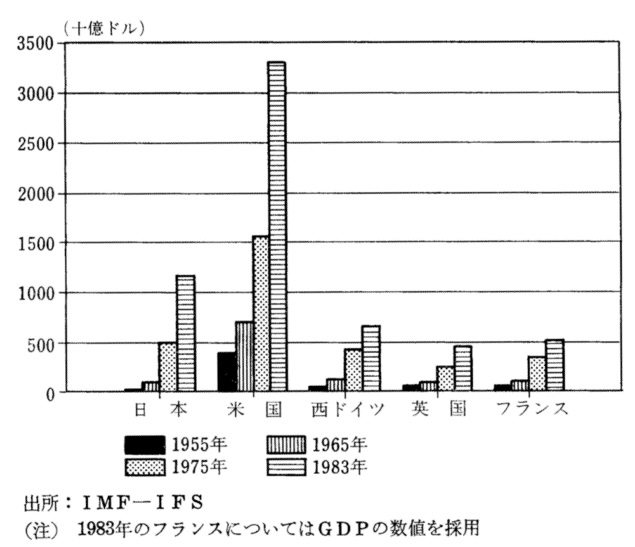
第1章 我が外交の基本課題
―戦後40年を迎えて―
はじめに
戦後40年の節目に当たる1985年において,我が外交のこれまでの軌跡を回顧し,相互依存の高まる国際社会において我が国の果たすべき役割に想いをいたし,世界の平和と繁栄のために貢献するとの決意を新たにすることは極めて重要である。
我々が戦後40年間享受してきた平和と繁栄は,日本国民の絶えざる努力の成果であることはもとよりであるが,同時に,我が国もその一員である国際社会とこれまでの国際秩序に負うところ大であった。
自由世界第2の経済力を持つ安定した民主主義国家としての地位を確立した現在,我が国は,自由民主主義諸国の一員及びアジア・太平洋地域の国としての基本的立場に立って,国際社会の平和と繁栄に積極的に寄与していかなければならない。
本年5月のボン・サミットで採択された政治宣言の以下の部分は,戦後40年の節目に当たって,自由と平和を信奉する諸国にとって共通の課題である。
「第二次大戦の筆舌に尽くし難い苦痛及び平和と自由の40年という共通の体験を回顧する時,我々は,改めて,すべての国民が平和,正義並びに抑圧,欠乏及び恐怖からの自由の恩恵に浴しうる世界,即ち,個人が自分自身,家族及び社会に対する責任を果たしうる世界,大小を問わずすべての国々が全人類のよりよい将来を求め相携えて働く世界の創造のために我々自身と我々の国を捧げるものである。」
1.我が国が選択した外交の基本的立場
(1)自由民主主義諸国の一員としての立場
40年前の終戦に際し,戦争の残した惨禍の中で,日本国民は平和で豊かな国をつくることを決意した。その後,我が国は,米国との安全保障体制の下,憲法の認める最小限の自衛力を維持して我が国の平和と安全保障を確保するとともに,他の自由民主主義諸国と協調して,我が国の平和と繁栄にとって欠かせない世界の平和と繁栄を維持するとの選択を行った。
我が国は,各国が国際連合を結成して,武力の不行使を誓い,諸国間の協力によって世界の平和と安全を維持しようとした理想を強く支持し,1956年の国連加盟後は国連との協力を我が国外交の最重要課題の一つとして,積極的に努力してきた。
国連は,地域的な平和維持活動の展開,国連海洋法条約のような普遍的な規範の法典化,開発途上国の発展のための国際協力など多くの分野で成果を収めてきた。しかし,世界の平和を効果的に担保するという国連に期待されている機能については,幾多の努力にもかかわらず,未だ理想にはほど遠い状況にある。
このため,各国は,憲章に認められた個別的又は集団的な自衛権の行使を確保するための措置を講ずるなどして各々の安全を図っている。また,世界全体としては,戦後間もなく始まった東西の冷戦以降,米ソ両国の間の力の均衡によって,平和が保たれてきたというのが現実である。
このような現実の下において,我が国は,絶えざる外交努力,日米安全保障体制と自衛力の保持という枠組によって,戦後三十余年の間,我が国の平和と安全を確保してきた。今や,この枠組は国民の間に広く受け入れられ,定着したと言いうるが,我が国をめぐる軍事情勢は厳しさを増しており,我が国は,なお一層の外交努力を払うとともに,日米安保条約の円滑かつ効果的な運用を確保し,憲法の許す範囲内での自衛力の着実な整備を図ることによって,我が国の平和と安全を保つ努力を続けている。
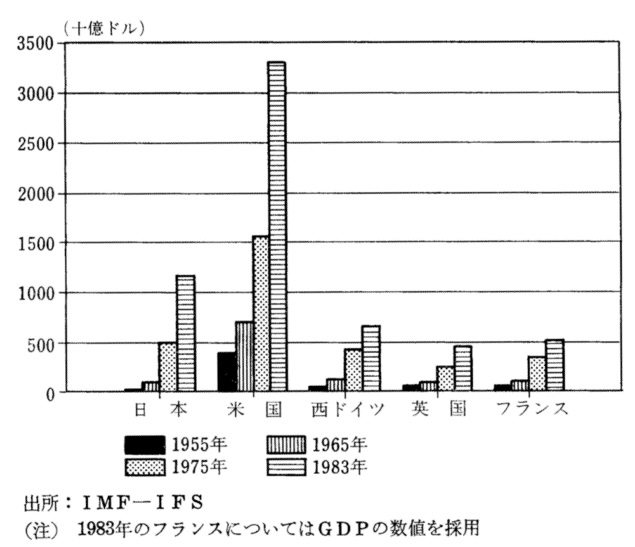
出所:IMF-IFS
(注)1983年のフランスについてはGDPの数値を採用
過去40年の間に,我が国は国民の努力と恵まれた国際環境によって,史上かつてない繁栄を達成し,今やその経済規模は,世界全体の約10%を占め米ソに次ぐまでになった。また・安定した民主主義国としての我が国の平和を志向する対外姿勢と地道な外交努力は,次第に諸外国の信任と評価を獲得するに至った。このように我が国の国際社会における地位が高まるに伴って,我が国の動きが世界政治・経済に影響を与える度合も増大し,我が国は,世界政治・経済の運営に大きな責任を持つようになった。
我が国の海外活動の発展,なかんずく経済活動の相互依存関係の深化に伴って,我が国の諸外国に対する関心の輪も広がり,今や,我が国は,その対外政治・経済政策について,広く世界の国々と緊密な協調を図るよう求められるに至っている。
戦後の我が外交における中心は,一貫して,我が国の外交の基本的立場である自由民主主義諸国との緊密な連帯と協力である。
人権の尊重と議会制民主主義を基盤とする我が国の民主政治体制を維持し,自由市場経済に基づく我が国の経済発展を継続して,我が国の平和と繁栄を維持していくためには,自由,民主主義及び市場経済という価値観を共有する諸国との協力が不可欠である。
このような協力の場としては、主要国首脳会議(サミット)やOECD(経済協力開発機構)が重要な協議・協調の場となっている。本年5月2日より4日まで西ドイツのボンで開かれたサミットでは,第2次大戦終戦40周年に際して,このような自由民主主義諸国の自由・民主主義堅持の決意と,相互の連帯を再確認するとともに,重要な経済的挑戦に対し,協力して対処することに合意した。
(2)アジア・太平洋地域の国としての立場
我が国は地理的にアジア・太平洋地域に位置する。また,この地域の他の諸国と多くの歴史的・文化的遺産を共有している。
しかし,我が国は,先の大戦において,この地域の多数の国に戦争の惨禍を残した。我が国の戦後外交は,このような過去への責任と反省に基づき,近隣のアジア・太平洋地域の国々との間において,賠償など戦後処理,国交正常化の話し合いから始まった。我が国自身,戦争の惨禍から復興するという苦しい状況の下にあって,我が国は誠意をもって最善を尽くすべく努力してきた。これが,アジア・太平洋地域の諸国との友好関係の増進と域内開発途上国の発展への協力という,我が外交のもう一つの柱の起点であった。
今や,アジア・太平洋地域は,世界で最も活力に満ちダイナミックな発展を示している地域となっている。我が国は,この地域の国々の中には,先の大戦に根ざした複雑な対日感情が残っていることを従来より謙虚に受けとめ,この地域の安定と繁栄の一助となるべく努力を積み重ねてきた。こうしたアジア・太平洋諸国と我が国との協力関係の強化は,我が外交の積極的展開の前提であり,かつ,主要な要素である。その意味で今後ともこれら諸国との友好協力関係の強化に一層の努力を払っていく必要がある。
中国と我が国とは,かってない安定した良好な関係にあり,同国との安定した友好協力関係は,アジアの平和と安定にとって肝要であり,長期にわたり維持・発展されるべきである。
日韓関係については,正常化以来の両国関係緊密化の新時代を画するものとして,中曽根総理大臣の訪韓を受けて全斗換大統領の訪日が行われた。日韓両国が今後互いに成熟した友邦として,永遠の善隣友好協力関係を維持していくことが重要である。
ASEAN諸国との間では,従来より,二国間の協力関係に加えて,ASEAN拡大外相会議などの場を通じて,協力関係を深めている。
84年に行われた中曽根総理大臣のインド,パキスタン訪問は,我が国のアジア外交の深さに加えその広がりを確認した。
また,85年初頭の中曽根総理大臣の豪州など4か国訪問は,大洋州諸国との関係緊密化を一層促進した。
アジア・太平洋地域では,広くこの地域を包含した「太平洋協力」の構想が,60年代以降各方面で検討されてきたが,最近,その気運がとみに高まり,各種協議機構で協力促進の検討が進められている。このような協力は,21世紀を見通した長期的視野から,
(あ)経済・文化・技術面を中心とし,
(い)排他的とならず開放的な協力として,
(う)ASEAN諸国などの自発的意志を尊重し,
(え)民間活動を支援しつつ進められるべきである。
この意味で,ASEAN拡大外相会議の場で太平洋協力が検討され「人造り」協力が進められつつあることは,この地域の「国造り」に資するものとして重要であり,また,民間活動が着実に成果を挙げてきていることは意義深い。
2.戦後の我が国の外交努力と今後の課題―平和と繁栄を求めて
このような基本的立場に立って,我が国は,戦後自ら目指した平和で繁栄した国家を達成すべく,外交努力を重ねてきた。
当初の段階においては,まず我が国の国際社会への復帰を果たすとともに,我が国の安全の保障と,国民の最低限の福祉を充足するための経済基盤の確保が急務であった。このため,我が国は,まず,52年,サン・フランシスコ平和条約締結と同時に日米安保条約を締結するとともに,漸次自らの自衛力を維持拡大して国の安全を確保するとの選択を行った。
我が国の主要国際機関・会議への参加等
IMF・世界銀行 ………………………1952年
ガット …………………………………1955年
国際連合…………………………………1956年
OECD ………………………………1964年
主要国首脳会議 ………………………1975年
さらに我が国は,IMF・世銀加盟(52年),ガット加入(55年),国連加盟(56年)と国際社会への復帰を進めた。次いで,57年の国連安保理初当選,63年のガット11条国への移行,64年のIMF8条国移行,OECD正式加盟を経て,国際社会における先進民主主義工業国としての地位を確立した。
この間,我が国外交の目標は,世界の主要国に追い付くことであったと言っても過言ではない。しかし,我が国が目覚ましい経済発展を遂げて,世界有数の経済力,工業水準を達成するに至った現在,我が国は,主要国の重要な一員となったことで足れりとする段階を過ぎたと言える。
我が国が,戦後,自由で民主的な政治体制を維持し,経済発展を遂げられたのも,同じ政治理念を維持する国々との協力関係を含め比較的恵まれた国際環境及びこれまでの国際秩序に負うものであり,我が国は,今後ともその維持・増進のために積極的な貢献をしていかなければならない。このことは,現に我が国が国際社会において占めるに至った位置付けからして,たとえそれが自己犠牲を伴うものであっても,取組んでいかなければならない課題である。
我が国は,このような世界における自らの地位に伴う責任を果たすことの必要性を認識し,それが究極的に我が国の国益に資するゆえんであることをはっきりと理解しなければならない。このような発想の転換の必要性は既に言われて久しいが,現在我が国が直面する世界情勢は,時の猶予を許さない状況にあり,我が国は大胆に,かつ,積極的にその外交課題に取組まなければならない。
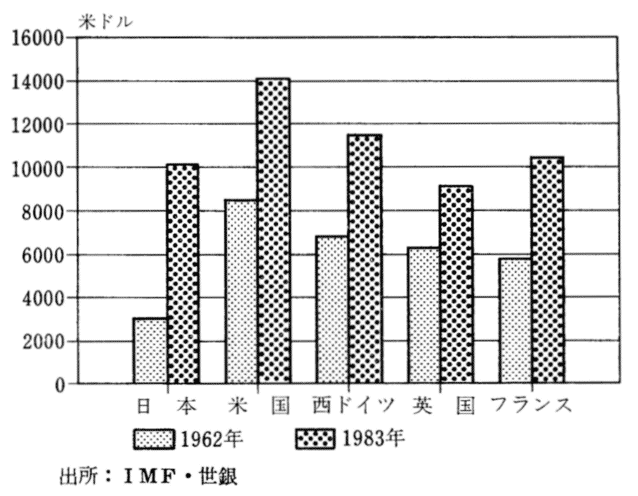
出所:IMF・世銀
(1)「開かれた日本」を実現するための努力
我が国は,戦後の復興・経済発展の過程において,自分自身の安全と繁栄を達成することに専念する余り,国際情勢に対して受動的に対応しがちであった。しかし,現在,世界の各地では,紛争や緊張が続き,多くの国が経済困難を抱え,開発途上地域では何億という人々が飢えと貧困に苦しんでいる。
日本国民が一丸となって戦後の苦境を乗り越えるに際し,重要な力となった,助け合いと調和の精神が国際関係においても遺憾なく発揮されていかなければならない。また,我が国だけの繁栄を求めることも相互依存の高まった今日の国際社会においては不可能である。我が国は,社会的に,経済的に,そして意識の上でも,世界に開かれた国際国家日本の実現を目指して努力しなければならない。
我が国が,戦後の荒廃の中から立ち上がり急速な経済発展を実現することができたのは,IMF・GATT体制下での多角的で無差別な自由貿易制度に負うところが大である。現在,世界各国の貿易依存度はますます高まってきており,特に日本の場合は,食糧,エネルギー等の一次産品輸入及び工業製品の輸出において,海外に決定的に依存している。
近年の世界経済の低成長傾向のみならず構造的要因に根ざしている保護貿易主義が世界に蔓延し,自由貿易体制が崩壊すれば,世界貿易は混乱に陥り,我が国は最も深刻な影響を受けることとなるであろう。我が国としては,自由で多角的な貿易体制を守り,世界経済の健全な発展を確保していくため,日本の地位にふさわしい役割と責任を果たすべく,国際化を推進していかなければならない。
1985年4月9日発表の対外経済対策(要旨)
1.対外経済問題諮問委員会報告への対応
(市場アクセス改善のための行動計画の策定等)
2.当面の措置と政策プログラム
(1)関税引き下げ,基準認証の改善
(2)製品輸入の促進
(3)電気通信,エレクトロニクス分野での市場アクセスの改善
(4)金融・資本市場の自由化及び円の国際化の促進
(5)節度ある輸出の確保
(6)経済協力の拡充
(7)投資交流の促進等
(8)外国弁護士の国内活動
国際化の推進とは経済面においては,財,サービス,資本の自由な流れに対する公式・非公式の障壁の除去を目指すことであり,特に諸外国が比較優位を有する製品等を積極的に我が国市場に迎え入れていくことである。
この過程で我が国は,これまで我が国の伝統や社会の特殊性によるものとして許容されてきた制度,慣行についても普遍性,合理性の観点から,これを見直し,積極的に国際社会との同質化を目指していくことが求められている。
最近の対外経済摩擦の高まりに対応するため,我が国は81年12月以来,一連の対外経済対策を決定,実施し,一定の成果をあげてきたが,これらの対策は,ややもすると,諸外国からの市場開放要求に対しその都度対応していくという受動的側面が強かった。このような反省も踏まえ,84年12月には,民間有識者から成る,対外経済問題諮問委員会が設置され,同委員会の報告を受け,85年4月9日,政府は新たな対外経済対策を発表し,今後我が国として自主的かつ積極的に対外経済問題に取組んでいくとの強い決意を示した。
この4月の対策では,特に市場アクセス改善の分野に関し,今後3年間にわたる包括的な行動計画(アクション・プログラム)を策定し速やかに実施に移していくことを明らかにしている。関税の引下げ,輸入制限の見直し,基準認証・輸入プロセスの改善,政府調達,金融・資本市場の自由化,サービス市場の一層の開放等を内容とするこのアクション・プログラムの策定にあたっては,「原則自由,例外制限」という大胆な発想を採用していくことが肝要である。
我が国のように1億余の人口を擁する国で,人種,言語,文化がかくも同質であり,宗教,風習が政治問題化することがかくも少なく,かつ,中流階級意識がかくも広くゆきわたっているということは世界に稀なことである。この単一民族国家と称されている我が国の特質は,戦後40年,その復興と成長の過程において,総じて大きなプラスとして働いた。均質,勤勉なる単一民族国家において,その社会の網の目は相当に細かく発展し,資源に乏しい我が国の国際競争力を強いものとした。しかし,このことは,視点を変えれば,日本社会の閉鎖性と受け取られる側面を持つことを意味する。
我が国は,現在,単なる経済面のみならず,文化,社会などあらゆる面で海外での活動を広げているが,その一方において,我が国自身の社会を諸外国に閉ざしておくことは許されない。我が国社会が,国際社会のなかで正しい評価と位置付けを得るためには,閉鎖性を克服することが必要であり,それは端的に言えば異質なものへの寛容性と包容力を伴ったものでなければならない。
この点に関連し,我が国がインドシナ難民の受け入れを行っていることは,かかる開かれた日本に向けての第一歩であり,また,これは日本の社会にとっての試金石とも言えよう。
日本の社会は,歴史的かつ地理的な要因もあり諸外国から見れば理解しにくい面もあるかも知れない。しかし,相互依存関係にある現代の国際社会において,我が国が孤立することは許されない。我が国固有の制度・慣行について,国際化できる部分は国際化し,それが不可能な場合には不透明な状態にせず相手国に十分説明するという姿勢が重要である。
我が国を一層開かれたものとすることは,日本社会を活力あるものとし,我が国自身にとってもプラスとなろう。この課題の実現には,かなり長期にわたる困難な努力を必要としようが,かかる努力は国際社会における我が国の責務を果たすために不可欠であり,かつその努力が現在ほど求められている時はない。
(2)平和と軍縮への努力対話の促進
平和を守るためには絶えざる努力が必要である。先に述べた日米安保体制を堅持することに加えて,第一に,東西対話の促進,紛争解決・緊張緩和のための環境造りといった政治的働きかけを行わなければならない。国連の平和維持活動への協力,軍備管理・軍縮問題への取組など多国間の場における外交努力も必要である。第二に,自由貿易体制の維持・強化,世界経済の健全な発展への貢献,開発途上国の安定と発展のための協力といった国際経済面での努力も平和な国際環境を醸成する上で,おろそかにできない。
主要な軍備管理・軍縮交渉
ジュネーヴの軍縮会議
米ソ軍備管理・軍縮交渉
欧州軍縮会議
中欧兵力削減交渉
世界の平和と安定にとって最も直接的な関連を有する東西関係,なかんずく,米ソ関係は,ソ連の一貫した軍備増強,アフガニスタンにおける事態,SS-20の配備増強等を背景に基本的には依然厳しい状況にあるものの,最近は,本年3月の新たな米ソ軍備管理・軍縮交渉の開始,米ソ首脳会談の実現の可能性が出てきたことなど若干明るい兆しが見えてきた。
我が国は,安定した東西関係を構築すべく努力することが世界の平和と安定にとって不可欠であると認識し,力の均衡に基づく抑止が平和維持に果たす役割を認めつつ,軍備管理を中心とする米ソ間の対話と交渉の促進を求め続けている。
米ソ間の軍備管理・軍縮交渉に加えて,多国間軍縮の場における努力も重要である。我が国は,84年6月,ジュネーヴの軍縮会議で,核実験全面禁止に至る現実的方途として段階的方式を提案した。我が国としては,今後とも,多国間の場において,核実験全面禁止,核不拡散問題,化学兵器禁止の早期実現等に関し具体的な貢献を行うべく,努力を続けていくことが肝要である。
我が国自身が東側諸国との間で対話を行っていくことも同様に重要である。最近の日ソ関係は,厳しい東西関係及び極東におけるソ連軍の軍備増強等を反映してやはり厳しい状況にある。ソ連との関係については,日ソ間の最大の懸案である北方領土問題を解決して平和条約を締結し,真の相互理解に基づく安定的な関係を確立するという我が国の基本方針に変わりはない。
我が国としては,最近,徐々に進展しつつある日ソ対話を更に推し進めるべく,忍耐強く努力していく考えである。ソ連側においても我が国の考え方を正しく理解し,関係改善を具体的行動で示すことが期待される。
東西関係において重要な位置を占める東欧諸国との関係については,本年6月,安倍外務大臣のポーランド,東独訪問に見られるように,相互理解と友好関係の増進を図ってきているが,今後ともかかる努力を続けていく必要がある。
現在,世界の各地では地域的な紛争や緊張・対立状態が存在している。イラン・イラク紛争,レバノン内戦を含む中東問題,カンボディア問題,朝鮮半島,中米,南部アフリカ,アフリカの角地域等における対立は,未だ地域的なレベルにとどまっているが,米ソ両大国を巻き込みかねない危険性をはらんでいる。イラン・イラク紛争について,我が国は,もとよりこの紛争の調停・仲介を行う立場にはないが,この地域の平和と安定を願う気持から,紛争の早期平和的解決に向けての環境造りに独自の努力を重ねてきている。
また,我が国は,カンボディア問題の包括的政治解決へ向けてのASEANの努力を引き続き支援するとともに,ヴィエトナムとの対話を維持しつつ,問題解決のための環境造りに不断の努力を続けている。更に,朝鮮半島問題に関しては,南北両当事者間の対話の動きや関係諸国の動向に注目しつつ,その緊張緩和のため可能な努力を続けている。ボン・サミットにおいては,このような我が国の立場を踏まえ,政治宣言に朝鮮半島の分割の克服の必要性に関する部分が挿入された。
(3)世界経済の健全な発展への貢献
現在の世界経済は,84年における米国の力強い景気拡大等を契機として全体として見れば景気回復基調にあり,各国のインフレも沈静化している。しかし,米国をはじめとする先進諸国における大幅な財政赤字,高金利,ドル高,欧州を中心とした高水準の失業,及び経常収支の不均衡に加え,これらを背景に高まりつつある保護主義圧力,開発途上国における累積債務問題等,多くの懸念材料が存在している。特に85年に入り,米国の成長が鈍化傾向を示す中,世界経済の持続的成長への不安が高まっている。
このような状況の下,我が国が世界経済の発展のために先ずなすべきことは,自由貿易体制の維持・強化である。そのためには,我が国経常収支の不均衡是正の努力を払うとともに,ガットの下での新たな多角的貿易交渉(新ラウンド)を早急に開始することが急務である。我が国の努力もあって,85年のOECD閣僚理事会では,85年夏の終わりまでに新ラウンド準備のための高級事務レベル会合を開催することが合意され,また,ボン・サミットでは86年中の交渉開始についてサミット参加国の殆んどの国の賛同を得ることができた。今後は,この高級事務レベル準備会合等での討議を通じ,交渉の対象項目及び態様などを決めるとともに,広汎な開発途上国の参加をも得て,早期に交渉を開始することが必要である。
また,米国の経済成長の鈍化が懸念される中,世界経済の安定的発展を維持していくためには,我が国としても民間需要を中心とした内需の拡大を図っていくことが肝要である。このためには,規制緩和等による投資機会の創出を通じ,これまで公共投資が主導的な役割を果たしてきた社会資本整備,福祉等の諸分野へ積極的に民間活力を導入していくべきであり,また,一層の消費拡大を図っていかなければならない。
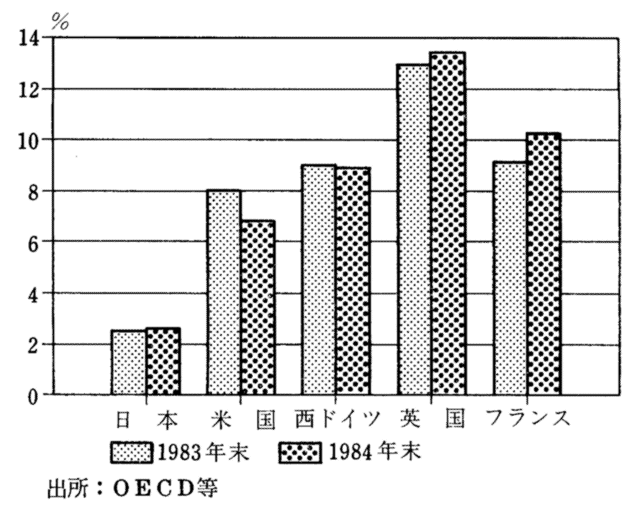
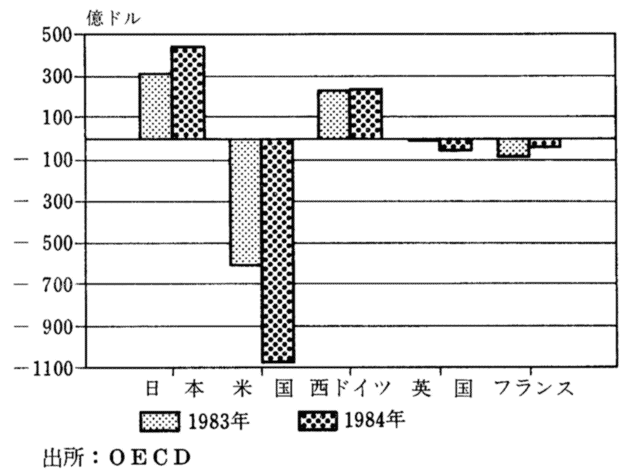
出所:OECD
国際通貨制度についても,85年6月東京で開催された10か国蔵相会議での検討結果を踏まえ,引き続きその機能改善に努めることが肝要である。我が国としては,国際的な努力に協力しつつ,我が国経済の世界に占める地位の向上及び国際金融の発展という趨勢の中で,積極的に円の国際的役割の増進に努めていく必要がある。
累積債務問題は,債務国経済のみの問題にとどまらず,政治的,社会的な問題を惹起し,更に国際金融上も大きな不安定要因となっており,国際社会全体が協力して取組まなければならない問題である。無論,問題解決のためには,債務国の自助努力が不可欠であるが,先進諸国としても,景気回復の持続,開放的な貿易,妥当な金利水準の実現等によって債務国の努力を支援していくことが必要である。我が国としても,国際機関等と協力しつつ積極的に取組んでいくべきである。
(4)開発途上国の安定と発展への協力
先進国を中心とした景気回復効果は開発途上国にも波及してきているものの,開発途上国の多くは一次産品価格の低迷,累積債務問題,高インフレ等の諸困難に直面しており,特に,難民問題,アフリカの飢餓・干ばつ問題の解決は急を要する。
開発途上国の安定と発展が如何に密接に世界の平和と繁栄に結びついているかは,開発途上国の政治的,社会的不安定が近隣諸国を巻き込んで地域的紛争へと発展する可能性があることを見ても明らかである。とりわけ対外経済依存度の高い我が国にとって,開発途上国の安定と発展に協力することは,我が国が国際社会において果たすべき責務であると同時に,我が国の繁栄と安定は平和な国際社会の構築によりはじめて確保しうるという意味で,我が国の国益にもかなうものである。
我が国の開発途上国に対する協力には,技術協力,資金供与等によって直接相手国の経済発展に貢献することから,開発途上国産品の我が国市場に対するアクセスの改善等を通じ,途上国の我が国に対する輸出拡大に協力することによって開発途上国の経済発展に寄与することまで多様な手段があり,これらを活用して総合的に協力を進めることが必要である。
我が国の対外経済協力の中心は,政府開発援助(ODA)である。二度にわたる中期目標の設定に見られるとおり,我が国は従来よりODAの計画的拡充に努めている。このような我が国の努力は国際的にも高い評価を得ているが,我が国がその国際的地位にふさわしい責任を果たしていくとの見地からは今後とも一層の努力が必要である。
このため,我が国は,昭和61年以降も,ODAに関する新たな中期目標を設定し,引き続きODAの着実な拡充に努めると同時に,可能な限り質の改善に努め,更には一層効果的・効率的な実施にも努力していく考えである。
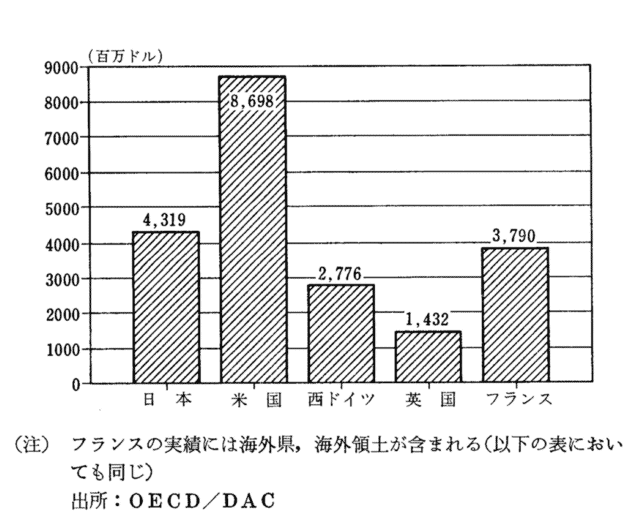
(注)フランスの実績には海外県,海外領土が含まれる(以下の表においても同じ)
出所:OECD/DAC
民間直接投資を促進することも重要である。民間直接投資は開発途上国にとって債務負担とならないだけでなく,経営ノウハウ,技術の移転等を伴い,開発途上国の経済基盤及び輸出能力の強化に効果的な役割を果たすものである。同時に,そのためには,開発途上国側の投資受け入れ環境の整備の努力が期待されている。
開発途上国の自助努力が実を結ぶためには,良好な国際経済環境の維持が是非とも必要である。本年のOECD閣僚理事会やボン・サミットにおいては,先進諸国が,景気回復の持続,開発途上国産品に対する市場開放,適正な金利水準の確保等に向けて努力することなど,国際経済環境の確保に努めるべきことが確認された。
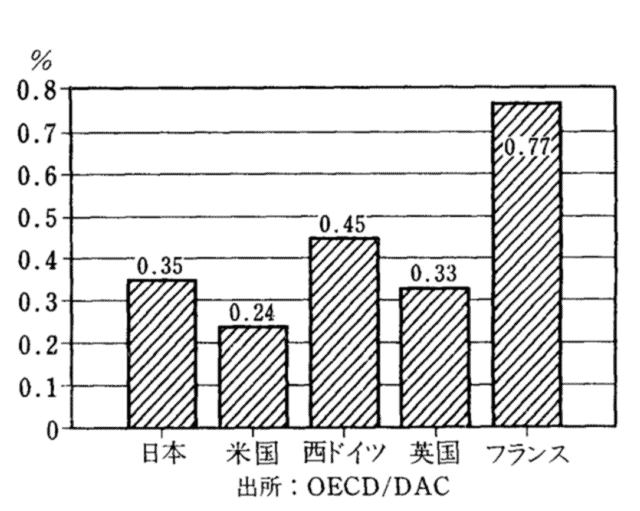
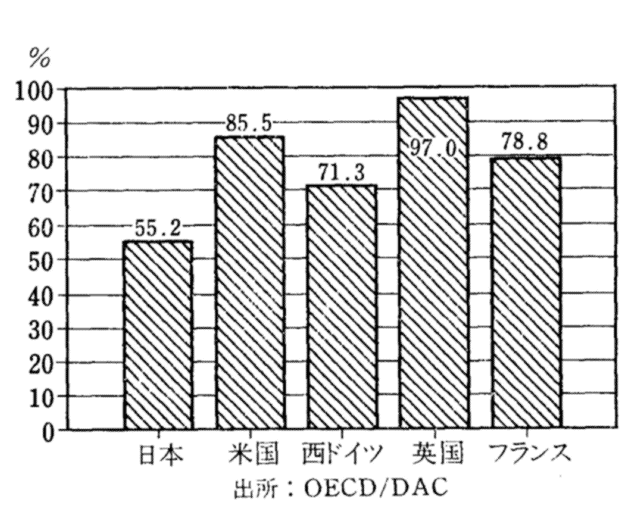
国連等多国間国際機関において開発途上国の発展のため先進諸国が協力・団結していくことも二国間ベースの協力と併せて重要である。
南北問題への積極的な取組の必要性が強調されて久しいが,その必要性は,いささかも減じておらず,我が国としては,従来の努力を更に続け,開発途上国の安定と発展に貢献していくことが肝要である。
このような我が国の積極的な姿勢を広く内外に示した最近の一つの事例は,飢餓・干ばつに悩むアフリカに対する支援である。84年の安倍外務大臣のアフリカ諸国訪問に加え,「アフリカ月間」の開催等もあって,日本国内の各方面でアフリカの危機についての関心が強まり,種々の募金,ボランティア活動,アフリカへ百万枚の毛布をおくる運動などに発展した。国連においても我が国の取組が評価され,アフリカ問題の討議の取りまとめを我が国が依頼されるまでになった。
今後ともこのようなモメンタムを失うことなく,官民を挙げてアフリカ諸国に対する協力を推進していくことが肝要であるが,更に,アフリカ支援運動にとどまらず開発途上国の安定と発展への協力という大きなテーマに対処するためには,政府レベルでの取組に加え,我が国民間各層の協力が不可欠である。
我が国の対アフリカ支援
1.民間活動
(1)募金総額約71.0億円(84年当初よりの総額)
(2)アフリカへ毛布をおくる運動
84年12月より85年2月末までの運動で,毛布約170万枚
(1枚3,000円で金額換算すると51億円相当となる)
2.サハラ以南アフリカに対する我が国の経済援助
(1)二国間ODAの推移
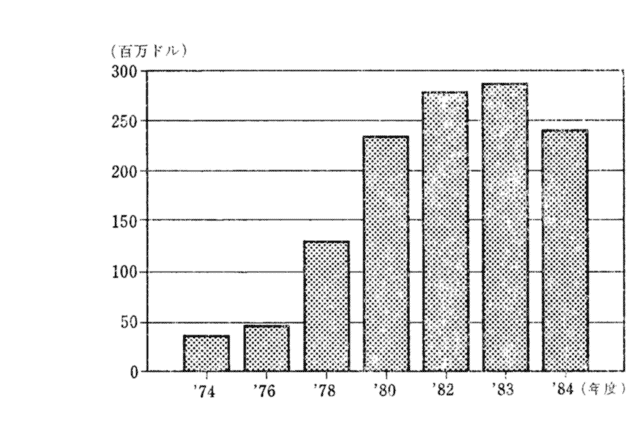
(2)二国間ODAの内訳(1984年)
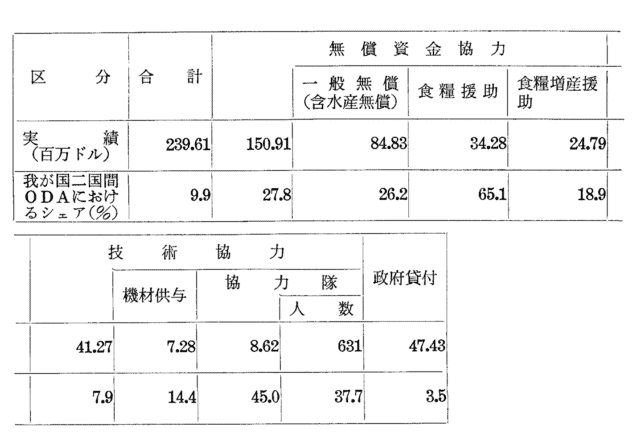
(5)安全保障政策の推進
我が国の平和と繁栄を確保するには,平素から我が国を取り巻く国際環境をできるだけ平和で安定したものとするよう努め,我が国に大きな影響を及ぼすような危機の発生を未然に防止することに意を用いなければならない。
既に述べたような種々の努力は,このために役立っている。
他方,そうした努力とともに,脅威が現実化した場合に対処するための備えを行っておくことも肝要であり,こうした備えを行ってこそ脅威が現実化することを抑止することができる。今日の国際社会の平和と安定が,究極的には力の均衡に基づいていることからも,これは明らかであろう。このような努力や備えに総合的な見地から取組むことは外交の中心的な課題であると言える。
自由民主主義諸国の一員である我が国の場合,この備えとして最も現実的な選択は,戦後の歴史が示す通り,自由と民主主義という基本的価値観を共有する米国との安全保障体制の堅持と必要最小限度の防衛力の整備であり,これによって,いかなる態様の侵略にも対応しうる体制を保持し,もって侵略を未然に防止することとしている。この選択は,現行の日米安全保障条約が締結されて以来四半世紀を経た今日,国民の大半が支持するところとなっている。
日米安全保障体制が我が国の安全保障の基盤であることに鑑み,同体制の円滑かつ効果的運用を確保し,その信頼性を高めることが我が国の安全保障にとって重要である。このような観点から,我が国は,米国との間で,防衛問題に関して緊密な協議を維持するとともに,「日米防衛協力のための指針」に基づく研究の推進,共同訓練の実施,対米武器技術供与取極の締結,F-16の三沢配備受け入れ,米軍の施設・区域の安定的使用のための努力等に代表される日米防衛協力を推進している。日米安全保障体制の信頼性の維持,向上のためには,良好な日米関係が基本であり,政治,経済,文化,科学技術を含めた広範で奥深いものとなっている緊密な日米協力関係を維持・増進することが重要である。
また,我が国は,日米安全保障体制を堅持するとともに,憲法の許容する自衛権の範囲内において,基本的防衛政策に従い,非核三原則を堅持しつつ,必要最小限度の防衛力の整備に努力してきた。現在,かかる考え方に基づき,厳しい国際情勢の下,「防衛計画の大綱」に定める防衛力の水準にできる限り早期に到達できるよう努力している。
今日,経済力の伸長に伴い,国際社会において我が国が果たすべき役割は益々大きくなっている。我が国としては,自由民主主義諸国の一員であり,アジア・太平洋地域の一国であるとの自らの立場を十分認識しつつ,平和と安定を求める努力を更に積み重ねていかなければならない。