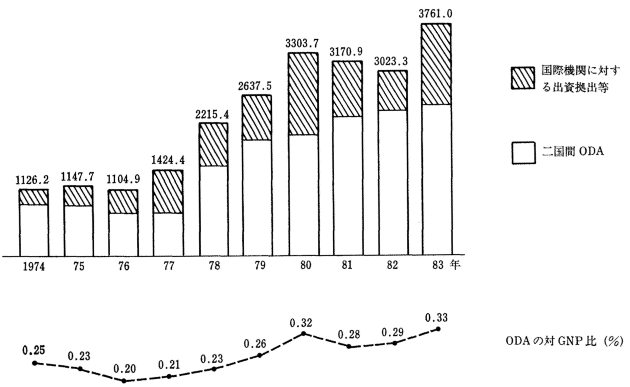
積極的姿勢を示すものである。
ODA事業予算全体では,対前年度比33.8%増の1兆2,952億円(対GNP比0.44%)が計上された。そのうち外務省所管のODA一般会計分は2,512億円(同8.1%増)とODA一般会計の約半分を占めている。84年度予算には,ODAの全般的質及び量の拡充に加え,(あ)基礎生活援助の拡充,(い)人造り援助の拡充,(う)効果的援助の実施を3本柱として援助予算の拡充に努め,国際協力事業団(JICA)を通じる技術協力の拡充及び無償資金協力の拡充を図った。
4. 効果的援助の推進
先進各国とも,財政困難を抱え,援助資金の大幅な伸びが望めないこともあって,援助の一層効果的な実施が求められている。
(1) 真のニーズの把握
効果的な援助には,まず相手国の真のニーズ(必要性)にこたえることが重要である。我が国は従来開発途上国の真の開発ニーズを見究めるための一つの方法として,開発途上国との「政策対話」を強化しており,具体的には年次協議,各種調査団の派遣等を通じて実施している。政策対話では先方の要望を聞くだけでなく,開発途上国側が,適切な経済政策をとっていくよう勧奨している。
我が国は,これら協議の結果を踏まえ,近年,援助の対象として,相手国国民が直接受益する基礎生活援助(農村・農業開発,飲料水,保健・医療,家族計画等)あるいは人造りに対する援助に重点を置いている。
(2) 評価
援助の実施後,我が国の援助が当初の目的に照らして効果を挙げているか,相手国の開発計画全体にいかなる貢献をしているか,さらに相手国との間の友好関係増進に役立っているか等の評価を随時行って,必要あれば改善措置をとり,また評価を通じて得た教訓を将来の援助に活かしていくことが重要である。このため外務省では,経済協力評価委員会の活動を引き続き強化充実するとともに,82年に続き83年11月に評価報告書を公表した。
(3) 先進国との政策対話
また先進国との間で援助政策に関する情報と経験を交換することは,援助資金の有効使用,また有効な援助政策の実施のための調整という観点から重要である。我が国は世銀,DAC等マルチの場での協議に加え,各先進国との政策対話を進めている。
(4) NGOとの連携
我が国の経済協力活動には政府のみならず,民間で協力活動に従事している非政府団体(NGO)の活動が重要な役割を果たしている。
特に,NGO活動は草の根にまで達するきめの細かい協力が行い得るなどの特質があり,我が国全体としての経済協力をより効果的,効率的に行っていくため政府としてもNGOとの連携及び協力の強化に努める考えである。
5. 援助を巡る国際的動向と日本
(1) 多国間援助と二国間援助
近年一部先進国の中には多国間援助(国際開発金融機関への出資等)に消極的な国も見られ,このため国際開発金融機関への出資・拠出交渉も必ずしも順調に進んでいない。多国間援助は,国際機関の専門性を活用できるなどの長所があり、我が国も国際社会の責任ある一員としてその拡充に努める考えである。
(2) プロジェクト援助とノンプロジェクト援助
先進国中には,深刻な経済困難におちいっている国に対しては,国内資金を必要とし,また時間の長くかかるプロジェクト援助より,国際収支改善に直接役立つ商品借款,債務救済等即効的なノンプロジェクト援助を重視すべきであるとの意見がある。我が国は,援助は開発途上国の自助努力を支援するとの考え方から従来よりプロジェクト援助を中心としている。しかし,我が国も相手国との二国間関係,その国際収支・経済事情等を踏まえ,必要に応じノンプロジェクト援助を実施していく考えである。
(3)混合借款(AF:Associated Financing)
OECD/DACでは,本来輸出信用や民間資金で賄われるべき商業的案件に対し,自国の企業への落札といった目的で希少なODA資金を併せて供与するなどODAが本来の趣旨から逸脱した目的に利用される傾向が急速に強まっているとの認識を踏まえ,5月AFの指針を採択した。
我が国は混合借款については従来から慎重に対応することとしており,援助案件としては適当であっても規模が大きいなどの理由により,円借款のみでは対応し難い案件についてケース・バイ・ケースで混合借款を供与している。
6. 国際協力総合研修所
技術協力は「人」から「人」へ,その全人格的触れ合いを通じて技術を移転することにより,開発途上国の「人造り」に寄与するという大きな意義を有している。したがって協力活動に直接従事する,十分な能力と豊富な経験を持った優秀な日本人専門家を十分に確保することが緊要となっている。このような人材の確保・養成のため10月に国際協力事業団(JICA)の付属機関として「国際協力総合研修所」が設立された。