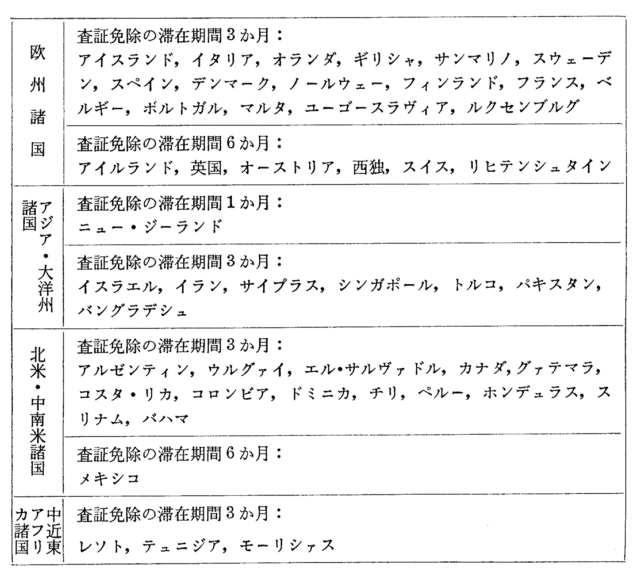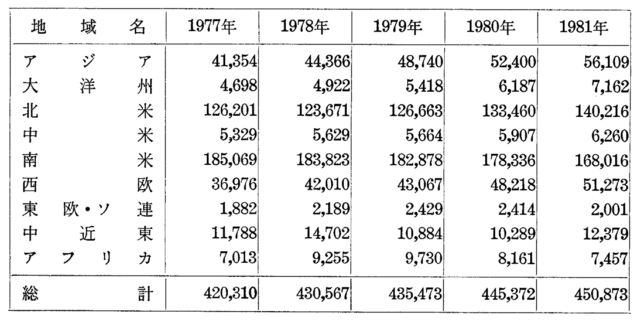
第6章 邦人の渡航と保護・援助
第1節 概要
国際的な相互依存関係が深まる中にあって,我が国の海外渡航者数は,80年に若干減少したものの,81年には再び400万人を超え,海外在留邦人数も45万人(長期滞在者20万人,永住者25万人)を超すに至っている。
外務省としては,かかる国際化時代の要請に即応するため,在留邦人の子女教育,医療等についての諸施策の充実に努めるとともに,在留邦人・邦人旅行者の保護・援助にも遺漏なきを期した。
特に,ラーマン=バングラデシュ大統領暗殺事件(5月末)及びポーランドの戒厳令布告(12月)の際には,通信途絶の厳しい条件下において,関係在外公館を動員し,現地在留邦人の安全確認及び保護に万全を期した。
国際テロリズム対策については,7月のオタワ・サミットにおいて,オタワ声明が出された。これは,航空機ハイジャックに関する78年のボン声明及び公館占拠・外交官人質事件等の国際テロリズムに関する80年のヴェニス声明を踏まえ,サミットのテロ対策を総合するとともに,パキスタン航空機ハイジャック事件に関連して,対アフガニスタン航空制裁を提案しているが,これは,ボン声明の具体的実施の最初のケースとして注目に値する。
第2節 邦人の渡航
1. 最近の傾向
63年の海外渡航自由化以来,一般国民による国際交流の活発化と観光渡航ブームにより,海外渡航者の数は,74年~75年の第1次石油ショックの時期及び80年の不況期を除き,年間20~30%前後の率で上昇の一途をたどり,79年には初めて400万人を超え,かつ戦後最高の水準に達した。81年も400万6,388人(対前年比2.5%増)となり,ほぼ79年の水準を維持している。これに伴い,国内における一般旅券発行数も,79年に最高の約198万件を記録した。80年には,この数値は,183万265件に一時的に落ち込んだ(対前年比7.6%減)ものの,81年には193万1,242件(対前年比5.5%増)に復帰し,再び79年の水準に近づきつつある。近年,これらの数字は,大体この水準で推移するかのごとき観を呈している(過去5年間の旅券発行数は別表参照)。
海外渡航者数と旅券発行数の推移は,国内経済の動向,海外情勢の推移,航空運賃等の諸要因に左右されるため,今後も流動的な面も排除し得ないが,一般国民の間に海外渡航熱が根強く存在していることから,たとえ上記の諸要因が悪化しても,当面の間,渡航者数が大きく減少する可能性は少ないものと考えられる。
5年間有効の数次往復用一般旅券は,70年に導入されて以来,旅券発行数の大部分を占め,81年には一般旅券発行総数の81%を占めている。
2. 渡航者の態様
(1) 観光渡航の主体は依然男性,青・壮年層であるが,最近,女性,中・高年齢者層の渡航が増加しつつある。
(2) 一般旅券の発行数を渡航目的別に分類すると,「観光」の比率が圧倒的に高く,81年では発行総数の91.3%を占め,次いで「経済活動」が7.4%となっている。
また,渡航期間別分類では,観光目的が多いことから,短期のものが多く,3か月以上の長期滞在(永住,赴任,留学,研究などで在留届の提出が義務づけられているもの)の割合は,81年には発行総数の2.0%にとどまっている。
(3) 一般旅券発給申請書によって81年の主要渡航先を地域別に分類集計すると,アジア(43.7%),北米(41.4%),欧州(10.0%),大洋州(3.3%)の順となっており,従来,このパターンに大きな変化はない。なお,77年以降アジアヘの渡航者の割合が減少しているのが目立ち,また,北米,欧州,大洋州への割合が増加しており,渡航先の多様化傾向が見られる。
(4) 81年の一般旅券発行数を年齢別に分類すると,20歳代(36.7%),30歳代(22.1%),40歳代(15.1%)の順は従来と同じである。
3.在留邦人
(1) 在留邦人数
過去5年間における在留邦人数の推移は,次のとおりである。
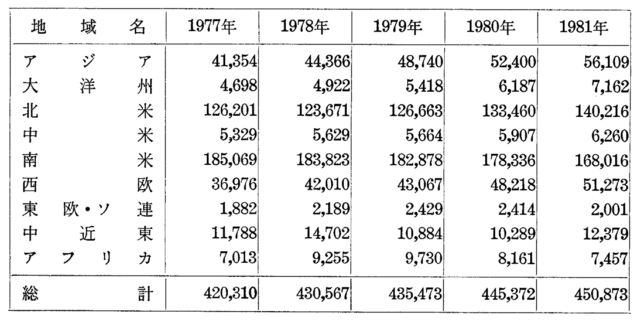
(2) 邦人団体
海外の各地に設立されている邦人団体の数は,次のようになっている(80年10月1日現在)。

第3節 緊急事態・事件に際する邦人保護
1. 近年,海外在留邦人数は増加の一途をたどり,また,世界各地で革命,クーデタ、内乱,紛争等が頻発していることから,在留邦人保護の任に当たる在外公館の責務は極めて重要なものとなっている。81年における緊急事態の主なものは,次のとおりである。
(1) 5月30日,バングラデシュにおいて,反乱軍がチッタゴン滞在中のラーマン大統領を殺害し,同地に立てこもった。政府軍側は,6月1日までに投降しない場合には,総攻撃をかける旨反乱軍に警告した。当時チッタゴンには約40名の邦人がいたが,通信手段が絶たれたため,現地大使館は,これら邦人の安全確保に留意するよう同国政府に要請した。また,チッタゴンが政府軍により制圧された直後,館員を現地に派遣して,邦人の安全を確認した。
(2) ポーランドでは80年以来緊張した状態が続いていたが,12月13日,同国国家評議会は全土に戒厳令を布告し,同時に国内外の通信手段が途絶した。当時,同国の在留邦人数は216名(うち,ワルシャワ在住172名)であったが,14日には現地大使館から戒厳令後の第一報としてワルシャワ在留邦人は全員無事と思われる旨報告が入った。
邦人在留地では,特に大きな衝突,混乱等は見られなかったが,14日に邦人技師3名が車で西独に脱出したのをはじめ,17日以降ポーランド航空臨時便が不定期運航を開始し,国際列車の運行も順調に進むようになり,在留邦人の出国者数は漸次増加した。
他方,地方在留者は通信の途絶により不安感に襲われていることが危惧されたので,17日には大使館員が邦人在留者の多い地方都市に出向いたほか,NHK国際放送を通じ,列車・航空機等による脱出が可能であるなど必要な情報を特別メッセージとして送った。その後も邦人の脱出は大過なく行われ,81年中に約60名が無事出国した。
(3) イラン・イラク紛争は依然未解決のままに推移し,10月には,イラクのバスラ地区で,邦人3名が砲撃により軽傷を負った。このため,現地大使館は,引続き邦人の安全確保に遺漏なきを期すべく努力している。
2. ハイジャックなど非人道的暴力行為事件は,81年中も世界各地で多発した。そのうち,邦人が人質となった事件は,3月のガルーダ航空機ハイジャック事件,5月のトルコ航空機ハイジャック事件及び12月のアエロ・ポスタル航空機ハイジャック事件の3件であった。トルコ航空機ハイジャック事件では,邦人2人が脱出の際負傷したものの,他の事件においては,人質となった邦人は,それぞれ無事救出された。いずれの事件においても,外務省は,関係在外公館と緊密な連絡をとりながら,人質邦人の安全救出のための努力を関係国に要請するなど,邦人保護のために最大限の努力を払った。
第4節 邦人に対する援助
1. 一般邦人,船員・船舶に対する援助
81年中に在外公館で取り扱い,外務省に報告のあった一般邦人に関係する事故件数は708件(955人)であった。このうち,地震,火災,風水害などの被害は11件(以下括弧内は死亡者数)(1人),船舶,航空機,列車,自動車事故75件(64人),山岳遭難,遊泳事故44件(65人),犯罪被害による死亡者10人,自殺(未遂を含む)31件(27人),病気101件(63人),精神異常49人,行方不明7人,邦人による殺人事件3件,窃盗詐欺7件などがあり,このほか,船員,船舶にかかわる犯罪,事故は101件(74人)であった。
これら事故,病気などにより援護の必要が生じた場合,外務省は在外公館と緊密な連絡をとりつつ,留守宅への通報をはじめ,当該邦人が安全かつ速やかに帰国できるよう最大の努力をしている。
また,81年には山岳事故が多発したため,山岳会等関係方面に対し事故防止につき注意を喚起した。
帰国を希望するが帰国費を負担し得ない邦人に対しては,審査の上貸付けを行っているが,81年の貸付けは13件(28人)であった。
2. 巡回医師団の派遣
外務省は,72年以来,海外在留邦人の健康維持の見地から,衛生環境が悪く,かつ,十分な医療施設のない開発途上国に在留する邦人を対象に巡回医師団を派遣している。81年度においては,中近東地域に2チーム,アフリカ地域に4チームアジア地域に3チームオセアニア地域に1チーム及び中南米地域に2チームをそれぞれ派遣し,約5,000名の邦人の健康相談に当たった。
3. 海外子女教育
5月現在,海外の学齢子女(小・中学生)は30,200名であり,このうち,46%が全日制日本人学校に就学しており,34%が現地校などに通学するとともに,補習授業校に通っており,残り20%が専ら現地校などに就学している。海外子女教育は,国内と異なった種々の問題を抱えているが,外務省は文部省と協力して,できる限り海外子女教育を充実強化するよう努めている。
(1) 援助の状況
援助は,施設の面と人的な面について行われているが,前者は校舎建設,借料補助,後者は現地採用教員や補習授業校講師の謝金補助である。
このほか,文部省が教員派遣,巡回指導,教材,教科書の補助を行っている。
外務省の海外子女教育予算は,81年度,16億円となっている。
(2) 日本人学校
日本人学校は,81年にハンブルグ,マドリッド,ベロオリゾンテの3か所に新設され,合計70校となった。
在籍児童生徒数は,5月現在13,834名で,うち約77%は開発途上国にいる。派遣教員(ほとんど公立学校教員)の数は,774名に上っている。
(3) 補習授業校
補習授業校は,現地校などに通学する邦人子女に対し,週末などに国語を中心に補習授業を行っているものであり,5月現在82校となっている。
在籍児童生徒数は,5月現在10,364名で,うち93%は欧米の先進国にいる。
補習授業校の講師は,主として,現地の在留邦人であるが,81年には合計753名となっている。生徒数100名以上の大規模な補習授業校及び全日制に準じた授業を行っている補習授業校に対しては,国内から専任教員が派遣されており,その数は,35名に上っている。
(4) その他
民間の財団法人「海外子女教育振興財団」が海外の邦人子女を対象とする通信教育を行っており,5月現在7,357人が受講している。
第5節 海外移住
最近の海外移住者数は,50年代後半の最盛期から時代の変化とともに漸減し,近年は年間3,500人前後で推移している。他方,移住者の子弟を含めた日系人数は,80年10月現在175万人を数える。移住の形態は,伝統的な中南米への農業移住に代わり,カナダ,豪州など先進国への技術,技能移住が増加しており,新しい移住傾向として注目される。
1. 移住施策
(1) 国際協力事業団(JICA: Japan International Cooperation Agency)の業務
JICAは,移住希望者及び既移住者に対する援助を行っている。外務省は,81年度においてJICAの行う移住事業のため,18億3,450万円の交付金及び14億5,000万円の出資金を支出した。JICAは,右により,(イ)移住希望者の訓練・講習,(ロ)送出,(ハ)営農普及,(ニ)医療・教育,(ホ)道路・電化等の生活環境整備(ヘ)事業資金の融資などの業務を行った。なお,同年度におけるJICA扱いの移住者送出数は,514人(うち渡航費支給162人)である。
(2) 都道府県の移住事業
外務省は,81年度において,都道府県の行っている県費留学生その他の移住事業に対し,総額6,222万円の補助金を交付した。
(3) 農業派米研修生事業
農業研修生派米協会は,66年以降我が国の農村青年を2年間米国に派遣し,学課研修及び農場実習を通じ,農業分野において国際交流に資する青年の育成事業を行っているが,右事業のため1億542万円の補助金を同協会に交付した。81年度における派遣者数は,115人である。
(4) その他の移住関係補助事業
日本海外移住家族会連合会の行う移住者子弟研修及び初期移住者訪日団受入事業に対し4,149万円,海外日系人協会の行う日系留学生中央研修事業に対し401万円の補助を行った。
2. 対ブラジル移住
JICAのブラジルにおける移住者援護機関であった同事業団現地法人JAMIC(移植民有限会社)及びJEMIS(金融信用株式会社)は,ブラジル政府の要請により9月末に解散した。しかしながら,未独立農をはじめとする多数の移住者に対する援護を今後とも実施する必要があり,また,ブラジル側も日本政府による援助は高く評価している事実にかんがみ,日本・ブラジル両政府間の合意に基づき,JAMIC,JEMISの行ってきた業務を現地日系諸団体がJICAから受託業務として引き継いでいくこととなった。融資業務は,同様にサンパウロに本店を有する南米銀行が実施することとなる。
3. 海外移住審議会
海外移住審議会(海外移住政策に関する政府の諮問機関)は,1月に第42回,7月に第43回総会をそれぞれ開催した。
第6節 外国人に対する査証
1. 査証の発給
我が国に来日する外国人は,協定又は取極などにより査証が免除されている場合を除き,原則として,その旅券に査証を受けなければならない。
査証発給件数は地域別に見ると下表のとおりであり,ここ2,3年アジア地域におげる増加が著しいが,これは,特に台湾からの観光客の増大によるものと見られている。しかし,来日する外国人を国籍別に見れば,依然米国人が首位であり,81年で約296,000人に達している。
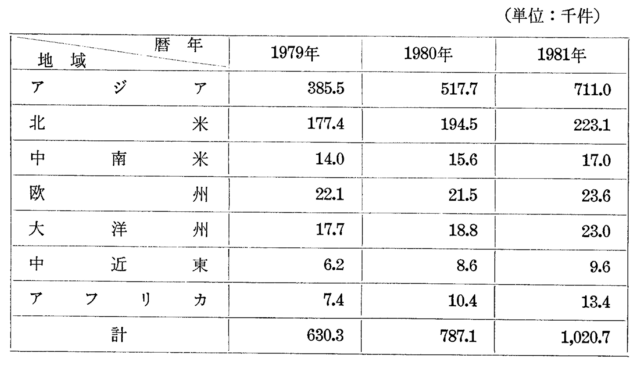
2. 査証に関する二国間取極
査証制度は,いずれの国においても,国内の公安を維持するため,外国人の入国,滞在により内国民の就業機会の確保などに悪影響が及ぶことを防止するため,重要な機能を果たしている。
他方,国際交通が発達し,国際間の人的移動も量的に拡大しつつある現在,観光,訪問,業務などの目的の一時旅行者に対し,査証取得を免除することは,国際間の人的交流の円滑化のために有効な方法であり,また,年間400万人に上る邦人の海外渡航者の大多数が,同様に,相手国から査証を免除されるならば,大きな利益を受けることになる。
我が国は,以上の見地に立ち,55年の西独をはじめとして,これまでに相互主義のもとに47か国と一部の査証につき相互免除を取り決めている。
その主な内容は,自国内で就業又は報酬を得る活動に従事しない短期(3か月以内の期間を定めているものが多い)の相手国籍滞在者には入国査証を免除するもので,相手国は,西欧のほとんど,北米・中南米の約半分及びアジアその他の若干の国である。
米国及び豪州とは査証免除取極はないが,渡航目的に応じ相当の長期間にわたり数次入国に有効な査証を相互に発給する取極を結んでいる。