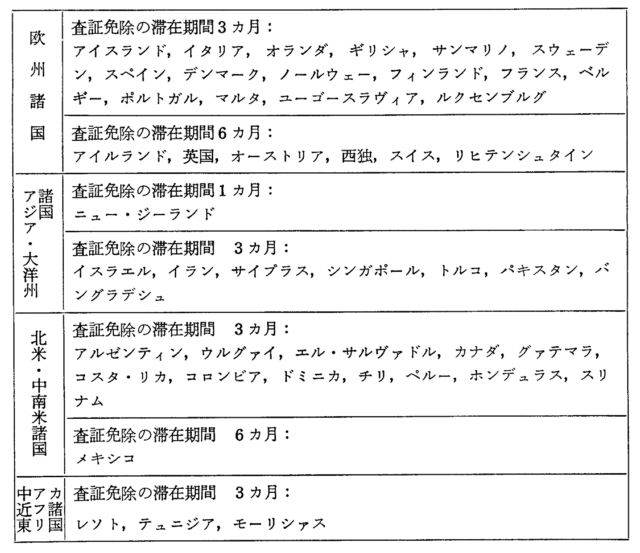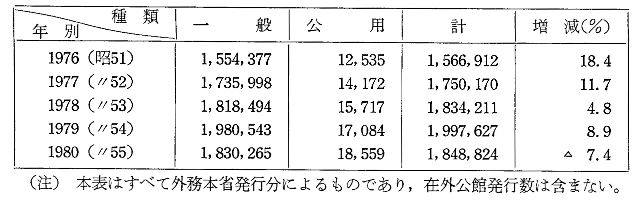
第6章 邦人の渡航と保護・援助
第1節 概要
80年における日本人の出国者数は,64年の海外渡航自由化以来初めて前年を下回り,近年連続していた年間10%前後の伸び率も,実に16年ぶりでマイナス成長となった。これは,一部外国における政情不安などによって観光目的の渡航が減ったことによる一時的現象と見られる。他方,海外長期滞在者と永住者を合わせた在留邦人数は対前年度比で2.2%増加し,445,000人を超えるに至っている。
外務省としては,これら在留邦人・邦人旅行者の保護・援助に遺漏なきを期しているが,特に,80年9月下旬に発生したイラン・イラク紛争に伴い,両国に在留する邦人約6,000名の保護と,そのうち約3,700名の引揚援護が,数あるこの種業務の中で最大規模のものであった。このために,外務省は関係在外公館を動員して,これら邦人保護に万全を期した。
在留邦人のための窓口である在外公館の領事部などは,従来からそのサービス向上に努めてきたところであるが,外務省としては,80年9月の行政サービスの向上に関する閣議決定を機会に,在外公館領事部のサービスを更に向上させることとし,各在外公館ごとに窓口サービスを抜本的に改善するための具体策を指示した。
第2節 邦人の渡航・在留邦人
1. 最近の傾向
第1次石油ショックから立ち直った1976年以降,年間10%前後伸び続けた海外渡航者と旅券発行の数は,80年には,対前年比で渡航者数が3.2%,旅券発行数が7.6%の減少を示した。これは,給与所得者の実質賃金の減少,第2次石油ショックによる航空運賃の値上り,一部外国における政情不安などの影響による一時的現象であると考えられ,これらの特殊事情が解消すれば再び元の状態に戻るものと見られる。
2. 旅券の発行状況
80年の国内における一般旅券発行数は,183万265件で,前年の198万543件に比し7.6%の減である(79年の対前年比は,8.9%増。過去5年間の発行数は別表参照)。一方,同年の海外渡航邦人数は,390万9,333人で,400万人を超えた前年に比し3.2%の減(79年の対前年比は,14.6%増)となっている。数次往復用一般旅券の発行数は,一般旅券発行総数の82%を占めている。
3. 渡航者の態様
(1) 一般旅券の発行数を渡航目的別に分類すると,「観光」の比率が圧倒的に高く,80年では発行総数の91.4%を占め,次いで「経済活動」が7.2%となっている。
また,渡航期間別分類では,観光目的が多いことから,短期のものが多く,3ヵ月以上の長期滞在(永住,赴任,留学,研究などで在留届の提出が義務付けられているもの)の割合は80年には発行総数の2.0%となっている。
(2) 一般旅券発給申請書によって80年の主要渡航先を地域別に分類集計すると,アジア(45.2%),北米(40.9%),欧州(9.4%),大洋州(2.8%)の順となっており,従来のパターンに大きい変化はないが,79年に比べアジア及び欧州への渡航者の割合がわずかに減少したのに対し,大洋州地域への渡航者の割合が増加している。
(3) 80年の一般旅券発行数を年齢別に分類すると,20歳代(36.3%),30歳代(23.3%),40歳代(15.4%)の順は従来どおりである。
〔別表〕 旅券発行数の推移(暦年)
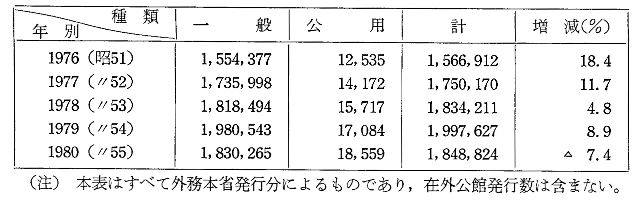
4. 在留邦人
(1) 在留邦人数
過去5年間における在留邦人数の推移は次のとおりである。
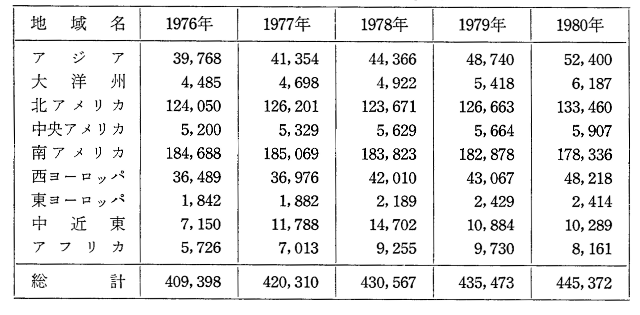
(2) 邦人団体
海外の各地に設立されている邦人団体の数は次のとおりである(80年10月1日現在)。
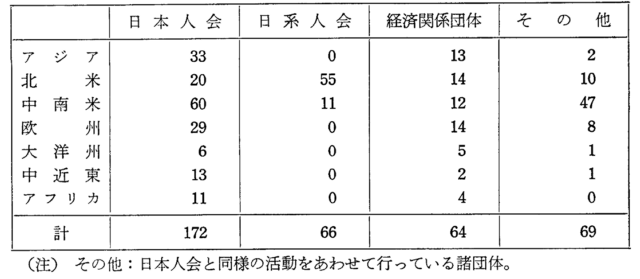
第3節 緊急事態・事件に際する邦人保護
1. 国民の海外進出規模が大きくなるに従い,戦乱など緊急事態が発生した際に,在留邦人の生命及び財産を保護する在外公館の役割が,ますます重要なものとなっている。80年においては,イラン・イラク間の戦闘の発生により,この点に関する国民の関心も一層大きなものとなった。80年における緊急事態等の主なものは次のとおりである。
〔アフガニスタン〕
79年末のソ連軍のアフガニスタン介入以降,政府軍と反政府ゲリラの衝突が首都カブールにおいても頻発し,治安が悪化したので,80年2月末現地大使館は在留邦人に引揚げ勧告を発出した。
〔韓国〕
5月には,韓国の光州にて暴動が発生し,現地公館は在留邦人及び旅行者の把握及び保護に尽力した。
〔イラン・イラク紛争〕
イランにおいては,79年以降在イラン米国大使館占拠を巡る緊迫した情勢が続き,現地大使館は不測の事態に即応できる体制を取り続けていたが,9月下旬,イラン・イラク紛争が発生し,当時両国に在留していた約6,000名近い邦人の安全確保が緊急の課題となった。紛争発生と同時にイラク在留邦人はクウェイト及びジョルダン経由で引揚げを開始し,イラン在留邦人も10月中旬よりトルコ及びソ連経由で避難した。当初,これら邦人のイラク出国時に若干の混乱が見られたものの,わが方現地大使館の尽力及び関係各国の協力により11月末までにイラクより約2,450名,またイランより約1,210名の邦人が引き揚げた。10月下旬イランから一部企業関係者が出国し,トルコへ入国した直後に,乗っていたバスが発砲を受け,2名が軽傷を負う事件が起きたが,この事件を除き今次紛争に際し,イラン,イラク在留邦人に大きな事故がなかったことは幸いであった。また,シャットル・アル・アラブ川水域には戦闘発生以来邦船7隻を含む80隻以上の船が出港できないまま閉じ込められているが,政府は関係国,国連などに早期安全出港が実現されるよう働きかけを行ってきている。
〔ポーランド〕
このほか,8月以降ポーランド情勢が緊迫したが,現地大使館は在留邦人の保護に遺漏なきを期すため連絡体制の確立など必要な措置を講じた。
2.ハイジャックなど非人道的暴力行為事件は,80年中に北米,中米地域並びに中近東地域を中心に各地で多発したが,邦人が人質となった事件は,80年8月のブラニフ航空機ハイジャック事件,同11月のヴェネズエラ国内航空機ハイジャック事件及び81年3月のガルーダ航空機ハイジャック事件の3件であった。これらの事件では幸いにも人質となった邦人は,それぞれ無事救出されたが,特にガルーダ航空機ハイジャック事件は,事件発生後解決までに4日間を要し,その間外務省は,関係在外公館と緊密な連絡をとりつつ人質邦人の安全救出のための努力を関係国に要請するなど,邦人保護のために最大限の努力を払った。
第4節 邦人に対する援助
1. 一般邦人,船員・船舶に対する援助
80年中に在外公館で取り扱い,外務省に報告のあった一般邦人に関係する事故件数は597件(769人)である。このうち地震,風水害などの被害は6件(以下括孤内は死亡者数)(14人),航空機,自動車事故53件(29人),山岳遭難遊泳事故34件(37人),犯罪被害による死亡者6人,自殺(未遂を含む)21件(19人),病気79件(54人),精神異常38人,行方不明13人,邦人による殺人事件1件,窃盗詐欺7件などがあり,このほか,船員,船舶にかかわる犯罪,事故は91件(死亡38人)であった。
これら事故,病気などにより援護の必要が生じた場合,外務省は在外公館と緊密な連絡をとりつつ,留守宅への通報を始め当該邦人が安全かつ速やかに帰国できるよう最大の努力をしている。
帰国を希望するが帰国費を負担し得ない邦人に対しては,審査の上帰国費の貸付けを行っているが,80年の貸付けは22件(42人)であった。
2. 巡回医師団の派遣
外務省は,72年以来海外在留邦人の健康維持の見地から,衛生環境が悪く,かつ,十分な医療施設のない開発途上国に在留する邦人を対象に巡回医師団を派遣している。80年度においては,中近東地域に2チーム,アフリカ地域に3チーム,アジア地域に3チーム及び中南米地域に2チームをそれぞれ派遣し,約7,400名の邦人の健康相談に当たった。
3. 海外子女教育
80年5月現在海外の学齢子女(小・中学生)は27,465名であり,このうち45%が全日制日本人学校に就学しており,36%が現地校などに通学するとともに,補習授業校に通っており,残り19%が専ら現地校などに就学していることとなっている。海外子女教育は国内と異なった種々の問題を抱えているが,外務省は文部省と協力して,できる限り海外子女教育を充実強化するよう努めている。
(1)援助の状況
援助は施設の面と人的な面について行われているが,前者は校舎建設,借料補助,後者は教員の派遣経費(在勤手当,旅費など),現地採用教員や補習授業校講師の謝金補助,医療費補助などが主なものである。このほか文部省が教材,教科書の補助を行っている。
外務省の海外子女教育予算は年々増大しており,80年度は56億円に上っている。
(2)日本人学校
日本人学校は,80年にメダン,ヴィトリア,プラハ,ドバイ,台中の5カ所に新設され,合計67校となった。
在籍児童生徒数は80年5月現在12,365名で,うち約76%は開発途上国に居る。派遣教員(ほとんど公立学校教員)の数は696名に上っている。
(3)補習授業校
補習授業校は,現地校などに通学する邦人子女に対し,週末などに国語を中心に補習授業を行っているものであり,80年5月現在77校となっている。
在籍児童生徒数は80年5月現在9,736名で,うち97%は欧米の先進国に居る。
補習授業校の講師は,主として,現地の在留邦人であるが,80年には合計693名となっている。生徒数100名以上の大規模な補習授業校及び全日制に準じた授業を行っている補習授業校に対しては,国内から専任教員が派遣されており,その数は,28名に上っている。
(4)巡回指導
日本人学校も補習授業校もない地域の邦人子女のため,日本人学校教員による巡回指導を行っている。80年には14カ所に巡回した。
(5)その他
民間の財団法人「海外子女教育振興財団」が海外の邦人子女を対象とする通信教育を行っている。
第5節 海外移住
最近の海外移住者数は,50年代後半の最盛期から時代の変化とともに漸減し年間3,000人台で推移している。他方,移住者の子弟を含めた日系人数は,増加傾向にあり,80年10月現在175万人を超える。移住の型態は,農業家族移住に代わり単身青年層の技術移住が増加している。また,移住先も米国,カナダなどの先進国がウェイトを占めている。
1. 移住施策
(1) 国際協力事業団の業務
国際協力事業団は,移住希望者及び既移住者に対する各種の援助を行っている。外務省は,80年度において同事業団の行う移住事業のため,約17億7,700万円の交付金及び14億5,000万円の出資金を支出した。同事業団は,80年度において,渡航費支給186人を含め中南米移住者207人を送出した。事業団は80年度において,(イ)営農指導,(ロ)生活環境整備,(ハ)教育対策,(ニ)事業資金の融資(約24億円の新規貸付け),(ホ)移住地現地調査(移住地における飲料水調査,国際協力事業団の試験場効果測定,老人問題,移住者子弟日本語教育問題の調査)などの業務を行った。
(2)ブラジル法人問題
国際協力事業団のブラジルにおける移住者援護は,同事業団の援護実施機関であるJAMIC(移植民有限会社)及びJEMIS(金融信用株式会社)によって実施されてきたが,ブラジルは同国の経済社会情勢の変化及びナショナリズムの高揚に対応するため,移住政策の転換を行い,79年12月に開催された「日伯移住混合委員会」の席上,JAMIC及びJEMISの両法人は,ブラジル国国内法に抵触するとして,その早期廃止をわが方に強く求めてきた。わが方は,両法人の過去20数年にわたる移住者援護の実績及び移住者に与える影響などを考慮して,両法人の廃止後の移住者援護方法,両法人の廃止に至るまでの暫定期間,JAMICの取得した入植地の処分,JEMISによる融資の回収などの多くの問題についての対処案を検討し,ブラジル政府と数次にわたり交渉してきた。その結果81年9月末に両法人を解散することに意見の一致を見た。
(3)都道府県の移住事業
外務省は,80年度において,都道府県の行っている各種移住事業に対し,総額6,516万円の補助金を交付した。
(4)日本海外移住家族会連合会の事業
外務省は,80年度において,日本海外移住家族会連合会の行う移住者子弟研修及び初期移住者の訪日団受入れ事業に対し,4,088万円の補助金を交付した。
(5)農業研修生派米事業
外務省は,80年度において,農村青年を2年間米国に派遣して学課研修及び農場実習をさせる事業のため,1億93万円の補助金を農業研修生派米協会へ交付した。
2.海外移住審議会
海外移住審議会(海外移住政策に関する内閣総理大臣の諮問機関)は,80年1月第42回総会を開催した。
第6節 外国人に対する査証
1. 査証の発給
わが国に来日する外国人は,協定又は取極などにより査証が免除されている場合を除き,原則として,その旅券に査証を受けなければならない。
査証発給件数は,地域別に見ると下表のとおりであり,ここ2,3年アジア地域における増加が著しいが,これは特に台湾からの観光客の増大が大きく影響しているものと見られる。しかし,来日する外国人を国籍別に見れば依然米国人が首位であり,80年で約267,000人に達している。
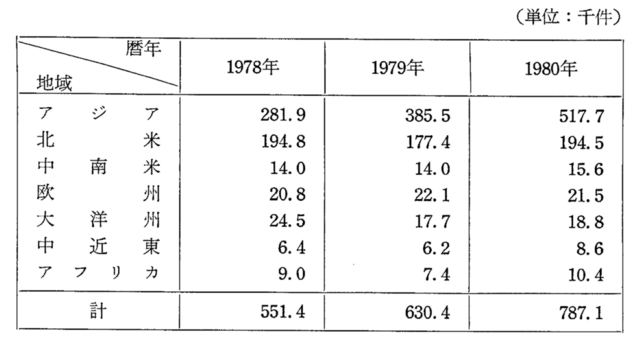
2. 査証に関する二国間取極
査証制度はいずれの国においても,国内の公安を維持するため,また,外国人の入国,滞在により国民の就業機会の確保や賃金などの就業条件に悪影響が及ぶことを防止するため,重要な機能を果たしている。
他方,国際交通が発達し,国際間の人的移動も量的に拡大しつつある現在,観光,訪問,業務などの目的の一時旅行者に対し,査証取得を免除することは,国際間の人的交流の円滑化のために有効な方法であり,また,年間400万人に上る邦人の海外渡航者の大多数が,同様に,相手国から査証を免除されるならば,非常に大きな利益を受けることになる。
わが国は,以上の見地に立ち,1955年の西独を始めとして,これまでに相互主義のもとに46カ国と一部の査証につき相互免除を取り決めている。その主な内容は,自国内で就業又は報酬を得る活動に従事しない短期(3ヵ月以内の期間を定めているものが多い)の相手国籍滞在者には入国査証を免除するもので,相手国は西欧のほとんど,北米・中南米の約半分及びアジアその他の若干の国である。
米国及び豪州とは査証免除取極はないが,これに代わるものとして渡航目的に応じ相当の長期間(最長4年)にわたり数次入国に有効な査証を相互に発給する取極を結んでいる。