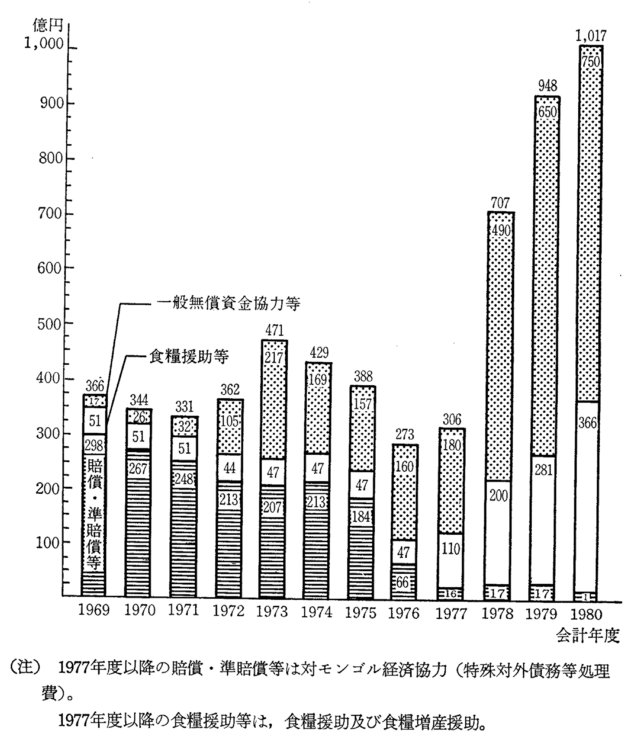
第3節 無償資金協力
1. 概況
無償資金協力とは,開発途上国に対する資金協力のうち,相手国政府に返済義務を課さないで資金を供与する形態の二国間援助である。
無償資金協力の目的は,開発途上国の経済,社会の発展,住民福祉の向上及び民生の安定に寄与することにある。69年に開始されたわが国無償資金協力は,今日までに資金の量が大幅に増加し,現在ではわが国政府開発援助を推進する重要な柱として,わが国と開発途上国との友好関係の増進に大きな貢献をなしている。
わが国の無償資金協力は,経済開発等援助費による一般無償援助,災害関係援助など(一般の無償資金協力)のほか,食糧増産等援助費による食糧援助(国際小麦協定の一部を構成する食糧援助規約に基づく援助で,米,小麦などの食糧を贈与するもの),77年度より開始された食糧増産援助(食糧増産努力を支援するための肥料,農機具などの贈与)から成っている。
わが国が80年において行った無償資金協力の支出額は約950億円であり,これは前年の支出額約709億円に比較すると約34%の増加となった。
なお,わが国が55年から実施してきた賠償,準賠償は,76年度をもって終了している。また,一般の無償資金協力のうち,技術協力と関連のある案件については,78年から国際協力事業団を通じて実施促進業務を行っている。
2. 一般の無償資金協力
(1) 一般無償援助
経済開発等援助費の主要な部分を占める一般の無償資金協力は,毎年,開発途上国の社会開発関連分野を中心として拡充の一途をたどってきており,80年度の一般無償援助のための予算も前年度に比して約15%の伸びを示した。
一般無償援助は経済的収益性が低く,相手国政府が自己資金あるいは借入れ資金により投資することが困難な案件を対象の中心としており,主な具体的対象分野としては,教育,医療・保健,農業,民生・環境改善,通信・運輸などがある。
これら分野別に,80年における主な援助案件を見ると,教育分野ではフィリピンのフィリピン工科大学総合研究訓練センター設立計画,ケニアのジョモ・ケニアッタ農工大学設立計画(第3期)などへの協力がある。またトンガに対しては小学校建設計画があるが,小学校完成後,日米両国がそれぞれ教員を派遣することによって日米協力が行われることになっている。
医療・保健分野では,タイのマハラート病院建設計画,エジプトのカイロ大学付属小児病院設立計画,ペルーの地域精神衛生センターなどへの協力がある。
農業分野の協力としてビルマの末端灌漑排水施設建設計画,ザイールの農業輸送力増強計画などがある。
民生・環境改善分野の協力には,ネパールやトーゴの村落水供給計画などがある。
通信・運輸分野ではバングラデシュの輸送用車輌修繕維持中央作業場設立計画,ルワンダの衛星通信地上局建設計画などへの協力がある。
また,わが国は,78年3月の国連貿易開発会議(UNCTAD)の決議に従い,わが国に対して公的債務を有している貧困開発途上国(18カ国)に対し,債務の条件調整を目的とする無償援助を債務救済として78年度から実施している。
80年における一般無償援助の供与国は37カ国を数え,総額542億円に達している。また一般無償援助の62%がアジア地域に,20%がアフリカ地域に供与され,27%が後発開発途上国(Least among Less Developed Countries; LLDC)向けとなっている。
(2) その他
一般無償援助のほかに経済開発等援助費に含まれるものとしては,次のものがある。
(イ) 水産関係援助
水産関係援助は,開発途上国の水産振興に寄与するために,漁業訓練施設,訓練船,水産研究施設建設関係プロジェクトなどに協力するものであり,80年においては9カ国に対し総額40億円を供与している。資金供与の対象となったプロジェクトとしては,漁業振興のための機材(漁網などの漁具,製氷機など),漁業訓練船などの供与及び水産研究所,漁業基地の建設などがある。
(ロ) 災害関係援助
災害関係援助は風水害,地震,旱魃などの自然災害に見舞われた国に対し緊急に支出される援助,及び内乱などの戦乱により発生した難民・被災民に対し人道上の観点から実施される援助からなる。
80年においてはアルジェリア・イタリアの地震災害などに約6億6,000万円,カンボディア難民・アフガン難民などに対し約36億5,000万円の援助を実施した。
(ハ) 文化関係援助
文化関係援助は,開発途上国における教育及び研究の振興,文化財及び文化遺跡の保存利用,文化関係の公演及び展示などの開催のために使用する資機材の購入に必要な資金の供与を行うものであり,75年度から,文化交流に関する国際協力の一環として実施されている。80年においては,15カ国に対し約5億3,000万円の援助を実施した。
3. 食糧援助
わが国の食糧援助は,ガットのケネディ・ラウンド(KR)関税一括引下げ交渉の一環として成立した国際穀物協定を引き継いだ国際小麦協定の中の食糧援助規約に基づき実施されている。
食糧援助規約は,深刻な食糧不足に悩む開発途上国に対し,拠出国が援助する穀物の量を規定している国際協定である。
同規約に基づき,わが国は68年以降,米及び被援助国が希望する場合には農業物資を食糧不足国に無償供与してきた。しかしながら77年度から食糧増産援助が開始されたことによりこの食糧援助は77年度以降,基本的に米を援助の対象としてきている。
なお,食糧援助規約については,加盟国の拠出量増大などを軸として,78年2月から改定交渉が開催されていたが,80年3月新規約につき合意が成立し,同年7月,「1980年の食糧援助規約」が発効した。この新規約により,わが国の年間拠出義務量は,小麦換算225,000トンから30万トンに増加した。
80年においてわが国は,食糧援助規約に基づく食糧援助として,8カ国,2国際機関に対し,総額約116億円を供与した。これらの援助を地域別に見ると,72%がアジア地域,14%がアフリカ地域に対して実施されており,また30%が後発開発途上国(LLDC)向けとなっている。
なお国際機関に対する援助としては,人道的観点から国連世界食糧計画
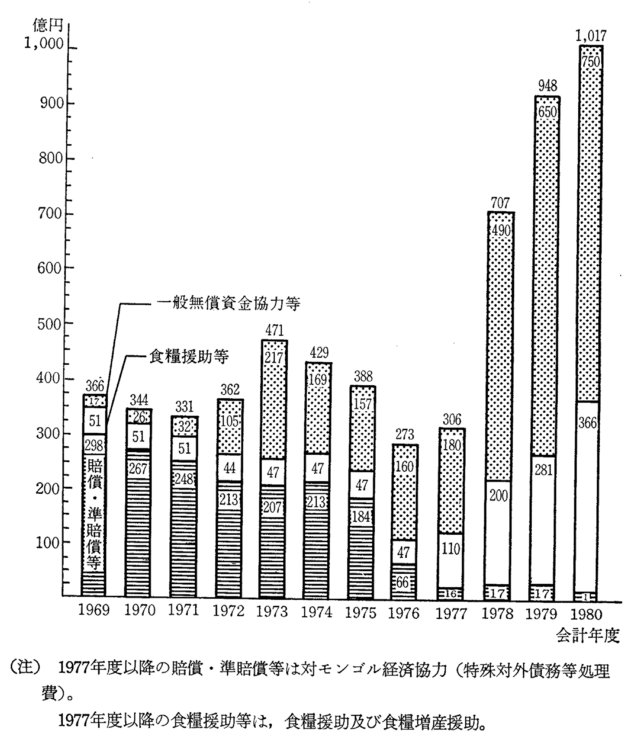
(WFP)を通じて実施したカンボディア難民・被災民,及びアフガン難民に対する援助,並びに国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)を通じて実施したパレスチナ難民に対する援助がある。
4. 食糧増産援助
わが国としては,開発途上国の食糧問題は基本的には,自助努力による食糧増産により解決されるべきであるとの立場をとっており,わが国はこうした自助努力を支援するため,これまで無償援助により食糧増産に役立つ各種の農業プロジェクトを実施してきた。
更に77年度からは,食糧増産援助として新たに予算措置を講じ,新予算の下で食糧増産援助は飛躍的に増加している。同援助は一般無償援助で実施される各種農業プロジェクト援助とともに,農業開発に重点を置いている開発途上国に対して大きな貢献をしている。
食糧増産援助によって供与される農業物資としては,肥料,農薬,小型農機具のほか,場合によっては耕耘機,トラクター,ポンプなどの農業用機械がある。
80年においては,21カ国に対し,総額約237億円の食糧増産援助を供与しており,それらのうちの78%がアジア地域に,8%がアフリカ地域に供与されており,また,33%が後発開発途上国(LLDC)向けとなっている。