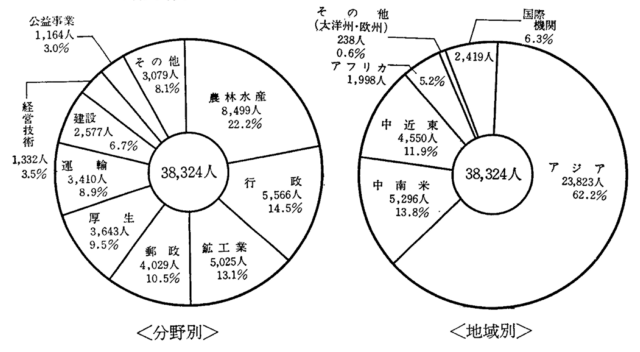
第2節 技術協力
1. 総論
技術協力は,主として開発途上国(又は地域)の経済及び社会の開発に必要な技術の普及あるいは技術水準の向上を目的として,研修員受入れ,専門家派遣などを通じて技術の供与を行う経済協力の一形態であり,人と人との接触を通じて諸国民間の相互理解と親善が深められるという特色を持つ。
わが国の技術協力は,政府ベース技術協力に政府委託費及び補助金などの政府資金による民間ベースの技術協力を加えたものである。政府ベース技術協力は,54年わが国がコロンボ・プラン(注)に加盟したことにより開始され,主として国際協力事業団(JICA)を通じて実施されている。同事業団は主として外務省交付金により,条約その他の国際約束に基づく事業などを実施している。そのほか政府ベース技術協力としては,通産省予算により国連工業開発機関(UNIDO)からの要請に基づく研修員の受入れ,セミナーの開催及びアジア生産性機構(APO)からの要請で実施する視察団及び研修員の受入れ,文部省所管の国費留学生の受入れ,農林水産省水産熱帯農業研究センター及び通産省工業技術院が行う協力事業などがある。民間ベース技術協力には,民間団体が政府の補助金あるいは自己資金により行う研修員受入れ,技術者派遣,調査団派遣などがある。
1980年におけるわが国の技術協力関係支出額は,2億7,778万ドル(629億8,292万円)に上り,対前年比14.8%増となった。
わが国の技術協力実績をDACベースでの国際比較で見ると,79年の協力額ではDAC加盟17カ国中第6位であり,わが国の政府ベース技術協力は着実に拡大の一途をたどっているが,政府開発援助総額に対する技術協力額の割合では第13位であった。わが国に対する開発途上諸国からの要請は,年々増大する一方であり,わが国としては政府開発援助の質的な改善を図るためにも,技術協力の質的量的拡充を重視し,真に相手国の経済及び社会の発展に寄与し得る協力の姿勢を貫いていく必要があろう。以下,国際協力事業団の事業の概要を述べることとする(ただし,以下に述べる80年度の実績数値は81年7月現在における集計数値である)。
(注)コロンボ・プランは,50年アジア・太平洋地域の英連邦諸国の開発につき主として技術協力の面から取り組むことを目的として発足した国際機関である(加盟国は,域内及び域外を併せ27カ国)。
2. 国際協力事業団による協力
(1) 研修員受入れ
研修員受入れ事業は開発途上諸国の中堅技術者,研究者,行政官などを当該国政府又は国際機関の要請に基づき日本に受け入れて,わが国の進んだ技術を研修する機会を与える技術協力の最も基本的な形態である。
80年度中に新規に受け入れた研修員は,3,371名であった。これによって,わが国が54年以来国際協力事業団を通じて政府ベースで受け入れた研修員は合計38,324名に達した。
80年度における地域特色としては,アジア地域に占める比率が減少したのに対し,近年とみにわが国との関係を深めつつある中南米地域の占める
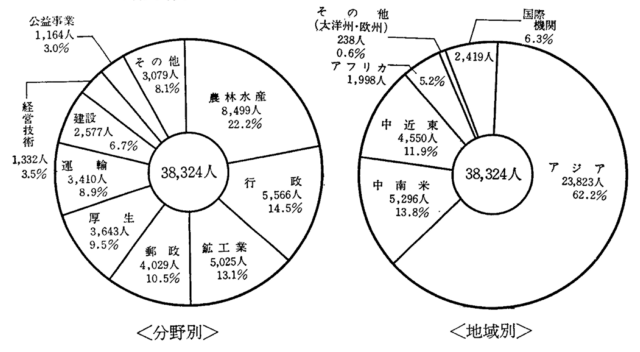
比率が増加していることが挙げられる。更に受入れ方式別実績では,集団・個別研修で320名,国連機関要請研修169名である。
他方80年度においても前年度に引続き,研修事業の内容の改善に努め,研修員の滞在費及び研修附帯費一人1ヵ月当たり基準額の増額など,研修内容の充実を図った。また,研修員受入れ数の増加に対応するため,80年4月に筑波インターナショナル・センターを,81年5月には筑波国際農業研修センターをそれぞれ開設した。
(2) 専門家派遣
開発途上国の要請に応じて主として相手国の政府,政府関係機関,試験研究機関,事業所,学校及び指導訓練機関などにおいて企画立案,調査研究,指導,普及活動及び助言などの業務を行うため各種分野の専門家を派遣し,技術協力を行う専門家派遣事業は,研修員受入れ事業と並び,いわば車の両輪をなす最も基本的な技術協力の形態である。
80年度中に政府ベースで国際協力事業団を通じて新規に派遣した専門家は,計4,783名であった。これによって,わが国が開発途上諸国への専門家派遣を開始した55年以来,政府ベースで派遣した専門家の累計は,総計29,714名に達した。
このうち開発途上国政府若しくは国際機関の要請に基づいて個別に派遣した専門家累計6,270名(80年度701名),このうち国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP),東南アジア漁業開発センター(SEAFDEC),アジア
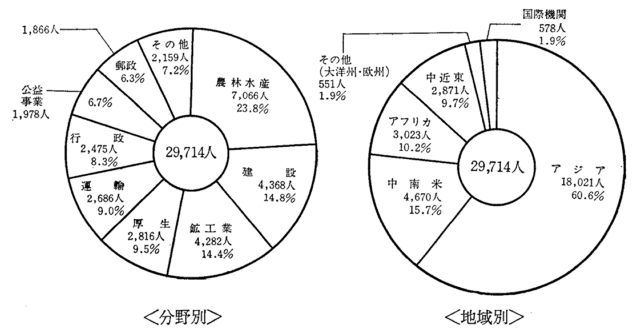
工科大学(AIT)などの国際機関へ派遣した専門家は,累計573名(80年度79名)である。
また80年度においても前年度に引続き,専門家生活環境整備の拡充,専門家健康相談巡回指導チーム派遣の拡充など,派遣専門家の待遇の福利厚生面での充実に努めた。
(3) 機材供与
機材供与事業は,開発途上国において一定の技術的知識又は経験があっても機材不足のため既存の技術が有効に活用されない場合に,わが国の行う技術協力と関連付けて必要な機材を供与する事業である。言わば「人」を通じての技術協力に,機材という「物」を有機的に組み合わせて,その効果を高めようとするものである。
なお,この機材供与事業は,専門家の携行機材,あるいは後述のプロジェクト協力に伴う機材などの供与とは別のものであり,通常「単独機材供与」と呼ばれている。
80年度に供与した機材はコミットメント・ベースで43件,総額12億5,064万円であった。80年度までの累計総額はディスバスメント・ベースで48億68万円で,地域別配分は,アジア・大洋州53.7%,中近東11.6%,アフリカ10.3%,中南米21.7%,その他2.7%となっている。
(4) 開発調査
国際協力事業団による開発調査は,開発途上国などの要請を受けて,当該国の経済,社会開発上有効と認められる公共的な開発計画に関して実施されるものである。したがって,その分野も農業開発,道路・港湾の建設,通信網整備,電源開発,資源開発,産業近代化など多岐にわたる調査を行っている。
80年度は新規及び継続分を合わせて165件,外務省予算で104億円に上る開発調査を実施した。これを地域的に見るとアジア地域87件,中近東地域11件,アフリカ地域32件,中南米地域26件,オセアニア地域9件となっている(具体的案件については資料編を参照)。
また海外開発計画調査(通産省予算)については99件,総額29億円の調査が実施された。資源開発協力基礎調査(通産省予算)は18件,17億円の調査を実施した。
(5) プロジェクト方式技術協力
プロジェクト方式技術協力とは,専門家の派遣・研修員の受入れ・機材の供与の3要素を組み合わせて,5年程度の協力期間にわたり一つのプロジェクトにおいて計画的に実施される技術協力を言い,通常,活動の拠点となるセンター,病院,研究所などにおいて鉱工業,農業,保健医療,家族計画などの各分野における専門技術者の養成を行い,これらの技術者を通じて開発途上国における技術の移転・定着を図っている。
事業区分としては,センター協力,保健・医療協力,人口・家族計画協力,農林業協力,産業開発協力の5事業に分かれ,各々以下のとおりの事業活動を行っている。
(イ) センター協力
(a) 概要:開発途上国の技術訓練センターなどを拠点として,各種技術分野における人材の養成・訓練を行う。典型的な協力内容は大別して一般的な職業訓練(機械,電気,自動車,板金溶接など)と特定分野(電気通信,海運・道路交通,鉱工業,水産など)での技術者養成及び研究開発プロジェクトに分けられ,開発途上国の「国造り」の必要性に応じ多様な協力を実施している。
80年度においては,34億3,100万円の予算規模をもって,17カ国28件の協力を行った。地域的にはアジアが中心であるが(14件),中近東に対する協力も比較的に多い(6件)。
(b) 最近の傾向
(i) 開発途上国のニーズに見合った適正な技術開発を主目的とする協力(現地の素材を使った半導体の試作,選鉱・精錬技術の開発,綿ポリエステル混紡技術開発など)が近年増加している(80年度協力案件5件)。
(ii) テレビ放送技術の移転,コンピューター操作要員や電子機器関連熟練工の養成など,わが国が得意とする先端技術分野での協力が増加している(80年度協力案件8件)。
(iii) 大学レベルの専門技術者及び研究者の育成プロジェクトが増加しており,人材育成の高度化及び多様化が顕著に見られる(80年度協力案件3件)。
(ロ) 保健・医療協力
(a) 概要:開発途上国国民の健康の維持増進を図り,社会福祉の向上に寄与することを目的とし,途上国で必要とする医師,看護婦など,医療,医学部門の人材養成・訓練を行う。協力内容は,ウイルス,細菌学,内科,外科,眼科など基礎・臨床医学の研究,特定疾病(結核,ライ,がんなど)の撲滅対策,プライマリー・ヘルス・ケア(住民の健康・医療サービス向上,公衆衛生改善,看護婦・保健婦の養成など,地域住民に直結した協力)に大別される。
80年度においては,31億8,000万円の予算規模をもって,25カ国29件の協力を行った。このほか,地理的関係などから,わが国の医学,医療について認識の余り深くない中近東,アフリカ,中南米諸国に対し,わが国トップ・レベルの医学者,大学教授を派遣し,学術講演などを通じ,わが国の医学,医療を紹介するなどの事業を行っている。
また,タイにおけるカンボディア難民救済のため,わが国は,80年度においても引続き保健・医療協力の一環として,難民救済医療チーム(延べ15チーム)を難民キャンプに派遣し,緊急医療活動を実施した。
(b) 最近の傾向:プライマリー・ヘルス・ケア部門ではブラジルのワクチン製造,ペルーの地域精神衛生プロジェクトがスタートしたが,これは多数の住民に直接裨益する新しい形のプライマリー・ヘルス・ケアとして期待されている。
(ハ) 人口・家族計画協力
人口・家族計画分野については,これまで医療協力事業の中で実施されてきたが,80年度においては,4億6,000万円の予算規模をもって,人口爆発に悩むアジアの4カ国を対象に母子保健などと総合した地域住民指向型のプロジェクトに力点をおいた広報普及活動,視聴覚教育活動,普及員の養成などに協力を行った。
(ニ) 農林業協力
(a) 概要:開発途上国の産業構造の中で農業の占める割合は極めて高く,また,途上国の国民の過半は農業従事者であり,そのほとんどが貧困に苦しんでいる。したがって農業開発への協力は,依然開発途上国の経済・社会開発上の最重要施策となっている。
プロジェクト方式技術協力の対応としては,生産性向上のための技術の移転・普及を重点的に実施しており,内容も農業・食糧増産,養蚕,畜産,林業,水産など多岐にわたっており,地域的には,わが国同様稲作中心のアジア地域に対する協力が圧倒的に多い。
80年度においては52億3,600万円の予算規模をもって,15カ国37件の協力を行った。
(b) 最近の傾向:末端農民の生産性向上に直接つながり得る技術普及対策を重視しており,80年度には,プロジェクト基盤整備費(9件),中堅技術者(農業普及員)養成対策費(2件)をもって,わが国によるローカル・コスト負担を大幅に拡大した。このほか適正技術開発研究費(1件)を新設するなどプロジェクト実施のための国内の支援体制を一層整備した。
(ホ) 産業開発協力
(a) 概要:開発途上国国内の産業上の諸条件に適した特定産業の育成・振興のためのプラニングから人材の養成,技術の研究・開発までの諸要素を適宜有機的に結び付けた総合的な協力要請にこたえ,開発途上国の中小規模工業など特定産業・地場産業の育成・振興に対し,総合的,多角的な協力を行うことを目的とする技術協力プロジェクトである。
80年度においては,10億3,000万円の予算規模をもって,9カ国12件の協力を行った。
(b) 最近の傾向:従来鉱物資源の活用を目的とした協力が多かったが,近年は,中小工業育成や野菜などの流通改善のための協力要請も強まってきており,地域的にも中南米からアジア,更にはアフリカヘも協力が拡大しつつある。
(6) 開発協力
(イ) 開発投融資
(a) 開発投融資の意義
国際協力事業団による開発投融資は,わが国民間企業などが開発途上地域などで行う経済協力に対する財政支援制度である。それは政府ベースと民間ベースの経済協力の連携の強化及び資金協力と技術協力の結び付きの強化を図るものであり,投融資対象事業が相手国の経済,社会の発展と民生の安定向上に資することを目的としている。
(b) 投融資業務の内容
国際協力事業団の投融資の対象は,開発途上地域などの社会の開発並びに農林業及び鉱工業の開発に資する次の事業であって,日本輸出入銀行あるいは海外経済協力基金からの貸付などを受けることが困難と認められる事業に対し,他の政府関係機関に比し相当緩和した条件の資金を供与するものである。
(i) 関連施設の整備
開発事業に付随して必要となる関連施設であって,周辺地域の開発に貢献する施設の整備事業,例えば,道路,橋梁,港湾施設,上下水道,市場,学校,病院,公民館,教会,訓練所などである。
(ii) 試験的事業
開発事業のうち試験的に行われるものであって,技術の改良又は開発と一体として行わなければ,その達成が困難な事業である。
資金供給の態様は,関連施設の整備の場合は貸付及び債務保証,試験的事業は貸付,債務保証及び出資である。
(c) 投融資事業の実績
80年度の投融資額は,関連施設の整備,試験的事業合わせて総額36億円となった。
(ロ) 開発協力調査及び開発協力技術指導
国際協力事業団の発足の意義の一つは,資金協力と技術協力の連携であり,前述の開発投融資の対象となる事業に関し必要な調査及び技術指導(専門家派遣及び研修員受入れ)を実施している。すなわち投融資対象となる事業が相手国の経済発展,地域開発,民生の安定などにどの程度資するか,あるいは当該事業が採算に乗り得るかどうかなどの必要な調査を実施するとともに,開発途上地域で実施している開発事業で民間企業が自力で対処し得ない技術的問題に対し必要な技術の指導を行っている。80年度は34件の調査を実施し,16人の専門家の派遣,並びに22人の研修員を受け入れた。
(7) 青年海外協力隊派遣
青年海外協力隊派遣事業は,開発途上国からの要請に応じ,必要な技術又は技能を身に付けた青年を派遣し,相手国の人々と,生活と労働を共にし
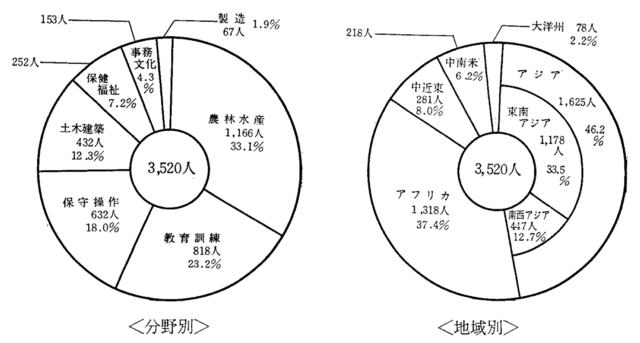
て,開発のための実践的な活動に従事せしめることを目的としており,65年に開始された。
協力隊員の派遣は,わが国政府と相手国政府との間での派遣に関する基本取極に基づいて行われている。80年5月15日にスリ・ランカと,更に81年1月鈴木総理大臣ASEAN訪問の際にタイ(1月19日)との間に基本取極が締結されたことにより,派遣取極締結国は,31カ国となっている。(うち,カンボディア,ラオス,エル・サルヴァドル,インド及びウガンダの5カ国には現在派遣していない。)
80年度において24カ国へ410名(シニア隊員6名を含む)の隊員が派遣され,これにより65年以来80年度末までに派遣された隊員数の累計は28カ国3,520名(うち女性隊員543名)となった(上表の地域別,分野別参照)。なお,81年3月末現在派遣中の隊員数は840名(うち女性隊員156名)である。
3. 国際協力事業団以外の協力
技術協力は広範な国民的理解と支持を得て進められることが望ましいとの見地から,外務省は,民間団体及び地方公共団体の技術協力事業の助成を行っている。
80年度に外務省が補助金などを交付し助成した団体は日本国際医療団,家族計画国際協力財団,国際開発センター,オイスカ産業開発協力団,国際技術振興協会,国際看護交流協会である。また,71年以降,外務省の補助金交付を受けて(補助率4分の3),地方公共団体が研修員受入事業を行っており,80年度には33道府県が計233名の研修員を受け入れた。