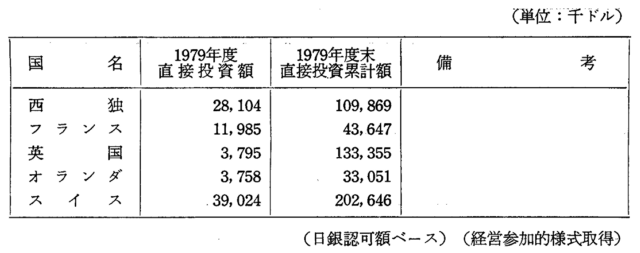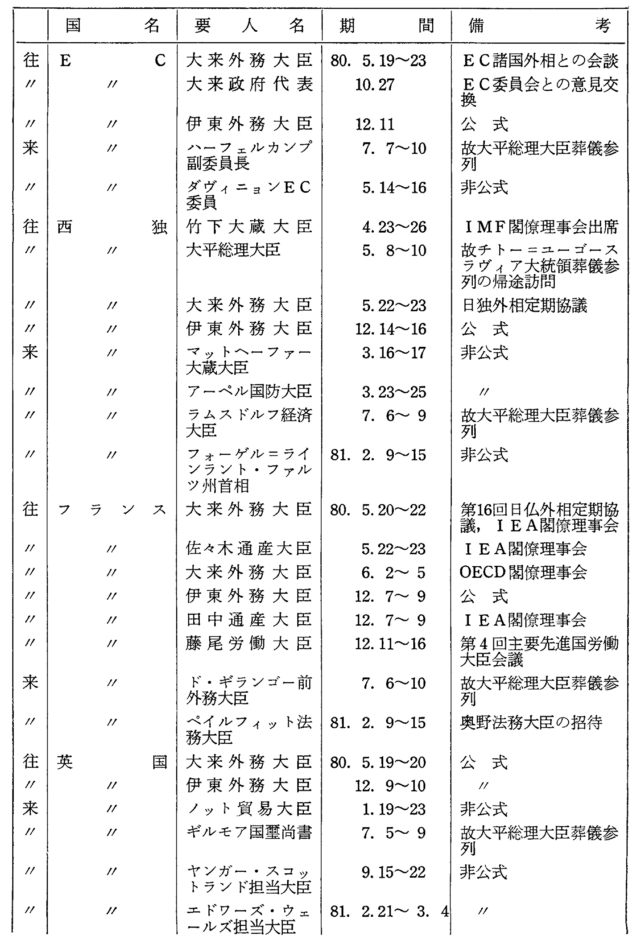
2. わが国と西欧諸国との関係
(1) 日・西欧関係全般
国家間の相互依存関係がますます強まり,国際情勢が複雑化するに伴い,先進民主主義国が協力して諸問題に対処する必要性は高まってきている。わが国と西欧は伝統的な友好関係によって結ばれているが,それに加え先進民主主義諸国の重要な一員として裾野の広い協力関係を樹立し,世界政治・経済の両面にわたり一層責任ある役割を果たすことが期待されるに至っている。
日・西欧間の関係を緊密化することは,双方にとって有益であるのみでなく,世界の平和と繁栄のためにも不可欠なものである。わが国と西欧諸国は,かかる共通の認識基盤に立ち,あらゆる分野における協力関係を強化すべく地道な努力を積み重ねてきている。
80年においては,日仏外相定期協議(5月),日独外相定期協議(5月),日伊外相定期協議(6月),が行われ,日・西欧関係の緊密化が図られたほか,別表に見られるがごとく要人の交流が引続き活発に行われた。
他方,わが国は対西欧外交を進めるに当たり,いわゆる大国のみを念頭に置いているものではなく,他の諸国ともきめ細かく関係を深めるよう努めている。このようなわが国の政策は,三笠宮・同妃両殿下のオランダ訪問(4月),伊東外務大臣のオランダ・ベルギー訪問(12月),ファン・アフト=オランダ首相の訪日(4月),グスタフ=スウェーデン国王夫妻の訪日(4月),トルン=ルクセンブルグ外相の訪日(7月),ファン・カルロス=スペイン国王の訪日(10月)など一連の要人往来に示されているとおりである。
(2) 日・西欧経済関係(日・EC関係)
(イ) 近年わが国の対EC黒字幅は貿易量の増大に伴って拡大を続けていたが,79年には対EC輸入の伸びが対EC輸出の伸びを上回った結果,前年並みにとどまった。しかし,80年に入り対EC輸出が対世界輸出の伸び率(対前年比26.0%増)を上回る伸び(同31.3%増)を示したのに対し,ECからの輸入が停滞(同3.5%増)したため,日本の対EC黒字幅は大幅に拡大した(88億ドル。対前年比72.5%増)。わが国の輸出急増は,自動車(数量ベースで対前年比19.3%増),カラーテレビ・セット(同39.4%増),工作機械(数値制御旋盤:金額ベースで対前年比93.6%増,マシニング・センター:同140.9%増)などの分野において顕著であった。
(ロ) EC諸国は高インフレ(80年は通年でEC全体として12.1%増),高失業率(同6.0%増),低成長(GDPの実質成長率は同1.3%増),伝統的産業の衰退などの経済的諸困難を抱えており,こうした事情を背景としてEC諸国内で保護主義的圧力が強まった。
(ハ) このような動きに対しわが国は,自由貿易主義の原則が崩されることのないよう積極的にEC側と対話を進めた。10月には大来対外経済担当政府代表がブリュッセルのEC委員会を訪問し,EC側の考え方を聴くとともにわが国の考え方を説明した。次いで11月17日に伊東外務大臣談話を発表し,日・EC経済関係に関するわが方の立場を公式に明らかにした。これら二つの機会を通じてわが国は,(i)ECの経済的諸困難は認識するが,それは日本の対EC輸出を主因とするものではない,(ii)EC側の一層の対日輸出促進努力を期待する,(iii)いかなる地域に対しても特定品目の集中豪雨的輸出が行われないよう民間企業に勧奨していく,(iv)投資交流を含む産業協力を推進する,などの考え方を説明した。
(ニ) これに対しEC側は11月25日の外相理事会で対日関係を討議し,日・EC貿易関係の現状及び見通しにつき深刻な懸念を表明するとともに,一部のセクターにおける日本側の輸出自粛と対EC輸入の拡大を求めた。
(ホ) 12月に入り,伊東外務大臣はEC諸国及びEC委員会を歴訪し,日・EC間の政治協力の推進及び経済問題に関して率直な意見交換を行った。EC各国の首脳とも日・EC貿易関係につき懸念を表明したが,いずれとも自由貿易を堅持しつつ日・EC関係を増進すべきこと,またそのために,産業協力を推進することで意見が一致した。
(ヘ) 81年になっても日本側の一部品目の対EC輸出は増加を維持した。こうした事態を背景に,2月のEC外相理事会は自動車,カラーテレビ・セット,同ブラウン管,一部工作機械について対日輸入監視制度の導入を決定した。
(ト) 時期は前後するが,EC側における動きの中で特記すべき事項として,EC委員会が80年7月の外相理事会に提出した「対日通商政策」を挙げることができる。その内容は,日本との協力関係を拡大するためEC諸国が有する対日差別輸入数量制限(57品目)を撤廃する代わり,一部の品目について日本側の時限的な輸出の自主規制を求めるというものであった。しかし,外相理事会は本件を事務レベルで引続き検討すべきことを決定したにとどまり,その後日・EC間の貿易不均衡の拡大傾向が次第に顕著になるに従い,差別数量制限の撤廃は時期尚早であるとの空気がEC諸国の間で強まっていった。
(チ) 日・EC間の経済関係を貿易関係にとどめず,広く産業の分野での協力関係に発展させようとする努力が続けられ,特に自動車産業において日・西欧企業の提携が決定されるなど,注目すべき前進が見られた。
(リ) 閣僚,官民実務レベルでの交流に加え,次代を担う若者を対象とした人物交流プログラム(EC側による欧州青年実業家日本研修計画)が前年に引続き実施された。
<要人往来>
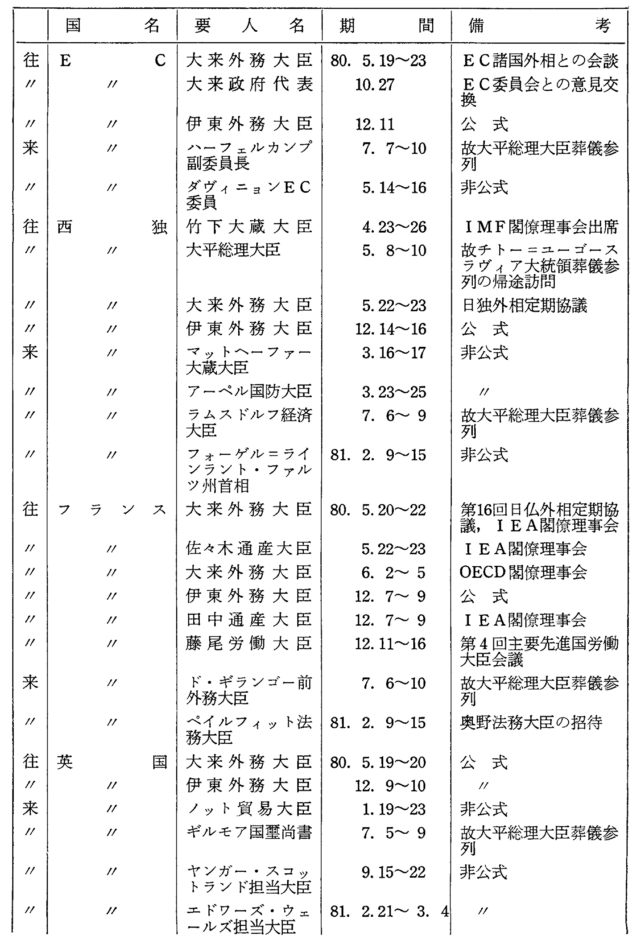
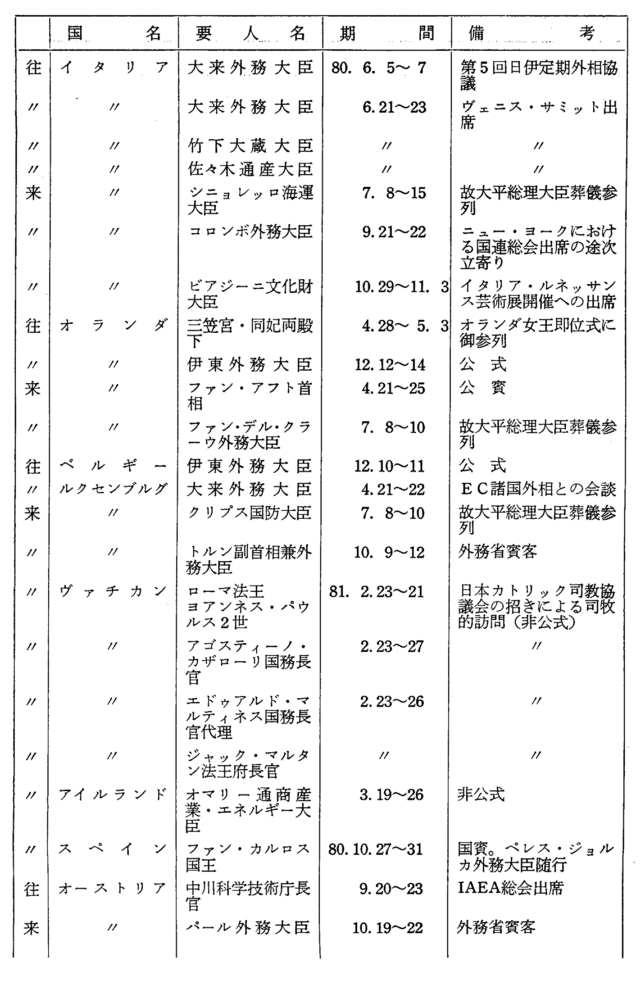
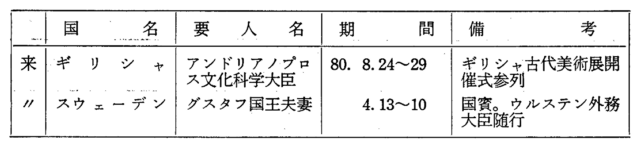
<貿易関係>
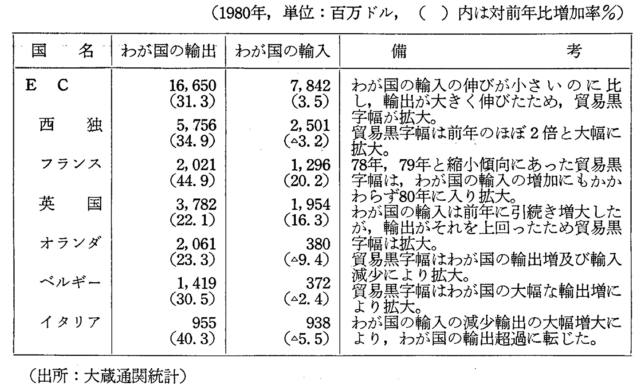
<民間投資>
(あ)わが国の対西欧直接投資
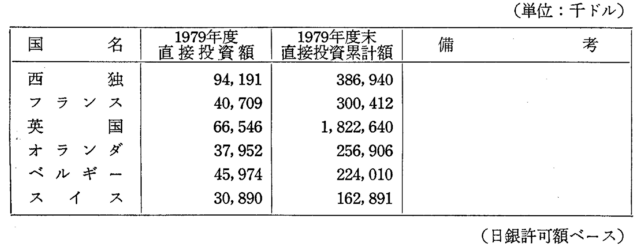
(い)西欧諸国のわが国に対する直接投資