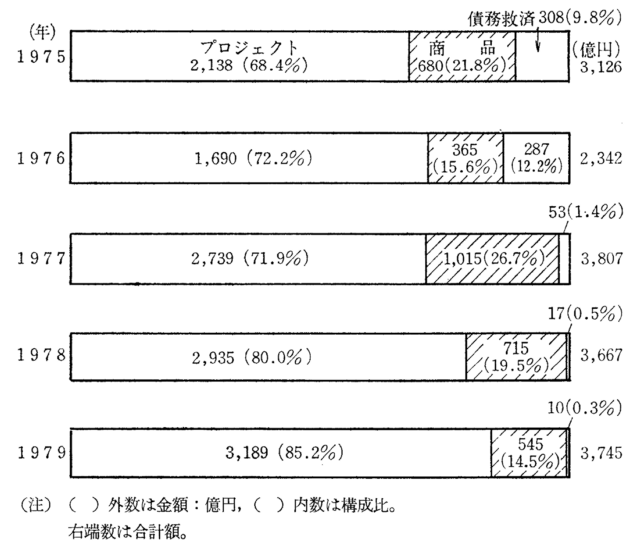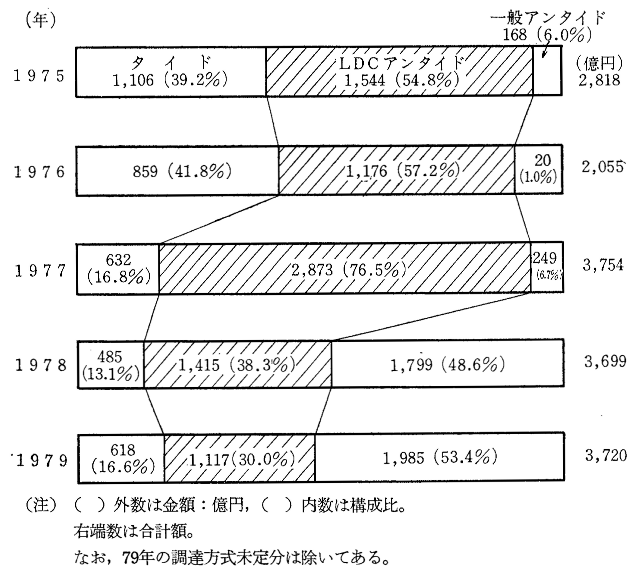
2. 政府直接借款
(1) 概 況
政府直接借款は,通常「円借款」と呼ばれ,わが国の2国間政府開発援助の大宗を占め開発途上国への重要な援助手段となつている。79年の供与実績(交換公文締結額)は,3,745億円と78年実績(3,667億円)をわずかながらも上回つた。この結果,79年末の供与額累計は3兆4,306億円と着実に拡大したほか,これまでに円借款を供与した相手国は,57カ国に拡大した。
また,ディスバースの対象となるパイプライン(交換公文締結済未ディスバース額)も積み増され,79年のネット・ディスバースメント(貸付実行額から回収額を控除した額)は78年に比べ,ドルベースで10.1%増加し,わが国政府開発援助3年間倍増(ドルベース)の基準年である77年に比べると92.1%増となつた。
借款の質については,平均供与条件が平均グラント・エレメント(以下G.E.)で78年の53.3%から79年には56.3%と顕著な改善をみせ,調達方式についても,一般アンタイ(注)の割合が53.4%と初めて過半を越えるに至り,供与条件,調達方式の両面から質的改善が促進された。しかしながら,借款供与条件は国際水準たるDAC諸国の借款平均G.E.61.5%(78年)には未だ至つておらず,今後とも量的拡充とともに質的改善が課題となつている。
(2) 79年供与実績の特徴
(イ) 一般アンタイド化の前進
円借款の調達方式は,"LDCアンタイイングに関するDAC了解覚書"に基づき77年まではLDCアンタイが調達方式の主流をなしていたが,77年末の対米通商交渉を契機として,一般アンタイ化を積極的に実施することに踏み切り,78年1月の牛場・シュトラウス共同声明第9項において「日本政府が資金援助を一般アンタイド化するとの基本方針を遂行する」旨の確認がなされた。こうした方針に基づき,78年4月以降の新規意図表明案件より一般アンタイドを基本方針とし,79年5月のマニラにおけるUNCTADV総会など主要な国際会議においてこうした方針を表明している。
こうした結果,一般アンタイド案件の割合は,図1のとおり78年に48.6%と77年(6.7%)から飛躍的に拡大したが,更に79年には53.4%と初めて一般アンタイ化率が過半に達した。
なお,79年において,タイド案件の比率は16.6%を占め,供与金額で618億円に上るが,これは78年9月経済対策閣僚会議で決定された総合経済対策に基づき実施された船舶及びプラント・バージに対する借款供与(総額約520億円)のうち約425億円が79年1~3月中に交換公文の締結に至つたためである。
(注)援助のアンタイイングとは,一般的にある資材及び役務の調達先を援助供与国に限定しないことを意味する。一般アンタイドとは,調達先をすべてのOECD加盟国及びDACの定める開発途上国に開放するものであり,LDCアンタイドとは,一般アンタイドまでの中間的措置として,調達先を援助国及び上記の開発途上国とするものである。
一般アンタイド化は,援助受取国にとつては,国際競争入札により,最も良質で最も安価な調達を可能とするものであり,援助資金の効率的使用につながるものである。
図1 調達方式別供与実績(交換公文締結ペース)
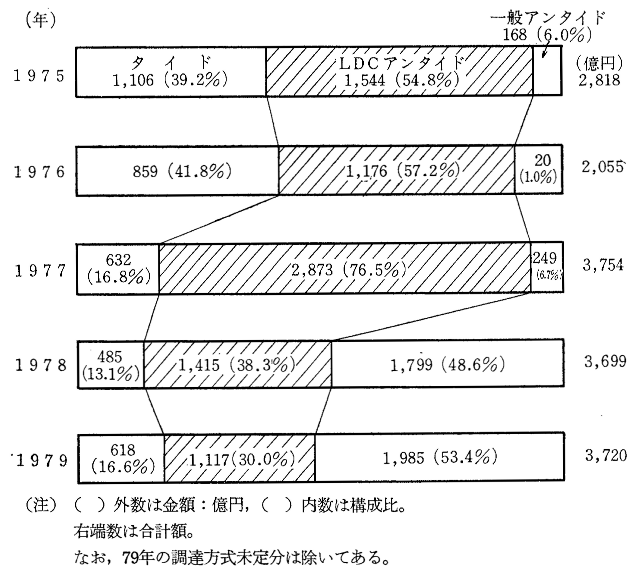
(ロ) 供与条件の改善
円借款の条件改善については,無償資金協力など贈与の比率の拡大とともに政府開発援助の質的改善の一環として,その全般的緩和に努めた結果,表1のとおり平均金利が78年の3.25%から79年には3.0%まで著しく改善したほか,償還期間,据置期間とも改善され,平均G.E.で56.3%と78年(53.3%)を大幅に上回つたが,DACの借款平均G.E.61.5%には達していない。なお,これまでバングラデシュに対して供与して
表1 平均条件(交換公文締結ベース,除,債務救済)
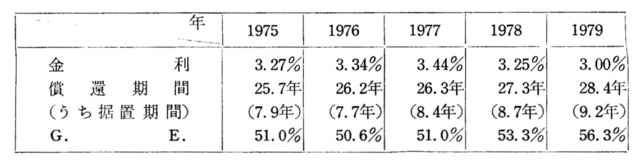
きた新規借款に対する最低金利も,78年の1.75%から1.25%へと一層緩和されている。
(ハ) 協調融資の活用
世銀など国際金融機関との協調融資は,円借款拡充策の一つとして,また,わが国円借款の供与経験が少ない地域における優良案件の発掘策の一つとして,その活用に努め,79年には,初めて世銀との間で協調融資協議が行われた。
この結果,世銀,米州開銀などとの協調融資案件として表2のとおり7カ国に対し総額539億円を供与した。
表2 国際金融機関との協調融資(1979年交換公文締結ベース)
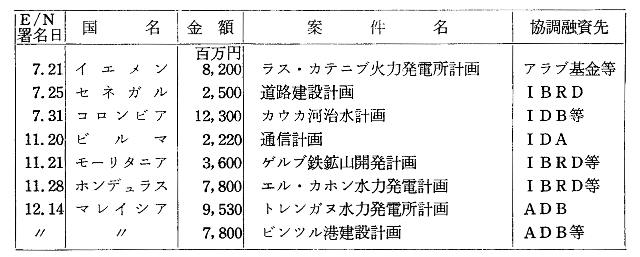
(ニ) 地域別・所得水準別動向
わが国は,これまで地理的,歴史的,経済的に密接な関係を有するアジア地域を重点に借款を供与してきている。この結果,ASEAN諸国を中心としたアジア地域のシェアは79年も74.1%とその大宗を占めている。
しかしながら,わが国経済力の拡大に伴つて,近年,アジア地域以外の諸国との関係も緊密の度合を深めており,79年には,中近東地域(53→487億円),アフリカ地域(162→272億円)の供与額が目立つて増加するなどわが国外交の基本方針に沿つて,非アジア地域への援助拡充が行われている(図2参照)。
また,所得水準別には,図3のとおりLLDC(後発開発途上国)に対する供与が拡充したほか,1977年の1人当たりGNPが580ドル以下の貧困国に対し,借款全体の87%が供与されるなど,国際的要請に見合つた貧困国重視のものとなつている。
なお,国別には79年中に新たに5カ国(モーリタニア,セネガル,シエラ・レオーネ,コロンビア,ホンデュラス)に対し初めて借款を供与し,79年末現在で,これまで円借款を供与した相手国は57カ国となつた。
図2 地域別供与実績(交換公文締結ベース)
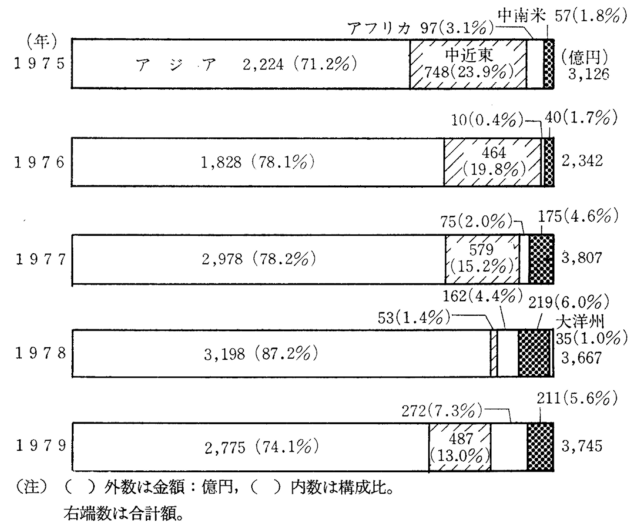
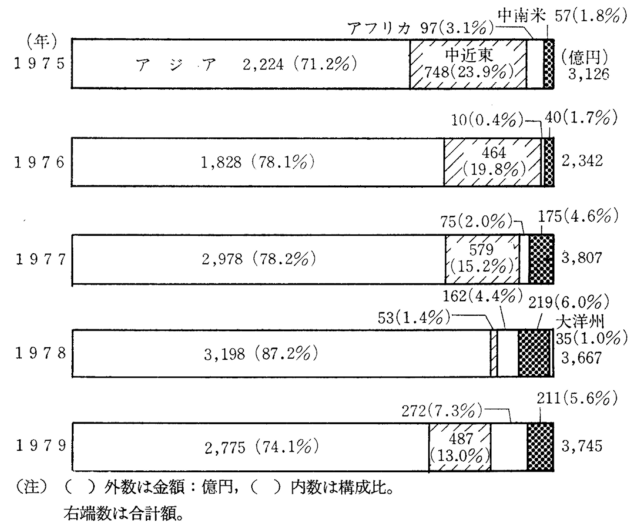
図3 所得水準供与実績(交換公文締結ベース)
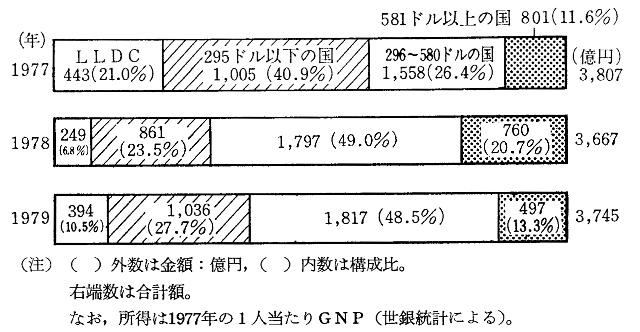
(ホ) 形態別動向
新規に供与する円借款は,形態上プロジェクト借款,商品借款に2分類される。前者は道路,港湾,通信施設などのプロジェクトに対して供与されるものであり,後者は,国際収支の悪化及び外貨不足から,国内経済を維持するのに必要な基礎的物資すら輸入できない場合などに,その輸入資金として供与するものである。近年図4のとおり商品借款の割合が減少しプロジェクト借款の割合が増加する傾向にあるが,79年も,商品借款の供与国は7カ国から6カ国に減少し,借款全体に占める比率も低下した。
また,既往債務に対し,その債務返済が困難に陥つた場合,国際的な協調のもとに行う債務繰延べなど債務救済措置は,79年中はパリ・クラブの決議に基づくペルーに対する債務繰延べ1件であつた。
図4 形態別供与実績(交換公文締結ベース)